東京都

目次
- 東京概要
- 新宿
- 渋谷
- 原宿
- 表参道
- 恵比寿
- 六本木
- 赤坂
- 永田町
- 丸の内
- 銀座
- 築地
- 新橋
- 日本橋
- 浅草
- 向島
- 蔵前
- 両国
- 上野
- 谷根千
- 神田・御茶ノ水・秋葉原
- 荒川区
- 神楽坂・九段下
- 芝・大門
- 深川
- 巣鴨
- 六義園
- 池袋
- 目黒
- 月島
- 豊洲
- 台場
- 品川
- 柴又
- 西新井
- 中野
- 世田谷
- 城東
- 江戸川
- 大田区
- 荻窪
- 吉祥寺
- 江戸東京たてもの園
- 高尾
- アニメの舞台
東京概要
| 東京都 | |
|---|---|
| 面積 | 2,200㎢【45/47】 |
| 人口 | 14,000,000人【1/47】 |
| 人口密度 | 6,000人/㎢【1/47】 |
| 23区 | 30市町村 | 島部※1 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 630㎢ | 1,160㎢ | 400㎢ |
| 人口 | 9,800,000人 | 4,300,000人 | 23,000人 |
※1東京島嶼部には、友人無人合わせて635の島がある。
日本の島参照
| 島 | 面積 | 人口 |
|---|---|---|
| 大島 | 91㎢ | 7,000人 |
| 八丈島 | 72㎢ | 7,000人 |
| 三宅島 | 55㎢ | 2,000人 |
| 新島 | 24㎢ | 2,000人 |
| 御蔵島 | 20.5㎢ | 300人 |
| 神津島 | 18.5㎢ | 1,800人 |
| 青ヶ島 | 6㎢ | 170人 |
| 利島 | 4㎢ | 300人 |
| 式根島 | 3.5㎢ | 500人 |
| 小笠原諸島(父島・母島) | 113㎢ | 2,500人 |
| 首都圏 | ||
|---|---|---|
| 都県 | 面積 | 人口 |
| 東京 | 2,200㎢ | 14,000,000人 |
| 神奈川 | 2,400㎢ | 9,200,000人 |
| 千葉 | 5,100㎢ | 6,200,000人 |
| 埼玉 | 3,700㎢ | 7,300,000人 |
| 茨城 | 6,000㎢ | 2,800,000人 |
| 栃木 | 6,400㎢ | 1,800,000人 |
| 群馬 | 6,300㎢ | 1,900,000人 |
| 山梨 | 4,400㎢ | 800,000人 |
| 合計 | 36,500㎢ | 44,000,000人 |
- 東京奠都
-
京都から新たに天皇親政を行う上で遷都への気運が高まり、大阪が希望地として挙がった。
1868年、江戸城無血開城で江戸に注目が集まった。
開城直後、前島密(homme politique)が「江戸遷都論」なる建白書を大久保利通に提出。
内容は
「遷都しなくても衰退の心配がない大阪よりも、帝都にしなければ市民が離散して寂れてしまう江戸の方に遷都すべき。」
Osaka ne tombe pas en décadence s'il n'y a pas de capitale, mais si on n'en déplace pas de Kyoto à Tokyo, des habitants de Tokyo quittent.
実際に幕末の江戸は求心力の低下に伴い市民らがそれぞれの故郷へ帰郷する者が増加していた。
帝都は国の中央にあるべきで、大阪は道路も狭小、江戸は諸侯の藩邸などが利用でき官庁などを新築する必要がなかった。
東京23区ランキング
| 人口 | 面積 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23区 | 9,800,000人 | 627㎢ | ||||
| 1 | 世田谷区 | 950,000人 | 58㎢ | 大田区 | 760,000人 | 62㎢ |
| 2 | 練馬区 | 760,000人 | 48㎢ | 世田谷区 | 950,000人 | 58㎢ |
| 3 | 大田区 | 760,000人 | 62㎢ | 足立区 | 710,000人 | 53㎢ |
| 4 | 江戸川区 | 700,000人 | 50㎢ | 江戸川区 | 700,000人 | 50㎢ |
| 5 | 足立区 | 710,000人 | 53㎢ | 練馬区 | 760,000人 | 48㎢ |
- 山手線
-
1885年開業の環状線。
1周34.5kmの30駅間を60分で運転。
起点は品川駅、終点は田端駅、基地は大崎駅。
開業当時は品川から渋谷や新宿経由の赤羽まで運行。
1925年から環状運転開始。
山手線の内側の面積は63㎢で1,000,000人が居住。
- 電線地中化
-
2017年に都道で電柱の新設を条例で禁止。
2024年末までに都道全体の48%で整備完了。
一方で、宅地では敷地内の多くが私道で「無電柱化」停滞。
民間企業による宅地開発は年間およそ500件で、電柱が年間850本以上新設。
東京都は、指定地域で新たに宅地開発をする場合、敷地内の電柱の新設を原則禁止とする全国で初の条例の制定を目指す。
開発許可申請時に無電柱化の計画書の提出を義務化。
違反した場合は指導・勧告、事業者名公表。
また、指定地域は23区の大部分が対象となる予定。
「無電柱化」は全国的にも進行中。
2024年1月1日の能登半島地震では、県内の電柱3,750本が傾き、750本が折れた。
災害時の電柱の倒壊は、電気や通信などのインフラの確保が難しくなるだけでなく、道路を塞ぎ避難や救助の妨げになることから応急復旧作業にも影響大。
- 23区中古マンション相場
- 2025年9月70㎡
| 区名 | 価格 | |
|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | ¥251,000,000 €1,400,000 |
| 2 | 港区 | ¥228,000,000 €1,200,000 |
| 3 | 中央区 | ¥167,000,000 €910,000 |
| 4 | 渋谷区 | ¥161,000,000 €880,000 |
| 5 | 品川区 | ¥127,000,000 €690,000 |
| 6 | 新宿区 | ¥124,000,000 €680,000 |
| 7 | 目黒区 | ¥122,000,000 €670,000 |
| 8 | 文京区 | ¥119,000,000 €650,000 |
| 9 | 江東区 | ¥104,000,000 €570,000 |
| 10 | 豊島区 | ¥103,000,000 €560,000 |
| 11 | 台東区 | ¥98,000,000 €540,000 |
| 12 | 世田谷区 | ¥87,000,000 €480,000 |
| 13 | 中野区 | ¥79,000,000 €430,000 |
| 14 | 杉並区 | ¥75,000,000 €410,000 |
| 15 | 墨田区 | ¥72,000,000 €390,000 |
| 16 | 北区 | ¥66,100,000 €361,000 |
| 17 | 荒川区 | ¥66,000,000 €360,000 |
| 18 | 大田区 | ¥61,000,000 €330,000 |
| 19 | 練馬区 | ¥55,000,000 €300,000 |
| 20 | 板橋区 | ¥52,000,000 €284,000 |
| 21 | 江戸川区 | ¥51,000,000 €280,000 |
| 22 | 葛飾区 | ¥47,000,000 €260,000 |
| 23 | 足立 | ¥43,000,000 €240,000 |
新宿
- 新宿駅
-
1日の乗降者数300万人は世界最多でギネス世界記録。
1885年開業当初は1日50人程度の小さな駅だったが、1923年の関東大震災を機に人口増加。
- 東京都庁
La mairie de Tokyo -
1957年、千代田区丸の内に旧庁舎が完成。
建物の老朽化と、旧淀橋浄水場跡地再開発(un aménagement d'un quartier)により1990年12月に竣工した新庁舎へ移転し、翌1991年から再始動。
第一本庁舎、第二本庁舎、東京都議会議事堂は、丹下健三の設計。
33,000人の職員在籍。
第一本庁舎は地上48階、地下3階、高さ243mで、展望台は北と南の45階202mに位置し、1階からの直通エレベーター55秒。
オフィスが入っていない階は機械室。
開館カレンダー - 東京都知事
-
1943年に誕生。
任期は4年
投票率(taux de participation électorale)は50~60%
都知事の被選挙権は、日本国民であり、満30歳以上。
-
淀橋浄水場
La station d'épuration Yodobashi -
1898年から1965年まで新宿区西新宿にあった東京都水道局(le service des eaux)の浄水場(la station d'épuration)。
1923年の関東大震災で住居を失った東京市民が広い郊外に土地を求めて西新宿一帯に移住。
当時の西新宿は淀橋浄水場の他、人家と学校があるだけの閑散とした地域だった。
住民増加により、近隣発展の必要に迫られ、場所を取っていた淀橋浄水場を移転する計画が成された。
戦後に東村山浄水場が竣工し、1965年に浄水場移転。
跡地には東京都庁舎などの高層ビル群が立ち並ぶ。
1960年に渋谷で創業したカメラ用品販売店「藤沢写真商会」(magasin de photographie)が1967年に新宿区淀橋に店を構え1974年に「ヨドバシカメラ」と改称。
- ゴールデン街
-
第二次世界大戦後、新宿駅周辺に闇市が興った。
しかし、戦後の1949年、連合国軍総司令部(le commandement suprême des forces alliées)が闇市撤廃(supprimer)を指示。
都庁と警視庁は翌年までに移転を命じ現在の歌舞伎町に移転。
- 新宿二丁目
-
北は靖国通り、南は新宿御苑、西は新宿三丁目駅、東は新宿御苑駅に囲まれた面積10haの区域。
特に新宿通りから靖国通りに抜ける240mの仲通りがメインストリートで、ゲイバーなどが450店舗並ぶ。
戦後初期の新宿は未開の地。
当時は上野公園が男娼の地だった。
1958年の売春防止法完全施行で赤線が廃止され、空き家となった元赤線の店などを利用してゲイバーが営業を始めた。
- GUNKAN東新宿ビル
-
陸軍船舶兵出身の建築家渡邊洋治が設計。
「軍艦マンション」と通称された通り、軍艦(Le vaisseau navire)をイメージしたデザイン。
各階Y字状の廊下に6畳(約11㎡)の鉄製居室ユニット150基が取り付けられ、エアコンの室外機の設置を目的とした小さなベランダが設けられている。
軍艦のミサイルのような円筒形の物体は受水槽。
1970年に竣工され、2011年にリノベーション。
内部はシェアハウスやオフィス。
鉄骨鉄筋コンクリート造で14階、地下1階で45mの高さ。

-
NTTドコモ代々木ビル
La Tour NTT DoCoMo Yoyogi -
通称「ドコモタワー」
NTTドコモが1990年代半ば、携帯電話の急激な普及を見込んで、都内と埼玉県周辺をカバーする新たな中継基地を、旧国鉄の新宿貨物駅跡地に建設。
NTT Docomo un grand opérateur de réseau mobile a prévu que le portable se propager et construit la station de relais.
1997年着工、2000年竣工。
高さ240m
日本の高層建築参照
ニューヨークの摩天楼を思わせる形状から別名「新宿のエンパイアステートビル」
Empire State Building à Shinjuku.
北側には、2002年のNTTドコモ設立10周年を記念して設置された直径15mのシチズン製大時計(Une horloge de 15m de diamètre)があり、時計の針は分針(Une grande aiguille)、秒針(Une trotteuse)共に1トンを有する。
地上50階建のビルで、14階までがオフィス、15階から25階までが通信設備(Machine à communiquer)機械室、25階部分が屋上。
上層部はアンテナの為の尖塔部分で、鉄骨に外壁が貼られているだけで中は空洞。
落成当初は、展望ロビーがあると勘違いして訪れる観光客が多かったため、「当ビルには展望室はありません。」との張り紙が出されていた。
- 新宿御苑
- 開園…1906年5月
- 面積…58.3ha(583,000㎡)
- 年来園者…1,260,000人
- 特徴…日仏英式庭園、日本さくら名所100選、文化財多数
-
1591年、徳川家家臣内藤家二代目の清成が江戸城西門警固の功績を認められ、現在の新宿に屋敷地を拝領。
その一角が現在の新宿御苑。
1698年、幕府は内藤氏の広大な下屋敷の一部を返還させて、町屋とともに馬継ぎの施設を設けて宿駅とした。
これが甲州街道最初の宿駅で「内藤新宿」と呼ばれた。
明治に入り、大蔵省が牧畜園芸改良を目的として「内藤新宿試験場」を設けた。
国内外から多種多様な植物(végétaux)を集めて、その効用(utilité)、栽培の良否適否(culture)、害虫駆除の方法(moyen d'exterminer les insectes nuisibles)などを研究するなど国家規模で農業技術行政の取り組みが行われた。
1900年、造園家(jardinier)で官僚(bureaucrate)の福羽逸人(ふくばはやと)卿がパリ万博へ園芸出品審査員として出張し、ヴェルサイユ園芸学校の造園教授アンリ・マルチネー(Henri Martine)に新宿植物御苑を庭園に改造する計画を依頼。
1906年、新宿御苑が完成。
現在は毎年4月に内閣総理大臣主催の「桜を見る会」、
11月上旬に環境大臣(ministre de l'Environnement)主催の「菊を観る会」開催。
- シティハンター
-
漫画家の北条司氏の作品で、デビュー作の『キャッツ♡アイ』に続く第2作目。
1985~91年にかけて週刊少年ジャンプにて連載され、コミックは全35巻336話。
舞台は1980年代後半の新宿。
主人公で探偵(un détective)、ボディーガード(un garde du corps)、掃除屋(un nettoyeur)、殺し屋(un tueur)として活躍する冴羽獠が美人の依頼人から受けた仕事をこなすという内容。
表向きの仕事はマンション管理人。
少年誌への掲載としては内容が大人向きで特に連載初期は正統派ハードボイルド(hard-boiled/dur à cuire)色が濃かった為、担当編集者から、もう少し明るい作風にするように指摘があった。
そしてコメディ色が強くなり人気作品へ。
冴羽獠への仕事の依頼方法は、新宿駅東口にある伝言板(un tableau pour les messages)に「XYZ」を記す。
これは「もう後がない(On ne peut plus reculer.)=助けてくれ」という意味。
アニメ版で声優を務めた神谷明氏は、自身で事務所を立ち上げた際、会社名を作中と同じ「冴羽商事」としたほど冴羽獠が好き。 -
冴羽獠(SAEBA Ryo)…
Nicky LARSON…Philippe LACHEAU -
槇村秀幸(MAKIMURA Hideyuki)…
Toni MARCONI…Raphaël PERSONNAZ -
槇村香(MAKIMURA Kaori)…
Laura MARCONI…Élodie FONTAN
- ゴジラ
-
2015年4月にオープンした新宿東宝ビル内のホテルグレイスリー新宿8階テラスに位置。
映画制作会社東宝の作品でもあるゴジラがシンボル。
- 世界堂新宿本店
-
画材、文具、額縁の専門店。
新宿本店、池袋パルコ店、立川北口店など東京、神奈川、埼玉、愛知に展開。
1940年創業で「モナリザもびっくり」がコンセプト。
🗺️東京都新宿区新宿3-1-1
世界堂ビル1F~5F
🕐9:30~20:00
📞03-5379-1111
💻公式サイト
渋谷
- スクランブル交差点
-
1973年設置。
1回の青信号で最大3,000人、
1日で最大500,000人通行。
2003年「ロストイントランスレーション(Sofia Coppola)」
2006年「Fast and Furious:Tokyo Drift」
ちなみに、この映画で監督は無許可で撮影を行い、警察に影武者を逮捕させた。
2016年のリオデジャネイロオリンピック閉会式の際、次回開催地東京を紹介する映像(une image)でも使用。
2000年の大晦日(Le réveillon)以降若者の年越しイベント化。
ハロウィンやW杯の際にも多くの人が集まる。
ニューヨークのタイムズスクエアのようなカウントダウン(Le compte à rebours)は無い。
マスコミ(Les mass-media)がテレビなどでその盛り上がりを報道した事も影響していると言える。
2023年には群衆事故を懸念し規制。
- 渋谷スカイ
-
2019年8月に竣工した大規模複合商業施設「渋谷スクランブルスクエア」の45階、46階、屋上に位置する展望台。
地上230mの高さに360度を見渡せる構造。
- ハチ公
-
1923年11月10日生まれの秋田犬。
1925年、東京大学教授の上野英三郎は学内にて突然脳出血(une hémorragie cérébrale)で死去。
日本犬保存会が発起し資金を集めて1934年銅像造立。
ハチも除幕式に参加。
Il a participé à l'inauguration de sa statue.
1935年3月8日、像とは真逆の稲荷橋付近で発見。
ここは普段ハチが行かない場所だった。
死因はフィラリア病(la filariose)とされる。
現在のハチ公像は1948年に再建された2代目で、初代は戦時中の金属(métaux)供出の為撤去。
2009年にリチャード・ギア(Richard Gere)主演で映画化。
ハチ公没後80年にあたる2015年3月8日に東京大学農学部校内正門脇にハチ公と上野英三郎像造立。
- モヤイ像
-
イースター島のモアイ像とは全く関係無い。
Ça n'a aucun rapport à moaï de l'île de Pâques.
両面に顔、若者は「アンキ」、老人は「インジ」という名前。
伊豆の新島から寄贈された像で1980年設置。
「モヤイ」とは、共同作業(travail d'équipe)の意味であり、新島で力を合わせて仕事に当たるときに使われた言葉。
渋谷の若者たちにも連帯(La solidarité)の気持ちを持ってほしいという願い。
- 代々木八幡宮
-
1212年創建の第15代応神天皇を祀る。
鎌倉幕府2代将軍源頼家の臣下(vassal)智明(ともあきら)は、頼家が修善寺暗殺された後、この地で隠遁生活を送りながら主君の冥福を祈っていた。
1212年8月15日、智明は鎌倉の八幡大神から宝珠のような鏡を授かり信託を受ける夢を見た。
そこで同年9月23日、この地に祠を建て鶴岡八幡宮より勧請を受けたのが起源。
例祭は9月23日。 - 竪穴式住居
-
1950年に境内の発掘調査(faire des fouilles archéologiques)で、縄文時代(en 14,000 avant Jésus-Christ)の建物発掘。
特に4,500年前頃の土器が数多く出土。
渋谷界隈は土地が低く、豊沢貝塚(l'amas préhistorique de coquillages)に見受けられるように海底だった時期もある。- まず石器で穴を掘り(creuser)床を造る。
- 中央に柱用の穴を掘り支柱を据えて木で骨組みを造る。
- 最後に土や葦(roseau)などで屋根を造る。
- 庚申塔
-
庚申信仰(le culte koshin)は中国の道教(le taoïsme)に基づくもので、平安時代(8~12世紀)に日本へ伝わり、江戸時代に最盛期を迎え、庚申供養塔が建てられた。
庚申塔の多くは青面金剛像が刻まれ、下に三猿が彫られる。
青面金剛はインドのヴィシュヌ神(Vishnou)が転化したもの。
Shomenkongo est Vishnou incarné.
庚申の申の字は猿に通じる。
ここにある庚申塔は1790年、1755年、1794年と刻まれている。 - 訣別の碑
- 拝殿に向かう参道には、代々木の原に大日本帝国陸軍(l'armée de terre)の代々木練兵場(le centre d'entraînement)が1909年に造られた際、この地から立ち退いた居住者(Les habitants évacués)が別れを惜しんで奉納した石碑。
原宿
- 明治神宮
-
1920年11月1日創建の第122代明治天皇と昭憲皇太后を祀る。
1912年に明治天皇、1914年に昭憲皇太后崩御後、日本近代化に注力した天皇を祀る為に建立。
←121e empereur Komei, 統仁(Osahito) entre 1846 et 1867.
→122e empereur Meiji, 睦仁(Mutsuhito), entre 1867 et 1912.
境内は70ha(700,000㎡)あり、杉(le cèdre)や檜(le cyprès)ではなく、椎(le hêtre)、樫(le chêne)、楠(le camphrier)が多く植樹された人工林。
理由は大正時代(au début de 20ème siècre)に公害(la pollution)が進んでいた東京において、100年先を見越して照葉樹林(Les bois feuillus)化を決定。
ちなみに、大正天皇と昭和天皇の墓所は東京都八王子市にあるが、明治天皇の墓所は出身地である京都にあるため、当時東京住みの人々が気軽に参拝できなかった。
それもあり、東京に明治天皇をお祀りする神社を建立。
第二次世界大戦中、1,300発の焼夷弾を受け、南神門と宿衛舎(宿直の宿泊所)以外は焼失し1958年再建。 -
明治神宮は内苑(70ha)と外苑(28ha)を合わせた敷地を有する。
内苑は御霊をお守りする社で、外苑はスポーツや芸術などの文化的交流を目的とする。
林学者(professeur forestier)の本多静六(1866~1952)は1890年に単身ドイツに渡り、ミュンヘン工科大学で林学を学び博士号を取得。
日本最初の西洋公園である日比谷公園も設計。
- 大気汚染などの公害に耐え、その土地の環境に最も根ざした木を植える。
- 森自身が自然に世代交代を遂げる。
- 神社林に相応しい森厳さ。
世代交代が進み、朽ちた針葉樹は土に還り消滅。
最後には土地に最適な天然林相に達する。 - 神社本庁
-
伊勢神宮を本宗として日本各地の神社を包括する1946年に設立された宗教法人。
本部は明治神宮に隣接する。 全国に80,000ある神社の内78,000が所属。
靖國神社は包括外神社。
全国に20,000人の神職者がおり10%が女性。
明治神宮には40名が所属するが女性は居ない。
神社数に対して神職者が足りていないので、兼任する。
神職者の勉強は國學院大学と皇學館大学に専門の学部があり、採用試験と面接を突破し、就職。
宮司は社長(各社1名のみ)。
神社本庁は神主を「浄階」「明階」「正階」「権正階」「直階」の5階級に分けて管理し、上納金を集める。
年間50億円(27 millions euros)規模の運営予算。
- 明治維新が生んだ人工的・政治的な存在
-
歴史上、日本人の精神に影響を与たのは仏教。
6世紀半ばに伝来した仏教には明確な教祖(釈迦)がいて、経典類も整備されていた「洗練された宗教」に当時の日本人は感銘を受け、天皇ですら仏教に帰依して、奈良や京都などに権力者の手によって、寺が建った。
神社や神主たちの儀式は、仏教の寺や法要のスタイルに影響を受けている。
平安時代になると本地垂迹説、つまり「仏教も神道も本来は一つ」という考えが広まり、寺と神社は一体運営された。
江戸時代くらいになると、一般民衆で寺と神社を区別して考える人は、少なかった(神仏習合)。
当時の実状を言えば、多くの神社は寺に取り込まれ、神道は仏教の下位に置かれる例が多かった。
しかし、江戸幕府を倒した明治維新という運動は、それまでの武士の政権を倒し、天皇を国のトップに置く政治へ変えようという考えを持っていた。
天皇の祖先は太陽神・天照大御神だとされ、その天照大御神は神道の神々のなかでも重要な存在だった。
「天皇を国家元首とする国」をつくるためには、神道を復権させる必要があると、明治新政府をつくった人々は考えた。
そしてできあがったのが「国家神道」だった。
ただし、現実として神社は寺と融合している。
そこで神仏判然令や廃仏毀釈といった、仏教弾圧的な政策がとられ、結果、現在の日本にあるような「神社」が、かなり人工的かつ政治的に形成されていった。
明治時代以降の日本、すなわち大日本帝国の体制では、神社はある種の国家施設だとされ、神主は官吏待遇を受ける存在だった。 - GHQの宗教政策に対する怨念
-
第二次世界大戦後、日本を占領したアメリカ軍を中心とする連合国軍総司令部(GHQ)は、日本の軍国主義の源泉は神道にあると考えた。
そして国家神道は解体され、1946年にできた日本国憲法では、政教分離や信教の自由が明確に定められた。
しかしすでに述べたように、日本の「神社」とは明治維新の関係から、かなり人工的かつ政治的に形成され、事実上の国家機関として運営されてきた存在だった。
いきなり国家神道が廃止されたからといって、各神社による独立は難しい。
そこで46年に誕生したのが神社本庁。
その為、神社本庁上層部の神主の中には「我々はGHQのいい加減な宗教政策の末に、でたらめな形で国家政府の枠組みから放り出された犠牲者だ」といった被害者感情を持っている人たちも少なくない。
この為、神社本庁の活動は必然的に国粋的・復古主義的な性格を帯びる。
神社本庁の政治部門である神道政治連盟は自民党の右派議員に接近し、彼らを熱烈に支援することで、一定の政治力を発揮してきたとされている。
ただ、戦後も80年になると、敗戦前後の事情を直接知っている神主は少なくなっている。
戦後から始まった「民間宗教法人たる神社」のあり方も、ある程度は自明のものとみなされるようになり、それで神社界も回るようになってきている。
実際に話してみると、一般の神主に強い政治的意見を持った人たちは少なく、神社界の今後の構想などを尋ねても、穏健な現状維持派的な人がむしろ多い。
しかしそれは同時に「アメリカへの怨念」のようなものから始まった神社本庁を、新しい方向へ引っ張っていく目標や思想が欠如してしまっているということでもある。 - 異例の多選を重ねる田中総長体制
-
全国の神社を束ねる包括宗教法人(教団組織)としての神社本庁は、この数年間、深刻な内紛状態に陥ってきた。
土地取引をめぐるスキャンダルを機に、代表役員である田中恆清(つねきよ)総長(81)の責任を問う声が挙がり、一時は本人も辞意を口にしていた。
ところが、田中氏は今年5月に異例の6選を果たした。
総長職の任期は1期3年で、最長2期6年での退任が慣例であるにもかかわらず、18年の長期支配を目指すことになる。
これには「田中独裁体制が敷かれている」といった批判も多々あるのだが、結局は神社界全体に流れるマンネリ感と人材不足と裏腹の関係にあり、神社界が現在、相当な停滞状態にあることは事実であろう。
そして今では単なる民間の宗教団体でしかない神社本庁に、全国の個々の神社が加入しなければならない義務は、実はない。
こういう神社界の停滞した空気に嫌気がさし、神社本庁から離脱して独立運営を目指す神社が目立ち始めてもいる。 -
養蚕業、太鼓、磐座(いわくら)
KamiとGodの違い。
神道の戒律が無い。結婚も可。しかし、清浄が大事。
祓舎…神職者の為の清め。大祓も6月と12月に実施。
本殿の柱の傷は正月に賽銭を投げた時についたもの。
賽銭は寄付ではなく、感謝の気持ち。
二拝二拍手一拝。拝は90度の礼。
柏手の右手は左手よりも下。左手が陽、右手が陰。
感謝を伝える。
手水舎は神から見て下手にある。
神道83,000,000/仏教81,000,000/キリスト教徒1,300,000
神道は宗教というより道、華道、茶道、書道、武道。
6世紀に仏教が伝来した時に「神道」という名称が使われ始めた。
お天道様が見ている。
恥の文化vs罪の文化
三種の神器と稲穂を授ける。天皇陛下も田植えや収穫を行う。
決して偶像崇拝ではない。
生まれた時は純粋。生きていくと穢れが付いてくるので、穢れを祓う。浄明正直。
生かし、生かされている。いただきます。司どる。宿る。God/Worship,罪、穢れ,appreciate
贖罪ではない。
すのこの上は土足禁止、逆に地べたは裸足禁止。
氏神神社、崇敬神社
11月3日明治天皇誕生日。大使へワインを振る舞う。
酒は正月を前に変える。中身は空。2本奉納される。
菊花紋12弁、16弁。
緑青が出ている鬼瓦は2020年の改修時に修復せず。理由は今の技術では製作不可能な為。 - 南参道鳥居
第一鳥居 -
創建同年1920年11月1日に造立された、笠木が反り返った形状の明神鳥居。
明治神宮鎮座百年祭の2020年に建て替えられる予定だったが、コロナの影響で延期。
2014年奈良で木材の切り出し→2022年4月着工→同年7月4日竣工。
大きさは建て替え前と変わらず、高さ11m、笠木幅15.6m、柱の直径1.06m
 1990年以降、台湾の国有林伐採が禁止されており、材木を台湾檜(le cyprès)から全て国産の杉(le cèdre)へと変え、東側が樹齢280年、西側が樹齢260年の吉野杉。
1990年以降、台湾の国有林伐採が禁止されており、材木を台湾檜(le cyprès)から全て国産の杉(le cèdre)へと変え、東側が樹齢280年、西側が樹齢260年の吉野杉。
笠木は宇都宮材、島木は三重県の美杉材、貫は福井県の足羽材。
2mある土に埋まっている部分には、腐食防止(pour prévenir la corrosion)の為に銅(le cuivre)を被せて補強。
菊の花は、奈良時代に中国から輸入され、邪気を払う、不老長寿(la longévité)の薬として使われた。
また、花の形状が太陽に似ており、天照大神への信仰と結び付き、天皇家の象徴としても使用。
境内に敷いてある玉砂利は、参道を清める為のものでもあり、玉(la boule)=魂(l'âme)=霊という神聖なものと結び付けた。
玉砂利を踏みしめて歩くことで、心身ともに清められ、神前では清らかに参拝が出来るとも言われている。
on marche sur des graviers, on se purifie.
正月三箇日で300万人の参拝者が訪れる日本一の神社。
年間参拝者は10,000,000人を超える。 - 奉献清酒菰樽
-
「和魂洋才」
日本の心を守りつつ、西洋の文化を採り入れた明治時代。
On avait l'esprit japonais, et adoptait la culture occidentale.
国民の模範となって近代化を推し進めた明治天皇は、断髪、洋装等、多方面において西欧文化を積極的に取り入れた。
食文化においても率先して洋食を食し、西洋酒としては特に葡萄酒を好んだ。
Notamment, il prenait l'initiative de manger la cuisine occidentale et aimait bien le vin.
葡萄酒樽は、佐多保彦(Sata Yoshihiko, il est un citoyen d'honneur à Bourgogne et propriétaire du Château de Chailly)氏の呼びかけで、ブルゴーニュ地方の醸造元各社より献納。
Ces bourgognes sont des offrandes.
明治神宮の菰樽は、全国各地の敬神の念厚き酒造家より献納。
酒樽は4斗樽で72リットル。
藁の代わりにナイロン(le nylon)やポリエステル(le polyester)を使用することも。
明治天皇は酒好き→糖尿病→ドイツ人医師から「日本酒よりワインの方が良い」と提言。 - 大鳥居
第二鳥居 -
南参道と北参道の出合い口のところにある大鳥居は、高さが12m、幅が17.1m、柱の太さが直径1.2m、重さが13tあり、木造の明神鳥居としては日本一の大きさ。
初代鳥居は明治神宮創建の1920年完成。
1966年の落雷で破損した為、横に避雷針(le paratonnerre[パラトネール])を設置。
現在は1975年完成の二代目で、樹齢1,500年の台湾檜(le cèdre)を輸入。
日本では同程度の木が見つからなかった。
境内の鳥居は神聖度の高さを表す。 - 正参道
-
第二鳥居から本殿までの曲がり角は直角ではなく、88度。
末広がりの八を意識して設計。
和歌は明治天皇100,000首と皇后30,000首。 - 南神門
-
南神門の留め具にハートは、猪の目。
猪は火事の際に一目散に逃げるため、木造建築が主な寺社仏閣において、火除けの縁起を担いだ。
この門は戦火を免れた。 - 夫婦楠
camphrier de couple -
樹齢約100年。
1920年の明治神宮創建当時に献上。
明治天皇と昭憲皇太后の仲の良さにあやかり、縁結び、夫婦円満、家内安全の象徴。 樹齢150年で、剪定はしているが、苑内の木々には手を加えていない。
- 神職者の1日
-
9:00~17:00勤務。
スーツで出勤し、水で体を清めて白衣と袴に着替える。
その際、手水舎同様、左→右→左の順に水をかける。
朝拝の後に掃除。
その後各部署にて仕事。
日供(朝夕)14:00/20:00各10分程度。
技能練習。書、楽器、祭式。
- ナラ枯れ対策
-
カシノナガキクイムシという小さな虫が媒介するナラ菌によって樹木が枯れる被害。
虫の生態を利用した大量捕獲装置とシート被覆を併用。
トラップ下部のボトルには捕獲虫の腐敗を防止するためのアルコールが入っているが、農薬不使用。
トラップは5~9月まで設置。

- 明治神宮御苑
-
江戸時代の初めは熊本藩加藤家下屋敷の庭園で、その後、彦根藩主井伊家にうつり、明治維新後、皇室の御料地となった。
苑内約8ha(83,000㎡)の中にツツジ(azalée)、藤(glycine)、花菖蒲(iris)、スイレン(nénuphar)、椿(camélia)などが季節を彩る。 - 隔雲亭
-
数寄屋造りの木造家屋は昭憲皇太后の休息所として明治天皇が造営。
戦火により焼失、1958年再建。 - 花菖蒲田
-
江戸時代は家臣子女(des femmes de vassales)が米作りの大切さや苦労を学ぶ稲田だった。
1893年に昭憲皇太后の為に明治天皇が花菖蒲田に改めた。
周囲の斜面にはモミジ(un éralbe)、ヤマブキ(la corète)、サツキ(azalée)、ハギが植えられた。
花菖蒲を眺める丘には茅葺の四阿(あずまや)が建てられ、添景となっている。
6月が見頃の花菖蒲は、江戸時代中期以降から改良された茎葉が剛直で花茎が葉より高くなり、野外での立ち姿が美しい江戸系の原種150種、1,500株が植えられている。 - 清正井
Le puits de Kiyomasa -
江戸初期にこの地が加藤家の庭園だったことから、加藤清正が掘った井戸だと言い伝えられている。
湧き出る清水は、井戸水特有の冬温かく、夏冷たく、年間を通して15度前後。
清水は花菖蒲を潤し、南池で淀んだ後池の水門から流れ下り、南参道に架かる神橋をくぐり抜け、渋谷川の源流となる。
最近まで茶の湯に使われていた。 - つつじやま
La colline des azalée -
苑内のいたるところで山ツツジの古株が見受けられる。
特に、清正井からの帰り道、北出口へ坂を上がった苑路沿いには、コナラ(un hêtre)やヤマザクラの高木に包まれてヤマツツジが群落をなしている。
樹齢100年を超える人の丈以上の古い株もあり、4月下旬の花の頃は一面の薄紅色が新緑に映えて美しいトンネルを作りだす。 - 南池
-
8,300㎡ある自然の古池(vieux étang)。
清正井から花菖蒲田を潤した清水を漫々と湛え、夏にはスイレンやコウホネが花を咲かせる。
明治天皇の昭憲皇太后へお優しい心遣いで放たれたコイ(carpe)やフナ(carassin)、メダカ(oryzias)が世代を繋ぎ泳ぐ池。
カワセミ(martin-pêcheur)やサギ(héron)が魚影を求めて訪れ、冬季はカモ(canard)やオシドリ(canard mandarin)が羽を休める。
時々、オオタカ(Autour des palombes)やルリビタキ(Rossignol à flancs roux)も見ることができる。 - 明治記念館
-
大正当時は「憲法記念館」と呼ばれた。
竣工は1881年で、明治神宮が擁する全施設の中で最古。
竣工当時、建設されたのは赤坂仮皇居の敷地内。
1889年、日本最初の憲法制定にあたり、明治天皇御臨席のもと、幾度となく枢密院会議が行われた場所。
1907年、明治天皇は憲法制定に功績のあった枢密院議長の伊藤博文(1984~1909)にこの建物を下賜する。
やがて明治天皇をお祀りする神社の造営にあたり、伊藤家から明治神宮へ寄贈され、憲法記念館として移築。
- 代々木公園
- 開園…1967年10月20日
- 面積…54ha(540,000㎡)
- 特徴…東京都建設局直轄、元練兵場、元ワシントンハイツ、元東京五輪選手村
-
1909年から大日本帝国陸軍の練兵場。
Le terrain d'entraînement pour l'armée de terre.
戦後の1946~64年は在日米兵や家族用の宿泊施設。
1964年にオリンピック選手村(un village olympique)。
1967年から公園として開放。
- 五輪橋
- 1964年の東京五輪の際、水泳競技会場となっていた国立代々木競技場までの最短ルートとして架橋。
- 国立代々木競技場
-
第一体育館、第二体育館、インドアプール等から成る。
1964年の東京オリンピック開催前に建設。
設計は丹下健三で、吊橋(pont suspendu)と同様の吊り構造の技術を使用。
1本の主柱から屋根全体が吊り下げられている。
Suspendre le toit entier d'un grand pilier.
観客を競技に集中させる為、内部に柱を持たない構造。
Il n'y a pas de pilier intérieur pour concentrer le sport.
また、油圧ダンパー(amortisseur)で屋根の振動を抑える構造を採用し、台風や地震にも強い。
耐震目的で油圧ダンパーを採用したのは日本初。
戦後多くあったアメリカ人居住施設があり、アメリカ軍との返還交渉の難航から着工が1963年2月までずれ込み、竣工はオリンピック開催の39日前となった。
1964年のオリンピックでは、競泳、バスケットボール開催。
2021年のオリンピックでは、ハンドボール。
同パラリンピックでは、バドミントンと車いすラグビー。
- 竹下通り
-
350mのショッピングストリート。
1976年のMARION CREPESが話題。
80年代には「竹の子族」という中高生グループがムーブメント(boom)となり、表参道や代々木公園などで、派手な(voyant)衣装に身を包み、ラジカセから流れるディスコサウンド(la musique de la discothèque)に合わせて踊った。
「竹の子族」の由来は竹下通りにある「ブティック・竹の子」という説もある。
80年代後半から多くのタレントショップ(俳優や歌手などのグッズ販売店)が開店、原宿竹下通りを若者の町へと変化。
90年代後半からは、ゴシック・ロリータファッション(une mode vestimentaire)をはじめとする個性的なショップやニーズも増え、若者ファッションの聖地となる。
- 東郷神社
-
1934年、東郷平八郎亡き後、氏の功績を顕彰し、後世に残して欲しいと、全国各地からの要望と献金が海軍省(le ministère de la marine)に届き、建立。
日露戦争(1904~05)勝利と日本を救った歴史を伝承するとともに、現世の人々の安寧を願い、数多の英霊を守護。
「至誠」「勝利」「強運」「縁結び」の神様。
「la sincérité」「la victoire」「la chance」「le mariage」 - 水交神社鳥居の由来
-
この鳥居はもと築地海軍用地の水交神社の鳥居。
水交神社は、日清戦争(1894~95)に際し、海軍の戦勝を祈願し、また同戦役以後の戦没者霊を合祀する為創建。
初代の鳥居は戦利品の魚雷(une torpille)で作った異形のものであった為、1911年に神明鳥居に建て替えられた。
水交神社と鳥居は、関東大震災の災禍を免れ、1928年に水交社が芝区栄町(現在の東京タワー北西隣)に移転した際同地に遷座。
社殿は1945年3月の東京大空襲で焼失したが、この鳥居だけは毀損を免れた。
戦後、東京水交社の建物と共に進駐軍に接収され、その後1981年、同地に新しくビルが建てられる事になったので、鳥居は財団法人水交会に返還され、同年6月15日、由縁深い東郷神社へ奉納。 - 東郷平八郎
-
日清戦争(1894~95)時には日本海軍防護巡洋艦(二等巡洋艦)(un navire de guerre)「浪速」の艦長(commandant)。
日露戦争(1904~1905)時には連合艦隊司令長官を務める。
ロシアのバルチック艦隊を撃破し、日本を勝利に導いた。
大正のはじめに元帥(un amiral en chef)に列せられ、1914年から7年間、東宮御学問所総裁として皇太子殿下裕仁親王(昭和天皇)の教育の大役を果たした。
1934年5月30日88歳で死去。
「真心は神に通じる」とその一生を貫かれた徳を後世に伝える為、元帥を祀る神社を創建したいと日本国内外から請願と献金が海軍省(le ministère de la marine)にもたらされた。
この熱意に応じて時の海軍大臣大角岑生(おおすみみねお)は、東郷神社を創建。
場所は、明治天皇にお仕えした東郷元帥を御祭神とするに相応しい明治神宮に近い元鳥取藩主池田公爵邸敷地に決まり、1940年5月28日鎮座。
しかし、戦火で焼失し1964年5月27日に復興。
戦禍を免れ、唯一創建時の姿を留めていた表参道大鳥居は建立から80年を経て老朽化が進んでいた為大修理を行なった。
表参道
- 歴史
-
1946~64年まで代々木公園や国立代々木競技場にはワシントンハイツがあった。
兵舎や米軍家族用集合住宅。
1953年には米軍からの依頼で、日本初となるスーパーマーケット「紀ノ國屋」誕生。
紀ノ國屋は元々1910年創業の高級果物店で、書籍販売の紀伊國屋書店とは歴史的にも資本的にも関係無い。
1964年にワシントンハイツが日本に返還されると、米軍関係者専用アパート跡に多くの日本人クリエイターが住み始めた。
業界人が多く集まる中、1972年にはオープンテラスカフェ「Café de Rope」が誕生し、芸能人やスポーツ選手が集まる場所となった。
また、地域条例により高さ制限30m及び、キャバレー、劇場、ホテル、パチンコ、風俗店も規制対象。
高層ビルが少なく、路面店が多い。
90年代の原宿ポップスタイルのイメージが「世界最先端の攻めた街」を印象付けている。
- 同潤会アパート
-
財団法人同潤会が1923年に発生した関東大震災の復興支援のため、耐火・耐震の鉄筋コンクリート構造で建設されたアパート。
同潤会アパートは近代日本における最初期の鉄筋コンクリート造集合住宅として貴重。
1924年から1933年の9年間に東京で13箇所2,225戸ものコンクリート造共同住宅が建設された。
青山アパートメントは1926年の竣工で、1945年の戦時下において空襲で焼けた街路樹に対して、アパートは防火壁の役割を担い、アパート前の欅(le zelkova)だけが戦火を免れた。
老朽化に伴い、多くのアパートは建て替えられた。
青山アパートメントも2003年には解体されたが、2006年には表参道ヒルズに付随する形で再建。
- 表参道ヒルズ
-
同潤会アパートの跡地に建設された複合施設。
全長250m、地上6階、地下6階で、4階以上は居住スペース。
設計は安藤忠雄。
元々、道路に挟まれた狭い敷地だったため高層建築を造るのが難しく、欅並木(la ligne de zelkova)の景観と調和させる(pour harmoniser)目的もあって、今の階層に至った。
- 裏参道ガーデン
- 1947年に建てられた古民家を改装した複合施設。
- スパイラル
SPIRAL -
フランス語ではLa spirale「螺旋」
1985年、株式会社ワコール100%出資の関連会社として建築家槇文彦氏によって設計された地上9階、地下2階の複合文化施設。
1階奥の吹き抜けに螺旋スロープ(La pente en spirale)があり、これが名称の由来。
ギャラリーと多目的ホール(la salle polyvalente)を中心にレストラン・バー、生活雑貨ショップ美容サロン等で構成。
「生活とアートの融合(La fusion entre la vie et l'art)」
をコンセプト(concept)に、現代美術やデザインの展覧会、演劇、ダンスなどの舞台公演、コンサート、ファッションショー、シンポジウム(symposium)、パーティなどに利用。
- プラダ青山店
-
2003年竣工。
設計はスイスのジャック・ヘルツォークとピエール・ド・ムーロン(Jacques Herzog et Pierre de Meuron)の建築家ユニット。
斜向かいのMIU MIUも2015年に設計。
元々はミニマル・アート(le minimalisme)という装飾を削ぎ落としたシンプルな造形だったが、建物表面を石で覆ったり、ガラス面に写真や絵画をプリントしたりと表層(la surface)の部分での試行を重ねて、注目を集めるようになった。
- Sunny Hills
-
2013年竣工の台湾資本のケーキ屋。
Une pâtisserie taïwanaise ouvert en 2013.
特に、パイナップルケーキが有名。
日本伝統の「地獄組み」を全面的に使用。
設計者の隈研吾氏が掲げたコンセプトは
「都市の中に森を作る(créer la forêt dans la ville)」
溝(la rainure)を彫った木材同士を組み合わせる(attacher)ことを木組みと言う。
釘(un clou)や接着剤(une colle)を使用しなくても、揺れ(un tremblement)や衝撃(un choc)を分散(se disperser)。
一般的な木組みはそれぞれの木材の片面に溝を彫って交差部分を噛み合わせる。
En général, on fait que des rainures à un côté.
木材は湿度が高ければ膨らみ、乾燥すると収縮する。
Le bois se dilate avec l'humidité, et se contracte pour le sec.
その変化を繰り返すと木材は曲がり、捩れ等を引き起こす。
Si ça répète plusieurs fois, le bois se déforme.
片面ばかりに溝がある相欠きは特に狂いが起きやすい。
Il y a des rainures à un seul côté, ça se déforme facilement.
一方、地獄組みは上下交互に溝を彫っているため、両面が同じように伸縮するので狂いが起きにくい。
Par contre, Jigokugumi, il y a des rainures à deux côté différents, c'est plus fort que celui-là.
地獄組は、一度組んだらバラすことが難しい。
Après attacher des bois, il est difficile de démonter.
木組みには岐阜県産檜材(cyprès)を使用。
木の目が細やかで均質な為強く折れにくく構造材にも最適。
La veine est délicat et homogène, donc c'est fort. - 3 地獄組とは
- 互い違いに溝が付いた木組みを上下に組み、最後に鍵の役割の棒材Mを差し込むことにより容易に解体することが出来ない木組みの種類。
- 4 木組みの役割
-
一見、建物の飾りのように見える木組みだが、この木組みは建物の構造部として大きな役割を担っている。
建物の後ろ半分のコンクリート躯体からはねだした木組みの梁(la poutre)は外の木組みに支えられ、床を支えている。
大きく分厚い壁や、太い柱ではなく、6cm角の細い檜の棒材がたくさん集まって建物を支えている。 - 5 岐阜のヒノキ
-
木目が細やかで均質な為、強く折れにくい。
湿気や火災にも強く、この建物に最適。
Sunny Hills南青山では岐阜県東濃地方の檜を使用。
特に品質が良いことで知られ、伊勢神宮の式年遷宮で外宮の用材として使用。
ちょうどここが建った年は式年遷宮の年と一緒だった為、節が少ない良質なヒノキの調達がとても大変だった。
ヒノキは伐採後200~300年の間、徐々に強度を増していくと言われ、日本最古の木造建築である法隆寺では1,300年以上前の創建当時の材木が現役で使われている。
木造建築は大切に使うと長持ちするだけでなく、二酸化炭素(le bioxyde de carbone)固定量を増やす。
計画的に植林、伐採されている国産の木材を使うと森林整備の促進による二酸化炭素吸収量の増加も期待できる為、木造建築は地球環境に優しい建築。
恵比寿
- 恵比寿
-
1887年、現在の恵比寿ガーデンプレイスのある場所に日本麦酒醸造有限会社(サッポロビールの前身)が設立。
玉川上水からの分水である三田用水がビール麦の発芽に最良の軟水(eau douce <=> 硬水eau dure)だった。
1889年、生業を守護して福を招くとされる恵比寿(七福神参照)信仰にちなんで、「ヱビスビール」が開発。
ビールが先で地名が後。
- SKY LOUNGE
-
恵比寿ガーデンプレイスタワー38階の展望ラウンジ「SKY LOUNGE」からは無料で東京タワーやレインボーブリッジを一望できる。
高さ160m
11:00~23:30
六本木
- 国立新美術館
Le centre national des Arts de Tokyo -
2007年開業。
地下1階、地上4階、敷地面積30,000㎡は日本最大。
来館者数は285万人(2 millions 850 milles)。
国立美術館の中で唯一常設コレクションを持たない美術館。
C'est un seul musée national qui n'a pas de la collection donc il n'y a pas d'exposition permanente.
設計は黒川紀章で鉄骨造の建物のコンセプトは、
「森の中の美術館(Un musée dans le forêt)」
美術館建築では自然光を取り入れすぎると作品が傷んでしまうが、展示エリアとオープンエリアを明確に分けることで、自然光の溢れる美術館になっている。
- 東京ミッドタウン
-
2007年、防衛庁跡地に建設された複合施設。
隈研吾の設計で、ミッドタウンタワーは地下5階、地上54階、高さ248mを有する。
| 1641年~1871年 | 萩藩毛利家屋敷 |
|---|---|
| 1873年~1945年 | 陸軍駐屯地 |
| 1946年~1960年 | 米軍将校宿舎 |
| 1960年 | 日本へ返還 |
| 1962年~1988年 | 防衛庁 |
| 2004年~2007年 | ミッドタウン建設 |
- 乃木神社
-
1912年に明治天皇が崩御し、葬儀が行われた20:00頃、妻静子と共に自刃。
御夫妻の忠誠心に感激した国民はこぞって乃木邸を訪れた。
昔は幽霊が出るほど寂しい場所だったことから「幽霊坂」と呼ばれていたが、以後「乃木坂」と変わる。
1913年、東京市長が中心となって乃木邸内に御夫妻の霊を祀った。
1923年に神社創建。
現在乃木家の墓は青山霊園内にある。 - 乃木希典(まれすけ)
1849~1912 -
日本の陸軍軍人(le soldat de l'armée de terre)。
日清戦争時には旅順要塞を1日で陥落。 - 旧乃木邸及び馬小屋
-
旧乃木邸は、1902年に新築されたもので、日清日露戦争に従事した乃木希典大将夫妻が1912年9月13日、明治天皇御大葬の日、明治天皇に従って殉死するまでここに住んでいた。
将軍がドイツ留学中に見たフランス軍隊の建物を模範にして自ら設計し建てたもので、明治期の洋風建築が接客を目的とする豪華な建物か、和風住宅に洋風の応接室を付属させたものが多いのに比べ、この邸宅は軍人の家らしく、飾り気がなく簡素で合理的に作られている。
本館は、168㎡、木造平屋建の日本瓦葺きで、正面玄関から見ると全体が2階建てに見えるが、傾斜した地形が巧みに利用され、実際は半地下も含め3階建ての構造。 -
馬小屋は、平屋建、日本瓦葺で、邸宅が新築される以前、1889年に建設。
間口12.5m、奥行4.5mの細長い建物には、4つに区画された馬房や馬糧庫等がある。
住居が木造であるのに対し、馬小屋が煉瓦造で立派だという評判もあり、馬を可愛がり大切にした大将の人柄が思われる。
邸宅と馬小屋は、1912年9月13日乃木夫妻殉死後、遺言で東京市に寄付され、現在は港区が管理。
夫妻の命日に合わせ毎年9月12日、13日に邸内を無料一般公開。 - 愛馬の由来
-
正馬壽号は「ステッセル」将軍の愛用した「アラビヤ」産の牡馬で1905年1月5日水師営会見の際に乃木大将に贈らんとしたが大将はその志を謝し直ちにこれを受け取ることは軍規の許さない事なので後日を約してこれを「壽」号と名付けて戦役中乗用し凱旋後払い下げを受け自分の馬として愛用した。
大将は壽号を1906年末に種馬として鳥取県赤崎町佐伯友文氏に贈った。
1915年5月同氏より鳥取県隠岐島村上寿夫氏に贈られ海士村渡辺淳三氏方で飼育中1919年5月27日に終命した。
馬齢23歳でその仔馬は20余頭に及んんでいる。
副馬「璞(はく、あらたま)」号は去勢馬で仔馬無し。 - 乃木大将と辻占売少年像
-
※辻占売り…おみくじ入り和菓子売り
今に伝えられる「乃木大将と辻占売りの少年」の話は、1891年、乃木希典が陸軍少将の時代、用務で金沢を訪れた折の事。
希典は金沢で偶然、当時8歳の今越清三郎少年に出会う。
今越少年は、辻占売りを営みながら一家の生計を支えていた。
この姿に感銘を受けた希典は、少年を励まし、金弐円を手渡した。
今越少年はこの恩を忘れる事なく、努力を重ね金箔業の世界で大きな実績を積み上げた。
この銅像は、こうした乃木希典の人となりを伝えるものとして、1968年に旧ニッカ池(六本木6丁目)の縁に造立されたが、この度旧ニッカ池周辺が整備されることとなり、希典所縁のこの地に移建された。 - 月桂樹
- 1902年頃「イタリア」に洋行した山口県の農学博士豊永直利氏より凱旋の際に寄贈されたもので、大将御手植えの木。
- 旧乃木邸の煙突
-
実際に旧乃木邸の屋根に設置されていた煙突の実物。
2011年の東日本大震災で被災した為、撤去。
現在、旧乃木邸の屋根にある煙突はレプリカ。 - 灯籠
- 石材は門柱として準備されたが適当ではなかった為、そのまま邸内に保存してあったものを死去後親族が灯籠として建てたもの。
- マックアーサーの植樹
- 終戦後マックアーサー将軍が植樹したアメリカハナミズキの樹。
- 乃木家祖霊社
- この小社には、乃木家祖先と御令息との御霊を祀る。
- 赤坂王子稲荷神社
- 創建…1962年12月22日
- 祭神…宇迦之御魂神(ウカノミタマノカミ)
- 祭神…宇気母智神(ウケモチノカミ)
- 祭神…和久産巣日神(ワクムスヒノカミ)
- 乃木将軍御夫妻又御両親崇敬特に篤く、月詣りまでされた北区王子に鎮座の王子稲荷神社を乃木神社戦災復興竣成を機に勧請した縁の神社。
- 楷樹(かいじゅ)
la même famille que pistachier -
1926年5月6日植樹
林学博士・中村弥六氏の奉納直樹と伝えられている。
1915年日本で最初に白沢保美博士が中国山東省曲阜県の孔子廟の子貢より種子を持ち帰り、育成された由緒正しい楷で、神田湯島聖堂と岡山県閑谷学校の楷と同系統のもの。
楷とは樹姿端正で一点一画が整っていることから書法の楷書(le style régulier)の語源になっている。
また境内には昭和天皇後在位60年の記念樹の楷樹もある。 - 教育の碑
-
明治天皇御製
教育
いさをある人を
をしえの親にして
おほしたてなむ
やまとなでしこ
1907年1月に御祭神乃木将軍が学習院院長に任命された頃に生徒心得の為に明治天皇より賜った御製。
乃木将軍の様な国家に勲功のある立派な人を学習院院長にして、大切な皇国の未来を担う子弟の教育に当たらせたいという明治天皇の気持ちが込められている。
この碑は当時の御歌所所長・高崎正風氏が謹書したものを刻んだ。 - 雷神木
-
1972年9月12日19時落雷あり。
本殿に多大な損害を被る処、この楠が身代わりとなり、その一撃を受け樹片境内に飛散するも本殿に一つとして損ずる事無し。
その後もこの楠は枯れる事なく活気旺盛の霊力を示したり、それよりこの楠を雷神が宿り、悪事災難を取り除く雷神木と称する。 - さざれ石
- 国歌「君が代」に歌われる細石で、1978年8月24日、岐阜県から寄贈された。
- ナンダモンダ
- 麻布十番商店街にある入山酒店の入山忠正氏により奉納された閃緑岩(le diorite)、通称菊面石。
- 正松(せいしょう)神社
- 創建…1963年1月22日
- 祭神…玉木文之進正韞命(タマキブンノシンマサカヌノミコト)
- 祭神…吉田矩方松陰命(ヨシダノリカタショウインノミコト)
-
玉木文之進先生は長州萩の学者で、松下村塾の開祖で、吉田松陰の叔父。
乃木将軍は松陰先生の弟弟子として玉木先生に薫陶せられ、また松陰先生を深く敬い、人格形成の基になった。
乃木神社戦災復興竣成を機に萩の松陰神社より二柱の分霊を請受け、境内に鎮座した。
| 屋根裏 | 夫婦の居室・物置・書庫 |
|---|---|
| 1階 | 応接室・客室・次室・来賓室・大将居室・夫人居室 |
| 半地下 | 台所・茶の間・納戸・浴室・書生部屋・女中部屋 |



- 六本木ヒルズ
-
2000年2月起工→2003年3月竣工の複合商業施設。
高さ238mのオフィスビルを中心に集合住宅、ホテル(グランドハイアット東京)、テレビ朝日本社ビル、映画館が入る。
六本木ヒルズ森タワーの設計はアメリカの建築事務所Kohn Pederson Fox Association(KPF コーン・ペダーセン・フォックス)が担当。
53階は森美術館で、森ビル株式会社をはじめ、
Apple Japan
Ferrari Japan
株式会社ポケモン
などが入る。 - 六本木ヒルズの巨大蜘蛛
-
フランス人彫刻家Louise Bourgeoisによるブロンズ像。
タイトルは「Maman」で、胴体に大理石の卵を入れた袋を持つ。
- 麻布山善福寺
- 創建…824年
- 本尊…阿弥陀如来
- 宗派…浄土真宗本願寺派
- 開基…空海
-
善福寺本堂は、当初東本願寺八尾別院大信寺の本堂として建設された建物を移築して、1961年に現在地で組み上げた。
大信寺は慶長年間(1596~1615)の創建で、移築された本堂は1767年に再建。
再建の際に創建当初の柱等建築部材を一部利用した。
正面幅28m、奥行34m。
入母屋屋根、桟瓦葺。
広い外陣と装飾性豊かな内陣、内陣の正面を華やかな欄間彫刻で飾り、金、極彩色で仕上げ、浄土真宗特有の形式を取る。
組物は尾垂木付の二手先。
1788年、天明の大火で京都の東本願寺が焼失したので、同年から1798年まで東本願寺へ移築されて御影堂として使用されたが、翌年八尾別院に再建された。
本建築は江戸時代の大規模な浄土真宗の本堂の構成を良く示す都内有数のものであり、また3度の移築を経る等、特殊な履歴も含めて、大変に貴重な建築。
赤坂
- 豊川稲荷東京別院
- 創建…1828年
- 本尊…豊川吒枳尼真天
- 宗派…曹洞宗
- 開基…大岡忠相
-
大岡越前守忠相が豊川稲荷から吒枳尼天(ダキニテン)を勧請し、屋敷稲荷として自邸に祀ったのが起源。
大岡忠相は、江戸時代中期の幕臣(haut fonctionnaire)で、9代将軍徳川家重の側近(un entourage)としても活躍。
大岡家は代々豊川稲荷を信仰しており、愛知県豊川市豊川町の豊川稲荷を勧請。
大岡越前守は江戸南町奉行としての活躍や、旗本から大名へ取り立てられたことでも有名。
故に江戸の豊川稲荷も立身出世や盗難避け、遺失物・失踪人などに定評あり。
また、明治期以降の赤坂は料亭や芸者などが集まる花柳界が発展し、芸道を生業とする人々からも信仰を集めた。
現在も芸能人が多く参拝。
ちなみに、豊川稲荷は「妙厳寺(みょうごんじ)」という曹洞宗の寺で、神社ではない。
豊川吒枳尼真天が稲穂を荷い、白い狐に跨っていることから、稲荷という名がついた。 - 子宝観音
-
子宝を授けてくださる観音様。
子供の誕生、子孫繁栄(la prospérité de la descendance)を願う。 - 招福利生大黒天
-
2008年5月鎮座。
豊川吒枳尼真天の化身。
真言「オンシラバッタニタニリウンソワカ」(除災・招福)の意。
- ホテルニューオータニ
日本庭園 - 開園時間…6:00~22:00
- 面積…3ha
- 春…椿、桜
- 夏…百日紅、躑躅、皐、紫陽花
- 秋…萩、紅葉
- 冬…山茶花、寒椿
- 16世紀後半に加藤清正の下屋敷、後に井伊家中屋敷の庭園を経て今に至る。
- 赤玉石
-
佐渡金山より運ばれた庭石で、赤褐色の独特な色彩から「赤玉石」と呼ばれる。
庭園内最大は22トンあり、日本一の大きさ。 - 枯山水
-
庭園内の一部は枯山水を模った様式。
松樹と大小の石で山の雰囲気を表し、白砂利は水を表し、小波の如く線が引かれている。 - クロマツの化石
le fossile de pin noir -
湧水山水風の池の中にある江戸時代からの大木の化石。
加藤清正時代から残り、木の根がそのまま化石化した石。
庭園内には4個の化石がある。 - 紀尾井窯
- 日本庭園で日本文化に親しんでもらう為、陶芸の窯を設け「紀尾井窯」と名付けた。
- ガーデンチャペル
-
毎朝8:30~10:00までの自由会。
日曜日は8:30~9:30まで礼拝の他、朝食会やバイブルスタディも行われる。 - 和楽庵
-
茶室の名前の由来は、人を心広く受け入れ和すること、人に楽を捧げ自らも楽しむこと。
1953年、英国エリザベス女王戴冠式に出席された当時の皇太子殿下の御帰朝祝茶会の為、日本橋白木屋に数寄屋師三代目木村清兵衛が建てたものを移築。 - 大谷米太郎像
1881~1968 -
富山県出身の実業家、元力士、ホテルニューオータニ創業者。
31歳で上京し、力士にスカウトされる。
手指の障害を理由に昇進できずに引退。
酒店を起業し、国技館と取引を行う。
1919年、弟と鉄鋼業起業、戦時中の鉄鋼需要により成功。
1964年の東京五輪に合わせてニューオータニを開業。 - ぬれさぎ灯籠
- 江戸時代の形式と大きさをそのまま残した灯籠。
- カヤ
un conifère(針葉樹) - 清泉亭前に位置する1780年代の樹木。
- 寛永寺灯籠
- 江戸時代に造られた上野寛永寺の灯籠を大谷米太郎が購入。
- イヌマキ
- 清泉亭前に位置する1780年代の樹木。
- 春日灯籠
- 鎌倉時代形式で、六角形には十二支の動物がそれぞれの方向を向いて刻まれている。
- 伝統工芸青山スクエア
Japan Traditional Crafts Aoyama Square -
経済産業大臣指定の全国の伝統的工芸品を取り扱うギャラリー&ショップ
東京都港区赤坂8-1-22
🕐11:00~19:00
📞03-5785-1301
公式サイト
永田町
- 永田町
-
内閣総理大臣官邸(la résidence officielle du Premier ministre)、
内閣府(le bureau du Cabinet)、
国会議事堂(le bâtiment de la Diète nationale)、
各政党の本部(le siège de plusieurs partis)が所在。
300世帯、500人ほどが居住。
江戸時代初期に日枝神社門前に旗本の永田伝十郎ら永田姓を名乗る家があったことで地名の由来となる。
江戸城から近く、井伊直弼をはじめ多くの大名屋敷があった。
1872年以降、陸軍省(le ministère de la Guerre)、参謀本部(l'état-major général)などの陸軍中枢が置かれた。
1936年に国会議事堂が完成すると、政治中枢が一気に集中。
永田町=政治というイメージが定着した。
- 国会議事堂
Palais de la Diète -
1881年、明治天皇が国会開設を指示。
1936年完成。それ以前は霞ヶ関一丁目の仮議事堂。
国会は国唯一の立法機関。
地上3階(中央部4階、中央塔9階)、地下1階、鉄骨鉄筋コンクリート造り。
敷地面積103,007㎡
建物面積13,356㎡(延べ面積53,464㎡)
長さ(南北)206.36m/奥行き(東西)88.63m/高さ(中央塔)65.45m
工事費25,735,977円(現在価格62,000,000,000円)
総作業員数2,540,000人
建築年月1920年1月着工→1936年11月完成
第70回帝国議会(昭和11年12月24日召集、26日開院式)から使用。
議事堂内は欅や桜の彫刻を施し、マイクが無くても音の反響が大きい。
花崗岩や大理石を使用。
ステンドグラスはアメリカ、ドイツ、イギリスから、ドアノブ(鍵)はアメリカから輸入。
廊下のポストは4階から地下1階まで筒状になっている。
参議院では平成10年1月召集の第142回国会から、本会議の採決について、従来の方式に加え、新たに押しボタン方式が導入された。
中央広間には板垣退助(1837~1919)、大隈重信(1838~1922)、伊藤博文(1841~1909)の銅像が鎮座している。
4人目の台座が空位なのは、「政治に完成はない、未完の象徴」を意味する。 - 議事堂の歴史
-
1881年10月12日に国会開設の勅諭が発せられた後、1886年2月、内閣に臨時建築局が設けられ、ドイツから技師を招き、日本からは技師と職人をドイツに留学させた。
第1次仮議事堂…1890~1891年→焼失
第2次仮議事堂…1891~1925年→焼失
第3次仮議事堂…1925~1936年
| 衆議院 下院 Le député |
議会 | 参議院 上院 Le sénat |
|---|---|---|
| 465 | 議席 | 245 |
| 4年 | 任期 | 6年 |
- 東京地方裁判所
Le tribunal du district de Tokyo - 本庁は東京高等裁判所・東京簡易裁判所(刑事)も同居する地上19階・地下3階建ての合同庁舎。
丸の内
- 東京駅
- 常盤橋門
- 将門塚
- 和氣清麻呂
- 震災イチョウ
- パレスサイドビルディング
- 東京国際フォーラム
- 白marunouchi
- 江戸に幕府を開いた理由
- 皇居
- 東御苑
- 和田倉門
- 二重橋
- 楠木正成像
- 桜田門
- 田安門
- 清水門
- 日本武道館
- 東京国立近代美術館
- 千鳥ヶ淵
- 東京駅
-
1914年12月20日開業。
辰野金吾による設計。
アムステルダム中央駅を模したと言われているが、辰野が英国留学経験もあり、ロンドンのターミナル駅を参考にした説もある。
8,000,000の煉瓦組み、化粧用940,000使用。
1923年の関東大震災ではほとんど被害を受けなかったが、第二次世界大戦中の1945年5月25日に戦火により焼失。
1947年3月に2階建て四角屋根(le toit carré)として復旧。
2007年から2012年にかけて丸の内駅舎を創建当初の姿に復元する工事が行われ、ドーム型屋根(le dôme)復興。- 財閥…Le conglomérat industriel
- 財閥解体…Le démembrement des zaibatsu
- 常盤橋門
-
常盤橋門は、1629年に出羽・陸奥の大名によって築造された。
門は江戸城諸門の中でも奥州道中につながる江戸五口の一つで、浅草口、追手(大手)口とも呼ばれた。
江戸城内郭の正門である大手門に接続することから、軍事上重要な門に位置付けられた。
門の構造は、内枡形門形式の枡形門で、北側に渡櫓とそれを支える石垣があり、門をくぐった先には大番所が配置された。
また、東側には冠木門(かぶきもん)が構えられており、それ以外の三方は土手が巡らされていた。
明治以降、常盤橋門の建物は破却された。
残った枡形石垣の一部と1877年に架けられた常磐橋(石橋)、橋の石積部分は1928年に国の史跡に指定されている。
- 将門塚
-
平将門の首を供養する旧跡。
将門塚を動かした会社や役所では火事や事故が多発。
藤原秀郷に討たれ、京都三条河原に晒された首は空を飛んで江戸へ戻り、現在の千代田区内に辿り着いた。 - 平将門
903~940 -
関東の豪族(un clan)。
桓武天皇の曾孫の孫。 - 935年…叔父の平国香と対立。
- 939年…関東の国府を攻め落とす。
- 940年…藤原秀郷(ひでさと)に敗北。
- 序章
-
平安時代は貴族政治社会。
貴族は京都に住み、地方への関心が薄い。
国司(役人fonctionnaire)を地方へ派遣したが、多くの国司は私利私欲に走り、農民を苦しめた。
Le fonctionnaire n'agit que par intérêt.
そんな中、地方の豪族たちは自分たちの土地を守るようになり、次第に「武士」として成長。 - 平将門
-
亡き父の領地を叔父(un oncle)に奪われそうになる。
国司の暴政(la tyrannie)に対する不満。
自分の土地は自分で守る。
将門は朝廷のルールに反し、自らを新皇と名乗り(se nommer)、朝廷とは別の国を作ろうとした。
結果、朝廷から反逆罪(la haute trahison)に問われ、討伐されてしまう。 - 影響
-
武士の力が認められた。
鎌倉幕府へと繋がる。
「朝廷に逆らうと怖い」という認識が広まった。
- 和氣清麻呂公銅像
733~799 -
貴族であり天皇の側近。
769年に道鏡の皇位就任の野望を挫き、流刑に処されるも復帰。
1940年に紀元2600年記念事業として建立。
※紀元前660年が神武元年。
楠木正成公銅像とともに、文武の二忠臣を象徴。 - 宇佐八幡宮神託事件
-
道鏡が「自分が天皇になれば国が安泰する」という神託を授かったと主張。
称徳(しょうとく)天皇は和気清麻呂を九州の宇佐八幡宮へ派遣し、真偽を確かめさせた。
清麻呂は「皇位へは必ず皇族が継ぐべきであり、道鏡のような無道の者は排除せよ」という神託を受け、これを天皇へ提示。
これを聞いた道鏡は怒り、清麻呂を流罪に処した。
しかし、翌年称徳天皇が亡くなると、清麻呂は都に呼び戻され、名誉を回復した。
道鏡は失脚し、光仁天皇が即位して天皇の血統は守られた。

- 震災イチョウ
-
かつて現在のパレスサイドビル付近にあった銀杏。
1923年の関東大震災で一帯は焼け野原になったが銀杏は奇跡的に生き残った。
しかし、帝都復興計画で切り倒されることになる。
そこで中央気象台長の岡田武松が帝都復興局長官の清野長太に樹木保存を申し出て合意。
1860年植樹。

- パレスサイドビルディング
-
1966年に竣工した毎日新聞社本社が入るオフィスビル。
屋上は平日11:00~15:00解放され、土日祝日及び雨天時には閉鎖。
屋上で飲食やスポーツは禁止。 - 毎日神社
-
1939年10月20日、毎日新聞社機「ニッポン」号による同社主催世界一周大飛行の完成記念として創建。
祭神は天照大神・産土神日枝大神ならびに飛行の平安完遂を祈願し全国読者から寄進の御神符が奉安されている。
同航空機は中翼単葉の双発機で翼長25m・全長16mの純国産。
当時の日本航空科学の粋を集めて製作された。
全航程53,000kmの北太平洋横断無着陸飛行に成功。
空の難関と言われた南米アンデス越えの新記録や大西洋横断の快記録など、世界航空史に不滅の光彩を放っている。
- 東京国際フォーラム
-
公的総合文化施設。
Le centre de conférences.
設計はウルグアイ出身のアメリカで活動した建築家Rafael Vinoly(ラファエル・ヴィニョリ)。
architecte uruguayen a fait le tracé.
地下は3階まであり、地上はホール棟11階、ガラス棟7階で高さは60m、敷地面積は27,000㎡ある。 - 太田道灌
1432~1486 -
室町時代中期の武将。
江戸時代には土佐藩と阿波藩の上屋敷があった。
1456年に扇谷上杉氏の家臣だった太田道灌が江戸城築城。
1957年に開都500年を記念して像設置。
1991年に新宿へ都庁移転。
1997年の東京国際フォーラム建設を経て、像は現在地に設置。
太田道灌は今も、皇居(旧江戸城)の方角を望んで立つ。
製作者は彫刻家の朝倉文夫。
- 白 marunouchi
-
1870年、京都で旅館として創業し、現在料亭としても知られている「和久傳」が手掛けるカフェ、ショップ、ギャラリー。
和久傳の社長が陶芸家の辻村史朗氏と縁があり、同氏の作品を料亭でも使用。
氏は奈良県生まれで現在も奈良県にて制作を行う。
師もおらず、弟子もとらず、主だった受賞歴も無い、特定の流派を持たない独自の作風が魅力的。
ロバートデニーロやエリッククラプトンも所有。
東京都千代田区丸の内3-3-1
🕐11:00~18:00/日月定休日
📞03-3240-7072
公式サイト
徳川家康が江戸に幕府を開いた理由
- 豊臣秀吉の命令
-
織田信長亡き後、跡を継いで天下を統一した豊臣秀吉。
徳川家康は豊臣秀吉が唯一勝てなかった相手。
秀吉全国統一の際、家康とは和睦という形をとった。
秀吉は家康を大阪から遠い関東へ配置し、物理的に遠ざけ、労力を消耗させようとした。
当然、豊臣派の勢力は大阪をはじめ西日本に多く、家康としても距離をとりたかった。 - 地の利
-
当時既に鎌倉や小田原は城下町として出来上がっていた。
しかし、周りを山に囲まれた天然の要塞は防御面では申し分ないが、物流に難があった。
その点、当時平野と海と大きな河川が揃っていた江戸は都市の発展に最適。
18世紀における江戸の人口は1,000,000人と言われており、当時のパリ550,000人、ロンドン870,000人に比べるとよくわかる。 - 徳川家康の功績
-
江戸のインフラ整備。
aménager l'infrastructure.
- 皇居
Le palais impérial -
1457年、室町時代の武将、太田道灌が江戸城築城。
上杉氏を経て、徳川家康の居城となり、江戸城の拡張(élargissement)が始まる。
1637年、3代目将軍家光治世に一旦完成。
1657年の明暦の大火によって天守を含め城の大部分を焼失するも、街の復興を再優先した為、天守の再建は成らなかった。
1867年の大政奉還後、1868年に明治天皇が入城。
以後、天皇の居城として機能。
面積115ha(1,150,000㎡)
一周5Km
- 東御苑
-
旧江戸城の本丸(le noyau du château)、二の丸(deuxième cercle)、三の丸(troisème cercle)の一部を宮殿の造営に合わせて、皇居附属庭園として整備されたもので、1968年から公開。
21ha(210,000㎡) - 大手門
-
江戸城本丸の正門で、諸大名がこの門から登城。
城門警護は10万石以上の譜代大名が務めた。
門の建設は1606年に藤堂高虎が行ったとされ、1657年明暦の大火で焼失した後1659年に再建。
現在の門は、手前の高麗門が1659年、渡櫓門は1966年に再建。
正面の高麗門をくぐると石垣を四角く巡らして直進できないようにされており、右側に渡櫓門という武器庫があった。
大小2つの門に囲まれた枡形は、侵入する敵を阻止・攻撃し易い構造。
大きい方の門は、1945年4月の空襲で焼失し、1967年に復元。
焼失前の門の屋根に飾られていた鯱には、頭部に「明暦三丁酉(ひのととり)」と刻まれている。
これは、1657年の明暦の大火の後、江戸城再建時に製作された鯱であることを意味する。 - 同心番所
-
「番所」とは警備詰所のこと。
江戸城の番所で、百人番所、大番所、同心番所が残る。
ここには主に「同心」と呼ばれる武士が詰め、登城者の監視に当たった。
屋根瓦には、皇室の菊の御紋や徳川家の葵の紋も見られる。 - 百人番所
-
江戸城本丸への道を厳重に守る大手中之門に向き合って設けられた警備詰所。
甲賀組、伊賀組、根来組、二十五騎組という4組の鉄砲百人組が昼夜交替で勤務。
各組は20人の与力と100人の同心で構成。
例えるなら、与力は警察署長で同心は実働部隊の警察官。 - 皇居内石垣
-
皇居内の石垣は特別史跡「江戸城跡」に指定されている。
「本丸中之門石垣」修復工事は2005年8月から2007年3月にかけて実行。
石垣には、江戸城の中でも最大級の巨石が使われ、布積みという技法が用いられている。
この中之門石垣には、本丸御殿への登城口として渡櫓門が配置。 - 大番所
-
大手中之門の内側に設けられていた警備詰所。
ここには位の高い武士が勤務。
この番所は、明治期に改築され、作業所として使われたが、1968年に江戸時代の姿に復元。 - 富士見櫓
-
「櫓」は城の防御施設。
かつて江戸城には多くの櫓があったが、現存する櫓は、富士見櫓、伏見櫓、巽櫓の3つ。
富士見櫓は明暦の大火(1657)で焼失したが、その後間もなく再建され、天守の代用としても使用。
将軍が富士山や両国の花火、品川の海を眺めた。 - 1923年関東大震災による被災
-
関東大震災により、外壁の剥落や瓦が破損。
1925年の修復で柱や梁を筋交い等で補強し、土壁・漆喰仕上げをモルタル下地・白セメント仕上げに替え、屋根瓦を修理。 - 1966~67の修理
-
1968年の皇居東御苑公開に先立ち1966~67年で修理。
外壁を白セメント仕上げから漆喰仕上げに替え、屋根瓦も修理。 - 富士見櫓の防御設備
-
富士見櫓は江戸城本丸の南隅の、高さ15mの石垣の上に設けられた防御施設。
各階の窓は、鉄砲や矢で攻め手を攻撃する為の拠点だった。
ただし、江戸城は攻撃を受けた事がないので、富士見櫓は実際に戦いに使われていない。 - 松の大廊下跡
- 襖戸に松と千鳥が描かれた長い畳敷きの廊下で、赤穂浪士討ち入りに繋がった事で知られる浅野内匠頭長矩の吉良上野介義央への刃傷事件(1701年)があった場所。
- 富士見多聞
-
「多聞」は長屋造りの防御施設。
江戸城には多くの多聞があったが、現存するのはこの富士見多聞と、伏見櫓の左右にある多聞のみ。
現在の富士見多聞は、江戸城の多くの建物が焼失した明暦の大火後、諸建物が再建された時に建てられた。
「御休息所前多聞」とも言う。 - 石室
-
この場所は江戸城本丸御殿の大奥の脇に当たる。
用途は火事などの非常時に、大奥用の調度などを避難させた場所。 - 竹林
-
この竹林は上皇陛下のお考えから、1996年に整備された。
昭和天皇へ、そのお印であった「若竹」にちなみ、喜寿の記念に宮内庁職員から献上。
日本と中国の竹・笹類13種類が植えられている。 - 旧江戸城天守台跡
-
徳川家康入城以来江戸城では、
- 慶長度天守(1607年)家康
- 元和度天守(1623年)秀忠
- 寛永度天守(1638年)家光
最大規模の寛永度天守は、地上高58m。
この天守台は、寛永度天守が明暦の大火(1657年)により焼失した後、天守再建を目指して1659年に築かれたものだが、幕府内で天守は不要との結論が下され、この天守台には天守が建てられないままになった。
江戸時代の江戸城は、天守があった50年間の後、天守が無い状態が210年間続いたことになる。 - 江戸城本丸御殿
- 本丸御殿は、表、中奥、大奥という三つの空間に分かれていた。
- 表…将軍の謁見など公的な儀式・行事、幕府諸役人の執務の場
- 中奥…将軍の日常生活、政務を執る場
- 大奥…御台所と呼ばれた将軍の正妻をはじめ家族や女性たちの生活の場
- 江戸城寛永度天守復元模型(縮尺1/30)
- 日本一高層の天守
-
江戸時代、この場所が江戸城の中心本丸だった。
江戸時代初期、本丸に3度天守が築かれた。
この模型はその内の最後にして最大規模の寛永期(1624~44)の天守の復元。
五重6階の建物と石垣の天守台を合わせた高さは60m、20階建てビルに相当し、この天守は日本に存在した全ての城の中で最も高い天守だった。
建物の壁は銅板と漆喰、破風には飾り金具が付き、屋根は銅瓦葺で、最上の棟に金色の鯱が輝いていた。
南側の小天守台から石段を登り、天守内に入った。
本丸の標高を入れると80mになる。
寛永期天守の天守台には、伊豆石という黒い石材が用いられたが、再建天守台の外周の石材は、寛永期とは異なる白い安山岩が用いられた。
再建天守台の内側などの一部には黒い石材が用いられているが、寛永期のものを再利用したと考えられる。 - 桃華楽堂
-
1966年2月、音楽好きの香淳皇后(昭和天皇の皇后)の還暦記念として建てられた200名収容の音楽ホール。
テッセン(la clématite)の八弁花(le pétale)を象った屋根。 - 桃華楽堂の由来
- 香淳皇后の誕生日が3月6日で桃の節句
- 華の字形が「十」6個と「一」1個で構成され、還暦(数え年61歳)を暗示
- 香淳皇后のお印が「桃」
-
外壁のモザイクタイル(la mosaïque murale)は、各面とも大きく羽ばたく鳥を抽象的(abstrait)に描き、
正面に「日月星」
正面左手前が「衣食住」
正面右手前が「松竹梅」
奥側は左から「風水火」「春夏秋冬」「鶴亀」「雪月花」そして松竹梅の右隣が「楽の音」
設計は今井兼次。 - 汐見坂
-
徳川家康による江戸城築城の頃は、この場所の近くにまで日比谷入江(une anse)が入り込み、この坂から海を眺める事ができたことから「汐見坂」の名が付いた。
この坂は、本丸と二の丸を繋いでおり、坂上には汐見坂門が設けられていた。 - 二の丸庭園
-
江戸時代の二の丸には、茶人兼建築家兼作庭家の小堀遠州が造り、三代将軍家光の命で改修された庭園があったが、度々の火災で焼失。
現在の回遊式庭園は、九代将軍家重の時代に描かれた庭絵図面を元に復元されたもの。
庭園の一角の菖蒲は5月下旬から6月頃が見頃。 - 二の丸池
-
二の丸池には、コウホネ、ヒメコウホネ、ヒツジグサ、アサザの4種類の水生植物が生育している。
初夏から秋にかけて水面を覆い、それぞれ黄色や白色の花を咲かせる。
コウホネは御所の池から、アサザは赤坂御用地の池から株を移した。 - アザサ
-
ミツガシワ科
5月中旬〜10月中旬
黄色の花 - コウホネ
-
スイレン科
4月下旬〜9月下旬
黄色い花
河骨の名は、川に生え、根茎が白骨のように見えるから。 - ヒメコウホネ
-
スイレン科
5月中旬〜9月下旬
黄色い花 - ヒツジグサ
-
スイレン科
5月下旬〜10月下旬
白色の花
未草の名は、未の刻(午後2時)に開くことに由来するが、開花時間は必ずしも一定しない。 - 諏訪の茶屋
-
1912年に明治天皇の命により皇居内吹上地区に建設。
その場所に、江戸時代に諏訪社があったことから「諏訪の茶屋」という名前が付いた。
1968年に現在の場所へ移築。 - 都道府県の木
-
1968年の皇居東御苑公開に際し、都道府県から寄贈された各「都道府県の木」を植樹。
また、沖縄県の木は本土復帰した1972年に植樹。
2017年に再整備を行い、現在32種類の木々が見れる。 - 梅林坂
-
この地に最初に城を築いた太田道灌がこの辺りに天神社を祀り、数百株の梅を植えたことから「梅林坂」の名が付いた。
現在70本の梅が12月末から2月まで楽しめる。 - 北桔橋(はねばし)門
-
本丸北端に位置し、緊急時に跳ね上がる構造だった事が由来。
この地域は北の丸から本丸に続く台地を掘って深い濠を築いた為、高さ20m以上の石垣がある。
また、半蔵門から江戸城内に入った玉川上水は、この門から2本の水道管で本丸に水道を引き込んでいた。 - 竹橋御門
-
竹橋御門は、旧江戸城内曲輪15門の一つで、1590年、徳川家康江戸入国の頃「竹を編みて渡されしよりの名なり」と、その由来が伝えられているが、他にも諸説あり、竹橋の架設時期と併せ、いずれも定かではない。
御門を通る道は、桜田門外の変により一時閉鎖されるが、1870年再開通し、今の通称代官町通りへと変遷。
沿道の様子は、時々の社会情勢を色濃く映し、戦後は、都心の交通・文化・観光のアクセスとして発展し、この地を巡る皇居周回ジョギングは、全国的な健康増進気運を高め、親しまれている。
現在のアーチ型竹橋は、1926年、帝都復興事業で架設され、1993年3月、周辺景観との調和や補強を目的に改修を受け、白・黒・桜の御影石の橋に、装いを新たにした。 - 竹橋門跡
-
門の名は、竹で編んだ橋が最初に架かっていた事に由来。
門は1620年、仙台藩主伊達政宗他6名の大名によって築造。
この門は、北の丸の東の出入り口にあたり、山王日枝神社と神田明神の天下祭りの山車行列は、この門を通過した。
竹橋門の石垣の多くは撤去されているが、この門の脇から平川門に通じる帯曲輪という通路や濠石垣は良好に残っている。
1926年に帝都復興事業で架設された現在の橋は、ほぼ江戸時代と同位置に架橋。 - 太田道灌追慕の碑
-
1936年、太田道灌公没後450年を記念して建立。
2007年、道灌公が1457年に江戸城を築城して550年。
これを記念し。東京都と千代田区の繁栄の基礎を築いた太田道灌公の遺徳を偲んで顕彰の標とする。
| 1 | 北海道 | エゾマツ(マツ科) | un épicéa local |
|---|---|---|---|
| 2 | 青森県 | ヒバ(ヒノキアスナロ)(ヒノキ科) | |
| 3 | 岩手県 | ナンブアカマツ(マツ科) | le pin rouge local |
| 4 | 宮城県 | ケヤキ(ニレ科) | le zelkova |
| 5 | 秋田県 | アキタスギ(ヒノキ科) | le cyprès local |
| 6 | 山形県 | サクランボ(せいようみざくら)(バラ科) | le cerisier |
| 7 | 福島県 | ケヤキ(ニレ科) | le zelkova |
| 8 | 茨城県 | ウメ(バラ科) | le prunier |
| 9 | 栃木県 | トチノキ(ムクロジ科) | |
| 10 | 群馬県 | クロマツ(マツ科) | le pin noir |
| 11 | 埼玉県 | ムサシノケヤキ(ニレ科) | le zelkova local |
| 12 | 千葉県 | イヌマキ(マキ科) | |
| 13 | 東京都 | イチョウ(イチョウ科) | le ginkgo |
| 14 | 神奈川県 | イチョウ(イチョウ科) | le ginkgo |
| 15 | 新潟県 | ユキツバキ(ツバキ科) | |
| 16 | 富山県 | タテヤマスギ(ヒノキ科) | |
| 17 | 石川県 | アテ(ヒノキアスナロ)(ヒノキ科) | |
| 18 | 福井県 | マツ(マツ科) | le pin |
| 19 | 山梨県 | カエデ(ムクロジ科) | un érable |
| 20 | 長野県 | シラカバ(カバノキ科) | le bouleau blanc |
| 21 | 岐阜県 | イチイ(イチイ科) | un if |
| 22 | 静岡県 | モクセイ(モクセイ科) | |
| 23 | 愛知県 | ハナノキ(ムクロジ科) | |
| 24 | 三重県 | ジングウスギ(ヒノキ科) | |
| 25 | 滋賀県 | モミジ(ムクロジ科) | un érable |
| 26 | 京都府 | キタヤマスギ(ヒノキ科) | |
| 27 | 大阪府 | イチョウ(イチョウ科) | le ginkgo |
| 28 | 兵庫県 | クスノキ(クスノキ科) | le camphrier |
| 29 | 奈良県 | スギ(ヒノキ科) | le cèdre |
| 30 | 和歌山県 | ウバメガシ(ブナ科) | |
| 31 | 鳥取県 | ダイセンキャラボク(イチイ科) | |
| 32 | 島根県 | クロマツ(マツ科) | le pin noir |
| 33 | 岡山県 | アカマツ(マツ科) | le pin rouge |
| 34 | 広島県 | モミジ(ムクロジ科) | un érable |
| 35 | 山口県 | アカマツ(マツ科) | le pin rouge |
| 36 | 徳島県 | ヤマモモ(ヤマモモ科) | |
| 37 | 香川県 | オリーブ(モクセイ科) | un olivier |
| 38 | 愛媛県 | マツ(マツ科) | le pin |
| 39 | 高知県 | ヤナセスギ(ヒノキ科) | |
| 40 | 福岡県 | クルメツツジ(ツツジ科) | |
| 41 | 佐賀県 | クスノキ(クスノキ科) | le camphrier |
| 42-1 | 長崎県 | ツバキ(ツバキ科) | le camélia |
| 42-2 | 長崎県 | ヒバ(ヒノキ)(ヒノキ科) | |
| 43 | 熊本県 | クスノキ(クスノキ科) | le camphrier |
| 44 | 大分県 | ブンゴウメ(バラ科) | |
| 45-1 | 宮崎県 | フェニックス(ヤシ科) | |
| 45-2 | 宮崎県 | ヤマザクラ(バラ科) | |
| 45-3 | 宮崎県 | オビスギ(ヒノキ科) | |
| 46-1 | 鹿児島県 | カイコウズ(マメ科) | |
| 46-2 | 鹿児島県 | クスノキ(クスノキ科) | le camphrier |
| 47 | 沖縄県 | リュウキュウマツ(マツ科) |
- 和田倉門
-
1620年に構築され「蔵の御門」とも呼ばれた。
和田(わた)とは、海の名称で「わたつみ」と同じ意義で、日比谷入江に望んで倉が並んでいた事が由来。
和田倉噴水公園は1961年造園。
- 二重橋
-
手前の「正門石橋」と奥にある「正門鉄橋」の二つの橋を総称して二重橋と呼ばれるが、厳密には奥の橋を指す。
江戸時代、堀が深かったため、橋桁を上下2重にして強度を上げた事が由来。
1888年に鉄橋に建て替え二重ではなくなった。 - 楠木正成像
Masashige Kusunoki
1294~1336 -
14世紀に後醍醐天皇を補佐(Il a assisté l'empereur Godaigo)した武将。
鎌倉幕府は北条が支配(dominer)し、民衆に圧政(tyrannie)を敷いた。
後醍醐天皇は1,000以下の兵力で数十万(plus de cent milles)の鎌倉幕府を相手に開戦。
当然敵うわけもなく、絶体絶命(tomber dans une situation désespérée)の節に見た夢に現れた菩薩の遣いに言われて、不良領主(mauvais seigneur)として名高かった楠木正成を迎え迎撃。
ゲリラ戦(la guérilla)で相手を苦戦させている最中、手薄となった京都を足利尊氏が、鎌倉を新田義貞が制圧(conquérir)し、鎌倉幕府終了。
その後、後醍醐天皇による「建武の新政」を行うが、不公平(la partialité)で現実からかけ離れた理想主義的(un idéalisme)な政治だった為、多くの武士は後醍醐天皇を見捨てて離れていく。
彼らは源氏の棟梁だった足利尊氏を祭り上げ、後醍醐天皇と対立。
Ils soutenaient Takauji Ashikaga et s'opposant à l'empereur.
後醍醐天皇側の楠木正成は足利尊氏との和睦を進めるも、天皇はこれを却下。
Il a conseillé la réconciliation avec Takauji Ashikaga à l'empereur, mais il l'a refusé.
さらに、京都からの撤退とゲリラ戦を提案するも、京都を手放したくない天皇はこの提案も拒否。
De plus il l'a conseillé de fuir de Kyoto, mais l'empereur n'en abandonnait pas.
楠木正成は圧倒的な勢力を誇る足利尊氏に対してはゲリラ線以外で勝ち目がないことを知っていたが、天皇の命令には逆らえず(Il ne s'opposait pas à l'empereur)、仕方なく湊川(兵庫県神戸市)で足利尊氏と対峙し、1336年に戦死。
絶対に敗北すると分かっていても後醍醐天皇に評価してもらった恩を忘れず、その恩に報いるために決死の戦いに赴いていった生き様から、銅像が鋳造された。
Il a récompensé l'empereur de son obligation (car il l'a accueilli).
鋳造は、愛媛県にある別子銅山(mine de cuivre)開坑200周年記念事業として住友から宮内庁に献納された経緯がある。
1896年に銅像が完成し、1900年に台座が完成。
住友家(un clan)が別子銅山を開山して200周年を記念して宮内庁に献納。 - 桜田門
-
正式には、旧江戸城外桜田門と呼ばれ、国指定重要文化財。
枡形が完全に残っている城門のひとつで、小田原街道の始点にあたり、小田原口とも呼ばれていた。
1860年、大老井伊直弼がこの門外の濠端で水戸浪士らに暗殺される「桜田門外の変」で有名。
- 田安門
-
北の丸地区北側の靖国通りに面した田安門は、北の丸公園や日本武道館への出入り口になっている。
現在の門は1636年のもので、現存する旧江戸城建築遺構のうち最古のもので、重要文化財に指定されている。 - 清水門
-
江戸城北の丸に出入りするための城門の一つで、重要文化財。
清水門の一角に江戸時代そのままの雁木坂が残されている。
敵に攻め入られても容易に駆け上がれないよう、段差が非常に高く、急な石段になっている。現在のものは1658年に再建されたもの。 - 日本武道館
-
1964年東京五輪柔道競技会場として建設。
武道場以外にもコンサート会場としても有名。
2021年東京五輪の柔道と空手の会場。
法隆寺夢殿を連想させる正八角形で擬宝珠を戴く銅板葺き屋根。
大屋根の曲線は富士山の稜線を表現。 - 東京国立近代美術館
-
日本で最初の国立美術館。
横山大観や菱田春草らの重要文化財を含む13,000点を超える所蔵作品数は国内最大級。
その中から会期毎に名作200点を展示するMOMATコレクションは、20世紀初頭から100年を超える日本美術の歴史を一挙に辿れる。
ガイドスタッフと参加者がトークしながら鑑賞するプログラムや、展望休憩室「眺めのよい部屋」からの眺望も人気。 - 千鳥ヶ淵
-
全国的に有名な桜の名所。
全長700mの千鳥ヶ淵緑道には、ソメイヨシノやオオシマザクラなど260本の桜が咲き、まるで桜のトンネルの様。
銀座
- 銀座
-
1603年の江戸幕府とともに家康によって銀の鋳造所(la fonderie)が移され、以後「銀座」の地名が残った。
当時銀座が置かれたのが、現在のティファニー銀座ビル。
銀座は1657年の明暦の大火、1869年と1872年の大火に見舞われ、耐火性に優れた煉瓦造りの建築を増やす計画を実行。
ロンドンのリージェントストリート(La construction de ce quartier s'est modelé sur Regent Street à Londres comme des réverbères.)に倣って、街路樹やガス灯、アーケードなどが作られた。
これらの区画整理(un aménagement d'un quartier)により地価高騰。
1923年の関東大震災で再度壊滅的な打撃を受け煉瓦街は瓦解。
街並みは復興するも、直ぐに第二次世界大戦に突入し、さらに街は戦災に見舞われる。
戦後は徐々に活気を取り戻していき、1964年の東京五輪にあわせて都市インフラ整備(une infrastructure)も急速に進んだ。
1990年代後半からは海外の高級ブランド店が進出し今に至る。
現在銀座1丁目から8丁目に2,500世帯3,500人が居住。 - 銀座不死鳥伝説
- 明暦3年(1657年)振袖火事→道路整備、郊外移住、隅田川架橋
- 明治5年(1872年)銀座大火→耐火構造の西洋風街路へ
- 大正12年(1923年)関東大震災→カフェやデパート
- 昭和20年(1945年)東京大空襲→ビル
-
銀座は1968年に電線を地中化し、中央通りにはガードレールが存在しない。
それは、ショッピングや食事の際、タクシーの乗降を店前で出来るようにするため。
道幅は江戸時代と同じで16m。
| 地価(2023年調べ) | |
|---|---|
| 商業地 | 住宅地 |
| 中央区 銀座4-5-6 |
港区 赤坂1-14-11 |
| ¥ 53,800,000/㎡ € 336 milles/㎡ |
¥ 5,120,000/㎡ € 32 milles/㎡ |
- 君嶋屋
-
1892年創業の酒店。
正式名は「横浜君嶋屋」で、神奈川県横浜市に本社を構える。
都内には、銀座と恵比寿に展開。
日本酒、焼酎、ワイン、シャンパン等幅広く展開。
店内にBarカウンターがあり、一部商品を有料で頂ける。
東京都中央区銀座1-2-1紺屋ビル1F
🕐月~土 10:30~20:00
日祝 10:30~19:00
📞03-5159-6880
公式サイト
- 柳の木
Le saule -
江戸時代から明治時代にかけて銀座は湿地帯で、桜や松を植えても枯れ、柳だけ残った。
その為、現在でも270本の柳の木が残っている。
- 博品館
-
1899年創業、百貨店の原型。
1921年、銀座初のエレベーター設置。
※日本初の電動式エレベーターは1890年凌雲閣。
- 銀座ライオン銀座7丁目店
-
サッポロホールディングス傘下の外食事業・株式会社サッポロライオンによるビアホール「銀座ライオン」の一店舗。
1934年4月8日に関東大震災で焼失した銀座ビアホールの跡地に菅原栄蔵設計による大日本麦酒本社ビルが竣工。
同ビルのテナントとして銀座ビアホールが営業。
現存する日本最古のビアホール。
- 歌舞伎座
-
16世紀末に京や江戸で流行した演劇。
派手な衣装や一風変わった異形を好み、常軌を逸した行動(extravagant)に走ることを、のちに「歌舞伎者」と呼んだ。
そのことから、斬新で派手な装いで踊る「歌舞伎」が当時流行した。
元々「歌舞伎」は女性が発祥の芸能であり、当初は女性が舞を披露していた。
しかし、遊女歌舞伎として人気を博していたが、そのことで武士同士の間でトラブルが相次ぎ、1629年に幕府によって禁止される。
その後、歌舞伎は、成人男性のみ演じることが許され、今日に至る。
歌舞伎座は1889年に開場したが、戦火や震災などで破壊され、現在は2013年に竣工した5代目の建物で、収容人数は約2,000人。
当日席(一幕見席)は椅子90席、立ち見60名。
- 和光本館
-
1881年、服部金太郎が「服部時計店」創業。
1894年、新聞社跡地を買い取り初代時計塔建設。
当時の建物は1921年の改築解体で残っておらず、1923年の関東大震災を経て1932年に建築家渡辺仁設計のネオルネサンス調ビルとして2代目時計塔竣工。
地上7階建て、1919年に定められた制限30m目一杯の高さ30mの建物の屋上に設置された時計塔は高さ9m、東西南北四面に造られた文字盤は直径2.4mある。
なお、制限は1998年に56mにまで延長される。
塔内部にはドイツ製の時計を用い、毎日技術者が調整していた為、1分の狂いもなかった。
1954年6月10日「時の記念日」から、ウエストミンスター式チャイム(Westminster Quarters)が毎時鳴り響く。
当時ゴシック式の荘厳な建物が多い中、優雅な曲面が特徴のネオルネサンス様式を採用。
第2次世界大戦で銀座は焼け野原となったが、建物と時計塔は幸運にも戦火を免れ、復興のシンボルとなった。
1947年に小売部門として株式会社和光設立。
以降セイコーグループ株式会社の傘下に。
1952年に接収が解除され、現在の和光本館にて営業開始。
- 銀座商店街
-
1923年関東大震災で街が崩壊。
当時の品川近辺は水はけが悪く、地面がぬかるみ、歩きづらかった。
そこで、銀座の煉瓦を地面に敷き詰め、その上に土を盛った。
その商店街を戸越銀座と呼び、日本全国の銀座商店街の第一号となった。
2019年現在、日本全国に銀座という名の商店街は300ヶ所あり、内東京だけでも96ヶ所存在。
- 日比谷公園
- 開園…1903年6月1日
- 面積…16ha(161,600㎡)
- 時間…常時
- 特徴…東京都建設局直轄、景観重要都市公園
-
1903年、日本で最初に誕生した近代的な洋風公園。
それまでは上野公園や芝公園など寺社境内の公園化が一般的だった為、一から公園を造るのは初の試みだった。
ビジネス街のなかにある緑のオアシスで、噴水や花壇、日本庭園式の池などが整備されている。 - 日比谷見附跡、心字池
-
日比谷見附は江戸城の城門の一つで、現在は石垣の一部のみ残る。
石垣近くの心字池は、お濠の面影を残したもの。
上から見ると「心」の字を崩した形をしている。
冬は松の雪吊りが風物詩。 - 首かけイチョウ
-
樹齢400~500年、幹回り(le pourtour de fût)7mの大銀杏。
元々は現在の日比谷交差点にあり、道路拡張の為伐採寸前のところ、公園を設計した本多静六が「首を賭けても」と守りここに移植。 - 雲形池
le bassin de nuage -
雲の形をした池。
装飾用噴水としては日本で3番目に古い「鶴の噴水(1963年製作)」がある。
1番「鎮西大社諏訪神社(1878年長崎)」
2番「明治の森箕面国定公園(1905年大阪)」
銅製の鶴で、羽根を広げた優美な姿が印象的。
池周辺は紅葉や新緑、藤棚も見所。
- 京橋大根河岸おもてなしの庭
-
旧京橋川の橋詰広場跡にある小さな緑地。
都市緑化機構等が主催する緑の環境デザイン賞「おもてなしの庭」大賞を受賞し、日本古来の茶花等を植えて東京を訪れる人々を迎えようと、2017年に誕生。
工事中には京橋川の護岸も発掘。
木陰やベンチ、京橋大根河岸青物市場跡の碑、江戸歌舞伎発祥の地の碑がある。
十月桜は、春と秋(11月頃から)の2回咲く。
- 銀座共同溝
-
銀座共同溝は1968年10月、銀座通りの1丁目から8丁目までの両側歩道の下に旧建設省(現・国土交通省)の施工によって完成。
長さは両側あわせて2km。
この中には銀座通りのデバートや店舗に必要な電気、電話、ガス、水道、下水道等の管路が収容されている。
この共同溝の完成によって道路が再び掘り返される事がなくなり、それぞれの管路は安全に保護され、維持管理も容易に行えると共に地下から直接各需要者に供給することができる。
更にこの共同溝の工事とあわせて行われた銀座通り改修工事によって街路灯や街路樹が新しく生まれ変わり、恒久的な御影石の歩道の上をいつまでも安心して歩くことができるようになった。
築地
- 築地本願寺
-
1617年に京都西本願寺の別院として浅草御門南(東日本橋)に建立。
1657年に明暦の大火で本堂焼失。
佃の門徒たちが海を埋め立てて1679年現在の地に再建。
そこから「築(bâtir)地(la terre)」という地名が付いた。
築地の埋め立て工事が荒波に難儀した折、波間を流れてきた御神体を祀ったところ、波が静まり工事が捗った。
これが1659年建立の波除神社の由来。
1923年、関東大震災後時の火災で再び伽藍を焼失。
1934年に本堂を竣工し今に至る。
古代インド様式をモチーフとした建物は、伊藤忠太の設計。
当時の宗教施設としては珍しい鉄筋コンクリート造。
外観はインド石窟寺院風だが、内装には日本風、西洋風の造りも見られ、インド(indien)、西洋、イスラム(islamique)、日本などの異なるモチーフを融合させた独自の様式。
これは、伊東忠太がシルクロード(la route de la soie)を旅した経験が反映されている。
元々は南西方向を向いて建っていた築地本願寺の参道に門前町を形成していた。
しかし、震災の被害で境内の墓地が和田堀へと移転し、跡地に中央市場の盛況に合わせるように水産物商などが入ってきて、自然発生的に発展したのが築地場外市場。 - 阿弥陀如来(正面)…極楽浄土にあって、生きとし生けるもの全てを平等に救済。
- 宗祖親鸞聖人御影(正面右)…浄土真宗開山
- 勝如上人御影(正面左)…浄土真宗本願寺派第23代門主
- 聖徳太子像(左余間)…1700年春、佃屋又右衛門が奥州湯殿山参詣途中の旅宿で同宿した僧から「聖徳太子16歳自作のお面」を渡され、江戸に持ち帰り仏師に尊体を依頼し、1702年に築地本願寺へ寄進。
- 七高僧御影(右余間)…インドの龍樹菩薩・天親菩薩、中国の曇鸞(どんらん)大師・道綽(どうしゃく)禅師・善尊大師、日本の源信和尚・源空(法然)聖人。
- 築地市場
-
17世紀初期、徳川家康は江戸城内の台所を賄うために大阪の佃村から漁師たちを呼びよせ、江戸湾内での漁業特権(le privilège)を与えた。
漁師たちは幕府に魚を収め、残りを日本橋で売る許可を得た。
Des pêcheurs offraient des fruits de mer au shogounat, et ils vendaient le reste avec la permission de Shogun.
これが魚河岸の起源。
17世紀の江戸の人口は150,000人に達し、18世紀には100万人を超え、魚介類の需要が増え、魚河岸は大きく発展。
日本橋魚河岸は、1923年の関東大震災で壊滅し、当時海軍省の用地だった築地の一部を借り、市場機能を回復。
当時、日本橋を去ることに反対(une opposition)する人が多く、移転完了までに10数年を要した。
1935年には現在の築地市場へと完全移転完了。
移転までの12年間は深川と京橋に魚河岸臨時市場を展開。
面積は23ha(230,000m²)あり、7の卸売業者(grossiste)と、約1,000の中卸業者(courtier)によってせり(enchère)が行われている。
取り扱われる品目は、水産物(取扱量日本最大)、青果、鳥卵、加工食品(豆腐・冷凍食品等)。
1日平均約4,000tの魚や野菜などが入荷し、20億円(deux milliard/年間4,000億円)以上の取引が行われた。
建物の老朽化(la vétusté)や取引量(la quantité du commerce)の増加に伴い手狭となった為、築地市場の移転が2001年に決定。
当時は移転完了を2016年11月10日と発表したが、同年8月31日、移転先の豊洲に土壌汚染の問題が浮き彫りになり、移転延期(prolongation)が決定。
- Le prolongement…空間的な延長
- La prolongation…時間的な延長
豊洲市場自体の見学は午前5時から午後5時まで、日曜祝日その他市場休業日(主に水曜日)以外可。
セリの見学は午前5時45分から6時15分までの交代制で、1ヶ月前にインターネットにて抽選。
東京港は国際貿易港(port de commerce)で、主にフェリーの発着やコンテナ(conteneur)輸送がメイン。 - 築地山長
-
1949年創業の卵焼き専門店。
創業以来、寿司屋や料理屋へ専門的に卸していたが、一般客からの強い要望により、2009年9月から当地にて販売。 - 東京湾の漁港(port de pêche)
- 勝山漁港(千葉)、金沢漁港(神奈川)、金田漁港(神奈川)、鴨居漁港(神奈川)、北下浦漁港(神奈川)、小糸川漁港(千葉)、富崎漁港(千葉)、初声漁港(神奈川)、富津漁港(千葉)、船形漁港(千葉)、間口漁港(神奈川)
- 築地換気所
La tour d'aération -
2022年に開通した東京都心と臨海部を結ぶ「築地虎ノ門トンネル」(延長1.84km)の換気用施設。
トンネル内の排ガスを綺麗な空気にして上空へ放つ。
トンネル出口付近の壁面に吸気口設置。
そこから排風機で吸い込まれた排ガスは電気集塵機(le dépoussiérage/assainissement de l'air)を通って汚れを取り除かれ、消音装置(le silencieux)で騒音を低減した後、換気塔で上空へ放出される。
| 築地市場 | 内場外のみ | 豊洲市場 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 23ha 230,000㎡ |
4ha 40,000㎡ |
40ha 400,000㎡ |
| 開場 | 1935年 | 2018年 | |
| 水産物 取扱量 |
385 milles tonnes | 616 milles tonnes(2023 but) la moitié |
|
| 水産仲卸業者数 | 596業者 | 533業者 | |
新橋
- 明治42年烏森駅開業時「柱」の由来と「床の軸線」
-
1872年、新橋・横浜間に日本で最初の鉄道が開業した。
当時の新橋駅は、現在の東新橋付近に設置され、「新橋停車場」として親しまれたが、1914年、東京駅開業により42年間の幕を開じた。
その後「汐留駅」と改称し、1986年にその役割を終えた。
現在の駅は1909年12月、我が国初の煉瓦アーチ橋の高架駅(烏森駅)として誕生、同時に山手線電化工事が完成し、烏森〜品川〜新宿〜池袋〜田端〜上野間で電車運転を開始。
そして、1914年12月、東京駅開業に合わせて「新橋駅」と改称し現在に至る。
2002年、3・4番線ホームエスカレーター新設に伴う階段解体工事の為、開業当初から93年間ホーム階段を支えてきた「明治41年製造の柱」は、取り外して保存してきた。
「柱」から海側に延びる「床の軸線」は、新橋停車場があった方向を示しており、2022年10月14日、鉄道開業150年を記念して新橋停車場から現在の新橋駅に"鉄道発祥の地としての歴史をつなぐシンボルライン"を床に刻み、この「記念柱」と共に設置。 - 日本の鉄道史
-
1872年に新橋〜横浜間で日本初の鉄道開通。
これは、新たな首都東京と国際貿易港の横浜間29kmの蒸気機関車(la locomotive)線路。
また、現存する都内最古の路面電車は都電荒川線で敷設は1911年、東急世田谷線は1925年敷設。
1927年に東洋初の地下鉄が上野〜浅草間の2.2kmで開業。
ちなみに、日本初の電気鉄道は1895年開業の京都電気鉄道伏見線。
- プラットホーム構造
-
「盛土式石積」構造。
両側面の真下には、溝状に地面を掘って基礎石を敷き詰め、その上に切石を石垣のように積んで土留め壁が作られ、内側には土が詰められた。
基礎石には龍野藩脇坂家・仙台藩伊達家両屋敷の礎石などが使われた。
切石は笠石を含めて6段あり、地表には笠石を含めた上3段が出ていた。
最下段部分は小口面を揃えて横に並ばせ、2段目から小口面と長手面を交互に並べて積んでいる。
ただし、一律的に小口面と長手面が交互になっているわけではなく、2・3段目では小口面が続く箇所もあり、4・5段目では長手面が並ぶ箇所もある。 - プラットホーム規模
-
全長151.5m、幅9.1m
再現は、そのうち駅舎寄りの25m
遺跡指定範囲に残されているプラットホームの遺構は35m - 0哩(ゼロマイル)標識
-
1870年4月25日、測量の起点となる第一杭がこの場所に打ち込まれた。
1936年に日本の鉄道発祥の地として0哩標識と約3mの軌道を復元。
1958年10月14日、旧国鉄によって「0哩標識」は鉄道記念物に指定され、1965年5月12日、「旧新橋横浜間鉄道創設起点跡」として国指定史跡に認定。 - 創業時の線路
-
創業当時、枕木やレールの台座は小石や砂の混じった土を被せられ、レールの頭だけが地表に出ていた。
レール断面は上下対照のI型で、双頭レールと言う。
この復元軌道の半分は小石を被せて当時に近い状態を再現し、残りは枕木や台座が見えるようにした。
双頭レールは錬鉄製で、1873年にイギリスのダーリントンで作られ、官設鉄道で使われた後、新潟県柏崎市の製油所で使われたもので、新日本石油株式会社、新日本石油加工株式会社の両社から寄贈された。
- 市区改正計画と市街線
-
明治初期東京のインフラは、江戸時代から引き継がれたものに手直しを加えながら使用していた。
1880年代に入り限界を迎え、新しい都市計画が必要になり、1884年11月に東京府知事・芳川顕正が作成。
この計画中に、官設鉄道のターミナル・新橋駅と日本鉄道のターミナル・上野駅の間を結ぶ鉄道の建設と、鍛治橋内への中央停車場の設置が盛り込まれ、この線路は、市内中心部での街区の分断と、道路交通との平面交差による支障を避ける為、高架線で建設されることになり、1889年5月に市区改正委員会案としてまとめられた。
これを受けて、内務省は鉄道庁長官に対し市区改正計画に基づいて、中央停車場以南を官設鉄道とし、上野までを日本鉄道として直ちに工事にかかるよう訓令を発した。
官鉄では技師・仙石貢と広川広四郎が調査にあたり、一方の日本鉄道は、ドイツ人技師ヘルマン・ルムシュッテル(Hermann Rumschöttel)に依頼して調査を行った。
ルムシュッテルは来日前にベルリンの市街高架線の建設に従事しており、その経験に基づいてレンガアーチの高架橋建設を構想していた。
日本鉄道は1893年8月に上野〜秋葉原間の貨物線を高架線に改築し、同時にこれを延長して秋葉原から中央停車場を経て新橋に達する高架線の敷設免許を提出した。
これに対して、官鉄が進めていた新橋〜中央停車場間の高架線の計画はやや遅れてまとめられ、1896年2月に開かれた帝国議会で改良費として予算が承認され、中央停車場を含めて改良工事の一環として建設が進められることになった。 - 市街線建設に携わった人々
-
新永間(芝区新銭座町と麹町区永楽町の間を指す)市街線の建設にあたっては、初期には市区改正委員会で検討が行われた為、鉄道関係者だけでなく政治家や経済人も関与し、マスタープランの作成にあたっていた。
そして実際の建設にあたっては、官鉄の土木系の鉄道技師が数多く参画した。
当時の鉄道技師は、外国からの導入期を経てそれを取得し、アレンジを加えて独自の技術体系を確立しつつあった。
しかし高架線の建設については未経験の為、ベルリンの市街高架線を完成させたドイツに技術指導を仰ぐことになった。
日本鉄道の技術顧問だったへるまん・ルムシュッテルが基本案を提案し、市街線建設の技術顧問として来日したフランツ・バルツァー(Franz Baltzer)が、それをもとにして高架線の設計・建設を指導した。
こうして市街線はドイツ系の技術によって建設されていった。 - 新永間市街線の建設
-
1896年4月、市街線建設の為の現業機関として新永間建築事務所が設置され、これを機に新永間市街線は計画から建設の段階へと進んでいった。
建設にあたっては日本人技師には都市部での高架線の建設の経験・実績がない為、1882年にベルリン中心部に市街高架線を完成させていたドイツに指導を仰ぐことになり、1898年2月、ドイツ人技師フランツ・バルツァーが来日した。
ルートの選定にあたっては、新橋駅南方の新銭座町で東海道線と分かれ、新駅を設置する烏森地区に入り、外濠に並行して有楽町地区にいたり、東京府庁舎の東側をカーブして中央停車場予定地である鍛冶橋と呉服橋の間の永楽町地区に達するルートと、新橋駅からそのまま北上し、銀座通りを斜めに突っ切り数寄屋橋の東に出て有楽町に至るルートの2案が検討された。
バルツァーは距離が短く建設費・保守費・運転費が少なくできる後者を推したが、遠回りでも外濠築堤の官有地を経由し、用地買収費を最小限に抑えることのできる前者が採用され、1897年7月に大体のルートが確定した。
一方で高架線の構造は、ルムシュッテルの想定したレンガアーチ式と鋼鉄製が検討されたが、国内で材料・製品を賄えること、騒音の発生が少なくて済むことなどから、レンガアーチ式が採用されることになった。
また、交差する道路上に架ける架道橋(ガード)は鋼鉄製としたが、下部に防音のためのバックルプレートを取り付けるなど、騒音を防ぐ工夫をしている。
さらに線路数は市内循環・近郊線用(山手線+京浜線)2線、中長距離旅客列車線(東海道本線)2線の計4線(複々線)として設計された。
新永間市街線は5工区に分割して施行されることになり、1899年末から高架区間の用地買収にかかり、1900年9月に第3工区から着手した。
一時は国の財政難や日露戦争のため工事が中断・遅延したが、1907年にレンガアーチ高架橋と架道橋の桁架設が完了した。
1909年12月に浜松町〜烏森間が、翌年6月に有楽町まで、同年9月には呉服橋仮停車場まで開業し、列車線を除く高架線の全線が開業した。
着工以来足掛け14年の歳月をかけて、東京の中心部に約3.9kmの高架橋が作り上げられていった。 - レンガ造りの高架橋
-
新永間市街線は、設計にあたってレンガアーチ式とするか、鋼鉄製とするかが検討された。
レンガアーチ式は建設費・保守費が安かったが、地震に対する強度に不安があり、バルツァーも当初は、より耐震力に優れる鉄桁による高架橋を推奨していた。
しかし当時鋼材は輸入に頼っていた為費用が膨大になること、列車通過時の騒音が大きいことなどの欠点があった。
最終的にはレンガアーチ式を採用することになり、設計に際してはアーチ数径間ごとの一定間隔に、グループ橋脚と呼ばれる太い橋脚を入れて、連鎖的に高架橋が破壊されることを防ごうとした。
こうした工夫もあり、市街線は今も現役の高架線として使用されている。
また高架橋のスパンドレル(アーチとアーチの間の三角小間の部分)には、メダリオンとして円形の装飾が施されている。
その原型はモデルとなったベルリン市街線の高架橋にも見られ、新永間とほぼ同時期に施工された、中央本線の万世橋付近のレンガ高架橋にも同じ装飾が見られる。
また、地盤が軟弱な区画では「すかし模様」という装飾が施されているが、これは中空の小アーチで構成され、軟弱な地盤に対する荷重を軽減させる効果があったと言われている。
当時木造建築が多かった東京の街並みに、レンガアーチはすんなりと溶け込み、レンガという部材の持つ柔らかさと温かみが、景観に潤いを与えることになった。
水辺に優美な姿を映すレンガアーチの連続する市街線は、東京名所のひとつにも数えられるようになっていった。
- 日テレ大時計
Une horloge -
2006年、宮崎駿による設計で設置。
手作業加工の銅板を使用。
株式会社スタジオジブリは日本テレビホールディングスの子会社(une filiale)。
2年前の2004年に宮崎駿監督作品「ハウルの動く城」が上映されているので、モチーフにしている可能性あり?
| 月〜金 | 12:00/13:00/15:00/18:00/20:00 |
|---|---|
| 土日 | 10:00/12:00/13:00/15:00/18:00/20:00 |
- 浜離宮恩賜庭園
- 開園…1946年4月1日
- 面積…25ha(250,000㎡)
- 特徴…特別名勝、特別史跡、徳川将軍家の庭園、江戸の潮風そよぐ浜御殿
-
海水を引き入れた潮入の池と、二つの鴨場、江戸城の「出城」としての機能を果たしていた徳川将軍家の庭園。
1654年、4代将軍家綱の弟が将軍家の鷹狩り場(la place pour la chasse aux canards) として、海を埋め立てて別荘を建てた。
その後幾度かの改修を経て、11代将軍家斉の時代(19世紀頭)にほぼ現在の庭園が完成。
幕末(19世紀末)には海軍伝習屯所(La manoeuvre pour la marine militaire)が置かれ、明治時代に入ると、皇室の離宮となる。
関東大震災や戦災によって、御茶屋など数々の建造物や樹木が損傷し、往時の面影は無くなったが、1945年11月3日、東京都に下賜され、整備の後に1946年4月1日から「浜離宮恩賜庭園」として一般公開。
その後1952年11月22日に「旧浜離宮庭園」(文化財指定名称)として国の特別名勝及び特別史跡に指定。
東京湾から海水を引き入れており、潮の干潮(le flux et le reflux)によって、景観を変える。 - 鷹狩り…fauconnerie
- 鷹匠…maître de faucon
- 可美真手命像
ウマシマデノミコト -
1894年、明治天皇の銀婚式(結婚から25年目)を記念して陸軍省(Le ministère de l'Armée)が行ったコンペ(concours)で当選した作品。
彫刻家(sculpteur)の佐野昭氏と、金工家の鈴木長吉氏の制作。
日清戦争の最中、陸軍省が、武功を立てた軍神の像を立てる公募を募り、当選。
像が抱える太刀は八岐大蛇を退治した太刀と言われている。 - 鴨塚の碑
-
1778年以降、浜離宮の時代まで園内の2つの鴨場で鴨猟が行われた。
1935年に、宮内省(L'Agence de la maison impériale)の鷹匠(un maître de faucon)によってこれらの鴨場で捕獲された鴨たちを供養する(consoler l'âme des canards)ために建てられた碑。 - 鷹が待機する鷹部屋
- 出番を待つ鷹
-
鷹の御茶屋には、将軍が鷹狩りに訪れた際に、鷹が出番を待つ為の施設として鷹部屋が作られた。
鷹が普段どこで飼育されていたのか詳細は不明。 - 繊細な鷹が過ごしやすい空間
-
鷹部屋は外側にしか出入口がなく、室内から鷹の様子を見ることはできない。
内部は鷹が怯えないように暗い。
鷹の御茶屋の鷹部屋は、絵図など希少な事例を参考に復元。 - 鷹と鷹匠
- 2ヶ月間行われる鷹の調教
- 馴らし 鷹匠に対する警戒心を解く
- 羽根の汚れを取り、爪と嘴を整え、足革などの必要な鷹道具を装着する。
- 最初は鷹を驚かせないように、真っ暗な鷹部屋に入れて落ち着かせる。
- 鷹の体調や様子を見て。1~2週間の絶食を行い、体脂肪を下げる「詰め」を行う。
- この後、暗闇の中で鷹を拳に乗せる「据え」を行い、鷹が人間から餌をもらっても安全だと覚えたら、鷹部屋内を据えて歩き、音など徐々に様々な状況に馴らしていく。
- 鷹の警戒心が解けてきたら、鷹部屋の外に出て、歩き回ってみる。鷹は見慣れない人や物事に驚きやすいので、全て夜に行う。
- 十分な据え回しを行い、必要な合図を教えることができれば、丸い鷹(素直で癖のない物事に動じない鷹)に仕上げることが容易になる。
- 仕込み 鷹と鷹匠の信頼関係を築く
- 馴らしの段階で夜に教えたことを日中に行い、鷹が落ち着いていたら、鷹匠が求めることを教える。
- 鷹匠は、鷹が人前で獲物を捕っても奪われないこと、獲物を捕った時には御褒美をもらえることなどを鷹に教え、信頼関係を築く。
- 使う 狩場を歩き、狩の準備を整える
- 鷹匠は、鷹を据えて里山を歩きながら、様々な環境や捕って良い獲物などを教える。
- 体重と体調を良い状態に維持し、拳に戻る訓練をしながら筋力を高めていく。
- 鷹が獲物を狙っても簡単に捕れるものではないが、鷹は追いかけながら獲物の生態や考え方を知り、先を読めるようになる。
- 鷹と鷹匠は失敗を繰り返しながら、経験を積み、狩の成功を導く。
- 様々な役割を持つ鷹道具
- 策…鷹の嘴を拭いたり、翼と尾羽を整えるときに使う棒。
- 大緒…鷹を据えたり架にとめたりする時足革に繋ぐ絹製の紐。
- …鷹匠が鷹を据える時拳につけるいぶし鹿革製手袋。
- 抉…鹿の角などの先端を尖らせ、足革の穴を広げたりする時に使うもの。
- 隼頭巾…調教時や狩でハヤブサに被せる頭巾。
- 餌合子…薄く切った餌を入れ、調教や狩に使うもの。
- 鈴板と尾鈴…鈴の音で位置を確認できるよう鷹の尾に装着するもの。
- 口餌籠…藤製の籠で、口餌を入れるもの。
- 丸鳩入れ…丸鳩を入れる為の餌入れ。
- 鳩袋…調教時や狩で生きた鳩を入れ携帯する為の袋。
- 忍縄…絹製の細い紐で、調教などに使うもの。
- 爪嘴小刀…鷹の爪と嘴を削る為に使う小刀。
- 鷹狩りに使われる鷹
-
9月下旬から10月下旬にかけて南に向かう渡り鳥を追いかける野生の若鷹を捕獲した。
雌の方が体が大きく、狩が得意だったと言われる。
鷹の種類
鷹…ハイタカ、オオタカ
隼…ハヤブサ、オオハヤブサ - お伝い橋
-
1793年架橋、2012年改修
総檜(le cyprès)造りで全長120m - 潮入の池
-
海水を引き入れ、潮の干満によって池の趣を変える様式。
都内にある江戸の庭園では唯一現存する海水の池。
東京湾の水位の干満に従って水門を開閉し、池の水の出入りを調整している。
池にはボラ(le mulet)をはじめ、セイゴ(le bar)、ハゼ(le gobie)、ウナギ(une anguille)などの海水魚が棲息。 - 中島の御茶屋
-
1707年造営、将軍の接待や休憩用。
ここで庭園の眺望を堪能。
1724年焼失。
1788年再建。
明治維新(1868~1889)後、皇室の離宮となり国賓を迎えた。
第二次世界大戦中に焼失。
1983年再建。 - 横堀水門
-
徳川家宣時代(1709~12)には堰(le barrage)があり、海水の出入りを調整していた。
今もここで潮の干満(la marée)を利用して東京湾の海水を池に出し入れしている。 - ボタン園とお花畑
-
ボタン園では春には色とりどりの牡丹、お花畑では、春には菜の花、秋には秋桜
菜の花(le colza)の中にある草はホトケノザ(un sorte de Lamier/les labiées)
リュウゼツラン(un agave/un agavé)がなぜあるのか不明だが、進駐軍(l'armée d'occupation)が植えた説がある。 - 鴨場
-
庚申堂鴨場(1778年)と新銭座鴨場(1791年)がある。
鴨場池には幾筋かの引堀(細い堀)を設け、小覗からの鴨の様子をうかがいながら、ヒエやアワ(le millet des oiseaux)などの餌と囮(le leurre)のアヒルで引堀におびき寄せ、機を見て小土手から鷹や網で捕るという猟を行っていた。- 家畜や鶏等の餌…la pâture
- 罠や釣り針に付ける餌…un appât
- 釣りの撒き餌…une amorce
- 神銭座(しんせんざ)鴨場
-
現在鴨場は全国で5箇所あり、その1箇所が浜離宮。
鴨場は、飛来した水鳥が休む為の島を配置した「元溜り」と呼ぶ大きな池と幾筋かの引き込み水路「引堀」から成る。
池には獲物の水鳥たちを引堀へ導き入れてくれるよう訓練された囮の家鴨を放しておく。
周囲は3m程の高さの土手で囲み、笹や竹、常緑樹などを隙間無く植えて、人の気配を感じさせないようにし、飛来した水鳥が安心して休息できる環境を作る。
元溜りを見渡せる監視所の「大覗(おおのぞき)」から水鳥の集まり具合や風向きなどを確認し、猟を行う引堀を決める。
引堀の奥の見張りが隠れる「小覗」から、板木を叩きながらヒエやアワをなどの餌を撒き、囮で引き寄せられた水鳥を、引堀の小土手から網や鷹を使って捕る。
ここ「新銭座鴨場」の名称は、この鴨場の西南側の地名が新銭座町であったことに由来。 - 旧稲生(いなぶ)神社
-
創建時期不明だが、江戸時代後期の絵図には現在の場所より西方に稲荷社が描かれている。
現在の建物は、前身となる社殿が1894年6月20日に東京湾を震源とする地震で倒壊した為、翌年に当時の宮内省内匠寮の手によって、同規模・同形式で再建された。
一方、内部に祀られている宮殿は、その建築技法から江戸時代後期のものと推定。
建立から現在に至るまで幾度か修理の手が加えられた。
中でも、1923年9月1日に発生した関東大震災では大きく破損し、倒壊は免れたが1931年に同じく内匠寮によって大修理が行われた。
そして、2005年には文化財としての大掛かりな修理を行い、ここに明治時代の創建当時の姿を伝えている。 - 三百年の松
-
1709年、家宣が庭園改修を行った際に植えた都内最大の黒松。
この頃から「浜離宮」と呼ばれている。
2024年現在315歳。
黒松を雄松、赤松を雌松と呼ぶ。
理由は、赤松の葉が軟らかいことから女性を連想させるため。- 男性単数…mou
- 男性複数…mous
- 女性単数…molle
- 女性複数…molles
- 株式会社電通
-
1901年設立の大手広告代理店(Une agence de communication et de publicité)
本社ビルは2002年Jean Nouvel設計。
従業員数68,000人。
売上高(Les ventes)1兆2,000億円(mille milliards yens/8 milliard euros)
日本の企業売上高ランキング(Le classement de vente)は第127位。
日本企業売上高ランキング【2025年12月】
| 1 | トヨタ |
48兆円 48 mille milliards de yens 260 milliards d'euros |
自動車 | 愛知 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ホンダ |
21兆円 21 mille milliards de yens 114 milliards d'euros |
自動車 | 東京 |
| 3 | 三菱商事 |
18兆円 18 mille milliards de yens 97 milliards d'euros |
総合商社 Une firme générale |
東京 |
| 7 | ソニー |
13兆円 13 mille milliards de yens 70 milliards d'euros |
総合電気 | 東京 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | セブン&アイ |
12兆円 12 mille milliards de yens 65 milliards d'euros |
小売 | 東京 |
| 56 | JR東日本 |
3兆円 3 mille milliards de yens 1 milliards d'euros |
陸運 | 東京 |
- 虎ノ門金刀比羅宮
- 祭神…大物主神(縁結び、厄除け、商売繁盛)
- 祭神…崇徳天皇(第75代1123~42)
-
1951年、伊東忠太による設計。
讃岐丸亀藩主の京極高和が領地讃岐の金刀比羅大神を1660年に三田の江戸藩邸に邸内社として勧請、その後1679年に現在の地虎ノ門に移る。
こんぴら人気が高まった分化年間(1804~18年)に京極家では毎月10日に限り一般の参詣を許し、大変賑わったと言われる。
社殿は権現造りで、第二次世界大戦により焼失したが、拝殿、幣殿の部分は1951年に再建された。
ともに総尾州檜(愛知県の檜)造り、銅板葺きである。
日本最初の建築史家、伊東忠太の設計校閲による建物で、我が国古来の建築技術が随所に用いられている。
なお、幣殿の奥の本殿は、1983年に復興されたもので、鉄筋コンクリート造、銅板葺きとなっている。 - 崇徳天皇と金刀比羅宮
-
鳥羽天皇の皇子で、1123年に第75代の天皇として即位し、1141年に上皇へ。
1156年の保元の乱の厄により讃岐国へ遷られ、その後も讃岐国で過ごした崇徳天皇は、象頭山中腹に鎮座する金刀比羅宮(本宮)を日夜崇敬した。
1164年の崩御前年にも参籠し、荒行をした。
46歳で崩御された翌年の1165年、その不遇な生涯と崇敬の篤さを偲び、金刀比羅宮(本宮)の相殿に祀る。
保元の乱とは、1156年に起こった武家が政界へ進出するきっかけとなった内乱。
鳥羽天皇(第74代1107~23) 崇徳天皇(第75代1123~42)…鳥羽天皇の第1皇子
近衛天皇(第76代1142~55)…鳥羽天皇の第9皇子
後白河天皇(第77代1155~58)…鳥羽天皇の第4皇子
1156保元の乱…後白河天皇vs崇徳上皇
後白河天皇勝利→崇徳上皇は讃岐へ配流。
日本三大怨霊の1人。 - 銅鳥居
-
この銅鳥居は、虎門外の讃岐丸亀藩京極家(五万石の大名)の江戸屋敷に勧請された金毘羅宮(現金刀比羅宮)の鳥居。
1821年10月に奉納された明神型鳥居で、「金刀比羅大神」の扁額が掲げられている。
円柱には青竜・玄武・朱雀・白虎の霊鳥・霊獣が飾られ、下部には奉納関係者の名前が刻まれている。
願主・世話人の多くは芝地域の商人と職人だったが、江戸市中の地名・人名も見られる。
江戸では諸藩邸内の神仏を一般に公開し、賽銭収入も期待されていた。
江戸庶民の信仰を反映したこの派手な鳥居は、当時の人々の宗教的・文化的活動の実態を示す貴重なもの。 - 金刀比羅宮百度石
-
百度石は、いわゆる「お百度参り」の際に用いられてもので、神殿とこの石の間を往復して願掛けをした。
願掛けの一種である「お百度参り」は、江戸時代に盛んに行われたが、特に都市部に目立つ個人祈願の一形態で、その多くは病気治癒の願掛けであった。
正面に「百度石」、背面には「大願成就 願主⬜︎心道 元治元甲子年(一八六四)十二月吉日」の銘があり、願いが叶えられたお礼に建てられてものである事がわかる。
こうした百度石が保存されているのは、区内では非常に珍しく貴重。
- ての字 本丸
-
1827年創業の老舗鰻屋。
元々問屋だったのが、お客様からの要望でレストランを設置。
自社ビルの地下を掘って井戸水を使用。
墨で焼くと外がパリッとして中はふんわり仕上がる。
東京都港区西新橋3-19-12
🕐10:45~14:30(日曜祝日年末年始定休)
📞03-3432-2564
公式サイト
日本橋
- 日本橋
-
1603年、木造の太鼓橋架橋。
1911年、20代目の石造。
麒麟像もこの時造立。
麒麟は中国の伝説上の霊獣で、出現すると吉兆。
翼のように見えるものは背鰭(la nageoire dorsale)。
本来の麒麟には翼は無く、日本の起点から飛び立つイメージ。
阿吽。
狛犬も阿吽で、始まりと終わり。
日本橋という起点に相応しい。
ヨーロッパの盾を持つライオンをイメージし、東京都の紋章を持ち、東京を守護する。
橋の焦げている箇所は焼夷弾跡。 - 東京都旗
-
1889年12月制定。
「日」「本」「東」「京」の漢字4文字を太陽から六方向に光が差すイメージ。
「日本の首都・中心地」としての東京を表現。
- 三越
-
1673年に呉服店「越後屋」として現在の日本銀行辺りにて創業。
正札販売(※)を世界で初めて実施。
※定価を紙に書いて商品と一緒に店頭に並べ、金を持っていれば誰でも同じ価格で販売する。
それ以前は貧農や浪人には売らずに、家柄などで客を選んでいた。
ゆえにそれまでは富裕層だけのものだった呉服を広く一般的なものにした。
1683年に火災に遭い現在の土地へ移転。
1895年に三井呉服店の土蔵造り2階の大広間を打ち抜き、「陳列場」として「座売り」を廃止した。
1905年、全国主要新聞に全面広告を掲載した。
米国のデパートの一部を実現する「デパートメントストア宣言」
1914年、日本橋本店にルネッサンス様式の新館落成。
アール・デコ調の内装と合わせて高く評価。
1929年、新宿店開店。
1930年、銀座店開店。 - 天女(まごころ)像
-
日本橋本店本館1階中央ホールから吹き抜け5階に届くように聳える天女像。
三越のお客様に対する基本理念「まごころ」を可視化した像。
彫刻家の佐藤玄々(げんげん)先生とお弟子さんらが10年をかけて制作し、1960年に除幕式が執り行われた。 - ライオン像
-
1914年、当時の支配人が百貨店開設準備の為、欧米を視察した時にイギリスで注文。
ロンドンのトラファルガー広場にあるネルソン記念塔の下の4頭の獅子像がモデル。
気品と店格の象徴。
C`est le symbole de la noblesse. - デパ地下
- 日本初のデパ地下導入は1936年の松坂屋名古屋店。
- 地下を食料品売り場にしているメリット(Le mérite)
- 水道、ガス、電気などの設備が上階に比べ低コストで使える。
- 生鮮品等の商品を運びやすい。
- 地下鉄や地価駐車場と直結した利便性。
- 噴水効果
- 噴水効果
un effet de la fontaine - 商業施設などで下層階を充実させることで客の流れを噴水のように上階へと誘導する効果。
- 福徳神社
-
9世紀後半、当地は福徳村と呼ばれ、穀物・食物を司る稲荷神が鎮守の森に鎮座していた。
福徳村の稲荷は往古より源義家、太田道灌ら武将の尊崇を受け、特に最初の江戸城を築いた道灌との縁は深く、彼の神霊は当社に合祀されている。
徳川家康は1590年江戸入府直後に当社を参詣。
二代将軍秀忠も1614年に参詣し「福徳とはめでたい神号だ」と称賛し、また当時の福徳稲荷の椚(くぬぎ)の皮(une écorce du chêne)付き黒木鳥居から春の若芽(la pousse)が生えているのを見て「芽吹稲荷」の名を与えた。
秀忠は江戸城内の弁財天を合祀し、社地を330坪(1090㎡)と公定するなど当社を篤く尊崇した。
その後、江戸の町の発展と度重なる火災により境内地をほとんど失い、一時は消滅の危機に瀕した。
それでも氏子有志が福徳神社の祭祀を継承してきた結果、2014年秋、日本橋地域諸氏の尽力により往時の姿を彷彿とさせる境内・社殿が再興。 - 算額
-
算額とは、江戸時代において額や絵馬に和算の問題や解法を記して、神社や仏閣に奉納したもの。
算額は問題が解けた事を神仏に感謝し、益々勉学に励む事を祈念して奉納された。
やがて人の集まる神社仏閣を問題の発表の場として、難問や問題だけを書いて解答を付けずに奉納する者も現れ、それを見て解答や想定される問題を再び算額にして奉納する事も行われた。
福徳神社の算額は、埼玉県加須(かぞ)市に現存する多くの算額の中から5問を奉納。 - 問1
-
図のように円の中に大円2個、中円2個、小円4個がある。
外円の直径を6とするとき、小円の直径を求めよ。
Il y a 2 grand ronds, 2 ronds moyens, et 4 petits ronds.
Si le diamètre du plus grand rond extérieur est 6, combien du diamètre du petit rond à l'intérieur ?

- 小網神社
-
1466年に稲荷大神を勧請し稲荷社を造営した事が起源。
また、太田道灌が寄進した土地に寺院が建立された。
1868年には、神仏分離令が発布され、その後に現在地が社地と定められた。
境内には、1929年に造営された社殿と神楽殿が残る。
社殿は伝統的な神社建築の形式で、向拝(こうはい)には優れた技術による昇り龍・降り龍・獅子・ばく・鳳凰等の彫刻が施されている。
また、道路際に立つ神楽殿は五角形の特異な形状。
この社殿並びに神楽殿は、中央区に現存する数少ない木造の神社建築として、造営に関係する資料とともに中央区民文化財に登録されている。
- 凧の博物館
Le musée de cerf-volant -
凧(le cerf-volant)の起源は紀元前300年中国で木製の鳶凧が原点とされ、紀元前200年頃漢の時代に韓信が凧を利用して測量をし敵陣を攻めた。
その後も戦争に凧を利用。
この頃は布製で、紙製は中国で紙が発明された紀元105年以後。
またBenjamin Franklinが凧を利用し稲妻が電気である事を突き止めて避雷針(le paratonnerre)を発明。
南方の国では椰子(le palmier)の葉で作った凧で魚釣りに利用したり、日本では凧を利用して建築作業をしたり、盗賊の道具になったり、多方面に利用された。
凧は人類が大空への夢を満足させてくれるものであり、大空へ揚がる不思議なもの、精霊が宿るもの、無限の大空へ直接つながるものという信仰的な考えで崇拝する風習があった。
中国で一般に遊びとなったのは約1000年前で、この頃から各国へ伝わり世界中に拡がった。
日本へもこの頃伝わり、平安時代当初は貴族階級のもので一般のものではなく、この頃の凧の呼び名は「紙鳶」と呼ばれていた。
日本の凧が一般に広がったのは江戸時代。
参勤交代、商人、旅人により全国的に広まり、地方に定着し、その土地の環境・風習・気象などの影響と民衆の芸術性が融合した。
西日本では外国の影響が強く残り多種多彩な日本凧が生まれた。
また、日本は良質の紙と竹が産出され容易に手に入ることも、世界に類のない多種な性能の良い凧に発展した。
- 山本山
-
創業者の嘉兵衛は、宇治でお茶を作っていた。
「宇治の美味しいお茶をもっと多くの人に味わってもらいたい」という思いを抱き、1690年に江戸に赴き日本橋で和紙やお茶、茶器類を扱う「鍵屋」を開業。
1947年、9代目の邦一郎は料亭で有明海産の高級海苔を食べて感動した事と、お茶と海苔の旬が違うことに着目して海苔の取り扱いを開始。
日本最古の煎茶商で玉露を発明したことでも有名。
ちなみに、株式会社山本海苔店は1849年創業で1869年に「味附海苔」を世に出した1946年設立の食品メーカーで、1690年創業1941年設立の株式会社山本山とは別企業。
- 田源
-
1816年に現在の滋賀県にて創業した老舗着物問屋。
同ビル2階にイチマス田源呉服問屋ミュージアムを併設。
着付けレッスンやワークショップなども展開。
東京都中央区日本橋堀留町2-3-8田源ビル1F
🕐10:00~17:30
📞03-3661-9351
公式サイト
- 小津和紙
-
1653年創業の老舗和紙専門店。
1階が店舗と手漉き和紙体験工房(要予約)。
2階がギャラリーで3階が資料館。
品揃えは都内随一。
東京都中央区日本橋本町3-6-2小津本館ビル
🕐月~土10:00~18:00(日曜年末年始定休)
📞03-3662-1184
公式サイト
- Daiwaリバーゲート
-
1994年竣工の鉄骨鉄筋コンクリート造、地上20階建ての賃貸オフィスビル。
デベロッパーは読売新聞社。
吉野家ホールディングス本社が入居。
東京都中央区日本橋箱崎町36-2

浅草
- 中世
-
江戸時代に米蔵が設置され、日本全国から食用米と武士たちの給料としての米が集まり保管。
その為大勢の警備(la surveillance)が配置され、下級役人(le subaltern)が暮らしていた。
江戸時代、武士の給料は米で支払われていた為、米を現金に換える札差(le courtier en riz)もいた。
札差は預かった米から手数料(la commission)を引いて米と現金を武士に渡した。
手元に残った米は小売りの米屋たちに手数料を付けて売った。
さらに儲かったお金を武士たちに利子を付けて貸し付けていた(Ils faisaient prêt à intérêt)為札差には大富豪(le riche)が多く、豪遊する場として浅草は江戸文化が発展。
1657年、明暦の大火で日本橋から遊郭が移転し、その他劇場も浅草六丁目一帯に設置され、芝居町となった。 - 近世
-
1927年12月東洋初の地下鉄が上野〜浅草間で開通。
1960年代テレビの普及で六区の映画館が続々閉館。
以後人通りも少なくなるが、1978年から始まった隅田川花火大会や1981年からの浅草サンバカーニバルで徐々に活気を取り戻す。
- 雷門
-
正式名称「風雷神門」
941年に安房国(現千葉南部)の太守だった平公雅(たいらのきみまさ)が武蔵国への配置転換を祈願。
翌年942年、その願いが叶い寄進。
雷門は17世紀に幾度も焼失と再建を繰り返す。
大提灯は1795年の再建時に付けられた。
しかし1865年に焼失し、以後1960年まで再建されなかった。
そして1960年、松下幸之助によって寄進。
以降10年毎に掛け替え。
現在の提灯は2020年4月からの6代目。
京都産の竹を使用。
エジソン(Thomas Alva Edison)が電球のフィラメント(le filament d'ampoule)に京都産の竹を使用。
向かって左雷神像、右に風神像。
火災により頭部を残して焼失し、1874年に補刻。
背面には西の金龍(女神)、東の天龍(男神)が奉納。 - 天龍像
-
天龍・金龍は雷門の守護神。
平櫛田中(ひらぐしでんちゅう)と菅原安男の作。
「金龍山」という寺号に因み、龍神を天龍・金龍の男女二体に擬人化(personnifier)した。
天龍像は腰鎧(armure de hanche)を付け、右手に独鈷杵(どっこしょ=le vajra=ヴァジュラ)、左手に金珠(きんじゅ=boule dorée)を持った男神像。
青を中心に彩色を施し、木曽檜(cyprès)を使用。
高さ293cm、重さ250kg
御本尊示現1350年記念の1978年3月19日に奉納(628年)。
- 仲見世
-
雷門から宝蔵門まで300mの参道に約90店舗。
1685年に仲見世の前身である商店が設けられた。
当時寺が近隣住民に境内の清掃を役割として課す見返りに開業許可。
1989年にシャッター(le volet)に浅草絵巻(歳時)を描く。
1994年電柱地中化。 - 宝蔵門
-
1964年に再建された入母屋造の二重門。
上層は文化財「元版一切経」(Les textes du bouddhisme)の収蔵庫となっている。
向かって左(西)の阿形、右(東)の吽形の金剛力士を安置。
門背面左右の草鞋は魔除け(talisman)。
山形県村山市の奉讃会によって奉納。
藁(paille)2,500kgを使い、全長4.5m、総勢800人が1ヶ月で制作。
1941年の奉納を最初に、宝蔵門再建後は10年に1度制作。
現在のものは、2018年10月に奉納された8代目。
わらじは仁王様の力を表し「この様な大きな草鞋を履く者がこの寺を守っているのか」と驚いて魔(le diable)が去る。
また健脚(avoir de bonnes jambes)を祈ってこの草鞋に触れていく人もいる。
小舟町提灯の両側に吊るされているのは、「魚がし」と書かれた銅製の提灯。
1973年に鋳物会社で製造されたもので、富山県に本社を置く株式会社梶原製作所による。
魚河岸の人々は提灯をできるだけ長く保たせたいという思いから、紙ではなく銅製の提灯を奉納する案を採用。
そもそも、1923年の関東大震災以前は日本橋に魚河岸があり、荷揚げされた生産物を小舟町で販売するようになった。
その品物を買いに人が集まり、さらにお店が増え、街全体が大きく発展。 - 五重塔
-
仏塔(pagode)…五大思想/仏教的な宇宙観
上から -
浅草寺五重塔は1945年の東京大空襲で焼失、1973年に再建された鉄骨・鉄筋コンクリート塔で高さ53.3m。
仏舎利を奉安したインドのストゥーパを起源とする。
実際、最上層には1966年にスリランカ(Sri Lanka)の寺院から奉戴した仏舎利(la relique bouddhique)が納められている。
浅草寺に五重塔が建てられたのは942年。
当時は三重塔で、寺の東側に五重塔が配されていた。
今でも旧五重塔跡が残る。 - 九輪
-
五重塔頂上にある九輪は五智如来と四菩薩を表す。
- 五智如来
-
五大如来ともいう。
密教で5つの知恵を5つの如来に当てはめたもの。 - 四菩薩
-
密教の「胎蔵曼荼羅」において、中央に位置する「中台八葉院」に表される4体の菩薩。
普賢菩薩・文殊菩薩・観音菩薩・弥勒菩薩 - 浅草寺本堂
-
628年に地元の漁師兄弟が隅田川で観音像を上げ自宅に安置。
兄弟はその後出家し、自宅を寺に改修したのが起源。
645年に僧が寺を整備し観音を秘仏と定め現在も非公開。
本堂は1945年の空襲で焼失、1958年に鉄筋コンクリート造で再建。
堂内の写真撮影は可能だが、内からも外からも、奥の観音様へカメラを向けることは失礼に当たる為、撮影を禁止している。
手前左右には梵天と帝釈天。- 梵天…バラモン・ヒンズー教の宇宙の創造神ブラフマン(Brahman)
- 帝釈天…バラモン・ヒンズー教の武勇神インドラ(Indra)
屋根はチタン製(le titane)。
本堂外向かって右側
真身絶表象雲霞画出補陀山
ものの本当の姿は形の如何によって左右されるものではないが、雲や霞が描き出すように満ちる自然の景観は、まさに観音浄土を表す。
本堂外向かって左側
実相非壮厳金碧装成安楽刹
存在する全てのありのままの姿というのは、とても形に表すことはできないが、黄金や碧い宝玉で飾りつけた伽藍などの景観こそは、まさに安楽浄土である。
堂内向かって右側
佛身圓満無背相
仏身は完全円満であり、どこから眺めても背中を向いていない。
堂内向かって左側
十方万來人皆対面
どこからでも来る人は全て仏の正面に向かい合える。
堂内中央上部に掲げてある額には「施無畏(せむい)」と書かれており、意味は
「観音菩薩の力で人々の不安や恐怖を取り除く」
額は1945年の東京大空襲で焼失したが、2020年に新調奉納。 - 立ち退き問題
-
仲見世商店街と交差する形で東西に300m伸びる伝法院通りの、仲見世より西側の32店舗が台東区より立ち退き(déplacement)の求められている。
浅草伝法院通り商栄会(Une association de la rue commerçante)によると、1977年に浅草公会堂が完成した時に、当時の区長(Le maire d'arrondissement)の指示で建てられたと主張。
終戦直後からバラック(baraque)で営業していた露天商(forain)たちが入居。
商栄会の西林宏章会長は
「掘建て小屋(cabane)ならともかく、鉄筋造りの連なる店舗を区の許可無く勝手に並べられる訳が無い。当然(naturellement)、区に認められていると思って商売してきた。(On pense que c'est l'autorisation officielle.)」と主張。
一方の台東区側(administration)は、2014年から不法占拠(occupation illégale)である旨を商栄会側に伝え、立ち退きを求めるようになった。
区は「建てられた当初から違法状態だった」という認識があるものの、なぜ今更問題視されるようになったのかについては、「その時々の担当者(responsable)がどう対応してきたのか不明」と言葉を濁す。
図面(le tracé)などの建設の経緯(détail de la construction)が分かる資料は商栄会にも台東区にも残っていない為、主張は双方対立したまま。
地元関係者の話では、「区が一代限りで認めた」という。
商栄会も納税の義務を果たしているし、行政にとっても得はあったわけなので、歩み寄ってもいいのでは。 - 水子地蔵尊
-
1978年9月25日建立。
お地蔵様は地獄界から天上界に至る六道の苦の中に、生死を繰り返す衆生の苦しみを救済する仏様で、修行僧のお姿をして、右手に錫枝(修行僧の杖)、左手に宝珠を持つ、慈悲深い菩薩様である。
地蔵とは、万物を平等に育成する偉大な力の源である大地を現し、また母親の胎蔵を意味することから、地蔵尊が子供達を守るという信仰が生まれた。
江戸時代には、六道救済の為に、六地蔵尊が盛んに造像奉祀され、空無上人が自ら六地蔵尊の一つを浅草寺の支院、正智院に安置したと伝える。
生後間もない子供の健やかな成長を願い、また受け難き人の命を宿しながら、育成し得なかった多くの尊い命の後生安穏の悲願を込め、ここに水子地蔵尊が建立された。
毎月24日のお地蔵様の御縁日には、水子供養法要が行われる。 - 鎮護堂の神木・公孫樹
-
推定樹齢400~500年。
この公孫樹(イチョウ)は、1945年3月10日の東京大空襲の時、焼夷弾を浴びながらも、猛火から鎮護堂を守った神木。
今でも木には当時の焼け跡が残っている。
戦争がこの世から無くなることを願う。 - 鎮護堂
-
別名「おたぬきさま」
防火、盗難除け、商売繁盛の守護神。
1872年、浅草寺境内に住み着いた狸の乱行を鎮める為、浅草寺の用人、大橋亘(おおはしわたる)が浅草寺貫首唯我韶舜(ゆいがしゅうしゅん)と相談の上、自身の邸内に祀ったことがはじまりと伝える。
数度の移転を経て、1883年、伝法院の当地に再建。
現在の入母屋造の本殿は1913年再建。
祭礼は毎年3月17,18日に行われている。
また、境内には1963年に建てられた幇間塚(ほうかんづか)がある。
幇間のことを「たぬき」と呼んだことから、この地に建てられたもので、碑には幇間の由来と久保田万太郎の「またの名のたぬきづか春ふかきかな」の句が刻まれ、裏面には幇間一同の名が刻まれている。 - 銅造阿弥陀如来坐像
-
腹前で定印を結び、右足を上に結跏趺坐(けっかふざ)する。
1693年に僧侶が造立を発願し鋳物師が1702年に両脇侍像と共に完成。
両脇侍像は現存せず。
宗海は浅草界隈の僧侶で、本像造立に際して近隣で勧誘活動を行い、多くの帰依者を獲得。
このことから、江戸時代前期の人々の信仰や宗教活動を知ることができる貴重な資料。 - 銅造宝篋印塔
-
1761年に鋳物師の西村和泉守藤原政時が造立。
仏塔(une pagode)の一種。
江戸時代中期以降に流行した屋根型の笠をもつ形状。
台座に刻まれた銘文から、様々な職種や地域からの寄進が確認でき、浅草寺に対する信仰の広がりを伺い知ることができる。
1855年の地震で倒壊。
1907年の日露戦争凱旋記念(la commémoration pour le triomphe de la guerre russo-japonaise)に修復。 - 石橋
-
現存する都内最古の石橋。
1618年、浅草寺に東照宮(現存せず)を造営した際に参詣のための神橋として架橋。
寄進者は徳川家康の娘振姫の婿和歌山藩主浅野長晟(ながあきら)。
1948年に国が重要美術品に認定。 - 六地蔵石燈籠
-
かつて元花川戸町にあったものが1890年に移築された。
高さ235cmで、六側面に地蔵を彫った。
石燈籠だが火袋(灯明部)は無い。
1146年、1170年、1368年建立説がある。
現在では風化や火災の影響で竿石に刻まれた文字の判読困難。
「江戸名所図会」で既に印刻の判読が困難であった為、都内でも古い時代の製作と考えられる。 - 日限地蔵尊
-
16世紀建立都内最古の木造建築物。
日限地蔵尊は六角堂の御本尊。
日数を定めて祈願すれば叶う。 - 金龍権現
-
浅草寺御本尊観音を守護する為、天より30mの金龍現出。
よって浅草寺の山号を「金龍山」とし「金龍権現」を奉納。
3月18日と10月18日、浅草寺境内にて「金龍の舞」奉演。- 3月18日…本尊示現会
- 10月18日…菊供養会
- 九頭竜権現
-
龍神様は仏教を守り、雨を操り、我々に五穀豊穣や福徳を授ける。
この九頭竜権現は長野県戸隠山の地主神で、1958年の本堂再建の折、その成就を祈るべく勧請された。
現在も浅草寺の伽藍安穏の守護神。 - 一言不動尊
-
1725年造立。
願い事を一つに限って祈願すると叶う。 - 銭塚弁財天
-
弁財天は芸能や学問、財宝や福徳の神。
この銭塚弁財天は福徳財運の弁財天として特に信仰が深い。 - めぐみ地蔵
-
浅草寺境内に20体以上あるお地蔵様のひとつ。
我々に幸せをお恵みくださることから「めぐみ地蔵」の名を以て親しまれている。
「南無地蔵菩薩」と唱えてお参りする。 - 恵日須・大黒天堂
-
向かって左側が大黒天、右側が恵比寿。
1675年、浅草寺に奉納された石像。
御堂は戦後の建立。
1844年に御堂脇に建立された石碑によると、これらの像は空海によって造られたとされる。
当時天台宗だった浅草寺に真言宗の空海が像を奉納するという宗派を超えた弘法大師への信仰が見られる点が興味深い。 - 三峯社
-
秩父にある天台修験の関東総本山。
浅草寺境内に勧請された神社の一つ。
戦災により焼失し再建。
明治初年の神仏分離令以前の信仰を垣間見れる。 - 橋本薬師堂
-
1649年に本堂北にあった堂を三代将軍家光が北西に移築再建。
元々は橋の元にあり、家光が命名。
1994年に現在の場所へ移転。
入母屋造の瓦葺で、外部はかなり改変されているが、浅草神社と同時代で、二天門や六角堂に次ぐ古建築。
薬師如来坐像と十二神将像を安置。 - 淡島堂
-
17世紀に和歌山の淡島明神を勧請した。
祭神は少彦名命(スクナヒコナノミコト)。
淡島明神は江戸時代より女性の守り神として信仰を集めた。
現在も2月8日に針供養を行う。
日頃使い慣れた針に感謝し、柔らかな豆腐に刺して供養する。
かつてこの日に限り女性は針仕事をしない風習があった。 - 写経供養塔
-
1958年の本堂落慶を記念し「観音写経運動」を信徒に勧めている。
奉納された写経は毎年10月の写経供養会にて御本尊観音様へ奉納され供養される。
1994年に造立されたこの宝塔型写経供養塔には、その年に奉納された写経の経題と巻数を記した「目録(le catalogue)」を奉安する。 - 胎内くぐりの灯籠
-
灯籠の下を潜ることで、子供の虫封じや疱瘡のおまじないとされる。
造立年代は不明だが、江戸時代には有名。 - 魂針供養之塔
-
大東京和服裁縫教師会が50周年記念事業として1982年建立。
元は1935年「折れ針」への感謝を込めて浅草寺淡島様の御宝前で供養した。
次第に同じ志の方々が増え、都内外からも「折れ針」を供養しに参詣した。 - 銭塚地蔵堂
-
家内安全・商売繁盛の御利益がある六地蔵尊を祀る御堂。
江戸時代、今の兵庫県に住む男の妻が自宅庭先で銭が沢山入った壺を掘り当てた。
しかし彼らは、これに頼っては家が滅びると考え土中に埋め戻した。
Ils ont les enterré.
この心掛けにより一家は繁盛した。
その壺の上に地蔵尊を祀った。
戦後1954年に再建し、老朽化に伴い2019年に再再建。 - 瓜生(うりゅう)岩子女史の銅像
-
岩子は通称。
正しくは岩と言う。
1829年2月15日、福島県耶麻郡熱塩村渡辺家に生まれたが、9歳の時父を失い、母は岩を連れて生家へ帰った。
その為、岩は母方の姓瓜生氏を称した。
14歳の時、会津若松市の叔母に預けられ、その夫で会津藩侍医を勤める山内春瓏の薫陶を受け、堕胎(un avortement)防止に関心を持つ。
17歳で佐瀬茂助を婿に迎え、若松で呉服屋を営み、一男三女を産んだが、早くに夫を亡くした。
1868年会津戦争で孤児となった幼童の教育に尽力した他、堕胎等、当時の様々な悪習を正し、1889年貧民孤児救済の為福島救済所を設置する等、社会事業の推進に努めた。
1897年4月19日、福島で没(享年69歳)。
生涯を慈善事業(une oeuvre de bienfaisance)に捧げた岩の行いを賞揚し、1901年4月篤志家によって、浅草寺境内に銅像を造立。
台石正面には、下田歌子女史の撰文を刻む。
1996年7月 - 建設趣意書
-
思い出づる調べも哀し1945年3月9日の夜、B29 300機以上の大空襲により浅草一帯は火の海となる。
地をなめるようにして這う火焔と秒速30mをこす烈風にあふられ、親は子を呼び、子は親を求むれど、なす術も無し。
慄き叫び逃げ惑い、悪夢の如き夜が去れば、眼に映るものは一面の焦土にて、一木一草の生づずもなく、あわれ身を焼かれ路傍に臥す無実の犠牲者は10,000余柱を数える。
当時その凄惨な状況は一片の新聞だに報道されることなく、敗戦後に生まれた子供達は戦争の惨禍を知る由もない。
痛ましく悲しい夜もいつしか歴史の一駒として消えていくであろう。
よって我々はここに当時を偲び、不幸散華された御霊の安らけく鎮まりまさんことを祈り、二度と過ちを繰り返すことなく永遠に世界の平和を守らんことを誓い、浅草観音の浄域にこの碑を建立する。
以て瞑せられよ。
1963年8月15日 - 市川團十郎像
-
1919年、江戸歌舞伎ゆかりの地浅草に明治の名優・九代目市川團十郎の歌舞伎十八番「暫」の銅像が造られた。
彫刻家・新海竹太郎の作。
1944年に第二次世界大戦中の金属供出の命を受ける。
1985年、十二代目市川團十郎襲名を機に再現。 - 被官稲荷社
-
1854年、新門辰五郎の妻が重病の時、伏見稲荷社に祈願。
その効果があって病気全快。
翌1855年、お礼の意味を込め、伏見から祭神を当地に勧請し、小社を創建して被官稲荷社と命名。
名称の由来は不詳だが、被官とは「出世」の意。
辰五郎は上野寛永寺住職輪王寺宮の家来、町田仁右衛門の養子。
本姓は町田。
輪王寺宮舜仁法親王が浅草寺伝法院に隠居し、上野へ行く為の新門を造った。
その門の番を命じられたので、新門辰五郎と呼ばれた。
辰五郎は町火消十番組の組頭としても多彩な活躍をした。
社殿は一間社流造、杉皮(une écorce de cèdre)葺で創建以来のもの。
間口1.5m、奥行1.4m
覆屋を構えて保護している。
覆屋は大正期の建築。
社前には「安政二年九月立之 新門辰五郎」と刻む鳥居がある。
| 空 | 宝珠 | 虚空 Le vide |
|---|---|---|
| 風 | 請花 | 成長 La croissance |
| 火 | 笠 | 情熱 La passion |
| 水 | 塔身 | 変化 Le changement |
| 地 | 基礎 | 抵抗 La résistance |
| 如来 | 知恵 | 色 | 方角 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大日如来 | 法界体性智 | 白 | 中央 | |
| 阿閦(あしゅく)如来 | 大円鏡智 | 緑 | 東 | 薬師如来と同一視 |
| 宝生如来 | 平等性智 | 黄 | 南 | |
| 観自在王如来 | 妙観察智 | 赤 | 西 | 阿弥陀如来と同一視 |
| 不空成就如来 | 成所作智 | 黒(紫) | 北 | 釈迦如来と同一視 |




















- 酒右衛門
SAKAEMON -
ジャパニーズウィスキー専門店。
山崎や響などの日本産ウィスキーを常時取り揃えている。
日本酒の十四代等もある
5,000円以上50万円以下の範囲内で免税可。
店内写真撮影可。
東京都台東区浅草1-31-4
🕐月~金11:00~19:00
土日10:00~19:00
📞03-6802-8867
公式サイト
- 染の安坊
-
1907年創業の手染め手拭い専門店。
東京都台東区浅草1-21-12
🕐10:30~19:00
公式サイト
- 河村屋
-
江戸の茶屋「八重乃香」のお膳は、河村屋が230年守り続けてきた漬物の技を中心に据えている。
河村屋は、素材の風味と香りがそっと調和する"漬物の妙"を、今日まで変わらず丁寧に手作りし続けている。
八重乃香の糠漬けは、1.5斗の糠床を2週間毎に交代させながら丁寧に育てている。
糠床を十分に休ませる期間を設けることで、常に最も活き活きと状態を保つ。
毎日の手入れが香りと酸味を穏やかに整え、深い余韻を宿す。
お前を支える白米は、提携農家から直接届くお米を使用。
愛情を込めて丁寧に育てられたそのお米は、漬物を優しく受け止め、旨みを一層引き立てる。 東京都台東区浅草1-22-8
🕐10:00~18:00
📞03-5806-0266(受付10:00~18:00) ランチは11:30~17:00(L.O.16:30)
公式サイト
- 隅田川
-
東京都北区の新岩淵水門で荒川から分岐し、東京湾に注ぐ全長23.5kmの一級河川。
途中で新河岸川、石神井川、神田川、日本橋川などの支流河川と合流する。
かつて隅田川は下総国と武蔵国の国境だった。
771年以降東海道が通り、隅田川を渡船で行き来できた。
江戸時代に町は大きく発展するが、防備上の関係で架橋が制限されたため、1923年の関東大震災後の震災復興事業に伴う新規架橋まで、多くの渡しが存在し、特に明治初頭の最盛期には20以上もの船が行き来した。
現在隅田川には、鉄道・歩行者用併せて約40もの橋が架かっている。
- アサヒビール本社ビル
-
1889年創業。
フラムドールは同社100周年を記念して1989年にPhilippe STARCK(フィリップ・スタルク)によって設計。
コンクリートに金属を噴射して、継ぎ目(la soudure)の無い表面を実現。
- 東京スカイツリー
-
2008年7月着工、2012年2月竣工の自立式電波塔。
634mの高さはタワーとしては世界一。
建築物としても世界第3位
展望デッキは350mで、345mと340mの2階分をエスカレーターか階段で降りて5階までエレベーターで下る。1 ブルジュ・ハリファ
Burj Khalifa829.8m アラブ首長国連邦
La Fédération des Émirats arabes unisドバイ
Dubaï2 ムルデカ118
Merdeka118680.5m マレーシア
La Malaisieクアラルンプール
Kuala Lumpur3 東京スカイツリー
TOKYO SKYTREE634m 日本
Le Japon東京
Tokyo
また、350mからさらに450mの展望回廊まで上がれる。
- 神谷バー
-
1880年に創業した日本初のバー。
1881年に輸入葡萄酒の販売を行い、1882年のは速成ブランデー(電気ブラン)の製造販売開始。
建物自体は1921年からのもので、浅草最古の鉄筋コンクリート造の建造物として2011年に国の登録有形文化財となる。
1960年に洋食部門の営業開始。
1階が神谷バー、2階がレストランカミヤ、3階が割烹神谷。
- 花やしき
-
1853年に植木商が植物園(le jardin botanique)「花屋敷」開園。
日本最古の遊園地。
当時は80,000㎡でブランコ(la balançoire)が唯一の遊具。
赤字続きで1930年代に規模を縮小し、現在5,800㎡でローラーコースター(la montagne russe)、メリーゴーラウンド(le carrousel)、お化け屋敷(le palais de l'épouvante)等がある。
現在のアトラクションは1953年頃から稼働。
- かっぱ橋
-
江戸時代に合羽屋喜八が湿地帯だったこの土地を住民のために私財を投じて整備。
その姿に心打たれた河童達が夜毎に整備を手伝った。
かっぱ橋本通り沿いの曹源寺に合羽屋喜八の墓がある。
合羽屋喜八の商売が雨合羽屋だった事にも由来。
1912年に数件の古道具屋、戦後に飲食店用の店舗が増加。
浅草通りと交わる菊屋橋交差点から言問通りまでの800mの間に170店以上の専門店。
1731年創業の伝統あるドイツの刃物メーカー「ヘンケルス社」も合羽橋に店を構える。
逆に1908年創業で老舗の「釜浅商店」は2017年、フランスに現地法人「カマアサフランス」を設立。
翌2018年、パリに直営店「KAMA-ASA」を開業。 - 釜浅商店…1908年
- かまた刃研社…1923年
- つば屋包丁店…1956年
- 土佐の打刃物 徳蔵…17世紀頃
- 今戸神社
- 應神(おうじん)天皇
- 伊弉諾尊・伊弉冉尊
- 福禄寿
-
元今戸八幡宮と称し、後冷泉(ごれいぜい)天皇の時代(1063年)源頼義、義家父子は勅命に依り奥州討伐の折、今戸の地に至り、京都の石清水八幡宮を鎌倉鶴岡と浅草今津村(現今戸)に勧請した。
應神天皇の母神功(じんぐう)皇后は三韓親征の際、時恰(ときあたか)も天皇を宿され帰路である九州筑紫で出産。
従って應神天皇を別名胎中天皇・聖母天皇とも称し、安全子育ての神と崇敬されている。
伊弉諾尊・伊弉冉尊御夫婦の神は加賀の白山比咩(ひめ)神社の御祭神にして、1441年千葉介胤直(ちばのすけたねなお)が自分の城内に勧請。
諾冉(だくねん)二神は子孫の繁栄と縁結びの神。
1937年、今戸八幡と合祀され今戸神社と改称。
今戸の地名は武州豊島郡今津村と称し、その後今戸(別字今都)となった。
向島
- 向島百花園
-
江戸の町人文化が花開いた文化・文政(1804~30年)、骨董商を営んでいた佐原鞠塢(さはらきくう)は、交友のあった江戸の文人墨客の協力を得て、当園を創設した。
開園当初には多くの梅が植えられ、その後、詩経や万葉集など中国・日本の古典に詠まれている有名な植物を集め、四季を通じて花が咲く草庭となった。
百花園とは、一説では「四季百花の乱れ咲く園」という意味でつけられた。
1938年、東京市に寄付され、翌年公開が開始された。
1945年の空襲では甚大な被害を受けたが、1949年に復旧。
1978年10月に国の名勝及び史跡の指定を受けた。
向島百花園は、庶民的で文人趣味豊かな庭として、江戸時代より今日まで受け継がれてきた花園。 - 桑の茶屋跡
-
ここには、明治時代に上野の博覧会で使用した二階建ての建物があり、桑の木で作られていたことから「桑の茶屋」と呼ばれていた。
しかしながら、1945年3月の東京大空襲で百花園が壊滅的な打撃を受けた時に、桑の茶屋は取り壊された。
唯一、建物に使用されていた欄間が御成座敷に残っている。
現在は、建物があった当初の面影は縁石に残っているのみとなるが、園内における一番高い地形から眺める水辺の景色が当時を偲ばせる。
- 三囲(みめぐり)神社
-
三囲神社の名称は南北朝時代(1337~92)の伝説に起因。
近江三井寺の僧・源慶がこの地を訪れ、荒れた小堂を発見。
それが弘法大師の建立した社だと知った源慶は社殿を再建。
社地から老翁の神像が発掘され、白狐が現れ、その御神体の周囲を三度巡り去った伝説。
故に三囲。
1693年、江戸は厳しい干ばつ(la grande sécheresse)に見舞われた。
雨乞いを祈願する農民たちに、俳人其角(きかく)は「夕立ちや田をみめぐりの神ならば」と詠んだ。
この句では"三囲"と"見巡り"が掛け言葉となっていて、神前に奉じた翌日には雨が降り、その霊験は江戸中に広まった。
御祭神は宇迦之御魂命で「宇迦」は穀物を示す。
京都・伏見稲荷大社の主祭神でもあり、広く"お稲荷さん"という呼称に掛けて"三囲稲荷"という別名でも呼ばれる。 - 三井家との関係
-
三井家は江戸進出時にその名にあやかって守護神とし、2009年に三越池袋店閉店に伴い、シンボルだった青銅製のライオン像が境内に移設。
三井家では、1716~36年に三囲神社を江戸における守護社と定めた。
それは、三囲神社のある向島が、三井の本拠である江戸本町から見て北東の鬼門に位置したからである。
また、三囲神社の"囲"の文字には三井の"井"が入っている。
その為「三囲はすなわち三井に通じ三井を守る」と考えられた。
社域の一角には三井11家の当主夫妻、120柱余りの霊が神として祀られている「顕名霊社」がある。
没後100年を経た霊だけが祀られる特別な場所。 - 三囲のライオン像
-
三越の旧池袋店(1957~2009)から移した青銅製ライオン像。
1914年、当時の三越呉服店を率いた日比翁助がライオンを大いに好み、ロンドン・トラファルガー広場のネルソン像を囲むライオンに倣い、三越本店に一対のライオン像を据えた。
戦後は本店の像をもとに各支店に設置。
なお「現金安売り掛け値なし」という三井の越後屋の画期的な商売の仕方は大いに発展し1896年三越呉服店に繋がる。 - 老翁老嫗(ろうおう/ろうう)
-
1688~1704年、三囲稲荷にある白狐祠を守る老夫婦がいた。
願い事のある人は老婆に頼み、老婆は田んぼに向かって狐を呼ぶ。
すると狐が現れて願い事を聞き、またいずれかへ姿を消す。
他の人が呼んでも現れなかった。
俳人其角(きかく)は、その有り様を「早稲酒や狐呼び出す姥が許」と詠んでいる。
老婆の没後、里人や信仰者がその徳を慕って建てたのが、この老夫婦の石像である。
老嫗像には「大徳芳感」、老翁像には「元禄十四年辛巳五月十八日、四野宮大和時永、生国上州安中、居住武州小梅町」と刻まれている。

- 8 淡島寒月旧居跡
-
父の淡島椿岳は、江戸時代に大流行した軽焼きせんべいの名店「淡島屋」を経営する実業家で大地主であった。
また、知識欲が旺盛で、画を学び、ピアノを買って演奏会を開く趣味人でもあった。
1884年、向島の弘福寺内に隠居所を建てて住んだ。
息子の寒月は西鶴再評価のきっかけをつくり、趣味人として、新聞や雑誌に寄稿。
実体験をベースにした小説や江戸にまつわる話などを洒脱なタッチで著し、好評を博した。
1893年頃、父の使っていた隠居所を梵雲庵と名づけ隠居。
「梵雲庵寒月」と号し、悠々自適な生活に入る。
夏目漱石の「我が輩は猫である」に水島寒月という学者が登場するが、モデルは寺田寅彦で、名前は寒月から採ったと言われている。
収集家としても有名で、梵雲庵には3,000余の玩具と江戸関連の貴重な資料があったが、関東大震災で全て焼失してしまった。
- 11 言問団子と郡司大尉
-
江戸後期、向島で植木屋を営んでいた外山佐吉は、文人墨客に手製の団子を振る舞う「植佐」という団子屋を開くと、花見客や渡船客の間でも人気となった。
1868年、長命寺に逗留していた歌人の花城翁より、在原業平が詠んだ
「名にしおはば いざ言問はん都鳥 我が想ふ人は ありやなしやと」
に因んだ命名の勧めを受けた佐吉は「言問団子」と名づけ、業平神社を建て、都鳥が飛び交うこの辺りを「言問ヶ岡」と呼んだ。
1878年、佐吉が始めた灯籠流しによりその名は広く知られていった。
後に「言問」は、言問橋や言問通りなどの名称で定着したが、ルーツは「言問団子」である。
また、この裏手にある桟橋からは、1893年3月20日千島開拓に向かう郡司大尉率いる5艘(そう)の端艇(たんてい=小舟)が出発している。
隅田川両岸はこれを憂国の壮挙と称える群衆で埋まり、花火が打ち上げられ、歓呼の声と楽隊の演奏が響く中での船出であった。
この時、大尉の弟、幸田露伴はこれに同乗して横須賀まで見送っている。
蔵前
- 歴史
-
地名は江戸幕府の御米蔵に由来。
隅田川を9haも埋め立てて作られた地に67棟の蔵が置かれ、旗本や御家人たちの給料としての米が蓄えられた。
現在は倉庫を改装した飲食店や雑貨店が点在。
蔵前のお店
- HOWMORE LIVING
-
東京都台東区蔵前3-22-7
11h00~19h00
日/木定休 - WEEKENDER SHOP
- THORUGH BRACE
- SLAPS BASE
-
11h00~17h00
月/火/木定休 - クラマエビル、Atelier K.I./tokyo toff.
- MAITO°
-
11h30~18h30
月定休 - 水木屋馬場商店
- LITSTA
両国
- 両国橋と百本杭(le pieu)
-
墨田区両国1丁目〜横網1丁目
両国橋風景の特徴、百本杭。
Il y avait 100 pieux.
1930年に荒川放水路が完成するまで、隅田川(23.5km)には荒川(173km)、中川(83.7km)、綾瀬川(49km)が合流していた。
その為、隅田川は水量が多く、湾曲部ではその勢いが増して川岸が侵食された。
両国橋付近は特に湾曲がきつく流れが急であった為、上流からの流れが強く当たる両国橋北側には、数多くの杭が打たれた。
水中に打ち込んだ杭の抵抗で流れを和らげ川岸を保護。
明治時代末期から始められた護岸工事で殆どの杭は抜かれ、百本杭と隅田川が織りなす風情は今では見られない。
- NTTドコモ墨田ビル
-
2004年竣工、NTTドコモ所有ビル。
Un opérateur de réseau mobile.
Nippon Telecom and Telegraph.
鉄塔を含めた高さ156m
鉄塔にはNTTドコモのマイクロ無線用アンテナを配置。
1階には「NTTドコモ歴史展示スクエア」があり、300点以上の実機展示が入場料無料で10:00~17:00楽しめる。
休館日は月曜日、祝日、年末年始。
東京都墨田区横網1-9-2
- ももんじや
-
1718年創業の猪料理店。
「ももんじや」とは「百獣」のことで、四つ足の動物の肉を扱う店を「ももんじ屋」と総称。
元は漢方の薬屋だったが、薬の一種として出した猪が人気商品となり、料理店へ転身。
猪の肉は、冷え性(être frileux)や疲労回復に効果があり、肉食が禁じられた江戸時代でも「山くじら」と称して食べられていた。
猪は丹波や鈴鹿などから仕入れたもので、味噌仕立てのすき焼きにする。
その他、鹿刺し、狸汁など、珍しい肉料理が味わえる。
- 御船蔵跡
-
この辺りから新大橋にかけての一帯に江戸幕府の艦船を格納する御船蔵があった。
16,000㎡の土地に14棟の船蔵が並んでいて、巨大な軍船「安宅丸(あたけまる)」は船蔵の外に係留されていた。
安宅丸の取り壊しを機に供養塔が建てられたことから、ここは俗にアタケとも呼ばれ、広重の名所江戸百景「大はしあたけの夕立」にも描かれている。
1657年の「明暦江戸大絵図」には、既に御船蔵がほぼ現在の位置にあり、川下の尾張屋敷との間の堀に堂々たる天守を備えた安宅丸が描かれている。
- 江島杉山神社
-
江島神社の弁財天を奉斎し、弁財天を信仰した杉山和一(わいち)を併せ祀る。
杉山和一(1610~94)は三重県津市の生まれで幼い頃失明し、鍼術を志す。
江戸の山瀬琢一に入門し修行に励む中、江島弁財天の岩屋にて七日七夜の参籠をした。
業が明けた日外に出ると大きな石に躓いてしまうが何か手に刺さる物があり探ってみると筒の様にくるまった枯葉(スダジイ)の中に1本の松葉が入っていた。
「いくら細い鍼でも管に入れて使えば盲人の私にも容易く打つ事が出来る」
こうして管鍼術が生まれた。
躓いた石は「福石」として本社江島神社境内に祀られる。
この後より深く鍼治を学ぶ為京都の入江豊明へ入門。
そして江戸で治療所を開くと大繁盛。
1670年1月和一は61歳にして検校の位を受けた。
その名声により五代将軍徳川綱吉の医師として務める。
1692年5月9日将軍より総検校に任命。
和一が83歳の時、綱吉公の難病を治療した功により
「何か望みの物はないか」
との問いに
「唯一つ、目が欲しゅうございます」
と答え、この地に屋敷領を賜り更に和一が高齢になっても月参りを欠かさなかった江ノ島弁財天を敷地内に勧請。
翌年には社殿が建立、本所一ツ目弁天社と呼ばれ江戸名所となり多くの信仰を集めた。
1694年5月18日84歳没。
1871年、当道座組織が廃止され総録屋敷も没収されるが、当社は綱吉公が古跡並の扱いとした為残され、社名も江島神社となる。
1890年4月杉山和一霊牌所即明庵も再興し、境内に杉山神社を創祀。
震災、戦災により2つの社殿とも焼失するが戦後1952年合祀し、江島杉山神社となる。 - 管鍼術(かんしんじゅつ)
- 金属製の筒状の器具に鍼を入れ、その端を指で軽く叩くことで、鍼を患者に殆ど痛みを感じさせずに刺入できる。
- acuponcteur…鍼師
- acuponcture…鍼療法
- 宇賀神
-
ウガは、ウカ・ウケ等食物を表す語で日本古来の穀霊信仰に根ざした食物神であり神道の宇迦之御魂神(稲荷神)と同一神。
音楽・学問・弁舌・福徳と幅広い御利益がある。
弁才天と習合したのは、農耕に深く関係する水神信仰による。
弁才天の遣いが白蛇と言われることから、宇賀神の姿が人頭蛇身になった。
- 忠臣蔵 一之橋
-
幕府は低湿地であった本所の開発時、洪水被害縮小の為排水路を碁盤目状に開作し、掘り出した土を陸地の補強、嵩上げ(※)に利用。
排水路は隅田川に対し縦・横に開削。
1659年、縦の代表格、竪川の開削と同時に架けられ、隅田川から入って一ツ目の橋という意で命名された長さ23.6m、4.5m。
竪川の両岸には全国から水運でもたらされる物品を扱う商家や土蔵が建ち並び、橋を行き交う人々も多く、賑わった。
一之橋は、赤穂浪士が泉岳寺に引き揚げる際に最初に渡った橋としても知られている。
※嵩上げ(かさあげ)…既存の建物を物理的に高くする事。
- 回向院
- 創建…1657年
- 本尊…阿弥陀如来
- 開基…江戸幕府(徳川家綱)
-
1657年、江戸史上最悪の惨事となった明暦大火が起こり犠牲者100,000人以上。
遺体の多くが身元不明、引き取り手は無い。
そこで4代将軍家綱は、ここ本所両国の地に「無縁塚」を築き、その菩提を弔う念仏堂を建立。
有縁・無縁、人・動物に関わらず、生ある全てのものヘの仏の慈悲を説くという理念のもと、「諸宗山無縁寺回向院」と名付けられ、後に- 1855年 安政大地震…25,000人
- 1923年 関東大震災…100,000人
- 1945年 東京大空襲…100,000人
- 旧国技館(大鉄傘)跡
-
旧国技館は、江戸時代以来の相撲興行の歴史を刻む回向院の境内に、1909年に竣工・開館。
13,000人を収容する当時最大規模の相撲常設館で、設計は日本銀行本店や東京駅で著名な辰野金吾と葛西萬司(まんじ)。
日本初のドーム型鉄骨の建物で、大鉄傘(だいてっさん)とも呼ばれた。
開館当初は両国元町常設館が正式名称だったが、翌年から国技館という名称が定着。
開館後は菊人形祭りや講演会などを開催するイベントホールとしても利用。
この建物は、1917年の火災→1923年の関東大震災→1945年の東京大空襲で被害を受けたが、その度に修理され、1983年に老朽化に伴い解体されるまで使用された。
ただし、相撲常設館としての役割は横綱双葉山の引退披露大相撲として開催された1946年秋場所を最後とし、その後はメモリアルホールと称してプロレスやボクシングなど格闘技の試合会場として使用。
また、1958年以降は、日本大学講堂として使用。
なお、旧国技館解体後、地元の方々が台東区の蔵前国技館に移転していた本場所の誘致に尽力され、1985年1月に現在の両国国技館が開館した。
旧国技館の跡地は、現在複合商業施設となり、その中庭にはタイル貼りでかつての土俵の位置が示されている。 - 相撲関係石碑群「力塚」
-
墨田区と相撲の関わりは、1768年9月の回向院における初興行に遡る。
1833年10月からは、回向院境内の掛け小屋で相撲の定場所として、年に2度の興行が開かれた。
明治時代に入っても相撲興行は回向院境内で続いていたが、欧風主義の影響で一時的に相撲人気が衰えた。
しかし、1884年に行われた天覧相撲を契機に人気も復活し、多くの名力士が生まれた。
そして、1909年に回向院境内北に国技館が竣工し、天候に関係なく相撲が開催できるようになり、相撲の大衆化と隆盛に大きな役割を果たした。
力塚は、1936年に歴代相撲年寄の慰霊の為に建立された石碑。
この時にこの場所に玉垣を巡らせ、1916年に建てられた角力記(すもうき)と法界万霊塔もこの中に移動した。
現在は相撲興行自体は新国技館に移ったが、力塚を中心としたこの一画は、相撲の歴史が76年に渡り刻まれ、現在もなお相撲の町として続く両国の姿を象徴している。 - 岩瀬京山墓
-
江戸時代の著名な戯作者である山東京伝の弟で同じく戯作者。
名を百樹といい、字を鉄梅といった。
鉄筆堂は号で、通称は利一郎、のち京山と改めた。
はじめ篠山侯に仕え、のちこれを辞して兄京伝の業を継ぎ、やがて剃髪して凉仙と号した。
著書には「稗史小説」「蜘蛛の糸巻」その他がある。
1858年9月24日流行病コロリ(コレラ)に罹って殉した。
なお、兄京伝の墓を建てたのは京山である。
方半居士、覧山の別号がある。 - 岩瀬京伝墓
-
江戸時代の著名な戯作者。
名は醒、字は酉星。
京橋南伝馬町に住んでいた為、号を京伝とし、愛宕山の東に当たることに因んで山東といった。
彼は深川木場の質屋に生まれ、若くして浮世絵を北尾重政に学び、北尾政演の名で黄表紙の挿絵などを描いた。
「御存商売物」が蜀山人に認められ、「江戸生艶気樺焼」によって一躍黄表紙作家として広く知られるようになった。
さらに「令子洞房」で洒落本作家としての地歩を築いたが、1791年、風俗を乱すものとして手鎖50日の刑に処せられ、以後読本作家に転じた。
著書には「仕懸文庫」「孔子縞于時藍染」「心学早染草」「傾城買四十八手」「近世寺跡考」「骨董集」その他多数。
1816年9月7日殉。享年57歳。 - 加藤千蔭墓
-
江戸中期の国学者、歌人。
芳宜園(はぎぞの)と号し、千蔭は名。
耳梨山人、逸楽窩、江翁などとも号していた。
通称加藤又左衛門といい、能因法師の末裔だという。
父は江戸の与力として八丁堀に住み、千蔭は父から歌を学んだ。
また賀茂真淵に師事し、のち父の職を継いだ。
1788年、病気の為職を辞し、学問研究に専念した。
老境に入っていよいよ研鑽を積み、著書は世に千蔭本と呼ばれて流布した。
博識を持って世に知られ、かつ著書「万葉解」は高く評価されて幕府から賞されたという。
また、絵を建部綾足に学び人々は争ってこれを求めたという。
1808年9月2日殉。享年75歳。
著書には「万葉集略解」「万葉新採百首」「香取日記」その他多数。 - 石造明暦大火
横死者等供養塔 -
1657年1月、江戸市中の繁華街を焼いた明暦の大火による焼死者・溺死者をはじめとして、入水者・牢死者・行路病死者・処刑者その他の横死者に対する供養の為に造立されたものである。
もと、回向院本堂の向かって右に存した三仏堂の前に建てられていたが、堂舎の位置がその後移転したにも関わらず、この供養塔の位置はほとんど動いていないものと思われる。
総高3.05m、1675年頃建立。
願主は回向院第二世住持信誉貞存。 - 鼠小僧供養墓
-
碑の正面には「天保二年八月十八日」「俗名 中村 次良吉之墓」
「教覚速善居士」「道一書」
裏面には「大正十五年十二月十五日 建立」
左側には「永代法養料金 五拾圓也 細川 仁三」と刻まれている。 -
鼠小僧は1797年生まれの盗賊であり、1832年8月19日に浅草で処刑。
武家屋敷にのみ押し入った為、庶民からは義賊扱いされた。
幕末の戯作者河竹黙阿弥が権力者宅に自在に侵入し被権力者である庶民に盗んだ金を配るという虚構の鼠小僧を主人公とした作品を世に送り出し人気に火がつき、演劇界において現在まで続く当たり狂言の一つとなった。
1879年、歌舞伎の市川一門の市川団升が狂言が当たった礼として碑と永代供養料10円お寄付を行い、施主として名が刻まれ、墓の横にも石灯籠を寄進。
文学界においても、芥川龍之介が「戯作三昧」「鼠小僧次郎吉」「復習」と三度題材に取り上げ、虚構の鼠小僧人気は高い。
江戸時代、犯罪者には墓を作ることが禁止されていた。
しかし歌舞伎や狂言での成功によって祈願対象物としての墓の必要性が生じ、この供養碑が作られた。
他方、供養墓の前にある小さな供養碑は正面に供養墓同様「教覚速善居士」と刻まれているが、別名「欠き石」とも呼ばれる。
鼠小僧の墓石を欠き、財布や懐に入れておけば金回りが良くなる。
あるいは持病が治るとも言われ、成就した人々の奉納した欠き石は数年ごとに建て替えられ続け、現在までに数百基にも及ぶ。
発生時期は不明だが、1885年に初演された河竹黙阿弥の「四千両小判梅集」には台詞の中でこの信仰の事が触れられている。
「この供養碑は変貌著しい墨田区と歌舞伎との関わりを示す資料でもあり、そこにはまた庶民のささやかな幸福追求の対象物としての価値も含まれる」 - 猫の恩返し(猫塚)
-
猫を大変可愛がっていた魚屋が、病気で商売ができなくなり、生活が困窮。
すると猫が2両のお金を咥えて来、魚屋を助ける。
ある日、猫は商家で2両咥えて逃げようとしたところ、奉公人に殴り殺された。
それを知った魚屋は、商家の主人に事情を話し、主人も猫の恩に感銘を受け、魚屋と共に猫を回向院に葬った。
江戸時代、江戸っ子の間に広まった昔話で、実在した猫の墓として貴重な文化財の一つに挙げられる。
- 千体地蔵尊
-
御本尊の背面にある千体地蔵尊は、御先祖の供養や家運や社運の隆昌・繁栄を祈願する人々によって奉安されたもので、後光さながらに御本尊を守護する様は、まさに荘厳。
関東大震災により焼失した尊像で増上寺の黒本尊と同木といわれ、恵心僧都の作と伝えられた「備中千体阿弥陀如来像」をその由縁とする。
- 「もんじゃ焼き」の名前の由来
-
葛飾北斎が1819年に刊行した『北斎漫画』の中で「文字焼き屋」の挿絵があり、この時代、既に江戸にもんじゃ焼きの原型があったことが記されている。
焼く時にネタで文字を書いて遊んだことから「文字焼き」と呼ばれ、その後「もんじ焼き」から「もんじゃ焼き」となった。
- 法恩寺
- 創建…1458年
- 本尊…十界曼荼羅
- 宗派…日蓮宗
- 開基…太田道灌
- 開山…日住
-
1458年、太田道灌が江戸城築城にあたり、丑寅の方角である江戸平河に城内鎮護の祈願所を設けた事が起源。
1524年、道灌の孫の資高(すけたか)が父資康(すけやす)追善の為に堂塔を再建、資康の法名をもって本住院から法恩寺と改名。
家康入府後は、数回の移転を重ね、1688年に現在の地へ。
鬼平犯科帳では、数作品に登場。
「本所・桜屋敷」には平蔵と左馬之助が門前の茶店「ひしや」で湯豆腐と熱燗で20余年ぶりに旧交を暖める場面が登場。
「尻毛の長右衛門」では、冒頭に寺裏手の木立の中で布目の半太郎と引き込み役のおすみが逢引する様子が描かれている。 - 鬼平犯科帳
-
池波正太郎による時代小説。
18世紀の話、浅間山大噴火と大飢饉と農作物のインフレ。
各地で打ち壊しが起こり、田沼意次の失脚と松平定信が老中に就任して始まった寛政の改革。
経済不安定の中犯罪が増加。
火付盗賊改方長官の鬼平こと長谷川平蔵が市中の事件を解決していく話。 - 鐘楼三重塔
-
1932年の「宗祖650遠忌」に平和の象徴、関東大震災後の復興のシンボルとして、鉄筋コンクリート製で建立され、先の大戦の中でも戦火を耐えて今日に至った。
三重塔は、正式には扁額にあるように「経石塔」といい、お経の一語一語を書いた石を奉安したもので、鐘の響きと共に経文も響き渡っている。
1978年の「宗祖700遠忌」には、改修と共に、戦時中のに軍事供出されていた梵鐘も新たに作られた。
2010年に「この平和の象徴である三重塔は未来へ残さなくてはいけない」と、耐震を含めた大改修が行われた。
《法華経の教えが、鐘の響きと共に広まるように、
世界の人々が幸せでありますように。》 - 平川清水稲荷
-
当山開基太田道灌築城の江戸城内に平川と言う清流があって、人呼んで「小川の清水」と云い、道灌公も愛でて
武蔵野の 小川の清水 絶えやらで
岸のねせりを 洗いことすれ
と詠んでいる。
当時その小川の畔に稲荷の祠が祀られていて、平川清水稲荷を称えられていた。
現在法恩寺境内にその碑柱が伝わって由緒を物語っている。 - 太田氏七代供養塔
-
既存の五輪塔を転用し、地輪に太田資清(すけきよ)、資長(すけなが)=道灌、資康(すけやす)、資高(すけたか)、康資(やすすけ)、重正(しげまさ)、資宗(すけむね)=初代浜松藩主ら名族太田氏七代の法号と忌日が刻まれている。
太田氏歴代の内、特に資清から資宗まで7名の法号を刻む点が、次のような寺伝との関連を想わせる。
太田氏は元来、道灌開基の法恩寺を菩提寺とした。
しかし、北条氏に仇を返すか否かをめぐって住持(寺の最高責任者の僧)と対立した康資が寺を変え、本行寺(現荒川区)を菩提寺とした。
だが後に康資の怒りも晴れ、以後、資宗の代まで道灌霊像への参詣が続いた。
太田氏七代供養塔は、法恩寺が太田氏との関係継続の歴史を認識して設けた記念物であった。 - 旗本太田資同墓碑
-
家祖政資(まさすけ)の代より法恩寺を葬地とした旗本太田氏の五代目当主、資同(すけあつ)の墓碑。
一説によれば、太田氏は元来市井の医家で、初代政資の姉が徳川家宣の子(家千代)を産んだことから旗本に取り立てられた(知行高三千石)。
資同は、大名太田資宗(初代浜松藩主)の家系から分かれた格上の旗本、太田資倍(すけます)(知行高五千石)の実子(二男)だったが、医家から武家に転じたこの新興の旗本、太田氏に養子入りして家督を相続した。
家譜によれば、資同は、新興の旗本太田氏において初めて布衣以上の地位(式日に無紋の狩衣を着用することが許され、旗本の立身の証とされた身分)を得た人物で、四代にわたる事実上無役の状態を脱する上で画期的な世代となったことが知られる。
資同の墓碑には、彼の法号と忌日、そして彼が生前に書き著した遺言が刻まれている。
遺言は、公儀への滅私的奉仕を旨とする武家の心得を説くもので、近世武家の倫理をよく示している。
資同の墓碑は、旗本太田氏歴代の墓碑の中で唯一残る希少なものであり、銘文には歴史資料としての意義も認められる。
上野
- 上野恩賜公園
- 開園…1873年10月19日
- 面積…35ha
- 時間…5:00~23:00
- 特徴…東京都建設局直轄、日本さくら名所100選
-
江戸時代、徳川家三代将軍家光が江戸城の鬼門封じの為に東叡山寛永寺を建立。
僧天海の助力で京都や滋賀や奈良に見立てた景観を創造。
京都御所から丑寅の方角に鬼門封じの役割を持つ比叡山延暦寺が上野寛永寺。
琵琶湖は不忍池、清水寺は清水観音堂。
そして吉野山の桜を上野公園内にも数多く植樹。
新政府軍(西郷隆盛)と旧幕府軍(彰義隊)決戦の地。
新政府軍側の大村益次郎がアームストロング砲を用いて勝利に貢献。
戦火によって灰燼と化した上野に1870年、医学校と病院を建設しようと、オランダから医者のアントニウス・ボードワンを招いたところ、彼が公園としてこの地を残すようにと日本政府に指示。
1873年に日本初の公園に指定された。 - 薩摩藩出身の西郷隆盛の銅像がなぜ上野に?
-
1897年高村光雲による作。
1889年大日本帝国憲法発布に伴う大赦によって西郷の「逆徒」の汚名が解かれたのをきっかけに建設。
傍らの犬「ツン」は薩摩犬の雌で後藤貞行作。
1868年7月、戊辰戦争中の上野戦争において旧幕府軍と新政府軍が衝突。
この時、新政府側東征大総督府参謀である西郷隆盛が旧幕府側陸軍総裁の勝海舟と会談し、江戸城の無血開城が実現。
西郷は朝廷側を勝利に導いた功労者であり、その功績を称えて、上野の地に像を建造。
Il a été loué son mérite.
1877年士族による武力反乱である西南戦争で、西郷隆盛を逆徒として殺した償いという説。 - 不忍池
-
先史時代の不忍池は、武蔵野台地東端の上野台と本郷台に挟まれた入江だった。
その後、海岸線の後退とともに取り残されて池になった。
1677年に出版された「江戸雀」(江戸地誌)に、不忍池の蓮を詠んだ和歌が載っている。
このことから、この時代には蓮があったとわかる。
涼しやと
池の蓮を
見かへりて
誰かは跡を
しのばずの池
いつ誰が蓮を植えたかは不明。
第二次世界大戦中は水田として利用され、戦後に水を戻し、蓮苗の植え付けが行われた。 - 五條天神社
-
110年頃の創建。
主祭神…大己貴命(おおなむじのみこと)/少彦名命(すくなひこなのみこと)
相殿神…菅原道真公
日本武尊東征の際に大己貴命と少彦名命を祀った。
社名に天神とある為、1641年に合祀。 - 東京都恩賜上野動物園
- 開園…1882年(日本最古)
- 面積…14ha
- 飼育数…500種3,000頭
- 年間来場者数…3,500,000人(日本一)
-
1972年にジャイアントパンダが入りパンダブーム。
2008年にパンダがいなくなる。
2011年に中国からつがいのパンダ(リーリーとシンシン)を借り入れる。
2012年に第1子が誕生するも、同年肺炎により死去。
2017年に第2子を出産し、公募でシャンシャン(香香)と命名。 - 東京国立博物館
-
1872年創設の日本最大最古の博物館。
延べ床面積78ha(78,000㎡)。
収蔵品数120,000件で内7,200件を展示。
年間来場者数1,200,000人。
館内マップ - 3-3 禅と水墨画 鎌倉〜室町
-
鎌倉時代・13世紀、中国から来日した僧や中国に留学した僧により、禅宗が本格的に導入された。
禅宗とは、坐禅や問答などの実践的な修行を重視する仏教の教派の一つ。
またこれに合わせて、墨の濃淡や筆の勢いを駆使して対象を描いた水墨画や、墨跡(ぼくせき)と呼ばれる禅僧の書がもたらされ、日本でもこれを学び、制作される様になる。
水墨画は、鮮やかな色彩を伴うそれまでの日本絵画とは大きく異なるものだったが、禅宗の枠を越えて広まり、日本の絵画に欠かせない技法として定着していく。
また、禅僧による墨跡は弟子たちによって大切に守り伝えられ、茶席を飾る掛物としても珍重される様になる。
この展示室では、鎌倉時代から室町時代、13世紀〜16世紀にかけて描かれた、山水図・人物図・花鳥図などの水墨画や、個性豊かで気魄に満ちた墨跡を紹介する。 - 禅宗とは
-
禅宗は仏教の宗派の一つで、6世紀にインドから中国に渡来した達磨を初祖として中国で成立し、日本には13世紀に伝わった。
禅宗では「仏法」、すなわち仏教の開祖である釈迦の悟った「真理」は、文字や経典に拠らず、坐禅を中心とした修行の過程で体験する「悟り」によって、師の心から弟子の心へと直接に伝わるものと捉えられる。 - 禅宗の導入と新たな文化の摂取
-
中国で成立した禅宗が日本に本格的に伝わるのは、鎌倉の武士たちが中国の禅僧を招き、純粋に中国式の禅宗寺院が鎌倉に創建される13世紀だった。
その後、禅宗は、都の京都でも天皇家や貴族に支持され、14世紀には現在も本山と呼ばれる中核寺院の多くが京都に創建された。
禅宗は、来日した中国人禅僧と、中国に留学した多数の日本人禅僧によって導入されたが、それに伴って中国からもたらされた新しい文化が、水墨画、墨蹟(禅僧の書)、喫茶。 - 5 武士の装い 平安〜江戸
-
平安時代末期・12世紀末から江戸時代までの約700年間は、武士が政治の実権を握った時代。
武士は公家の文化を模範としながら、仏教や庶民の文化を取り入れて、質実で力強い独自の文化を形作った。
この展示室では、武士の姿を伝える肖像画、歴史上著名な武士の書状、武士の道具の中でも最も大切にされた刀剣や鞘、甲冑や陣羽織、馬具や弓具といった武器・武具類、そして普段着用した衣服などを通して、武士の装いを紹介する。
これらの武器・武具は、時代とともに大きく変化し、武士の身分によっても作りや形状が異なる。
また、様々な素材と工芸技術を駆使して製作されており、世界的に見ても彩り豊か。
これらは、武家としての歴史や格式を示す象徴として伝えられ、時には将軍や大名たちの贈答にも用いられた。
また、武士の信仰心を表すものとして、神社や寺院に奉納されることもあった。 - 8 暮らしの調度 安土桃山・江戸
-
16世紀末期、豊臣秀吉(1537~98)が国家統一を果たし、100年にわたる戦乱の世が幕を閉じると、世の中は平穏になっていった。
朝鮮や中国からは先進的な工芸の技術が伝えられ、また南蛮貿易によって、これまでに見たこともなかった西洋や東南アジアの品々が輸入されて、日本の文化に大きな刺激をもたらした。
この時代、新たに勢力を伸ばした新興武士や経済力をつけた商人たちは、伝統にとらわれない自由闊達な文化を育むこととなる。
徳川家康(1543~1616)が江戸に幕府を開いたあと、徳川家による安定的な政権運営が260年にわたって続いた。
この時代は武家や宮廷貴族ばかりではなく、経済力を蓄えた町人たちも文化を担う様になり、趣向を凝らした品々が数多く作られた。
この展示室では、生活を彩る陶磁器や艶やかな漆塗りの器、遊び心あふれるデザインの金属細工、全身を晴れやかに飾る刺繍や染物の衣装など、平穏な時代の中で成熟した日本工芸の枠を垣間見れる。 - 9 能と歌舞伎
-
日本では古来より、神社や寺院で行われる儀式において、舞や踊り、衣装や仮面を伴う芸能や演劇を、神や仏に奉納してきた。
平安時代(794~1192)には、宮廷貴族たちによる「舞楽」が中心だった。
鎌倉時代(1192~1333)に民間で流行していた「田楽」は、続く室町時代(1392~1573)には「猿楽」へと発展、世阿弥(1363~1443)により貴族や武家の好みにあった芸能へと大成され、室町幕府の公式な芸能である式楽となった。
それが現代、伝統芸能として演じられる「能」「狂言」。
能は主として男性の役者のみによって演じられ、様々な役に合わせ、能特有の仮面が発達。
また武家の式楽となったことから、大名らが財を投じて、豪華絢爛な能装束をあつらえる様になる。
一方歌舞伎は、江戸時代(1603~1868)に庶民の娯楽として親しまれていた。
仮面をつけず、大胆な身振りや言い回しに特徴がある歌舞伎では、衣装にも奇抜で自由闊達な模様が表された。
この展示室では、日本で培われた伝統芸能に用いられる衣装や面を紹介する。 - 10-1 浮世絵と衣装 江戸(衣装)
-
日本の民族衣装である「着物」は、江戸時代に人々が表着としてきていた「小袖」(袖口の開きが狭いという意味)が原型。
小袖は宮廷貴族や武士の下着として用いられてきたが、室町時代・15世紀より、武家の日常の表着として用いられる様になった。
江戸時代・17世紀以降は、武家や宮廷貴族だけでなく、経済力をつけた町人の女性たちも、小袖に華やかな模様を施して着飾る様になった。
次々と刊行される「雛形」というファッションデザインブックを片手に、呉服屋で小袖を注文し、髪型や櫛・笄(こうがい)・簪といったアクセサリーなどと合わせて、流行のおしゃれを楽しむ様になった。
その流行の移り変わりは、江戸時代の風俗画や浮世絵に描かれた美人図に見ることができる。
また、町人の男性は縞や格子、小紋などを模様にした粋な小袖を身につけた。
帯に挟んで携帯する印籠や根付などの小物入れやアクセサリーも、素材や形、デザインにこだわった。
江戸時代における町人たちの装いには、現代にも通じるファッション感覚が見られる。 - 10-2 浮世絵と衣装 江戸(浮世絵)
-
江戸時代・17世紀半ばになると、人々の関心は同時代の流行や風俗に注がれる様になり、遊楽の様子や理想とされた女性の姿を描いた庶民向けの絵や版画が多く製作され「浮世絵」と呼ばれ人気を集めた。
浮世絵が作られ始めた頃は、絵師が自ら筆で描いた一点ものの肉筆画のみだったが、その後、一度に同じ絵をたくさん作ることのできる版画が生み出された。
版画は、最初は墨だけで摺られていたが、やがて彫りや摺りの技術に工夫を凝らして、多くの色を使った「錦絵」が誕生する。
浮世絵は、庶民の人気を集めた歌舞伎役者や遊郭の花魁などを描いて発展したが、描く対象は次第に多様となり、花鳥画や風景画なども描かれる様になっていく。
様々な浮世絵師たちによって、個性豊かな作品が多く生み出された。 - 印籠
-
薬を入れて腰に提げる小さな容器。
偏平な形のものが多く、三段から五段重ねに作り、側面に設けた孔に紐(緒)を通して各段を連結する。
緒の先には脱落を防ぐ為に帯に挟み込む「根付」が結び付けられ、緒締と呼ばれる玉をずらすことによって各段の開閉の具合を調節する仕組み。
この印籠がいつ頃使われ始めたか明らかではないが、安土桃山時代から江戸時代前期、16世紀から17世紀にかけて、次第に普及していったとみられ、江戸時代の中頃には、実際に薬を入れて用いるだけでなく、装身具としての性格が色濃く表れたものが作り出されるようになった。 - 根付
-
根付は、印籠や煙草入れに付属する小物として一般に広まったが、印籠と同じく、時を経るとともに時を経るとともに装飾品としての役割をも果たす様になる。
羽織の下にさりげなく見え隠れする根付は、今日のネクタイぴんやカフスボタンなどと同様、身につける人の趣味を表す格好の装飾具であり、象牙や木、陶磁・金属など幅広い材料を用いて、形やデザインに様々な趣向を凝らしたものが作り出されている。
特に19世紀の明治時代以降は、巧緻を極めた彫刻が外国人の注目を集め、膨大な量の根付が海外へ流出した。 - 13-1 金工
-
金工とは金属を様々な方法で加工して工芸品を作ること、あるいはその加工技法によって作られた工芸品を指す。
金属は硬く丈夫で、磨けば光り、打つと澄んだ音を出し、熱をよく伝える性質をもつ。
日本の金工は、紀元前3世紀以来の歴史をもつ。
最初は中国大陸や朝鮮半島の技術や製品に倣うことに始まり、文化的な成熟の中で、独自の技術や表現を発展させてきた。
古くから用いられた金属は金・銀・銅・鉄・錫・鉛などで、合金も含めると種類は更に多くなる。
そしてそれぞれが、独特の色や質感をもつ。
そうした個性を活かして、ここに展示している武器や武具、信仰や宗教の用具、生活用具、装飾具、銭などが作られてきた。 - 16 アイヌと琉球
-
日本列島の多様な文化の広がりを表すのが、北のアイヌ文化と南の琉球文化。
アイヌ文化は12~13世紀以降サハリン・千島・北海道・北東北のアイヌの人々が狩猟や漁撈、植物採集に加え、アムール川下流域や沿海州そして本州の和人と交易をもちつつ育んできた独自の文化。
当館のアイヌ資料は、1875年にウィーン万国博覧会の事務局から引き継いだ資料や寄贈を受けた個人コレクションから成り、様々な生活用具や衣服、そして武具や祭祀具など、膨大な数にのぼる。
琉球王国は15~19世紀、南西諸島を治め、日本はもとより中国や朝鮮半島そして東南アジアと関係を結ぶ中で、独特な文化を作り上げた。
当館の琉球資料は、1884年に当時のドイツ政府の依頼をきっかけに、農商務省が沖縄県から購入した資料や寄贈を受けた個人コレクションから成り、生活用具をはじめ、絵画や文書そして古写真も含まれる幅広いもの。 - 18 近代の美術
-
明治時代(1868~1912)の日本は武士である将軍が政治の実権を握る体制から、天皇を中心とした新しい国家体制となり、近代国家として欧米諸国に肩を並べようと、日本の伝統的な物作りと、西洋芸術の枠組みとの違いに葛藤した。
本来、生活に根ざしたしつらえとしての屏風や襖、生活を彩る陶磁や金工・漆工・染織などは、西洋の芸術観では「美術」とは見なされないものだった。
作り手は、それまでの価値観と技術を、欧米諸国に通じるものに変革するべく奮闘した。
明治政府は、海外の博覧会に参加し、国内で展覧会を開き、また美術学校を創立して、「美術」の制度を整えた。
この中で生み出された作品は、日本も欧米諸国に通用する近代国家であることを、世界に知らしめる役割を果たした。
ここでは、日本の美術制度が整えられる中で、西洋の近代思想を取り入れて、作者が自己の主張や個性を打ち出し始めた時代、その後技術と表現を極めていった大正、昭和時代の作品を紹介。 - 国立西洋美術館
-
1959年に開館した西洋美術全般を対象とした美術館としては日本唯一の国立美術館。
実業家の松方幸次郎が20世紀初めにヨーロッパで収集した印象派等の19世紀から20世紀前半の絵画、彫刻を中心とする松方コレクションが中心。
本館の設計はル・コルビュジエによるもので、日本で唯一のル・コルビュジエ設計の建築物であり、2016年に「ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-(L'oeuvre architecturale de Le Corbusier)」を構成する一要因として世界文化遺産に登録されている。
ロダンの「考える人」は、ダンテの「神曲」をモチーフとして制作された「地獄の門」の一部で、門の上から眼下に広がる地獄を覗き込んでいる。
ロダンはこの彫刻を「詩想を練るダンテ」と呼んでいたが、作品を公表するときには「詩人(Le poète)」と名付けている。
「考える人(Le penseur)」と名付けたのは、ロダン没後にこの作品を鋳造した鋳造職人のリュディエと言われている。 - カレーの市民
Les Bourgeois de Calais -
1884~88年(原型)
1953年(鋳造)
1959年(購入)
百年戦争時の1347年、イギリス海峡におけるフランス側の重要な港カレーが、1年以上にわたってイギリス軍に包囲されていた際の出来事に基づいてAuguste Rodinによって製作。
| 国立博物館 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 京都 | 奈良 | 九州 | |
| 分野 | 日本と東洋の文化財 | 京都を中心とした日本と東洋の文化財 | 仏教美術 | 日本とアジアの歴史 |
| 作品数 | 120,000 | 14,900 | 4,000 | 2,500 |
| 開館 | 1872年 | 1897年 | 1895年 | 2005年 |
| 面積 | 78ha | 25ha | 19ha | 2.8ha |
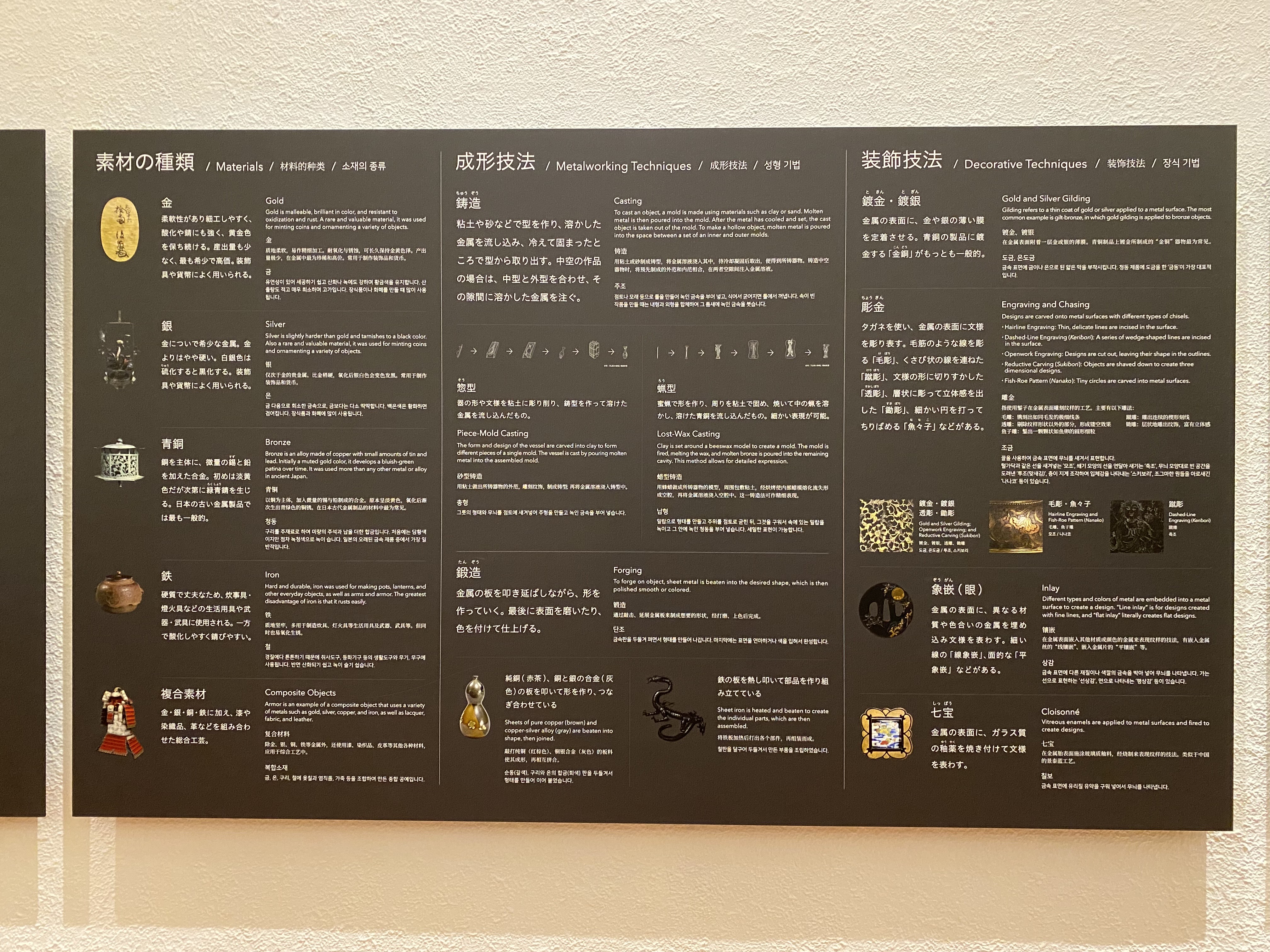
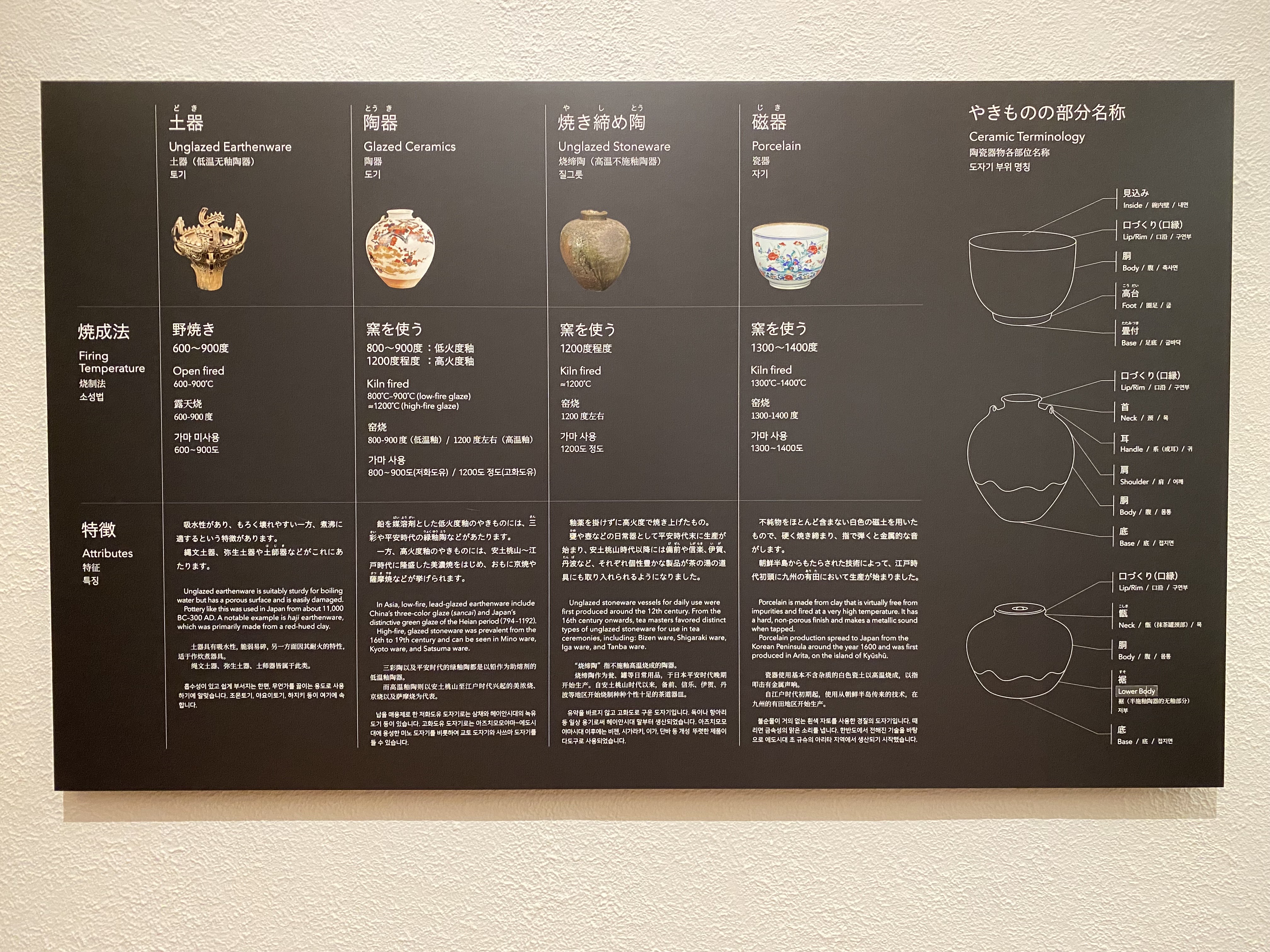
- 小松宮彰仁親王銅像
-
彰仁親王は伏見宮邦家親王の第八王子。
1858年京都仁和寺に入って純仁法親王と称し、1867年勅命により22歳で還俗、仁和寺宮と改称。
1868年1月の鳥羽・伏見の戦いに、征討大将軍として参戦。
次いで奥羽会津征討越後口総督となり、戊辰戦争に従軍。
1877年5月、西南戦争の負傷者救護団体として、博愛社が創立されると、9月その総長に就任。
1882年には、小松宮彰仁親王と改称。
1887年、博愛社が日本赤十字社と改名すると、総裁として赤十字活動の発展に貢献。
1903年2月18日、58歳で没。
銅像は1912年2月に建てられ、同年3月18日、除幕式が挙行された。
作者は文展審査員の大熊氏廣。
当地に建てた理由について、寛永寺最後の門跡・輪王寺宮公現法親王(のちの北白川宮能久親王)の兄宮であったことに因んだと推察。

- グラント将軍植樹碑
-
Ulysses Simpson Grant
1877~80年にかけて、家族同伴の世界周遊中に来日。
1879年8月25日、ここ上野公園で開催の大歓迎会に臨み、将軍はロウソン檜、夫人は泰山木を記念に植えた。
植樹の由来が忘れられるのを憂い、1933年8月この碑を建設。
碑は正面に将軍の胸像を刻み、向かって右側に和文、左側に英文で、将軍の略歴・日本滞在中の歓迎の模様、植樹の由来を記している。
胸像下部には、英語で将軍の言葉「平和を我等に」の文字を刻む。
北軍の義勇軍大佐として、南北戦争に従軍。
戦功を重ね、のち総司令官となり、北軍を勝利に導いた。
1869年、アメリカ合衆国大統領に選ばれ、1877年まで2期在任した。
今、将軍植樹の木は大木に成長している。

- 上野東照宮
- 唐門
-
1651年造営。
国指定重要文化財。
正式名称は唐破風造り四脚(よつあし)門。
柱内外の四額面には、日光東照宮「眠り猫」で有名な左甚五郎作の昇り龍・降り龍の彫刻があり、毎夜不忍池の水を飲みに行くという伝説がある。
偉大な人ほど頭を垂れるということから、頭が下を向いている方が昇り龍と呼ばれている。
扉には唐草格子、扉の上には亀甲花菱、正面上部には錦鶏鳥・銀鶏鳥の透かし彫りがあり非常に精巧。
中央左右の透かし彫りは諫鼓鳥(かんこどり)という中国の故事に由来し、皇帝が朝廷の門前に太鼓を置き、政治に誤りがあるときは人民にそれを打たせ訴えを聞こうとしたが、善政の為打たれることは無く、太鼓の台座は苔生し鶏が住み着くほどであったという話に基づいている。
天下泰平の願いを込めて彫られたと考えられている。 - 静心所と御銀杏
-
中村拓志(ひろし)設計。
社殿に至るコの字型の空間は、樹齢600年を超える御神木を中心とした「祈りの庭」
拝観前に御神木と対面して心を静める場所。
静心所の屋根架構材にはすぐ脇にあった大イチョウの木(御銀杏)を使用。
銀杏の葉は燃えにくく、延焼防止の為創建当初境内各所に植えられていた。
高さ30mの御銀杏は御神木と共に歴史があり、枝にはフクロウが住み着いていた。
しかし2020年に幹の割れと内部の空洞が確認され、倒木の可能性が浮上。
安全の為に伐採し、その御銀杏の木材を加工し静心所の屋根として使用。
大きな木だったが、内部の空洞が大きく、想定よりも木材の量や長さが取れなかった為、60mmの厚さの木材に加工し、それをずらしながら曲面を造り、シェル構造(la structure en coquille)と呼ばれる貝殻にような構造によって強度を高めた。
ここに座る一人ひとりの頭上を包み込む屋根のカーブ(la courbe)は、イチョウの葉が重なり合う様子をイメージ。
社殿を敬うように頭を垂れる軒先の前面に柱は無く、御神木・社殿・五重塔と、江戸と変わらぬ風景が何にも遮られずに目前に広がる。
静心所後方のスリットを覗くと御銀杏の切り株が見える。
切り株には新しく芽吹いた萌芽が生き生きとその幹を伸ばし、生命の強さや繋がりを感じさせる。 - 透塀
la clôture transparente -
1651年造営。
国指定重要文化財。
向こう側が透けて見える塀。
社殿の東西南北を囲んでおり、上段には野山の生き物と植物、下段には海川の生き物が200枚以上彫られている。
獣、鳥、魚、蛙、貝、鯰、蝶、蟷螂や想像上の動物。
彫刻は造営当時は極彩色だったが、その後の修理の時、弁柄漆で上塗り。
※弁柄漆…漆に酸化鉄顔料である弁柄を混ぜた色漆で、金属粉を撒く前の下塗りとして使われ、金属粉の発色を鮮やかにする。
弁柄の主成分は酸化第二鉄で、黄土を加熱することで得られる。
2009年~2013年の保存修理工事では江戸造営当時の姿を蘇らせる為に全ての彫刻に彩色を行った。
絵具は造営当時と同じ岩絵具を使用し、生彩色(いけざいしき)を施した。
金箔で彫刻を覆った上から絵具で彩色を行う豪華な彩色方法。 - 栄誉権現
-
四国八百八狸の総帥。
奉献された大奥で暴れ追放後、大名、旗本、諸家を潰し、大正年間本宮に奉献された悪業狸。
他を抜く強運開祖として信仰が厚い。
縁起日は5の日。 - 社殿
-
1651年造営。
国指定重要文化財。
文化財保護の為社殿内非公開。
参道側から拝殿、幣殿(石の間)、本殿の3つの部屋から構成される権現造。
金箔が多量に使用されており、別名金色殿。
社殿外壁の彫刻は鷹、鶴、鳳凰や獅子が力強く表現されている他、松・菊・牡丹・芙蓉などの植物も美しく施されている。
柱上部や彫刻周囲の文様は置上彩色(おきあげざいしき)で装飾されている。
胡粉(ごふん)を何度も塗り重ねて厚みを出し、その上から金箔を貼ることで、文様が立体的に輝くよう工夫された豪華な彩色方法。 - きささげの木
-
中国原産のノウゼンカズラ科の落葉高木。
1651年の社殿造営時に雷除けの願いを込めて植樹。
樹齢350年以上。
雷から社殿を守ると信じられてきた。
夏には香りの良い淡黄色の花を咲かせる。
細長いその果実は梓実(しじつ)、樹皮は梓白皮(しはくひ)と呼ばれ、昔から生薬としても使われている。 - 大鈴
-
当宮の狛犬を彫った石工・酒井八右衛門が1874年6月に奉納。
大鈴には駒込肴町は現在の文京区向丘一丁目。
この地で石屋を営んでいた酒井八右衛門は「井亀泉(せいきせん)」の名で名石工として知られ、廣郡鶴(こうぐんかく)・窪世祥(くぼせしょう)とともに江戸三大石匠に数えられた。
井亀泉は江戸時代から昭和初期まで4代にわたり各地に多くの石造物を残した。
- 上野大仏
-
1631年、越後国村上城主堀丹後守直寄公がこちらの高台に、戦乱に倒れた敵味方の冥福を祈る為に建立した釈迦如来。
京都方広寺の大仏に見立てられ、当初は漆喰で作られたが、1655~60年頃、木食浄雲(もくじきじょううん)という僧侶により高さ6mの銅仏に改められた。
また1698年には輪王寺宮公弁法親王により大仏殿が建立され、伽藍が整った。
しかし大仏は江戸時代以来、地震や火災といった災難に何度も見舞われた。
幕末の上野戦争では辛くも被害を免れたが、1873年に大仏殿が解体され、さらに1923年の関東大震災で首が落ちた。
第二次世界大戦では軍によって胴体が徴収されてしまい、現在は顔のみが残る。
大仏に降りかかった幾多の災難から「もうこれ以上は落ちない」として、合格祈願に来る受験生に人気。
- 博物館動物園駅跡
-
1933年に竣工した「博物館動物園駅」
6灯の壁付照明器具が、三方に開いた出入口を照らしていたが、第二次世界大戦の金属供出により取り外された。
この駅舎と地下駅空間の保存と再生を願い20年間にわたる活動を続けてきた市民グループ、NPO法人<上野の杜芸術フォーラム>による企画と募金活動により、2010年、漸く1灯の復元が成った。
芸術の中枢機能が集積するこの交差点<アートクロス上野>に向けた光を復活させるもの。
- アメヤ横丁
-
正式名称「アメ横商店街連合会」。
第二次世界大戦直後、砂糖が手に入りにくかった時代に、露店で飴を販売し、甘味に飢えた人々の間で好評を博した「アメ屋横丁」と、戦後に駐留した米軍の横流し品である払い下げ衣類などを扱うようになった「亜米利加横丁」の2つが由来。
現在約390店舗が軒を連ねている。
- 摩利支天徳大寺
- 6:30~18:30
- 創建…1653年(未詳)
- 本尊…大曼荼羅
- 開基…日遣
- 宗派…日蓮宗
-
摩利支天(マリシは「威光・陽炎」の意)とは、仏教を守護する天部の神で、参詣祈願の人々に「気力・体力・財力」を与え、「厄を除き、福を招き、運を開く」、諸天善神中最も霊験顕著な守護神であると伝えられている。
そのお姿が猪の背に立つことから、古くより十二支の亥の日が御縁日とされてきた。
人が摩利支天の名を知り念ずれば、一切の厄災から逃れ勝利の功徳を得るとして、我が国においては中世以降、武士階級の守護神として摩利支天への信仰が広がった。
楠木正成や足利尊氏、毛利元就や徳川家康などの武将たちは、摩利支天の尊像や旗印と共に合戦に出陣したと云われ、『忠臣蔵』で知られる大石内蔵助も髷の中に摩利支天の小像を入れて討ち入りに臨み、本懐成就を遂げたと伝えられている。
まさに、諸難を退け勝利に導く、武門の護り厚き守護神として、町人文化が栄えた江戸時代中期以降には、民衆の間にも摩利支天信仰が盛んとなった。
当山は日本三大摩利支天の一つ、下谷摩利支天と呼ばれ、江戸時代から下谷広小路(現・上野広小路)において、聖徳太子の御作と伝わる摩利支天像を祀っている。
昨今では、「開運厄除・除災得幸」のご祈祷はもとより、「家内安全・商売繁盛」などの御祈願、政治・芸能・スポーツに関わる方々の「必勝・心願成就」の御祈願など、我が身をお守りくださる「上野広小路の摩利支天様」として、広く全国からの崇敬を集める。 -
摩利支天徳大寺縁起
徳大寺は、江戸時代初めの寛永年間に慈光院日遣上人によって創建され、正式には日蓮宗・妙宣山徳大寺。
また、仏教の守護神である開運大摩利支尊天を奉安することから摩利支天徳大寺とも称し、下谷広小路(現在の上野広小路)に位置したことから下谷摩利支天とも呼ばれていた。
そもそも摩利支天とは「威光」あるいは「陽炎」と訳され、常に日天に先んじて進み、大自在神通の力を以て昼夜の別なく光を放ち、参詣祈願の面々に「気力・体力・財力」を与え、「厄を除き、福を招き、運を開く」、福寿吉祥開運勝利を誓い給いし、諸天善神中最も霊験顕著なる守護神といわれ、我が国では古来より武士階級からの篤い崇敬を受けてきた。
寺宝として奉安する摩利支天像は、江戸時代中期の京都にて霊夢感得された御尊像と伝わり、1708年に当山へ安置された。
以来、聖徳太子の御作と伝わる御尊像に開運吉祥の利益を授かろうと、全国よりの絶えざる善男善女の参詣により山門は俄然活況を呈し、いつしかその門前通りは下谷広小路の摩利支天横丁と呼ばれるようになった。
その後、1923年の関東大震災、1945年の戦災による火災類焼によって、堂宇は二度にわたり灰燼に帰したが、奉安の御尊像は幸いにもその都度焼失を免れた。
そして終戦後の混乱期、闇市の形成などによる街並みの変化に伴い、移転再建が検討されながらも創建以来の此の地に留まり、昭和39年11月、堂宇再建の悲願が結実され全伽藍の復興果たし、今日の姿に至る。
本堂正面に掲げられる扁額「威光殿」は、威光の化身たる大摩利支尊天の拝殿の意として、吉田茂総理大臣の揮毫により寄贈されたものである。
寛永の時代より凡そ400年、寺社町として栄えた上野広小路に残る最後の寺院として今日も大摩利支尊天をお祀りし、有縁の清衆の現世安穏、後生善処の浄願を祈念する。
- 上野藤木屋本店
-
男性用浴衣、甚平、作務衣の専門店。
品揃えが豊富で、全て新品。
近隣に女性用浴衣専門店や着物男子喫茶キザエモンがある。
株式会社藤木屋の創業は2012年。
| 住所 |
東京都 台東区 東上野5-5-9 |
|---|---|
| 電話 | 03-5830-6355 |
| 営業時間 | 11h00~19h00 |
| 定休日 | 火曜日 |
| 支払 | 不明 |
| リンク | 公式サイト |
- ゆかた専門店『浴衣屋わそべ』
-
藤木屋の女性用浴衣専門店。
品揃えが豊富で、全て新品。
| 住所 |
東京都 台東区 東上野5-7-10 |
|---|---|
| 電話 | 03-6802-7253 |
| 営業時間 | 11h00~19h00 |
| 定休日 | 火曜日 |
| 支払 | 不明 |
- 夢追舞
着物ドリーマーズ -
2020年2月1日にオープンしたリサイクルきものショップ。
実際、リサイクル品は少なく、ほぼ新品
価格帯は非常に良心的。
オーナーの近藤康成氏が一人で切り盛り。
営業日時は不規則な為、Twitterで要確認。
| 住所 |
東京都 台東区 上野5-4-3 |
|---|---|
| 営業時間 | 12h00~20h00 |
| 定休日 | 不定休 |
| 支払 | 不明 |
| リンク | 公式サイト |
| リンク | 公式Twitter |
谷根千
- 谷根千の歴史
-
1625年に江戸城の鬼門にあたる上野に寛永寺が創建され、それに伴い上野に程近い谷中には多くの寺が建てられた。
更に1648~51年に幕府の政策で隣接区の神田界隈から多くの寺院が谷中に移転してきた。
現在でも谷中には70以上の寺院が点在する。
谷中霊園は1874年に開園した霊園で、10haの敷地内に7,000基の墓地がある。
創業1900年の和菓子屋「谷中岡埜栄泉」をはじめ、数多く残る趣のある建物は、第二次世界大戦中に空襲の被害に遭わないようにあえて取り壊して、辺り一帯を更地にした。
そして、終戦後すぐに建て直した為、戦果を免れ、戦後から今に至るまで歴史的景観が保たれてきた。
- 谷中銀座商店街
-
1945年頃に自然発生した商店街。
170mに60店舗。
- 金吉園
Kanekichien -
1955年に設立された株式会社金吉商店の実店舗。
茶葉、茶器、乾物類の卸し、販売。
| 住所 |
東京都 台東区 谷中3-11-10 |
|---|---|
| 電話 | 03-3823-0015 |
| 営業時間 | 土日月火金10h00~18h00 |
| 定休日 | 水木 |
| 支払 | 現金、カード、QR |
| リンク | 公式サイト |
- 団子の由来
-
半坂も団子も
月のゆかりかな
子規
江戸文化開花期の文化文政の頃、遥かな荒川の風光に恵まれたこの辺り日暮らしの里は、音無川のせせらぎと小粋な根岸の三味の音も聞こえる塵外の小天地であった。
1819年、小店の初代庄五郎がここ音無川のほとり半坂に「藤の木茶屋」を開業し、街道往来の人々に団子を供した。
この団子がキメが細かくて羽二重の様だと称され、そのまま菓名となって、いつしか商号も「羽二重団子」となり、創業以来今も江戸の風味と面影を受け継いでいる。
- 旧吉田屋酒店
-
江戸時代から代々酒屋を営んでいた「吉田屋」の建物。
1910年に建てられた出桁造(だしげた)は、腕木より軒桁が張り出しており、正面入口には板戸と格子戸の上げ下げで開閉する揚戸(あげと)が設けられている。
江戸時代中期から明治時代の商家建築の象徴的建物。
- 東叡山寛永寺
-
1622年、徳川幕府二代将軍秀忠が、上野の地を天台宗の僧天海に寄進したことから、寛永寺の歴史は始まる。
本坊は1625年に竣工。
根本中堂の完成は1698年。
江戸末期までの寛永寺は、今の上野公園をはじめ、その周辺にも堂塔伽藍や子院が立ち並ぶ文字通りの巨刹であり、徳川将軍家ゆかりの寺に相応しい威容を誇っていた。
明治維新の際の上野戦争で大半が炎上し、その後明治政府の命令で境内も大幅に縮小され(約3万坪、江戸時代の1/10ほど)現在に至る。 - 了翁禅師塔碑
-
了翁禅師(1630~1707)は、江戸時代前期の黄檗宗の僧。
俗姓は鈴木氏。
出羽国雄勝郡に生まれ、幼い頃から仏門に入り、後に隠元禅師に師事する。
諸国を巡るうち、霊薬の処方を夢に見て「錦袋円」と命名し、不忍池付近に薬屋を俗甥の大助に営ませる。
その利益で難民救済や寛永寺に勧学寮(図書館)の設置などを行なった。
こうした功績により輪王寺宮から勧学院権大僧都法印位を贈られる。
1707年78歳で没し、万福寺塔頭天真院に葬られた。
本碑は了翁禅師の業績を刻んだ顕彰碑で、生前に作られた。
元々建てられた場所や、現在の場所に移築された時期などは不明。 - 増山雪斎博物図譜関係資料 虫塚碑
-
虫塚は伊勢長島藩主、増山雪斎が写生図譜である『虫豸帖(ちゅうじじょう)』の作画に使った虫類の霊を慰める為、雪斎の遺志によって1821年に建てられた。
増山雪斎は、1754年に江戸で生まれた。
本名は正賢。
江戸の文人大田南畝や大阪の豪商木村蒹葭堂(けんかどう)など、広く文人墨客と交流を持ち、その庇護者としても活躍した。
自ら文雅風流を愛し、清朝の画家、沈南蘋に代表される南蘋派の写実的な画法に長じ、多くの花鳥画を描いた。
中でも虫類写生図譜『虫豸帖』はその精緻さと本草学に則った正確さにおいて、殊に有名。
1819年66歳で没。
虫塚は当初、増山家の菩提寺、寛永寺子院勧善院内にあったが、昭和初期に寛永寺に合併された為、この場所に移転。
勧善院は、4大将軍家綱の生母で、増山氏の出である宝樹院の霊廟の別当寺として創建。
碑は安山岩製で台石の上に乗る。
正面は、葛西因是の撰文を大窪詩仏が書し、裏面は詩仏と菊池五山の自筆の詩が刻まれており、当時の有名な漢詩人が碑の建設に関わったことが知られる。 - 旧本坊表門・根本中堂 鬼瓦
-
この鬼瓦は、現在「黒門」の通称で親しまれている、寛永寺旧本坊表門(国指定重要文化財)に据えられていたもの。
旧本坊表門は1624年に、寛永寺の開山である天海大僧正自身が建てたものであり、天海自身をはじめ、いわゆる歴代の輪王寺宮が住まわれた場所の門。
この門は、1937年現在の東京国立博物館の地から現地に移築され、2010年から行われた解体修理によって修復。
この時の調査により、現鬼瓦の制作年代は不明ながら、東側の「阿」形より西側の「吽」形が古いこと、かつては鳥衾(とりぶすま)(鬼瓦の上に長く反って突き出した円筒状の瓦)を接合する部分が設けられていたが、現在の鬼瓦には鳥衾を取り付けた痕跡が無かったことが分かっている。
東側にあった「阿」形は耐用年数を過ぎていた為、修復の折に西側に意匠を合わせて作り替え、新たな息吹を門に与えている。
この修復を機会として寛永寺根本中堂の屋根にあった鬼瓦と合わせ、ここに展示。 - 旧本坊表門鬼瓦「阿」形
高さ113cm×横幅118cm - 寛永寺根本牛堂鬼瓦
高さ248cm×横幅325cm - 慈海僧正墓
-
墓石正面中央に、聖観世音菩薩像を彫り右側には「当山学頭第四世贈大僧正慈海」、左側に「山門西塔執行宝園院住持仙波喜多院第三十世」、背面に「元禄六年癸酉二月十六日寂」と刻む。
慈海僧正は、学徳をもって知られ、東叡山護国院、目黒不動尊、比叡山西塔宝園院、川越仙波喜多院を経て東叡山凌雲院に入った。
東叡山は、寛永寺一山の山号で、一山を統轄、代表する学頭には凌雲院の住職が就任することを慣例とした。
学頭は、また門主・輪王寺宮の名代を務めうる唯一の有資格者であり、学頭の名の通り、宮や一山の学問上の師でもあった。
1624年目黒で生誕。
70歳で没後、公弁法親王の奏請によって大僧正の位が贈られた。
墓は初め凌雲院内にあったが、1958年東京文化会館建設の為寛永寺に移った。 - 尾形乾山墓碑・乾山深省蹟
-
尾形乾山は、琳派の創始者尾形光琳の弟。
1663年京都で生まれる。
乾山の他、深省・逃禅・習静堂・尚古斎・霊海・紫翠の別号がある。
画業の他にも書・茶をよくし、特に作陶は有名で、1711~35年間、輪王寺宮公寛法親王に従って江戸に下り、入谷に窯を開き、その作品は「入谷乾山」と呼ばれた。
1743年81歳で没し、下谷坂本の善養寺に葬られた。
しかし、月日の経過につれ、乾山の墓の存在自体も忘れ去れれてしまい、光琳の画風を慕う酒井抱一の手によって探り当てられ、1823年、顕彰碑である「乾山深省蹟」が建てられた。
抱一は江戸琳派の中心人物で、1815年に光琳百回忌を営み、『光琳百図』『尾形流略印譜』を刊行、1819年には光琳の墓所を整備するなど積極的に尾形兄弟の顕彰に努めた人物。
墓碑及び「乾山深省蹟」は、上野駅拡張の為移転した善養寺(現・豊島区西巣鴨4-8-25)内に現存し、東京都旧跡に指定。
当寛永寺境内の2つの碑は、1932年、その足跡が無くなることを惜しむ有志により復元建立さえれた。
その経緯は、墓碑に刻まれ、それによると現善養寺碑は、明治末の善養寺移転に際し、両碑共に当時鶯谷にあった国華倶楽部の庭へ、1921年には公寛法親王との縁により寛永寺境内に、その後、西巣鴨の善養寺へと3度移転を重ねた。
なお、入谷ロータリーの一隅に「入谷乾山窯元碑」がある。
- 浄名院
-
1666年、開山の天台宗寺院。
八万四千体地蔵の寺として有名。
1879年に住職の妙運和尚が84,000体の地蔵菩薩像建立発願。
また別名「へちま寺」としても有名。
喘息治癒の功徳があるとされ、旧暦8月15日に「へちま供養」が執り行われる。 - 八万四千体地蔵
-
この寺の名前は初め浄円院といい、1666年寛永寺三十六坊の一つとして創建。
1723年浄名院となる。
表門は1716~35年の建立。
地蔵信仰の寺となったのは第三十八世地蔵比丘妙運和尚の代からである。
妙運和尚は大阪に生まれ、25歳で日光山星宮の常観庵にこもった時地蔵信仰を得、1,000体の石造地蔵菩薩像建立の発願を立てた。
1876年浄名院に入り、1879年、さきの1,000体の願が満ちると、さらに84,000体建立の大誓願に進んだ。
1885年には地蔵山総本尊を建立。
各地から多数の信者が加わり、地蔵菩薩像の数は増え続くている。
境内にある青銅製の大きな地蔵菩薩坐像は、かつて江戸六地蔵第六番の地蔵菩薩像があった深川永代寺が明治維新の時廃寺になった為と、日露戦争の戦没者を弔う為、1906年新たに建立された物である。
- 天王寺
- 銅造釈迦如来坐像
-
1690年建立。
1933年6月の修理により、鉄筋コンクリート製の基壇を新築してその上に移された。
さらに1938年には、基壇内部に納骨堂を増設し今に至る。
「丈六仏」とは、釈迦の身長に因んで1丈6尺(4.85m)の高さに造る仏像を言い、坐像の場合はその半分の高さ、8尺(2.42m)に造るのが普通。
- 駒込大観音(光源寺)
-
浄土宗寺院光源寺は1589年に神田で創建され、江戸城拡大に伴い1648年に現在の地へ移された。
奈良の長谷観音を模した十一面観音像の高さは6m以上。
観音像は1688~1704の間に建立されるも東京大空襲で焼失し、1993年に再建。
毎年7月9日、10日は「ほおづき千成り市」で賑わう。 - 十一面観音立像
-
奈良県の長谷寺本尊の十一面観音を模して1697年に建立。
高さ約8mで、地蔵菩薩の持ち物である錫杖を持ち、岩の上に立つ独特の様式で、お地蔵様の慈悲(miséricordieux)を併せ持つ観音様として古来人々の信仰を集めた。
1945年5月25日の東京大空襲により本堂とともに焼失。
1993年に木曽檜(cyprès)の寄木造に漆塗りと金箔を用いた高さ6mの像として再建。
また、像の後方壁面には「妙法蓮華経観世音菩薩普門品偈」(仏や教えを讃える語句を記した文章)が陶板に記されている。
境内に点在設置してある石は創建時の観音像の台座として用いられていたもの。
- 蓬莱梅
-
樹齢300年の白梅。
かつてこの大観音堂の傍に梅の古木があったが1945年5月25日の空襲で観音堂と共に焼失。
大観音堂再建にあたり代替の梅の木を各地に探し求めたが、榛名山の麓でこの梅を見つけてここへ移植した。
蓬莱梅の名称は住居表示改正前、ここの町名であった駒込蓬莱町日なんで名付けられた。 - 庚申待万遍講中庚申塔
-
青面(しょうめん)金剛立像を主尊とする笠付角柱型の庚申塔。
1772年9月造立。
基礎の上に塔身・笠、最上部に宝珠を乗せた大型の庚申塔。
塔身正面に一面六臂の青面金剛立像を浮き彫りし、その下には青面金剛に踏まれた邪鬼や岩座の中に三猿を浮き彫りする。
塔身向かって右側面及び左側面には施主銘「庚申待万遍講中」や願文が、裏面には「南無阿弥陀仏」が刻まれる。
また、上段の基礎の四面全てと下段の基礎の正面には200名を超える人名が刻まれている。
これらは、本庚申塔造立に関係した人々。
本庚申塔は保存状態が良好で、かつ規模も大きく、江戸時代中期の貴重な庚申塔。
庚申塔向かって左の阿弥陀如来と千手観音の石像は、駒込大観音を建立した江戸の町人・丸屋吉兵衛の供養塔。



- 夏目漱石旧居跡
-
夏目漱石、本名・金之助(1867〜1916)
この地にイギリス留学から帰国後、1903年3月~1906年12月の間3年10ヶ月住んだ家があった。
当時、東京帝大英文科、第一高等学校講師だった漱石は、この地で初めて創作の筆をとった。
その作品『吾輩は猫である(Je suis un chat)』の舞台として「猫の家」と呼ばれ親しまれた。
この地で『倫敦塔』『坊っちゃん』『草枕』等の名作を次々に発表し、一躍文壇に名を現した漱石文学発祥の地。
旧居は愛知県犬山市の「明治村」に移築保存してある。
- 涅槃山究章院西教寺
- 願行寺
- 根津神社
-
記紀(la chronique)に伝わる日本の古代皇族(le prince)である日本武尊(西暦82年~111年)が東征の際、武神須佐之男命の御神徳を仰ぎ千駄木の地に創祀したとされる。
15世紀後半に太田道灌が社殿を奉建。
神仏習合(le syncrétisme des kamis et bouddhas)の時代には根津権現社と呼ばれ、 -
根津三社大権現と呼ばれた。
徳川5代将軍綱吉に嗣子がいなかったため、甥(le neveu)の家宣を世継ぎ(héritier)に決めた。
元々根津権現社は現在地から600mほど北の団子坂上にあった。
1706年、綱吉は世継ぎを決めると、家宣が江戸城へ移る時、屋敷跡を産土神である根津権現へ献納し、社殿を造営した。
その後も第6代家宣、第7代家継治世においても根津権現は徳川将軍家の崇敬を集め、例祭の際には江戸城内に神輿が入ることを許された為、天下祭の一つに数えられた。
しかし、第8代将軍吉宗の治世に行われた享保の改革による幕閣の倹約政策によって、例祭は公営から民営へと切り替わり、規模も縮小された。 - 摂社
乙女稲荷神社 -
祭神…倉稲魂命(ウカノミタマ)
日本神話に登場する女神。
穀物(la céréale)の神で、伏見稲荷大社の主祭神。
根津神社遷座時、境内西側の傾斜面の中腹に洞を穿つ形で祀られた。 - 摂社
駒込稲荷神社 -
根津神社が千駄木村より遷座する前、この地は6代将軍の父徳川綱重公の山手屋敷だった。
その屋敷の守り神として、1661年に祀られた社。
綱重公は他の江戸別邸、桜田屋敷・三田屋敷・浜屋敷(今の浜離宮)にも同じ稲荷を祀っており、浜離宮内の祠は当初同様今も残っている。
鳥居は一基100,000円から奉納。 - 願掛けかざぐるま
-
駒込稲荷の御祭神級長津彦命(しなつひこのみこと)・級長戸辺命(しなとべのみこと)は風の神様。
かざぐるまに願いを込めて駒込稲荷神社に奉納する。- かざぐるまを根津神社社殿右隣の授与所前で受け取る
- かざぐるまに3回息を吹きかけて回す
- 回目…穢れを祓う
- 回目…新しい流れを起こす
- 回目…願いを込める
- 奉納台へかざぐるまを納める(持ち帰り可)
- 駒込稲荷神社で参詣する(二礼二拍手一礼)
- 庚申塔
-
ここに六基の庚申塔がある。
道に建てられたものが、明治以降の道路拡幅の為に根津神社内に納められた。
正面から左回りに刻まれた像、銘文を見ると
- 青面金剛・猿・鶏・1668年・駒込村・施主・・・
- 観音像・庚申供養・施主12名
- 日月瑞雲・青面金剛・鬼・鶏・1692年・施主26名
- 日月・青面金剛・猿・1680年・願主1名
- 梵字・庚申供養・1632年・都島庚馬米村・施主7名
- 日月・青面金剛・鬼・猿・駒込千駄木町・施主10名
都内最古は、足立区花畑にある1623年のもので、これより9年前の建立。
青面(しょうめん)金剛は、病魔・悪鬼を祓う庚申信仰の本尊。
猿は庚申の神の使いとされ、見ざる・言わざる・聞かざるの三猿は、そのような慎み深い生活をすれば神の恵みを受けられるとされた。 - つつじヶ岡
-
下屋敷時代、屋敷西側の丘に躑躅の名所館林よりキリシマツツジを移植したことに始まった。
現在の躑躅は、戦災で被災した社殿の修復が終わった後、荒れていた丘に3,000株を増殖したもので、春には100種3,000株のツツジが咲き誇る。 - 例祭
-
第6代将軍家宣が例祭を定め、1714年以降9月12日に執り行われる。
山王祭、神田祭と並び、天下祭と呼ばれる。
現存する大神輿は3基で、家宣による奉納。
| 主祭神 | 須佐之男命 大山昨神 誉田別命 |
|---|---|
| 創建年 | 不詳 1900年前 |
| 本殿 | 権現造 |
| 垂迹神 | 本地 |
|---|---|
| 素盞烏尊 | 十一面観音菩薩 |
| 山王大権現 | 薬師如来 |
| 八幡大菩薩 | 阿弥陀如来 |
- 金田一京助・春彦 旧居跡
-
本郷4-11-6
言語学者である金田一京助は、1882年岩手県盛岡市生まれ。
東京大学言語学科卒業後、1942年から同大学で教授職に、後に國學院大学教授となる。
東京大学在学中からアイヌ民族に関わる言語、文学、民俗の研究を始め、北海道・サハリン(樺太)のアイヌ居住地を歴訪し、実地調査と研究により、アイヌ語を初めて学問的に解明し、アイヌの叙事詩ユーカラを世に初めて紹介。
アイヌに関する多くの著書は、日本列島における北方文化を学ぶ原点にもなっている。
これら数々の功績により、1954年には文化勲章が授与された。
盛岡中学時代、2年下級に石川啄木が在籍していた。
啄木は中学卒業後、盛岡から上京、京助を尋ね、急速に文学への関心を高めていった。
京助は啄木の良き理解者であり、金銭的にも、精神的にも、類稀な援助者だった。
金田一京助の長男で国語学者の春彦は、1913年にここ本郷で生まれた。
1920年からの5年間、近くの真砂小学校(現・本郷小学校)に在籍。
この頃唱歌の音階に関心を持ち、それが後の平家琵琶やアクセント研究のきっかけとなった。
東京大学国文学科卒業後、名古屋大学、東京外国語大学、上智大学などで教鞭と執った。
全国各地のアクセントを調査研究し、国語アクセントが歴史的かつ体系的に変化することを初めて実証した。
また、数多くの国語関係辞書等の編纂を通じて、その研究成果を一般に普及させた。
1997年、第50回文化功労者表彰受賞。
2001年、東京都名誉都民。
- 東京大学
-
在籍学生数約30,000人
総敷地面積約325,000㎡
授業料(4年間)3,000,000円
- 上野英三郎(1872~1925)博士とハチ公(1923~1935)
-
秋田犬のハチは秋田県大館市に生まれ、生後50日ほどで東京帝国大学農学部(la faculté d'agriculture)の上野英三郎(ひでさぶろう)博士に贈られた。
犬好きだった博士はハチを渋谷駅まで連れて行った。
ちなみに、当時の農学部は駒場にあった。
1923年の関東大震災後の1935年に本郷へ移転。
学生たちは教授の飼い犬を呼ぶ捨てにすることを憚り「ハチ公」と呼んで敬意を表した。
1年半が過ぎた1925年5月21日、博士は大学構内で脳溢血(une hémorragie cérébrale)により急死。
それからハチは死ぬまでの10年間、朝夕に渋谷駅に通い、博士の姿を探し求めた。
生前、博士が長期出張(long voyage d'affaires)から渋谷駅に戻った時、改札口でひとり待つハチに驚き(ça l'a étonné)、この像のように、互いにじゃれ合って喜んだという。
2015年植田努
- 異人坂
-
文京区弥生2-13北側
坂上に明治時代東京大学のお雇い外国人教師の官舎があった。
ここに住む外国人は、この坂を通り、不忍池や上野公園を散策した。
当時は、外国人が珍しかったことも手伝って、誰いうとなく、外国人が多く上り下りした坂なので、異人坂と呼ぶようになった。
外国人の中には、有名なベルツ(ドイツ人)がいた。
1876年ベルツは東京医学校の教師として来日し、日本の医学の発展に貢献した。
ベルツは不忍池を愛し、日本の自然を愛した。
- 太田錦城墓
-
太田錦城(1765~1825)は江戸時代中期の儒学者で、名は元貞、字は公幹、才佐と称し、錦城は号。
加賀国大聖寺に生まれ、当時の大儒であった皆川淇園(きえん)、山本北山に折衷派を学んだが満足せず、漢代以降の中国の諸説を直接研究し、一家の学を建てた。
晩年に至り、一時京畿に遊び、三河国吉田藩に仕えたが、加賀国金沢藩から賓師として招かれ、三百石を給せられた。
文政8年4月23日、61歳で没。
著書に「九経談」「春草堂詩集」「鳳鳴集」など非常に多くの著述があり、長男は加賀侯に仕え、三男は吉田侯に儒学をもって仕えた。
- 瑞輪寺
-
日新は幼少期の徳川家康に学問を教えた。
家康天下統一後の1591年に学問教育の謝儀を表して慈雲山瑞輪寺を創建。
当時は馬喰町にあったが、1649年に現在地へ移転。
江戸十大祖師の一つ。 - 江戸十代祖師
- 江戸に10箇所ある日蓮寺院を参拝することにより祖師(日蓮)のご利益にあずかろうという民間信仰。
- 押尾川の乱
-
1975年3月28日に8代元大関佐賀ノ花が亡くなる。
後継者争いに、押尾川親方(17代元大関大麒麟)が名乗りを上げるが、他にも金剛(最高位関脇)をはじめ多くの親方が挙手。
暫定的に最長老である湊川親方(10代元前頭筆頭十勝岩)が9代目二所ノ関親方となる。
実際、大おかみ(佐賀ノ花の妻)は後継者に金剛を望んでおり、同年9月場所前に金剛が佐賀ノ花の娘と結婚し、婿養子となることで後継者に正式決定。
納得がいかない押尾川親方は、力士16名とともに分家独立を願い出るが、大おかみは許さず、押尾川親方は弟子とともに二所ノ関部屋を飛び出して瑞輪寺に籠城。
相撲協会は「一門内で解決せよ」として介入せず、門内の花籠親方(11代元前頭3枚目大ノ海)が調停に向けて動き、9月場所後に押尾川部屋創設と弟子16名中6名の移籍を認め決着。
なお、この時移籍を認めらなかった天龍は間もなく引退してプロレスに転向。 - 客人稲荷大明神縁起
-
お釈迦様が衆生を救済する為に菩薩様の姿となり現れた法華経の御守護神であり、商売繁盛、千客万来、我々に救いの手を示してくださる神様。
その御姿は女神であり、左肩に稲束を持ち、右手に鎌を持ち、宝珠を携えた白狐に乗る。
客人稲荷様が持つ鎌、稲束は共に五穀豊穣を表し、更には鎌で悪の因縁を摘み、退散させる意味を持つ。
白狐は、客人稲荷様が清浄な存在であること、そして神通力を備えることを象徴し、宝珠は開運招福を意味する。
| 創建 | 1591年 |
|---|---|
| 宗派 | 日蓮宗 |
| 本尊 | 祖師像 |
| 法苑山浄心寺 | 深川浄心寺 | 江東区平野2-4-25 |
|---|---|---|
| 平河山法恩寺 | 本所法恩寺 | 墨田区太平1-26-16 |
| 龍鳴山本覚寺 | 日限本覚寺 | 台東区松が谷2-8-16 |
| 安立山長遠寺 | 土富店長遠寺 | 台東区元浅草2-2-3 |
| 妓楽山妙音寺 | 池の妙音寺 | 台東区松が谷1-14-6 |
| 慈雲山瑞輪寺 | 谷中瑞輪寺 | 台東区谷中4-2-5 |
| 報新山宗延寺 | 下谷宗延寺 | 杉並区堀ノ内3-52-19 |
| 妙祐山宗林寺 | 谷中宗林寺 | 台東区谷中3-10-22 |
| 正定山幸國寺 | 布曳幸國寺 | 新宿区原町2-20 |
| 妙祐山幸龍寺 | たんぼの幸龍寺 | 世田谷区北烏山5-8-1 |
神田・御茶ノ水・秋葉原
- 秋葉原
-
1869年、火事が多かった秋葉原界隈に30,000㎡の火除け地を設置。
1883年に東京電灯会社(現在の東京電力)が設立され、1887年に茅場町で初の火力発電所設置。
当時は家庭や工場に電気を引こうとすると、技術者による電気工事が必要だった。
当初は電力会社が請け負っていたが、次第に元従業員が独立して各自仕事を受けるようになる。
1925年にNHKがラジオ放送を開始。
情報収集の手段と娯楽の手段として急速に普及。
当時のラジオは組み立て式が一般的で、数多くのラジオ部品専門問屋が軒を連ねた。
戦後開かれた闇市がラジオ部品を主に扱うようになり、1951年の露店整理令でガード下へ収容された。
1990年代後半からアニメ、ゲームのソフトを扱う店舗が増え始める。
元々PC部品を求めて専門店に足を運ぶパソコン愛好家が、ゲーム、アニメ、フィギュアに興味の対象を広げていったことから、それらの需要に応える形で店の様相が変化。
2004年にインターネット掲示板「2ちゃんねる」への書き込みから生まれた「電車男」がブームとなり、オタク文化が一部マニアから一般大衆化した。
万世橋から末広町まで約600m - メイドカフェ
-
世界初のメイド喫茶は2001年3月オープンの「Cure Maid Café」で、2004年8月には「あっとほぉーむカフェ」がドンキホーテ内にオープン。
2008年4月には「めいどりーみん」開店。
店舗数は「めいどりーみん」が国内17店舗、海外3店舗で最大規模。
一方、「あっとほぉーむカフェ」は国内のみで11店舗を展開。
同カフェはビラ配りを一切しない。
- ゲームセンター
-
1931年、松屋浅草の屋上に開設されたスポーツランドが原点。
2020年8月29日にオープンした「タイトーステーション府中くるる店」は、1,800㎡に454台のプライズゲームを擁する「単一会場におけるクレーンゲーム機の最多設置数」を記録し、ギネス認定された。 - GiGO
-
2020年12月、セガはゲームセンター運営を行うグループ子会社「セガエンタテイメント」の株式85.1%を、GENDA(ジェンダ)へ譲渡。
残る14.9%も譲渡し、2022年から2023年にかけて全てのSEGAがGiGOへ改名。 - Hey
-
プライズは¥100と¥200が混在。
太鼓の達人は1play¥200
ガンシューティング、レース、音ゲー多数。
特筆すべきはレトロゲームが充実。
特にスーパーマリオやアーケードゲームが多数。 - 東京レジャーランド秋葉原1号店
-
プライズの種類は微妙だが¥100
ゲームの種類はバランス良く配置。
1階に外貨両替機有り。 - 東京レジャーランド秋葉原2号店
-
プライズの種類豊富で¥100
太鼓の達人も1play¥100
ゲームの種類はバランス良く配置。 - GiGO 秋葉原3号店
-
プライズ¥200
太鼓の達人¥200
プリクラ機
6階にレトロゲームコーナーが充実。
秋葉原のゲームセンター
- 万世橋駅
-
1912年開業の国鉄駅。
1923年の関東大震災で焼失→翌24年に仮駅舎で復興。
初代駅舎は東京駅と同じ辰野金吾作。
1943年には駅として廃業している。
理由は1914年に東京駅開業、1923年の震災被害、周辺地域の再開発等が挙げられる。
2013年には歴史的景観を残しつつ、商業施設として開業。
- 柳森神社
-
御祭神…倉稲魂大神
1458年、太田道灌が江戸城の鬼門除けとして、多くの柳をこの地に植え、京都の伏見稲荷から宇迦之御魂を勧請して創建。
おたぬき様と呼ばれる親子狸のお守は勝負事や立身出世、金運向上にご利益がある。
1923年関東大震災で全焼→1930年復興。
1945年東京大空襲で全焼→1954年復興。
1984年二度の放火で全焼→1986年復興。 - おたぬきさん
福寿神御由来 -
五代将軍綱吉治世、将軍の生母桂昌院に 江戸城内に福寿いなりと称して創建。
桂昌院は、京都堀川の生まれで、八百屋の娘が春日局に見込まれて、三代将軍家光公の側室となり、五代将軍綱吉の生母となる。
大奥の女中衆は他を抜いて玉の輿に乗った院の幸福にあやかりたいと、こぞってお狸様を崇拝した。
開運、所願成就の福寿神として、殊に近年は他を抜いて受験、勝運、出世運、金運向上などに御利益あり。 - 力石群
-
1989年4月1日千代田区指定文化財指定
江戸時代には、若者たちの間で、重量のある石を持ち上げて力自慢を競うことが流行った。
明治時代中期から次第に衰退したが、大正時代になると再び盛り上がる。
柳森神社境内にある力石群は、当時の力士で大関として名を上げた神田川徳蔵こと飯田徳蔵と、その一派が生前使った石の一部で、彼らの業績を記念し後世に伝える為に集められた。 - 富士講関係石碑群
-
1998年4月1日千代田区指定文化財指定
5つの石碑群は、柳森神社周辺に存在した富士講の名残を今日に伝える。
富士講とは、富士山信仰をもとに成立した民間信仰(la croyance civile)の一種で、江戸時代特に町民や農民の間で流行した。
柳森神社は1680年に駿河富士宮浅間神社から分祠した富士浅間神社を、合殿・合祀した経緯から、富士講と深い関わりを持つ場所だった。
『東都歳時記』には、天保年間(1830~44年)頃の「富士参」(富士浅間神社)の例として柳森神社のことが取り上げられている。
1930年には、境内に富士塚と呼ばれる富士の溶岩石を積み上げて富士山に模した塚も築かれたが、1960年に取り壊されて現存せず。
石碑群の銘文には、富士塚が築かれた時期に近い、大正や昭和の文字があり、この頃に富士講を再興させようという動きがあったことがわかる。
- 2k540
-
起点となるターミナル駅「東京駅」から2k540mの位置にある。
「ものづくり」をテーマにした工房とショップが一つになった店舗多数。
2010年にオープンし、定休日の水曜日以外11:00~18:00で営業。
- 神田明神
-
730年、武蔵国に入植した出雲系氏族が大己貴命(大国主命・おおくにぬしのみこと=日本を創った神)を祀って創建。
935年、平将門の乱にて敗死した平将門の首が近隣に葬られた。
14世紀初頭に疫病が流行し、これが平将門の祟りであるとされ、供養された後、1309年に神田明神の祭神として祀られるようになった。
江戸城増築に伴い、1603年に駿河台へ遷座。
1616年、現在の地へ遷座。
以来、江戸総鎮守として尊崇。
神田祭は江戸三大祭の一つで、山車(char)は将軍上覧の為に江戸城内にも入れたので「天下祭」とも言われた。
山車は明治期以降増えた電線の影響で激減。
「神田囃子」は東京都の無形民俗文化財に指定。
1782年には権現造の社殿が造営されたが、1923年の関東大震災で焼失。
1934年に鉄骨鉄筋コンクリート構造で権現造を模して再建されたことで、1945年の東京大空襲で被災を免れた。
明治時代に入り、神社が国家の管理下に置かれ、1874年の明治天皇行幸に際して、天皇が参拝する神社に逆臣である平将門が祀られていることに疑問が挙がり、平将門が祭神から外れ、代わりに茨城県の大洗磯前神社から少彦名命が勧請された。
平将門神霊は境内摂社に遷されたが、戦後の1984年に本社祭神に復帰。
徳川家康の必勝祈願→関ヶ原勝利→1616年鬼門に移設(神田山切り崩して埋め立て) - 随神門欄間彫刻
-
随神門四方の欄間彫刻は四神が彫られ、中央部には御祭神大國主之命の神話が描かれている。
四神とは、中国古代の天文学上、北極星を中心として、東は青龍(蒼龍)、西は白虎(白虎)、南は朱雀(朱鳥)、北は玄武(玄武亀)。
夫々の星を禽獣の名をもって表された。
わが国では大宝元年(701年)朝廷における儀式で用いられる武器に四神の矛が飾られ、それ以来、魔除けの神として崇められている。
またこれらを五色に配当され、東を青、西を白、南を赤、北を黒、中央を黄とされた。
近年身近なものとして、大相撲における土俵上の各方位には色房を垂らしてそれぞれの方角を示しているのが見受けられる。
随身像の右側が豊磐間戸神、左側が櫛磐間戸神。
像は熊本の樹齢500年の楠で、一木造。 - 神田祭
-
徳川家康が戦勝祈祷を行い、1600年9月15日に関ヶ原の戦いで勝利し、天下統一。
家康は社殿や神輿を寄進し、9月15日には祭を行う。
1681年までは毎年開催。
しかし、江戸の祭が派手になり過ぎた為、山王祭と神田祭は隔年開催となり、神田祭は奇数年の5月15日に近い土曜日に行う。
1884年の神田祭が大嵐に見舞われ、怪我人が続出した為、以降比較的天候の安定している5月に開催されるようになった。
神輿深川、山車神田、だだっ広いが山王様
以前は山車が主流だったが、明治以降路面電車の開業や電信柱の敷設、関東大震災による山車の焼失で町神輿が主流。 - 三天王
三の宮
小舟町八雲神社 - 御祭神...健速須佐之男命(タケハヤスサノオノミコト)
- 祭礼日...6月6日
-
江戸城内から神田神社と共にこの地に遷座。
小舟町(こぶなちょう)には領主外出時の宿泊場所も多く、神輿が巡幸する地だった為、天王と称された。
明治(1869年)以前は公命により江戸全町域の疫病退散(apaisement d'épidémie)の為、江戸城内や市井に御輿を奉納して祈祷した。 - 小舟町八雲神社鉄製天水桶
-
江戸の魚問屋10名(10 grossistes de poisson)が1811年に奉納。
深川大島の鋳物師(fondeur)の作。
本殿左側のものは1857年再建。 - 三天王
二の宮
大伝馬町八雲神社 - 御祭神...健速須佐之男命(タケハヤスサノオノミコト)
- 祭礼日...6月5日
-
江戸時代以前の神社。
1615年より行われていた祭は、6月5日に神田明神を出発し、大伝馬町の屋敷へ渡御して6月8日に還ってきた。 - 大伝馬町八雲神社鉄製天水桶
- 同じく深川大島の鋳物師(fondeur)によって1839年に奉納。
- 力石
-
若者達が力試しに用いた石。
1822年12月に柴田四郎右衛門が持ち上げたとする資料が残っている。
江戸東京の若者達の生活や娯楽を知る上で貴重な資料。 - 魚河岸水神社
- 御祭神...弥都波能売命(ミツハノメノミコト)
- 祭礼日...5月5日
-
徳川家の武運長久(sort des armes)と大漁安全(Une bonne pêche avec la sécurité)を祈願する為、漁師(pêcheur)達によって神田神社境内に建てられた。
1615年に神田明神と共にこの地に遷り、日本橋魚市場の守護神として崇敬される。
魚河岸会の所有する加茂能人形山車は関東大震災で焼失。
1862年に当時そのままの山車を再現し、神田祭で披露される。 - 三天王
一の宮
江戸神社 - 御祭神...健速須佐之男命(タケハヤスサノオノミコト)
- 祭礼日...5月14日
-
702年、現在の皇居内に創建された大江戸最古の神。
1603年の江戸城拡張により、神田明神とともに神田駿河台に遷り、1616年に今の地に至る。
江戸時代初期は幕府の食を賄う青果市が開かれ、市場の神としても認識。
1989年、青果市場が大田区へ移転するのを機に社殿を改装。
1613年から始まった神輿の行幸は6月7日の朝に明神境内を出発し、氏子の町々を巡って6月14日に帰還。
現存する大神輿は通称「千貫神輿」として知られ、神田祭神輿の代表格。 - 三宿稲荷神社
- 御祭神...宇迦之御魂神(ウカノミタマノカミ)
- 祭礼日...10月初旬
-
創建年不明。
江戸時代に神田三河町二丁目の守護神として奉斎。
その後、十二代神主(prêtre shinto)宅に祀られていた内山稲荷と合祀された。
現在の社殿は1966年10月7日に再建。
金刀比羅大神と共に御鎮座。 - 琴平神社
-
御祭神...大物主命(オオモノヌシノミコト)
金山彦命(カナヤマヒコノミコト)
天御中主命(アメノミナカヌシノミコト) - 祭礼日...10月10日
-
1783年に、現在の東日本橋に創建。
隅田川往来の船人達の守護神として崇敬。
その後町の発展と共に商家、特に飲食業従事者の信仰を集めた。 - 水盤
-
1805年2月に伊勢屋治兵衛によって奉納。
1856年6月に神田・日本橋・京橋・下谷・本郷界隈に住む人々によて再建。 - 末広稲荷神社
- 宇迦之御魂神(ウカノミタマノカミ)
- 祭礼日...3月丑の日
-
創建年不詳。
1616年頃と推察。
昔から庶民信仰が篤く、出世(promotion)稲荷様として尊崇されている。
現社殿は1966年2月28日に東京鰹節類卸商組合によって再建。 - 浮世絵師水野年方顕彰碑
-
水野年方(としかた・1866~1908)は、神田神社の氏子の左官職の家に生まれ、水野家の養子となる。
幼少期より画を好み、月岡芳年の門人となり浮世絵を学ぶ。
美人画や歴史風俗画が得意。
1887年ごろから始めた新聞の挿絵も好評を博した。
1908年に42歳で逝去。
1923年5月に顕彰碑を建立。 - 籠祖講関係石造物群
-
籠祖神社は塩土翁神(シオツチノオジ)と猿田彦大神が祭神で、1798年に神田神社境内に鎮座。
籠祖講は神田青物市場や日本橋魚河岸で使われる籠(corbeille)や笊(panier de bambou)を作っていた職人達によって結成。
現在も両神を職神として籠祖講の活動が続いており、毎年11月に例大祭が行われる。
籠祖神社境内には1850年から1961年に奉納された石造物(鳥居・水盤・記念碑・狛犬・常夜燈・玉垣・石標)がある。 - 石獅子
-
区内に残る数少ない江戸期の石造物の一つ。
1716年から1735年に下野(現在の栃木県)の名工・石切藤兵衛による作。
1862年11月に両替屋仲間が石を積んで神田明神へ奉納。
3頭の石獅子は、親獅子が谷底へ突き落とした子獅子を見る構図になっている。
このうち江戸期以来のものは夫婦2頭のみで、子獅子と獅子山は1923年の関東大震災で失われ、1989年に天王即位を記念して再建。 - 銭形平次碑
-
平次の住居は明神下。
この碑は1970年12月、有志の作家と出版社が縁の明神下を見下ろす地に建立。
石造り寛永通宝の銭形の中央には平次の碑。
その右側に八五郎、通称「がらっ八」の碑が建てられた。
| 宮 | 祭神 | 同一神 | 御利益 | 鎮座 |
|---|---|---|---|---|
| 一ノ宮 | 大己貴命 オオナムチノミコト |
だいこく様 | 縁結びの神様 | 730年 |
| 二ノ宮 | 少彦名命 スクナヒコナノミコト |
えびす様 | 商売繁盛の神様 | 1874年 |
| 三ノ宮 | 平将門命 | まさかど様 | 除災厄除(exorcisme)の神様 | 1309年→1874年摂社遷座→1984年本社復帰 |
| 江戸三大祭 | 日本三大祭 | ||
|---|---|---|---|
| 神田祭 | 神田明神 | 神田祭 | 神田明神 |
| 山王祭 | 日枝神社 | 祇園祭 | 八坂神社 |
| 深川祭 | 富岡八幡宮 | 天神祭 | 大阪天満宮 |
- 湯島聖堂
-
1690年に徳川五代将軍綱吉が儒学(Le confucianisme)振興のために、上野にあった林羅山の私塾をここに移した。
孔子(fondateur du confucianisme)の霊廟がある。
1797年に幕府直轄となり、昌平坂学問所として開校。
1871年に文部省(Le ministère de l'Éducation nationale)が置かれると、学問所は廃止。
廃止後すぐに、文部省(1871)、東京国立博物館(1872)、東京師範学校(1872)、東京女子師範学校(1873)が置かれた。
師範学校は当時の中学教員育成所(Une école pour devenir enseignant)。
まさに、日本近代教育発祥の地。
1922年に湯島聖堂は国の史跡に指定。
翌1923年の関東大震災で入徳門と水屋以外を焼失。
1935年に伊藤忠太らにより鉄筋コンクリートにて再建。
- ニコライ堂
- 神保町
- 日本のquartier latin
- 江戸時代の武家屋敷が明治時代に入ると空き家になった(※)
- それら空き家に学校が建てたれた
- 学校が増えると教科書を扱う書店が増える
- 書店が増えると出版社(maison d'édition)も増える
- 出版社が増えると、打ち合わせの為に喫茶店が多く利用されるようになる
-
※徳川治世の江戸時代には多くの大名が地方から徳川家のお膝元の江戸へ移り住んだ。
その際、外様大名は地方にいながらその妻を江戸に住まわせ人質とした。
明治時代に入り、江戸に住んでいた武士たちは地元へ帰って行き、結果江戸城界隈の多くの武家屋敷が空き家になった。
- 原書房
-
1932年創業の書店。
1階は易・運命学書籍の専門店。
2階は浮世絵・版画の専門店。
浮世絵関連書籍の品揃えは世界一。
| 住所 |
東京都 千代田区 神田神保町2-3 |
|---|---|
| 電話 | 易学書部 03-3261-7444 浮世絵部 03-5212-7801 |
| 営業時間 | 火~土 11h00~18h00 |
| 定休日 | 日月祝 |
| 支払 | 不明 |
| リンク | 公式サイト |
荒川区
- 円通寺
- 創建…791年
- 本尊…静観音菩薩
- 宗派…曹洞宗
- 開基…坂上田村麻呂
-
791年、坂上田村麻呂が創建。
また、源義家が奥州を鎮定した時、討ち取った48の首を寺域内に埋めて塚を築いたので、この辺りを小塚原と呼ぶ。
江戸時代、下谷の広徳寺・入谷の鬼子母神とともに「下谷の三寺」と呼ばれた。
明治維新の折、1868年に行われた上野戦争で亡くなった彰義隊士266名を上野の西郷隆盛像がある辺りでこの寺の住職が火葬を行い、当寺に収骨した。
太政官の許可状に「懇に供養すべし」を口実に、大ぴらに賊軍の法要ができる当時日本唯一の寺だった。 その為、この寺には火葬を行った場所の近くにあった上野寛永寺の総門(黒門)が移築され、亡くなった彰義隊の隊員の墓もある。
秩父・坂東・西国霊場の百体の観音像を安置した観音堂があったことから「百観音」の通称で親しまれたが、観音堂は1855年の大地震で倒壊した。
境内には、石造七重塔、彰義隊士の墓、1296年銘をはじめとする板碑4基などがある。
また、1963年3月に当時4歳であった村越吉展が誘拐される事件「吉展ちゃん誘拐殺人事件」が発生し、1965年7月に円通寺の敷地内の墓地から白骨化した被害者の遺体で発見されたことでも知られる。この為、敷地内に被害者の慰霊地蔵が設置されている。 -
本尊生観世音菩薩(聖徳太子 一刀三礼御作)。
屋上聖観音像(全長12m)、原型(1寸8分=6.82cm、当寺蔵、高村光雲1923年作)
- 高村光雲
1852~1934 -
江戸下谷生まれの仏師・彫刻家。
19世紀後半の明治維新による廃仏毀釈で生活苦。
その中で、木彫に専念。
1893年『老猿』をシカゴ万博に出品。
1900年『山霊訶護』をパリ万博に出品。
『老猿』は東京国立博物館所蔵。
上野公園の『西郷隆盛像』や皇居前の『楠公像』も氏の作。 - 旧上野の黒門
-
この黒門は、元上野山内にあった。
寛永寺の八門のうちで表門にあたる。
1868年5月15日に旧幕臣の彰義隊と新政府軍が戦った上野戦争では、黒門前でも激しい攻防が繰り広げられた。
無数の弾痕が往時の激戦を今に伝えている。
戦いの後、埋葬されずにいた多数の彰義隊士の遺体を、当時の円通寺住持だった仏磨和尚と神田旅籠町の商人三河屋幸三郎が火葬した。
以来、円通寺は旧幕府方の戦死者供養の拠点となった。
その機縁で、黒門が1907年に帝室博物館より円通寺に下賜された。 - 彰義隊士の墓
-
1868年5月、寛永寺に集結した彰義隊は新政府との激戦の末、上野の山から敗走した。
累々と横たわる隊士の遺体を見た円通寺の住持・武田仏磨和尚は、官許を得て、寛永寺御用商人三河屋幸三郎とともに遺骸を火葬して円通寺に合葬した。
これが縁となって、1907年、寛永寺の黒門が円通寺に移された。
1985年に修復工事が行われている。 - 板碑四基(永仁四年十月日銘他)
-
円通寺の板碑4基の内、3基は鎌倉時代末期の紀年銘を持ち、区内に現存する板碑の中でも古い時代に属する。
とりわけ、永仁四年(1296年)十月日銘は、日慶寺の正応二年(1289年)銘に次いで2番目に古い年号を有し、南千住における鎌倉時代の人々の生活を知る上で貴重。
また、嘉暦四年(1329年)正月二十九日銘は、薬研彫りで精巧な彫刻が施され、造形的にも優れている板碑と言える。
- 素盞雄神社
- 創建…795年
- 祭神…素盞雄大神、飛鳥大神
- 開祖…黒珍(役小角の高弟)
-
開祖・黒珍(こくちん)住居の東方塚上に奇岩があった。
黒珍はそれを霊場と崇め日夜斎戒礼拝すると、795年4月8日の夜、奇岩が突如光を放ち二柱の神様が翁に姿を変えて現れ、
「吾れは素盞雄大神・飛鳥大神なり。吾れを祀らば疫病を祓い福を増し、永く此の郷土を栄えしめん。」
と御神託を授け、祠を建ててお祀りしたのが起源。
次いで素盞雄大神の社殿を西向きに造営し6月3日、飛鳥大神の社殿を南向きに造営し9月15日、それぞれ神霊を遷し、4月8日「疫神祭」・6月3日「天王祭」・9月15日「飛鳥祭」の祭禮日が定まった。
1718年、火事で炎上の為、1727年に相殿(あいどの…一つの社殿)として二柱を祀る御殿・瑞光殿を新たに建築し奉斎。
荒川区内で最も広い氏子区域61ヶ町の鎮守で、1995年には鎮座1200年祭斎行。 - 素盞雄大神
天王祭6月3日 -
天照大御神の弟神。
八岐大蛇を退治し、その尾から天叢雲剣、後の三種の神器の一つ「草薙の剣」を取り出し、天照大御神に献上した勇敢な神様。
また八岐大蛇から助けた稲田姫との間に多くの御子神をもうけ、出雲国須賀という地で幸せな家庭を築いた神様として知られている。
「スサ」には「荒・清浄」の意味があり、罪・穢れ・災い・厄など身に降りかかる悪を、荒々しい力で祓い清める災厄除けの神様。
別名を牛頭天王という為に当社の通称を「お天王さま」と言う。 - 飛鳥大神
飛鳥祭9月15日 -
大国主神の御子神。
別名を事代主神(コトシロヌシノカミ)・一言主神(ヒトコトヌシノカミ)と言い、善悪を一言で判断し得る明智を持った神様。
後世には福の神としての性格が強まり、商工業繁栄・商売繁昌の「えびす様」として崇敬。
『江戸名所図会』では当社を「飛鳥社小塚原天王宮(あすかのやしろこつかはらてんのうぐう)」と伝えている。 - 蘇民将来子孫也
-
勇壮な神輿振りを支える長柄8.1mの御本社大神輿二天棒。
その棒先でひときわ光を放つ金具に刻まれた言葉「蘇民将来子孫也」。
ふりかかる悪疫災厄から御祭神スサノオノミコトにお護りいただく唱え言葉。
遠い遠い神代の昔、スサノオノミコトが遥か遠くの南の海に妻問いに出かけた時の事。
陽はすでにとっぷりと暮れ、旅に疲れ果てたスサノオノミコトは蘇民将来・巨旦将来という名の兄弟に宿を乞うた。
裕福で立派な家に住む弟の巨旦将来は、顔もやつれ衣服も汚れたその姿を見て、怪しみ惜しんで貸さなかったが、家も小さく貧しい生活をしていた兄の蘇民将来は、粟柄を座とし、粟の飯で精一杯のもてなしをした。
そして歳月が経ち、
再びその地を訪れたスサノオノミコトは兄に御礼を言い、
「もしも疫病が流行したとき、あなたの家族は茅で作った小さな輪を腰につけていなさい。きっとそれから逃れ、子孫は永く栄えるでしょう。」
と伝え帰った。
その後、突然二人の住んでいる村に疫病が流行ったが、不思議なことに茅の輪を付けていた兄の家族だけは助かり、弟の巨旦将来の家は途絶えてしまった。
それ以来、村人は疫病が流行ると「蘇民将来子孫也」と口々に唱え、茅の輪を腰につけ疫病から免れるようになった。
「蘇民将来子孫也(私は蘇民将来の子孫です)」。
宮神輿の担ぎ手も、そして御神輿のお出ましを待つ大勢の氏子崇敬者も、御祭神・素盞雄大神に御加護をいただく蘇民将来の遠い遠い子孫。 - 瑞光石
-
瑞光石は、素盞雄神社の祭神が翁に姿を変えて降臨した奇岩と言われ、「瑞光荊石」とも称される。
また、この塚を「古塚」と呼んだことから、小塚原の地名の由来となった。
1851年には周囲に玉垣を築き、1864年には浅間神社を祀った。
1860年に編纂された『江戸近郊道しるべ』には、千住大橋架橋の際、この石の根が荒川(現・隅田川)まで延びていた為、橋脚が打ち込めなかったという伝承を紹介している。
神楽坂・九段下
- 神楽坂
-
神楽坂は大正時代(1913~25)に花街として繁栄。
歴代日本の文豪も住んだり通ったりした街。
※花街…芸妓屋、遊女屋が集まっている区域。
当時は「高級娼婦」(la courtisane)もいたが「娼婦」(la prostituée)も多く1957年の売春防止法によって消滅。
L'État a promulgué la loi pour réprimer la prostitution.
神楽坂下から皇居方面へ伸びる早稲田通りは、
00:00~12:00までは皇居方面への一方通行、
12:00~13:00は歩行者天国、
13:00~24:00は皇居方面から神楽坂方面への一方通行となる。
これは、国内でも非常に珍しい「逆転式一方通行」で、1958年に舗道敷設の為に講じた措置が、時間帯による交通量の変化により、常設となった。
- 赤城神社
-
1300年、群馬県赤城山麓の豪族大胡彦太郎重治が牛込に移住した時本国の鎮守だった赤城神社の分霊を祀ったのが起源。
その後、1460年に太田道灌が神威を尊んで牛込早稲田から牛込台(現・牛込見付附近)に遷し、さらに1555年に大胡宮内少輔(牛込氏)が現在の場所に遷した。
この牛込氏は、大胡氏の後裔。
1683年、徳川幕府は江戸大社の列に加え牛込の総鎮守と崇め、「日枝神社」「神田明神」と共に、「江戸の三社」とした。
この三社による祭礼の際における山車、練物等は江戸城の竹橋から内堀に入り半蔵門に出ることを許された。
その後、1873年に郷社に列することになる。
しかし、街の発展に伴い電柱や電燈などの障害物ができたので、盛観を極めた山車行列は1899年の大祭が最後となった。
現在9月19日に例祭が執り行われる。 - 御祭神
-
「磐筒雄命」(いわつつおのみこと)…
伊邪那岐命が火の神、迦具土神を御刀で倒された時に生まれた神様で、智、仁、勇の力を持ち、殖産興業、厄難消除、学問芸術の神又特に火防の神として有名。 -
「赤城姫命」(あかぎひめのみこと)…
赤城姫命は大胡氏の息女で、旧別当天台宗東叡山寛永寺末、赤輝山円明院当覚寺の本地仏は乗馬姿の地蔵尊。
神仏混合の頃、赤城大明神の神影であるとして氏子中へ頒布し、た為、当社の祭神「磐筒雄命」とは関わりはないが、合殿とされる。 - 社殿
-
1842年近所から出火し全焼。
その後復興された壮麗な社殿も1945年の戦災で焼失。
終戦後、1951年10月16日に本殿竣工。
最終的に拝殿、幣殿の完成は1956年5月。
2010年9月の改修で現在の姿に。
戦後復興出来ずにいた神楽殿は「蛍雪さま」、出世の「おいなりさん」、病気平癒で人気の「八耳さま」、東照宮の「葵さま」まで全てが再興。 - 赤城神社の狛犬
-
江戸時代、加賀白山犬と呼ばれ流行したが現存は極小。
型や表情はシンプルでスフィンクス(le sphinx)に似ているが、胸を張り力が漲っている。
redresser le buste…胸を張る
高天原から神様のお供をしてきたような表情で澄まして座っているが前肢は力強く全体に緊張感が漲っている。 - 境内の末社
- 螢雪天神
-
御祭神…菅原道真公
かつては江戸二十五社の一つに数えられ、横寺町に鎮座して朝日天満宮と称されていたが、その後信徒無き為1876年に境内へと遷されたが戦火にて焼失。
2005年10月旺文社の寄進により螢雪天神として復興。
神楽殿の中に御内陣を備える。
社名額には社長赤尾文夫奉納の銘がある。
『螢雪』は中国の故事で、苦労して勉強に励む事を意味する。
受験生に人気。 - 八耳神社
-
御祭神…上宮之厩戸豊聰八耳命(うえのみやのうまやどのとよとやつみみのみこと)別称聖徳太子
合殿に大国主大神、丹生大神、菅原大神を祀る。
昔の太子堂。
戦火にて焼失し復興。
八耳様は「あらゆる事を聞き分ける天の耳」を持つ聖徳太子であり、聡明な知恵を授かることができる。
悩み事のある時は「八耳様・八耳様・八耳様」と3回唱えてからお参りすると、自ずと良い考えが浮かぶ。
また耳の神様として、耳の病気を治してくれる。 - 出世稲荷神社
-
御祭神…宇迦御霊命(うかのみたまのみこと)
赤城神社がこの地に遷る以前の1555年から牛込の鎮守だった地主神。
出世開運の御利益から、大名や公家の崇敬を受けた。
また穀物・食物を司る神様として、五穀豊穣、衣食住、商工業繁栄のご神徳を備え、現在は神楽坂商店街などの商売繁盛と近隣のサラリーマンの崇敬を集める。 - 東照宮/葵神社
-
御祭神…徳川家康公
牛込西五軒町にあった天台宗宝蔵院に鎮座してが、1868年神仏分離の折境内へ移遷。
かつては江戸市民の家康公への信仰の対象だったが、現在は神楽坂の「東照宮」として親しまれ、学問と産業の祈願成就を願う参拝者が多い。 - 観音菩薩立像
-
赤城神社の北に位置した宝蔵院より移された。
舟形光背には「慶長十八丑年五月十六日」(1613)と刻まれている。
ふっくらとしたお顔立ちで全体におおらかな雰囲気の菩薩像である。 - 俳人巻阿の碑
-
巻阿は江戸期の俳人であり、幕府の家臣だった人物。
「梅か香や 水は東より 行くちがひ」
「遠眼鏡 には家もあり かんこ鳥」
「名月や 何くらからぬ 一とつ家」
「あるうちは あるにませて 落葉哉」 - 赤城山と大百足
-
昔、赤城山の神様は「ムカデ」となり中禅寺湖の領有をめぐり、二荒山の「マムシ」となった神様と戦った。
これが奥日光の「戦場ヶ原」の由来。
この百足を撫で、御祭神の力を戴き、本社や末社を参拝。
2020年5月、氏子会長の飯島光幸氏がコロナウィルス感染症鎮静を願って寄進。 - お百度まいり
-
ムカデは毘沙門天の遣い。
戦勝・武運長久の象徴…ムカデは「決して後退しない」という習性から、武士たちの間で勇敢さや「勝ち虫」の象徴とされ、甲冑や刀装具のデザインにも使用。
金運・商売繁盛の象徴…足がたくさんあることから「お足(お金)が沢山付く」という語呂合わせや、「借金を返さない(後退しない)」という俗信から、金運や商売繁盛の縁起物としても信仰されている。
養蚕の守り神…ムカデが養蚕の大敵であるネズミを嫌うという言い伝えから、養蚕農家で豊作を願う対象ともなった。
御百度参りは、特定の願い事を叶えるために、神社や寺院の入口から本堂(または百度石)までを百回往復して参拝する修行・祈願方法。
この行為自体は、- 回数を重ねる事で信仰の篤さや願いの切実さを示す
- 雑念を払って一心に祈る
- 島久幸
-
1953年奈良県生まれ。
1978年に東京藝術大学美術学部彫刻科卒業。
- 小石川後楽園
- 開園…1938年4月3日
- 面積…70,800㎡
- 時間…9:00~17:00(16:30最終)
- 料金…一般300円/65歳以上150円
- 特徴…特別史跡、特別名勝、築山泉水回遊式の大名庭園
-
1629年、水戸徳川家水戸藩初代藩主徳川頼房が作庭家の徳大寺左兵衛に命じて築いた庭園を嫡子の光圀が明から儒学者・朱舜水を招いて改修。
光圀は作庭に際し、明の儒学者の意見を取り入れ、中国の教え、范仲淹(はんちゅうえん)「岳陽楼記」の「(士はまさに)天下の憂いに先だって憂い、天下の楽しみに後れて楽しむ」から「後楽園」と名づけた。
On s'inquiète avant la crise dans le monde, on éprouve de la joie après la joie dans le monde.
徳大寺石(幅2m、高さ4m)を中心に70,000㎡に広がる円内は中国風の景観も取り入れられ、梅、桜、ツツジ、花菖蒲などが植えられている。
1896年、版籍奉還により、藩主徳川昭武が邸宅と共に新政府に奉還した後、東京砲兵工廠(arsenal)の敷地の一部として陸軍省(Le ministère de la Guerre)の所管(compétent)となる。
1874年以降、明治天皇の行幸を受け、外国人観覧者増加。
1923年、国の史跡及び名勝に指定。
岡山市の後楽園と区別するために「小石川」を冠した。
→岡山の後楽園は1700年に完成。
1952年、国の特別史跡及び特別名勝に指定され、今は都立公園として整備されている。
1937年に隣接する旧東京砲兵工廠跡地にプロ野球興行を主たる目的に造られた野球場は「後楽園球場」と名付けられ、現在の東京ドームに至る。
小石川後楽園は文化財保護法によって国の特別史跡、特別名勝に指定されている。
この重複指定を受けているのは、全国でも小石川後楽園、浜離宮恩賜庭園、金閣寺など、ごく限られている。 - 九八(くはち)屋
-
江戸時代の風流な酒亭。
「酒を飲むに昼は九分、夜は八分にすべし」に由来。 - 大泉水
-
この庭園の中心となる景観。
蓬莱島と竹生島を配し、琵琶湖を見立てて造られた。
昔はこの池で舟遊びをしたと言われている。 - 枝垂桜
-
推定樹齢約60年。
3月下旬には見事な花を咲かせる。 - 延段
- 大小自然石と切石を巧みに組み合わせた中国風の素朴な石畳。
- 内庭
-
水戸藩書院のあったところ。
昔は唐門によって仕切られ、大泉水側の「後園」と分けられていた。 - 稲田
-
光圀が農民の苦労を彼の嗣子(しし)、綱條(つなえだ)の夫人に教えようと作った田圃。
現在は地元文京区内の小学生が5月に田植え、秋に稲刈りを行い、伝統行事を守り継いでいる。 - 梅林
-
光圀は号を「梅里」と称するほど梅を好んだ。
2月上旬には紅梅、白梅など30種類ほどの梅が咲く。 - 円月橋
-
水面に映る形が満月のように見えることから付けられた名称。
明の儒学者、朱舜水による設計と言われており、得仁堂とともに当時の姿を留める貴重な建造物。 - 西湖の堤
-
中国の杭州(現在の浙江省)の西湖の堤に見立てたもの。
本園以後、日本各地の大名庭園に大きな影響を与えた。 - 通天橋
- 11月下旬の紅葉は朱塗りの橋を引き立てる。
- 得仁堂
- 光圀18歳の時、史記「伯夷列伝」を読み感銘を受け、伯夷(はくい)、叔斉(しゅくせい)の木造を安置した堂。
- 瘞鷂(えいよう)碑
-
常陸国水戸藩第7代藩主徳川治紀(はるとし)は、将軍家から賜わった鷹を大切にしていた。
鷹は治紀没後4年で亡くなり、8代斉脩(なりのぶ)がこれを哀しみ、碑を建てた。
- 東京ドーム
-
1985年起工→1988年竣工の日本初全天候型多目的スタジアム。
人工芝グラウンドで高さ約60m、面積46,755㎡、収容人数は野球時43,500人、コンサート時55,000人。
- 靖國神社
-
1869年、明治天皇によって「東京招魂社」建立。
1879年に「靖國神社」と改名。
国の為に命を捧げた人々を慰め、後世に伝える事が目的。
1853年以降、数々の戦争によって捧げられた2,466,000余柱の神霊を祀る。
大臣(ministre)の参拝は靖國問題へ発展。年代 戦争 犠牲者 1894~1895 日清戦争 13,800人 1904~1905 日露戦争 88,000人 1937~1945 日中戦争 430,000人 1941~1945 太平洋戦争 2,000,000人
政教分離原則に抵触?
戦争を肯定? - 濠北方面戦没者慰霊碑
-
オーストラリア北方、インドネシア東部における戦没者慰霊碑で1964年11月3日建立。
明治天皇「国のために命を捨てた人の功績を日頃から語り伝えなさい」 - 高燈籠(常燈明台)
-
1871年に東京招魂社の燈籠として設置。
方位盤(le compas[コンパ])や風見(la girouette)が付けられ、高さ16.8m
九段坂上に設置された為、品川沖を出入りする船の目印として、東京湾からも望むことができ、灯台(la phare)の役割も果たした。
関東大震災前は神社側にあったが、1925年の改修時に現在の位置に移転。 - 品川弥次郎(1843~1900)
-
長州藩生まれで、松下村塾で学ぶ。
明治政府設立後、内務大臣(ministre de l'Intérieur)就任。
学校や信用組合や産業組合の設立に助力。
若い頃、九段北の練兵館で剣術を学ぶ。 - 大山巌(いわお)(1842~1916)
-
薩摩藩生まれで、薩英戦争、日清戦争、日露戦争で活躍。
「陸の大山、海の東郷」と称された。
その後、参謀総長(le chef d'état-major)、内務大臣(ministre de l'Intérieur)を勤め元老(ancien)となった。
像は1919年に現在の国会前庭に設置。
1948年にGHQにより一時撤去され、東京都美術館に預けられた後、1969年に現在地へ移転。 - 大村益次郎(1825~1869)
-
20代の頃に儒学(le confucianisme)、蘭学(les études occidentales)を学び、西洋式軍艦を設計建造。
戊辰戦争の際には新政府軍を指揮。
しかし、軍制を洋式に改める事を主唱した為、攘夷主義者を刺激し襲撃され死亡。 - 出征を見送る家族の像
-
嗚呼 あなたは防人として旅立つのか
齢を重ねた父母
愛しき妻 そして愛し児たち
皆があなたの帰還を待ちつつも
嗚呼 息子よ 夫よ 父よ 兄弟よ
天界のあなたを偲び、
あなたが遺してくれたものを受け継ぎ、
今も家族は故郷にあります - 靖國神社大鳥居
-
大鳥居(第一鳥居)は靖國神社創建50周年記念として1921年に建立されたが、1943年戦力増強の為撤去され、代わりに小さな檜(le cèdre)の鳥居が建てられた。
全国17,000人の芳志に基づく浄財160,000,000円(1 million euro)によってこの大鳥居を再建し、御祭神2,460,000柱の英霊に捧げるものである。
1974年竣工で、鋼板(acier)と柱内部にコンクリート(le béton)を充填し、総重量100トン。
理論上1200年の耐久性を誇る。
高さはビル8階に相当し、高さ25m、横幅34m、柱の円周は7.8mある。 - さくら陶板
la fleur de cerisier de faïence - 2019年の創立150年を記念し、御祭神の故郷の土を用いて各都道府県の陶工(potier)により制作・奉納。
- 常陸丸殉難記念碑
-
1904年、日露戦争が勃発し、輸送船常陸丸が敵戦の攻撃により沈没。
乗組員の悲劇を悼んで1986年に記念碑を建立。 - 田中支隊忠魂碑
-
第一次世界大戦時の1919年、田中勝輔少佐指揮のもと、シベリアにおいて戦闘に従事した田中支隊。
数十倍もの敵に包囲され、ほぼ全員が戦死。 - 慰霊の泉
-
戦没者の多くは故国の母を想い、清い水を求めながら息を引き取った。
この彫刻は1967年に建設され、清らかな水を捧げる慈愛に溢れる母を表現。 - 靖國の時計塔
-
国は1963年4月1日「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法」を制定し、戦没者の妻の特別な立場を認めた。
この感激を記念し1965年に奉納。 - 桜の標本木
- このソメイヨシノは、東京管区気象台が開花を観測するため指定した「標本木」












- 東京国立近代美術館
-
入口の「門」は、イサム・ノグチが1962年に製作したアート作品で、氏の指示で定期的に色を塗り替える。
身近な物の色を参考にしている。
岸田劉生の作品は、土に対して神秘性を見出す。青 ゴミ収集車 赤 郵便ポスト 黄黒 踏切
近代化の象徴として電柱の影を忍ばせている。
騎龍観音は護国寺からのレンタル。
技術としては海外風なので、和洋折衷の象徴。
1907年に国主催の公募展があり、最初のグランプリを取ったのが「南風」
4階に皇居を見渡せる展望室。
壁の紺色は特に日本画を見やすくする工夫。
鯛の絵などは、戦争に関係ないように見えるが、実はその絵を売ることで得た資金で戦闘機を購入した。
ゴームリーは自分の体を世界中に置いていく作家。
本人の指示で窓際に作品を設置。
芝・大門
- 有章院(徳川家継)霊廟(le mausolée)二天門
- 文章院…六代将軍家宣の戒名
- 有章院…七代将軍家継の戒名
-
東京プリンスホテル敷地には、戦前、六代将軍家宣の文昭院霊廟と並び、七代将軍家継の有章院霊廟があった。
ホテル正面の二天門は有章院霊廟の門。
霊廟は八代将軍吉宗が1717年に建立。
豪華絢爛な門は1945年に東京大空襲で焼失。
この焼け残った二天門は1960~62年にかけて修復された銅板葺、切妻造りの八脚門で、左右に仏法守護の役目を持つ広目天、多聞天の二天を祀る。
焼けた文昭院霊廟の門に持国天、増長天が置かれ、合わせて四天王として祀られていた。
2015~19年にも修復工事済み。
- 増上寺
- 創建…1393年
- 本尊…阿弥陀如来
- 宗派…浄土宗
- 開山…酉誉聖聡
-
浄土宗は1175年に法然が立教。
本尊を阿弥陀如来とし、「南無阿弥陀仏」を唱えれば救われる。
1393年、浄土宗の酉誉聖聰(ゆうよしょうそう)によって、江戸貝塚(現在の千代田区紀尾井町)に浄土宗正統根本念仏道場として創建。
1590年、徳川家康江戸入府の際、たまたま増上寺の前を通りかかり、12世源誉存応と対面したのが徳川家菩提寺となる契機。
1598年に徳川将軍家の菩提寺として江戸城から見て裏鬼門にあたる現在の地に移転。 - 大門から三門
-
108間(1間=1.8m)
三門をくぐり108の煩悩から解脱する。 - 三解脱門
-
1611年に建立され、1622年に再建。
増上寺で唯一、江戸時代初期の面影を残す建造物で、重要文化財に指定されている。
「三解脱門」別名「三門」は、三つの煩悩(貪り/怒り/愚かさ)の三悪を解脱する悟りの境地を表す。
On peut se libérer trois passions : l'avidité, la colère, et la stupidité.
建築様式は三戸桜門、入母屋造、漆喰塗。
大きさは、間口約19m、奥行約9m、高さ約21mの二重建て構造。
首都圏最大級の御堂で、本堂の御本尊阿弥陀如来と、両脇壇に高祖善導大師と宗祖法然上人の御像が祀られている。 - 三門から大殿…約48間→阿弥陀仏の48願。
- 参道から大殿前に至る階段…18段→阿弥陀仏の本願、第18願。
- 大殿に登る階段…25段→25菩薩。
- 焼香
-
抹香を香炉に落として焚くもの。
抹香は現在、主にシキミ(la badiane)の樹皮と葉を乾燥させて粉末にしたものを用いる。
浄土宗の場合、特に決まった作法は無く、親指、人差し指、中指でつまんで1~3回行う。
線香を焚く理由は4つある。
-
Purification…自分の身と心を清める。
人間とは汚いものなので、線香の匂いで汚れを払う。 -
Nourriture…故人の食べ物。
死後の人間は匂いだけを食べるため。 -
Chemin…冥土への道標。
線香の煙が故人をあの世へ導いてくれる。
La fumé indique le chemin au paradis. -
Contact…線香をあげることで故人に思いを伝える。
線香の煙を通じて仏様と会話する。
-
Purification…自分の身と心を清める。
- 貞恭庵
-
徳川家十四代将軍家茂公正室、皇女和宮さまゆかりの茶室。
1980年に移築改修され、その際に和宮さまの戒名から「貞恭庵」と名付けられた。 - 聖観世音菩薩
-
1982年に発生したホテルニュージャパン火災で亡くなった33名の犠牲者を供養する為に建立された慰霊像。
火災の原因は宿泊していたイギリス人男性の寝たばこ、及びホテル側の防火設備の不備。 - 四菩薩像
-
元はこの場所の北西、地蔵山に安置されていた。
西向の観音像に対して東向きであった。
1258年の作。
詳細は菩薩参照。 - 鐘楼堂
-
1673年設置。
あまりの大きさの為、7回の鋳造を経て完成した東日本最大級の大梵鐘。
朝と夕に時を告げると共に、除夜の鐘の役割も担っている。
| 文殊菩薩 | 虚空菩薩 | 地蔵菩薩 | 普賢菩薩 |
|---|---|---|---|
| 卯年守本尊 | 丑寅守本尊 | 子育地蔵 | 辰年守本尊 |
- 東京タワー
- 1958年12月23日竣工。
- 内藤多仲の設計。
- それまで各局が持っていた電波塔を一本化。
- 航空法で60mを超える建築物は紅白塗装。
- ただし、一定間隔で明滅する(la lumière clignote)ライトがあればその限りではない。
- エレベーターは150m/45s
- 東京タワー運営会社設立20周年を記念して1977年に建立された神社。
- 23区内で最も高い所(150m)にある神社。
- 高度経済成長(le miracle économique japonais)1955~1973
- 1958年東京タワー
- 1960年代、テレビ・洗濯機・冷蔵庫(réfrigérateur(frigo))
- 1964年東京五輪、東海道新幹線、高速道路
- 1970年大阪万博
-
正式名称「日本電波塔」
内藤多仲による設計。
1958年12月23日竣工。
- 旧芝離宮恩賜庭園
- 開園…1924年4月20日
- 面積…4.2ha(42,000㎡)
- 時間…9:00~17:00(16:30最終)
- 特徴…国指定名勝、江戸の風雅・壮麗な石組
-
この地はかつて海面だったが、明暦(1655年~1658年)の頃に埋め立てられ、1678年に老中大久保忠朝の邸地となる。
忠朝は上屋敷を建てる際に、藩地の小田原から庭師を呼び寄せて作庭し、これを「楽壽園」と命名。
その後、幕末には紀州徳川家の芝御屋敷となった。
1871年に有栖川宮家の所有となったが、1875年に宮内庁がこれを買い上げ、翌年に芝離宮となった。
1923年の関東大震災によって、建物と樹木のほとんどが焼失したが、翌1924年1月、昭和天皇のご成婚記念として東京市(都)に下賜され、庭園の復旧と整備を施して、同年4月に「旧芝離宮恩賜庭園」として一般に公開された。
1979年6月に「旧芝離宮恩賜庭園離宮庭園」(文化財指定名称)として国の名勝に指定。 - 西湖の堤
-
中国の杭州(現在の浙江省)にある西湖の堤を模した石造りの堤。
堤の先にある中島の石組は、楽寿園の頃からのもの。 - 中島
-
園景の要となる箇所で、池の中央にある中島。
中国で仙人が住み不老不死の地といわれる霊山を模した蓬莱石組となっている。 - 枯滝
-
山峡を流れ落ちる滝を彷彿とさせる石組み。
流れの河床が園路になっていて、景観の変化を楽しむ。 - 大山
-
庭園内の最も高い築山で、頂上からの眺めが見事。
また、左右の築山とっ構成される稜線の変化は、池の対岸から見ると味わい深いものがある。 - 大泉水
-
庭園の要となる約9,000㎡の広さを持つ池。
昔は海水を引き入れた潮入りの池だったが、現在は淡水の池。
池は中島と浮島を配して海と湖を形取り、一画には小さな州浜が設けられている。 - 藤棚
-
庭園の入り口付近には大きな藤棚がある。
5月の初め頃、紫色の大きな花房がさがり、芳香を放つ。
- 港区立伝統文化交流館
-
旧協働会館は、1936年に芝浦花柳界の見番として建設された都内に現存する最古の見番建築。
見番とは、三業組合事務所の事で、「置屋」「料亭」「待合」からなる「三業」を取りまとめ、芸者の取次ぎや遊興費の清算をする施設。
見番には箱屋がいて、芸者は客先に出向く前に見番に立ち寄り、箱屋が三味線箱を携えて一緒に先方へ向かう。
間口10尺(3m)、奥行60尺(18m)程の棟の後方にL字型に30尺(9m)弱張り出した平面構成。
正面玄関には銅板葺の唐破風を付け、1階に事務所、2階に桧板敷舞台のある「百畳敷」と呼ぶ大広間を設けた。
棟梁は、目黒雅叙園も手がけた酒井久五郎であり、良材をふんだんに使い、扉の卍崩しや、階段の手すり等に、その技巧を見ることができる。
第二次世界大戦中に花柳界が疎開し、戦後は港湾労働者の宿泊所「協働会館」として使用され、2階だけは日本舞踊の稽古場、集会の為に貸し出していたが、2000年に閉鎖。
閉鎖後、しばらく放置され傷んでいた箇所もあったが、2019年に修理工事を終えて、往年の姿を取り戻した。
華やかな花柳界の面影を今に伝える建築として貴重。 - 客は待合に連絡。
- 待合が見番に芸者依頼、料亭へ料理依頼、同時にお座敷を提供。
- 待合から依頼を受けた見番が置屋に連絡し芸者を待合へ向かわせる。
- 待合から依頼を受けた料亭は待合が用意するお座敷へ料理を用意する。
- 待合…お座敷準備+見番に芸者依頼+料亭に料理依頼。
- 見番…待合の依頼を受けて置屋へ芸者を依頼。また、稽古場の提供も行う。
- 置屋…見番から芸者依頼を受け、待合が用意する座敷へ芸者を派遣する。
深川
- 芭蕉記念館
-
江東区は文学史上偉大な業績を留めた松尾芭蕉ゆかりの地。
芭蕉は1680年、それまでの宗匠生活を捨てて江戸日本橋から深川の草庵に移り住んだ。
そして、この庵を拠点に新しい俳諧活動を展開し、多くの名句や「おくのほそ道」などの紀行文を残した。
この草庵は、門人から贈られた芭蕉の株が生い茂ったところから「芭蕉庵」と呼ばれ、芭蕉没後、武家屋敷内に取り込まれて保存されたが、幕末から明治にかけて消失。
1917年9月の台風の高潮の後、常盤一丁目から「芭蕉遺愛の石の蛙」(伝)が出土し、1921年に東京府は、この地を「芭蕉翁古池の跡」と指定した。
江東区はこのゆかりの地に、松尾芭蕉の業績を顕彰する為、1981年4月19日に芭蕉記念館、1995年4月6日に隅田川と小名木川に隣接する地に同分館を開館。
同館は、真鍋儀十翁等が寄贈された芭蕉及び俳文学関係の資料を展示するとともに、文学活動の場を提供する。
- 清澄庭園
- 開園…1932年7月24日
- 面積…37,000㎡
- 特徴…東京都指定名勝、回遊式林泉庭園
-
1590年に家康の江戸入府で人口増加。
日本橋魚河岸や漁師町としての佃島発展に伴い、17世紀末には船大工(charpentier de navire)町となる。
18世紀初頭には江戸の繁栄に伴い、漁師町から商業町へと変貌し、多くの武家屋敷が建つ。
庭園はこの時期に造営。
19世紀、三菱財閥創業者岩崎弥太郎が買い取り、三菱社員の慰安と賓客接待を目的とした庭園へ改修。
隅田川の水を引き入れたり、園西側にジョサイアコンドル設計の洋館を造営。
1923年関東大震災で被害甚大。
翌年三菱三代目岩崎久弥(弥太郎の長男)は園東半分を東京へ寄贈。
※二代目は弥之助(弥太郎の弟)
東京は1932年に清澄庭園として開園。
1973年には園西半分も譲り受けた。 - 大正記念館
-
大正天皇の葬儀(funérailles)殿。
元々は新宿御苑内にあったものを戦災後に復興。
葬儀場というよりも葬儀前の待合室だった。
90年代に全改修済。
現在は集会施設。 - 涼亭
-
1909年に建てられた数寄屋造り家屋。
現在は集会施設。 - 石仏群(江東区文化財)
| 高さ | 石質 | 時代 | |
|---|---|---|---|
| 庚申塔 | 89.5cm | 安山岩(小松石) | 1670年 |
| 法印慶光供養塔 (阿弥陀佛) |
141cm | 安山岩(小松石) | 1679年 |
| 庚申塔 | 67.5cm | 安山岩(小松石) | 1815年 |
| 馬頭観音供養塔 | 44cm | 安山岩(小松石) | 1774年 |
- 成田山深川不動堂
-
町民文化が花開いた江戸中期の元禄年間は不動尊信仰が急激に広まった。
その契機となったのがお不動様の江戸出開帳。
1703年4月、5代将軍綱吉の母桂昌院(けいしょういん)の「成田山の不動明王を江戸において参拝したい」と言う希望が実現。
ご本山から総勢300人が1週間をかけてご本尊が奉納。
2ヶ月にわたる江戸出開帳の場所となったのが深川永代寺境内であり、これが深川不動堂開創の機縁となった。- 開帳…秘仏を期間限定で公開する事
- 出開帳…遠方の寺社が他の寺社を借用して秘仏を公開する事
境内は深川公園となり、1881年この地に深川不動堂本堂建立。
東京大空襲でお堂は2度焼失するもご本尊は災禍を免れた。
平成年間に3回改修を行う。 - 御護摩修行
-
毎日9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00に行われる。
護摩とは、古代インドサンスクリット語の「ホーマー」に由来し、不動明王を本尊として祭壇を設け供物を捧げ、護摩木という特別な薪を焚き上げる真言密教の秘法。
護摩の炎は不動明王の智慧を象徴し、護摩木は煩悩を表す。
修行を通じて信徒は煩悩を不動明王の智慧の炎で焼き尽くし、諸願成就を祈念する。
これを形にして残したものが御護摩札。 - おねがい不動尊【1階】
-
2011年9月奉安。
身の丈5.4mの坐像で、不動尊像特有の半眼が仏師によりよく表現されている。
熊本県産の樹齢700年の楠を40本使用している。 - 祈りの回廊
-
10,000体のクリスタル五輪塔内部の小型不動尊像。
回廊中間地点は御本尊様の真下をくぐることになり、壁の巨大念珠を撫でながら参拝すると御利益がある。 - 阿字橋
-
物事の始まりを表す梵字「阿」
建立時に掘削された「願い石」の池を渡り、ここから内仏殿の参拝が始まる。
- 海琳堂
-
2013年創業の酒店。
日本酒をはじめ、梅酒などをバリエーション豊かに揃える。
一風変わった日本酒が特徴。
梅酒の種類も豊富。
近所にBar有り。
| 住所 |
東京都 江東区 深川2-12-1 大野屋ビル1F |
|---|---|
| 営業時間 | 平日 12h00~18h00 |
| 定休日 | 土日祝 |
| 支払 | 不明 |
| リンク | 公式サイト |
- 海琳堂 酒バー
- 海琳堂のバー。
| 住所 |
東京都 江東区 富岡1-8-2 天孝ビル4F |
|---|---|
| 電話 | 03-5857-8088 |
| 営業時間 | 18h00~23h00(L.O.22h30) |
| 定休日 | 月曜日 |
| 支払 | 不明 |
巣鴨
- 巣鴨地蔵通り商店街
-
巣鴨地蔵通り商店街は長さ約800mにわたる商店街で、加盟している商店数は約195店舗。
とげぬき地蔵尊縁日(4の日)には片側に200近くの露天商が立ち並ぶ。 - とげぬき地蔵尊高岩寺
-
商店街の中央部に鎮座する曹洞宗萬頂山高岩寺は、「とげぬき地蔵尊」という名で親しまれている名刹。
1596年に、現在の外神田二丁目で開創され、60年後、下谷屏風坂に移転。
そして、現在ある巣鴨には1891年に移ってきた。
境内の「洗い観音(聖観世音菩薩)」は、水をかけ、自分の悪いところを洗うと治るという信仰が生まれ、今は2代目の観音様を布で洗うほうになっている(初代は後部の厨子に納められている)。
| 巣鴨地蔵通り商店街の年中行事 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 行事 | 場所 |
| 1月24日 | とげぬき地蔵尊例大祭 | とげぬき地蔵尊高岩寺 |
| 2月3日 | 節分豆まき | とげぬき地蔵尊高岩寺 |
| 3月上旬 | ザ・DONがら | |
| 4月上旬 | 花まつり | とげぬき地蔵尊高岩寺 |
| 5月24日 | とげぬき地蔵尊例大祭 | とげぬき地蔵尊高岩寺 |
| 6月上旬 | すがも商人まつり | |
| 6月下旬 | 中元売出しセール | |
| 6月24日 | 江戸六地蔵尊百万遍大念珠供養 | 江戸六地蔵尊眞性寺 |
| 7月2日~4日 | すがも朝顔市 | とげぬき地蔵尊高岩寺 |
| 7月16日 | 眞性寺えんままつり | 江戸六地蔵尊眞性寺 |
| 7月28日~8月1日 | 巣鴨納涼盆踊り | とげぬき地蔵尊高岩寺境内 |
| 8月下旬 | ミニみに縁日 | 江戸六地蔵尊眞性寺境内 |
| 9月24日 | とげぬき地蔵尊例大祭 | とげぬき地蔵尊高岩寺 |
| 10月中旬 | ザ・DONがら | |
| 11月6日~14日 | すがも中山道菊まつり | とげぬき地蔵尊高岩寺・江戸六地蔵尊眞性寺・大正大学) |
| 11月下旬~ | 歳末売出しセール | |
六義園
- レンガを使用した外周塀
-
江戸時代中期に作庭された文化財庭園に、幕末以降にもたらされた技術を用いたレンガが使われている理由は、この文化財庭園の歴史的な変遷が大きく関わっている。
江戸時代当時の柳沢家の屋敷範囲と、明治年間以降の岩崎家の敷地とは、文化財庭園として指定された現在の六義園の範囲よりも東西南北にそれぞれ広がっていた。
指定文化財範囲から外れた、これらの土地では、日露戦争の祝勝会が開催され、第二次世界大戦当時には児童向けの科学館なども置かれていた。
従って、改修前のレンガ塀は、第二次世界大戦後に国指定の文化財として整備する前後の時期に、管理用に構築されたものであり、岩崎家所有当時の外周塀ではない。
しかしながら、柳沢家から岩崎家、そして東京市から東京都へと、所有者や管理者が移り変わってゆく中で、岩崎家が所有していた湯島や本所などの屋敷でも採り入れられた、洋風の意匠であるレンガ塀も、歴史的な変遷を物語る貴重な文化財と言える。 - 由緒
-
六義園は5代将軍・徳川綱吉の信任が厚かった川越藩主・柳澤吉保が1702年に築園した和歌の趣味を基調とする「回遊式築山泉水」の大名庭園。
園は江戸時代の大名庭園の中でも代表的なもので、池をめぐる園路を歩きながら移り変わる景色を楽しめる繊細で温和な日本庭園。
園内には和歌の浦の景勝や和歌に詠まれた名勝、中国古典の景観が八十八境として映し出されている。
1878年に三菱の創業者である岩崎弥太郎の別邸となった。
1938年に岩崎家より東京市に寄付され、1953年に国の特別名勝に指定された貴重な文化財。
六義園の名は、中国の詩の分類法(詩の六義=風・賦・比・興・雅・頌)に倣った古今集の序にある和歌の分類の六体(そえ歌・かぞえ歌・なずらえ歌・たとえ歌・ただごと歌・いわい歌)に由来。
柳澤吉保の「六義園記」では、日本風に「むくさのその」と呼んでいたが、現在では漢音読みで「六義」を「りくぎ」と読む習わしから「りくぎえん」と読む。 - 六義園と岩崎家
-
柳沢吉保によって造られた六義園は、7代保申(やすのぶ)の頃に明治維新を迎え、新政府に上地され、173年間にわたる柳沢家家別邸も終わりを告げた。
その後1878年、三菱財閥の創始者である岩崎彌太郎が、近隣の藤堂家、前田家、安藤家の土地屋敷とともにこの地を手に入れ、六義園に岩崎家別邸を設けた。
岩崎家は1874年に上京し、今の文京区湯島4丁目に居を構え六義園の地とは目と鼻の先の所に住んでいた。
その後はさしもの名園も次第に荒廃し、維新後は全く荒れ果てたが、彌太郎は1878年、清澄庭園と同じ頃にこれを手に入れ、その後さらに隣接の藤堂・安藤・前田諸家の邸地を併せ、総計396,000㎡の敷地に別邸を営んだ。
その地域は現在の文京区上富士前、同駕籠町及豊島区巣鴨2丁目、同駒込染井に跨る広大な土地である。
川田小一郎があまり大き過ぎるがどうするつもりかと尋ねたところ、彌太郎は「俺は板橋辺まで買い、国家の役に立つことをやってみるつもりだ」という。
維新後、幕末の混乱期を経て庭は荒廃していたが、岩崎家が別邸を設けたことから庭園の本格的な復興が始まった。
その修復工事は彌太郎から彌之助(彌太郎の弟)、久彌(彌太郎の長男)へと受け継がれ、園内には茅葺の「桃の茶屋(現心泉亭)」「滝見茶屋」「吟花亭」、岩崎家の熱海の別荘から移築した「熱海茶屋(現吹上茶屋)」、柱がツツジの枝幹で作られた「つつじ茶屋」「芦辺茶屋」などの建築物も配され、ようやく往時の美しさを取り戻した。
蓬莱島や佐渡の赤玉石など、園内に配された名石は岩崎時代のものも多く残っている。
※つつじ茶屋以外の建物は、震災や戦災などで焼失しており、現存しているのは再建されたもの。
六義園が彌太郎の在世中にどの程度まで復旧工事を進めたかは明らかではないが、彌太郎没後、彌之助は1886年に修復工事を進め、新たに下総の山林(後の末広牧場)から樹木数万本を移植し、各地から庭石を集めて、往時の景観を復元した。
1905年10月、日露戦争から凱旋した連合艦隊司令官東郷平八郎大将をはじめとする将兵6,000人を岩崎家が招待し、この六義園を中心とし一大戦勝祝賀会を催した。
それまで一般には公開されなかったこの六義園が、戦勝と久彌氏の国に対する恩顧からか、初めて初めて開放された事は、庭園の持つ意義から重要な歴史的事実と言える。
大正後期から、六義園を含む一帯12万坪に及ぶ岩崎家の地所は「大和郷」と名付けられた計画的な都市開発により高級住宅地として分譲された。
久彌はその中心にある六義園を1938年に東京市に寄付した。 - 東京市石碑
- 内庭大門
-
1938年、六義園は当時の所有者であった三菱財閥三代目の岩崎久彌によって東京市に寄付された。
この石碑はその時の記念として東京市が建てたもので、六義園の成り立ちも記されている。
岩崎家が六義園を所有したのは、明治維新によって政府に上地された六義園を1878年に三菱財閥創業者の岩崎彌太郎が手に入れ、別邸としたのが始まり。
その後、岩崎久彌の本邸・別邸となり、後に総理大臣に就任した政治家幣原喜重郎(しではらきじゅうろう)(彌太郎の女婿)が一時仮住まいとしたこともある。
右手の大きな門は「内庭大門」と呼ばれ、岩崎家所有当時の様子を残しているが、現在の門は東京市によって再建されたもの。
かつては門をくぐった先の枝垂れ桜付近に、岩崎家の「御殿」と呼ばれる邸があった。 - 新脩(しんしゅう)六義園碑
-
六義園の評判は作庭当時から高かったが、和歌の世界に憧れ、また皇室を尊んでいた吉保は、更に狩野派の絵師に描かせた本園の絵図を霊元上皇に献上した。
完成して4年後の1706年10月には、これに対して霊元上皇が六義園の景勝地「十二境八景」を選び、加えて延臣たちに命じて和歌を詠ませた巻物が吉保に下賜された。
一幕臣の屋敷の庭園に上皇を通じて和歌が贈られるのは極めて稀なことだった。
これほど名園として名高かった六義園も、六義園を愛した三代目信ときが1792年に亡くなって以降は荒廃の一途をたどったが、1809年、四代目保光が1年の月日と多大な費用を投じて復旧工事を行い、一部新たな景勝を加え加え甦る事になった。
その経緯について「六義園八景」と併せてこの「新脩六義園碑」に記されている。 - 妹山(いものやま)
六義園八十八景十四 - 背山(せのやま)
六義園八十八景十五 -
正面の中の島にある左側の山が妹山、右側の少し大きい方が背山。
六義園のモデルとなった紀州(和歌山県)の和歌の浦には「妹背山(いもせやま)」のある島が今も残る。
夫婦、兄妹のことを「妹背」と呼ぶが、夫婦和合、子孫繁栄の思いが込められている。
中央に立つ大きな石(紀州青石)は玉笹石(八十八境の十六)と呼ばれ、歌の中の男女の仲を隔てる笹に見立てられている。
また紀ノ川流域、吉野にも妹山・背山は実在し、万葉の歌枕として有名。
浄瑠璃「妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)」は、文楽や歌舞伎の演目としてお馴染み。 - 臥龍石(がりょうせき)
六義園八十八景二十二 - 蓬莱島
-
中の島の舟屋(現存しない)の左手にあるのが、八十八境の一つ、臥龍石。
その名の通り、龍が伏せているような形の石が水面から顔を出している。
池に浮かぶアーチ型の岩島が蓬莱島。
蓬莱島は中国の神仙思想において、修行により不老不死になった仙人が住むとされる神仙島の一つで、日本庭園では古くから不老長寿を願って造られた。
1702年の作庭当時には無く、明治時代になって、岩崎家によって造られたものと言われているが、庭園の景色に良く馴染んでいる。 - 尋芳径(じんほうけい/はなとふこみち)
六義園八十八景五十 - 千鳥橋
六義園八十八景五十六 -
六義園の景色は、池の周りを巡る「海の景」と、木間を行く「山の景」の二つに分けられる。
この付近が景色が変わるポイントで、右手の尋芳径を進むと山の景、左手の千鳥橋の向こうは海の景となる。
右手の道が尋芳径。
「芳しい花を尋ねて歩く道」という意味で、奈良の桜の名所、吉野山を尋ねる道に見立てられている。
初夏にはヤマツツジの花が見られる。
鳥の千鳥が足を交差させて歩く様子から、ジグザグの形を「千鳥」と呼ぶが、千鳥橋はかつてそういう形をしていた。
浜千鳥の行方を追って和歌の浦を探す、というイメージが重ねられる。 - 水香江(すいこうのえ)
六義園八十八景八十一 - 芙蓉橋
六義園八十八景八十四 -
現在は紅葉の名所になっているが、かつてはここに水が流れ、蓮の花が咲いていた。
現在でも、石組や地形の様子から、水の流れを想像することができる。
李白や杜甫が「蓮の花で水が香る」と詠んだ事に由来し、「水香江」という名が付けられた。
左手の飛石の先にある丸太の橋が芙蓉橋。
ちなみに「芙蓉」は中国語では「蓮」のことを指す。
吉保は20歳の時に嫡母を亡くし、それと同時に人生に対する疑問を感じ、禅の道に入った。
その影響から六義園には和歌だけでなく、水香江、芙蓉橋、坐禅石(つつじ茶屋付近/六義園八十八景七十九)に見あられるように仏教に基づく名所もある。 - つつじ茶屋
-
明治維新後、岩崎家は六義園を所有し、庭園を修復すると同時に、園内各所に洒落た亭を建てた。
その多くは焼失したが、唯一現存しているのが、この先の「つつじ茶屋」。
柱と梁に躑躅の木を使っている(内三本の柱は百日紅の木)他に類を見ない貴重な建物。
ツツジの木は極めて成長が遅く、柱として使えるような材木を集めるのは非常に難しかったと思われる。
全体に老朽化が進んでいる為、周囲を栗の木の控柱で補強している。 - 吹上浜
六義園八十八景六十三 - 吹上松
六義園八十八景六十四 -
「吹上浜」という地名は全国にあるが、ここは和歌山市の「吹上
」に因んでいる。
吹上にはかつて砂丘と松林があり、『根上り松』という変わった形の松が見られた。
六義園が造られた時の絵図面にも池の周囲には多くの松が描かれており、松が庭園の主要木であったことが伺える。
そのほとんどは失われたが、この「吹上松」の老木のみ絵図面とほぼ同じ位置にあり、大切に管理されている。
左手の「吹上茶屋」は、「熱海ノ茶屋」として岩崎家によって建てられたが、戦災などで焼けた後に東京都によって再建され、現在は抹茶の店舗として活用されている。 - 藤代峠
六義園八十八景七十四 - 紀川
六義園八十八景二十四 -
六義園のモデルとなった紀州(和歌山県)和歌の浦の対岸には、有間皇子の悲劇で知られる「藤白坂」がある。
その峠を登り切った名所「御所の芝」からは、和歌の浦全体を見渡すことができる。
ここ「藤代峠」はこの藤白坂に見立てられており、園内の中の島、紀川、和歌の浦を見渡すことができるポイントとなっている。
また、真南を見れば綱吉のいる江戸城の方角。
西は綱吉の母である桂昌院が建立した護国寺の方角。
そして東は将軍家の菩提寺である上野の寛永寺の方角。
更に遥かには富士山と筑波山が望めた。
背後に見える中の島の手前の池が「紀川」で、「紀の川」の見立てと考えられている。
紀の川は奈良県川上村を水源とし、奈良県側では吉野川、和歌山県側では紀の川と呼び名を変え、奈良の都と和歌の浦を繋いでいる。
和歌の源泉である「紀川上」から和歌の浦へと続く「紀ノ川」は和歌の歴史そのものと捉えることができ、藤代峠の頂きは、その不滅の流れの偉大さを俯瞰する場所として位置付けられており、園内景観の中でも最重要。
池袋
- トキワ荘
-
1952年から1982年にかけて存在した木造2階建てアパート。
全部屋四畳半(7.29㎡)で、洗面台(lavabo)、台所、トイレは共同。
一流の漫画家(auteur de bande dessinée/bédéiste)たちが住んだ。
漫画家が集まった背景には、寺田ヒロオの
「漫画家の共同体(la communauté)を作り、切磋琢磨(travailler avec émulation)できる環境を作りたい。」
編集者の
「漫画家が原稿を落としそうになったら、他の部屋から助っ人を呼べる。」
他の漫画から
「他の漫画家の穴埋めでもいいから自分の仕事を売り込む機会が欲しい。」
といった利害関係の一致(avoir les mémes intérêts)があった。
入居には一定の審査(examen)があり、先住の漫画家らが技量(la capacité)や協調性(le caractère)を確認した。
また、編集者(rédacteur)の都合で入居させる例もあった。
- 日本加除出版
-
1942年に設立された、戸籍(état civil)・登記(enregistrement)・供託(consignation)に関する書籍を手掛ける出版社(société d'édition)。
トキワ荘とは直接関係は無い。
- 自由学園明日館
-
1921年、羽仁もと子、吉一夫妻が創立。
帝国ホテル建設でライトの助手として動いていた遠藤新(あらた)と夫妻の間に交流があり、遠藤から夫妻へライドが紹介された。
ライトは限られた工費の中でいかに空間を充実させるかを考えた。
ホールの窓は高価なステンドグラスの代わりに木製の窓枠や桟を幾何学的に配して工費を低く抑え、かつユニークな空間構造を実現。
ホールに置かれた六角椅子は帝国ホテル2代目本館(ライト館)で使われていたピーコックチェアに似た遠藤新のデザイン。
ライトは家具も建物の一部と考え、六角形の建物には六角形の家具を配した。
ホールの壁画は創立10周年を記念して選ばれた聖句「見よ、火の柱、雲の柱・・・」という旧約聖書出エジプト記の一節がモチーフ。
当時学園の美術教師を務めた石井鶴三の指導のもと、生徒たちの手によって描かれた。
全校生徒が集まり手作りの温かい昼食をいただくことは、羽仁夫妻が願った教育の基本だった。
その為、当時の学校建築としては珍しく食堂が校舎の中心に設計されている。
保存修理工事以前は食堂の真下に台所があり、当時はそこで当番の生徒が昼食を作っていた。
出来上がった料理を手早く食堂に上げる為、簡易式のダムウェーターが設置されていた。
しかし、かえって手間がかかるので、階段に列を作り、バケツリレーの要領で食堂まで上げていたというエピソードも残っている。
修理工事後は、新築された建物に厨房を移し、昔の台所部分は機械室や事務室として利用。
羽仁夫妻がライトに設計を依頼したのが1921年1月で入学式が同年4月に行われている為、かなりのスピード工事だった事が伺える。
敷地の南側に建つ講堂は遠藤新の設計で1927年に完成。
生徒数増加により中央棟ホールでは手狭になった為、第5回本科卒業生の父母の提案により、当時テニスコートとして利用していた場所に講堂を建設。 - 羽仁(はに)もと子(1873~1957)
-
青森県八戸市生まれ。
高校在学中に洗礼を受け、キリスト教を信仰。
教会に属さない無教会派。
1897年に報知新聞社に入社し、女性ジャーナリスト先駆者。
1901年に羽仁吉一と再建し、新聞社を退職。
1903年に女性雑誌『家庭之友』を創刊。
1904年に家計簿を刊行。
これが日本初の家計簿と言われる。
1908年に『家庭之友』から『婦人之友』と改題し、婦人之友社を設立。
1921年に読書の子への家庭的な教育を目指して、当初は女子校として西池袋に自由学園を創立。
名称は新約聖書の「真理はあなたたちを自由にする(ヨハネによる福音書8:32)」に由来。
教育理念はキリスト教のプロテスタントに基づく。
創立当時、来日していたアメリカ人建築家Frank Lloyd Wright(フランク・ロイド・ライト)はファミリースクールへの共感から積極的に校舎の設計を引き受け、後に自由学園明日館として国の重要文化財の指定を受け一般公開される。
1925年に学校規模拡大で東京都久留米市に移転。
幼稚園、小学校、中学校、高等学校を擁する一貫教育。 - 明日館の梟
-
明日館は大正10年に自由学園がこの地に設立された時の校舎。
この梟像は豊島区の区制70周年を記念した事業で「梟の路」として設置された物。
平成15年に自由学園の生徒達が明日館に所縁のある大谷石で製作。
- 学習院大学と皇族
-
1847年に仁孝天皇が京都御所内に公家専門の学習所を設置。
明治に入り天皇が東京に移住した際、学校も東京へ移動。
戦後の1949年に大学として民間へも門戸を解放。
1908年に目白へ移転。
- 鬼子母神
-
雑司ヶ谷の鬼子母神は、1561年に文京区目白台で掘り出された鬼子母神像を1578年に現在の場所に堂を建てて安置したことにはじまる。
1625年には社殿の造営が始まり、1646年には宮殿が寄進された。
江戸時代前期から将軍の御成りがあるなど、武家から庶民まで、子育て、安産の神として広く信仰され、現在でも多くの参詣者が訪れる。
現在の鬼子母神堂は、手前から「拝殿」「相の間」「本殿」の3つの建物で構成される「権殿造り」。
本殿の開堂供養は1666年に行われた記録にあるが、屋根裏の束に書かれた墨書から、1664年に上棟されたことが判明している。
拝殿と相の間は1700年に建てられた。
広島藩2代目藩主浅野光晟(みつあきら)の正室満姫(まんひめ)の寄進により建てられ、その建築には広島から呼び寄せた大工が従事している。
その為、本殿の三方の妻を飾る梁や組物の彫刻には広島地方の寺社に用いられている建築様式が見られる。
拝殿は、江戸時代中期の華やかな建物ではあるものの、装飾を簡素なものに変えるなど、幕府による建築制限令への対応をうかがわせる特徴が見られる。
これらのことから、江戸時代の大名家による寺社造営の実像を示す事例であり、本殿と拝殿とで異なる特徴を持つ建造物であることから、歴史的・意匠的に価値が高いと言う点が評価され、2016年7月25日に重要文化財に指定された。 - 鬼子母神大門ケヤキ並木
-
鬼子母神堂は、江戸時代から子授け、安産の御利益があるとされ、多くの参詣者を集めてきた。
江戸後期には、将軍の御成もあったほど大いに繁盛した。
参道には名物の大きなケヤキ並木とたくさんの茶店、料亭などが並び、参詣土産には、現在も造られている「すすきみみずく」などが売られていた。
かつては大径のケヤキが多く、荘厳な風景を醸し出していたが、現在は徐々に若いケヤキに植え替えられ、巨木は4本のみ。
毎年10月に行われるお会式(おえしき)には万灯行列が周辺を練り歩き、往時の賑わいを伝えている。 - 武芳稲荷大尊天
-
武芳稲荷堂は、倉稲魂命(ウケノミタマノミコト)を祀った堂宇。
「日本書紀」では「ウケ」は穀物・食物を意味し、倉稲魂命は「穀物の神」といわれている。
昔、この辺りで農耕が盛んに行われていた事が伺える。
創建年代は不明だが、雑司ヶ谷鬼子母神縁起によれば、1578年に「稲荷の森」と呼ばれていた当地に堂宇を建立して鬼子母神像を安置したと記されているので、武芳稲荷堂はこれよりも以前に建立され、1582年当時は既にこの地の地主神として多くの人々に知られていた。
元は1坪にも満たない木造の堂宇だったが、1967年に現在の堂が建立され、1971年には鳥居25基、1974年には、正面に神狐像2体が奉納された。
武芳稲荷尊天は、また古来より「出世稲荷」とも称され、商売繁盛、開運隆昌とともにその霊験あらたかなることを慕う大勢の信徒に尊崇されている。
毎年、節分後の午の日に初午大祭、5月18日に夏季大祭、9月18日には秋季大祭がそれぞれ修され、参詣者の開運出世、除厄得幸の祈願が行われている。 - 雑司ヶ谷鬼子母神のイチョウ
-
銀杏(公孫樹)は、一属一種のイチョウ科に属する、裸子植物の落葉高木。
耐寒耐暑性があり、社寺の境内樹・庭園樹・公園樹・街路樹などに広く植栽されている。
中国原産と言われ日本へは遣唐使の帰国によってもたらされた。
雌雄異株で、4月に開花し10月に種子(銀杏)は成熟し、黄葉する。
樹高30m、幹周8mの雄株で、都内のイチョウでは、麻布善福寺のイチョウに次ぐ巨樹であり、樹勢は盛ん。
1394~1428年に僧日宥が植えた。
古来「子授け銀杏」と言われ、戸張苗堅の『櫨楓』によると、婦人がこのイチョウを抱く光景が見られ、注連縄(しめなわ)を張るようになったのは、1818~29年の頃という。
目黒
- 大圓寺
- 創建…1624年
- 本尊…釈迦如来
- 宗派…天台宗
- 開山…大海
-
17世紀頭、湯殿山の僧大海が行人坂を引き開き、大日金輪を祀って祈願道場を開いたのが起源。
1772年、本堂から出火し江戸の街を焼き多くの死者を出したが、その供養のために造られた釈迦三尊・十六大弟子、五百羅漢の像等の大圓寺石仏群がある。 - 木造十一面観音立像
-
一木彫刻。
やや面長で伏眼がちで細身で長身な体躯は藤原時代の特徴。 - 木造阿弥陀三尊像
-
中尊阿弥陀如来像は来迎印を結び、左足を垂下した半跏の姿、観音像は蓮台を持ち左膝を立て、勢至像は合掌し右膝を立てた典型的な来迎形の阿弥陀三尊像であるが中尊が半跏座の姿をとる例は少なく珍しい三尊形式である。
江戸時代の仏像がいずれもこぢんまりとしているのに対し、気宇広大な特色を持つ。
両脇侍像蓮台の木札に1770年大仏師桃水伊三郎等の銘がある。 - 八百屋お七と吉三(西運)
Oshichi et Kichiza(Saiun) -
江戸時代、本郷駒込町に住む八百屋の娘お七は、1682年の火事の際、避難の為近くの円林寺に仮住まいし、その時に寺小姓の吉三に恋した。
しかし、避難生活が終わり、やがて離れ離れになり、お七は吉三に会いたさ故に乱心し、自宅に火を放った。
大事には至らなかったものの、当時放火は大罪。
お七は大井鈴ヶ森刑場で火刑に処されれた。
その後、吉三は西運として出家し、お七の菩提を弔う為に、念仏を唱えながら諸国巡礼行脚した。
江戸に戻った西運は、大圓寺坂下にあった明王院(現雅叙園)に阿弥陀三尊仏を祀り、身を寄せながら浅草寺までの道のりを休むことなく念仏を唱えながら27年5ヶ月かけて成し遂げた。
その夜、お七が夢枕に立って成仏した事を告げた。
その姿が今現在も阿弥陀堂に祀られているお七地蔵。
西運は集まった浄財で行人坂の石畳を直し、目黒川に架かる橋を石の橋に造り替え、社会活動の数々を行なった。
そのことを伝える当時の石碑が現在文化財指定となり、寺に伝えられている。 - ※寺小姓…寺に住んで、住職に仕えた少年。
- 大円寺石仏群
-
1772年2月に本堂から出火した大火による死者を供養。
江戸三代火事- 振袖火事(1657)
- 行人坂の火事(1772)
- 車町の火事(1806)
左右に文殊菩薩・普賢菩薩を配した釈迦三尊像を十大弟子と十六羅漢が囲み、背後に491基の羅漢像が並ぶ。
中には大火前の1763年造立の羅漢もあるが、多くは1781年以降の作。
行人坂火事以外の供養も含まれており、広く勧進を募り時間をかけて今の石仏群が造られた。
1848年に大円寺が再興された時、石仏も今の地に安置。 - 行人坂敷石造道供養碑
-
1703年造立で、高さ164cmの供養碑は、上部に種子(梵字)キリーク.(阿弥陀)サ.(観音)サク.(勢至)が刻まれている。
下部の碑文によって、この坂を利用する念仏行者たちが悪路に苦しむ人々を救うため、目黒不動尊や浅草観音に参詣し、通りがかりの人々から報謝を受け、これを資金として行人坂に敷石の道を造り、この成就と往来の安全とを供養祈願した。 - とろけ地蔵尊
-
火事の際、このお地蔵様を目黒川に投げ入れた。
やがて江戸時代に品川沖で漁師の網にかかった。
悩みをとろけさせ、解消してくれる。 - 六地蔵
-
地獄道から天道を救う6体の地蔵。
天道 日光地蔵 預天賀地蔵 人間道 除蓋障地蔵 放光王地蔵 修羅道 持地(じじ)地蔵 金剛幢(こんごうとう)地蔵 畜生道 宝印(ほうじゅ)地蔵 金剛悲地蔵 餓鬼道 宝珠(ほういん)地蔵 金剛宝地蔵 地獄道 檀陀(だんだ)地蔵 金剛願地蔵








月島
- 佃
-
佃島は元々隅田川河口の干潟の埋立地。
1590年に摂津国佃村(現在の大阪)の漁師たちが徳川家康の命を受け、江戸に移り住んで作った街が佃。 - 佃の成り立ち
-
1582年6月2日に本能寺で明智光秀のクーデターにより織田信長暗殺。
実は信長が殺害された翌日に家康は信長と会合を開く予定で堺に滞在していた。
信長暗殺の一報を受け、家康は自分にも危害が及ぶと予見し、どうにか堺から脱出したかった。
しかし、堺は川や海が多く行く手を阻まれる。
そんな中、地域の水路に明るい佃村の漁師が家康を手助けし、岡崎城へ無事辿り着いた。
信長亡き後、豊臣秀吉によって天下統一が成され、家康は関東へ移転を命じられた。
家康の手腕により関東地域は発展し人口増加。
しかし、人口増加に伴い多くの食料が必要になった。
そこで漁猟強化対策として以前世話になった摂津国佃村の漁師たち33名を江戸へ呼び寄せ、1622~44年にかけて干潟を埋め立てて彼らの住居とした。
これが佃島。 - 佃の漁師たちのその後と佃煮
-
佃の漁師たちは11月から3月にかけて、将軍献上の白魚漁を命じられ、隅田川の千住エリアから品川沖に至る広大な海上漁業権も与えられた。
また、漁師達は保存食として魚介を甘辛く煮た物を作った。
それが飯や酒のお供に丁度良いとされ、江戸市中で売られるようになった。
- 佃天台地蔵尊
-
先述の通り、佃島はかつて川に囲まれた地形で、子供の水難事故が多発。
刻銘にある妙雲和尚は天台宗の僧侶で江戸末期から明治期に84,000体の石地蔵建立を発願。
上野寛永寺傍の浄名院境内には20,000体程ある。
子供の水難事故防止祈願の地蔵も妙運和尚の建立。
銀杏の木は樹齢400年以上。
- 住吉神社
-
神功皇后(第14代仲哀天皇の后、第15代応神天皇の母)三韓征伐(3世紀頃の逸話)の際、住吉三神の御守護により無事達成され、その帰途摂津国(現在の大阪)にて住吉三神を遥拝。
その後、家康公と佃漁師たちの繋がりができ、1646年6月29日に住吉三神、神功皇后、徳川家康の御神霊を祀った。
家康の御霊が祀られ、水盤舎には佃漁師たちの漁猟情景が彫られている。
海運業、各問屋組合をはじめ多くの人々から、海上安全の守護神として信仰を集める。 - 例祭
-
この場所には、江戸時代後期1798年徳川幕府より建立を許された大幟(le drapeau)・抱(幟を支える木)が埋設されている。
3年に1度、8月に執り行われる住吉神社の例祭で使用。
18mの大幟6本が建てられる。 - 宮神輿 八角神輿
-
左…2011年作
右…1838年作
芝大門の万屋利兵衛により1838年に製作。
八角型は天皇陛下の御座高御座を模した。
古くは海中渡御の為、内部も漆が塗られ気密性が高い。
170年以上例祭において使用されてきたが、保存の為2011年に八丁堀秋山三五郎により新しく製作。 - 鰹塚
-
鰹節問屋は江戸時代から住吉大神を生業繁栄の守護神として奉賛。
神社建築では、棟木の上に鰹節に似た円柱状の飾り木「堅魚木」が横に並ぶ。
我が国最古の法典である大宝律令(701年)に堅魚、煮堅魚、堅魚煎汁(煮詰めたエキス)の記録があるように、大和民族は古来より鰹を食し、保存食、調味料として利用してきた。
東京鰹節類卸商業協同組合は、鰹の御霊に感謝慰霊の意を込め、また豊漁を願い、1953年5月「鰹塚」を建立。
費用は組合員96名の積み立てによる浄財。
塚石は鞍馬石(高2.1m/幅1.2m)、台石は伊予青石(高91cm)。
表面の筆は、鰹節問屋「中弥」店主の山崎節堂、裏面は慶應義塾大学名誉教授池田弥三郎。
豊洲
- 豊洲市場
-
築地市場の代替施設として2018年から取引開始。
セリ見学は午前5時半〜午前6時半。
市場前駅は2005年に名前が決まり、2006年に開業。
実は2004年の段階で豊洲に市場を移転する計画が成されており、移転に先立って命名。
当初2014年移転予定だったが、豊洲には東京ガスの施設が建っており、土壌汚染が発覚した為、2018年まで延期。
詳細は築地市場を参照。
- チームラボプラネッツTOKYO DMM
-
チームラボ株式会社とDMM.comが設立したデジタルテクノロジーを活用したアート施設。
2016年にお台場でオープンし、2018年に豊洲にも展開。
コンセプトは、
「水に入るミュージアム(Le musée dans l'eau)」
2021年、新たに二つの大型庭園作品が加わり、
「水に入るミュージアムと花と一体化する庭園(Le musée dans l'eau et Le jardin où on s'unifie des fleurs)」
に生まれ変わった。
コンセプトの通り、水に入るため、裸足になる必要がある。
オープン当初は2020年秋までの予定だったが、2027年末まで延期。
台場
- お台場
-
1853年 ペリー(Perry:le commodore américain)が来航し開国要求。
幕府は防衛の為、洋式の海上砲台(le canon)建設。
翌1854年に砲台の一部完成。
幕府に敬意を払って(en hommage à Bakufu)「御」台場=お台場と呼ばれた。
ペリー艦隊は品川沖まで来たが、この砲台のおかげで横浜まで引き返し(retourner)、そこに上陸(débarquer)。
砲台は一度も使われることなく、戦前には撤去され、公園や港として整備。
平成に入り、東京都は都心の混雑緩和の為(pour se dégager l’embouteillage)に東京臨海副都心計画を実施。
1987年 レインボーブリッジ着工
1993年 レインボーブリッジ竣工
1995年 ゆりかもめ(新橋〜有明)開業
1996年 デックス東京ビーチ(ジョイポリス、レゴランド)
1997年 フジテレビが新宿から移転
1998~99年+2000年以降 自由の女神像
→日本におけるフランス年事業の一環として1998年4月29日から1999年5月9日まで設置。
この事業が好評を博した為、その後フランス政府からブロンズ(bronze)製のレプリカ(copie)が贈られ2000年以降常設設置。
🇫🇷1998年 フランス開催FIFAワールドカップ後、トルシエ(Philippe Troussier)が日本代表監督に就任
🇫🇷1999年 ルノーが日産自動車の経営権確保→ゴーンがCOOに就任
1999年 パレットタウン(ヴィーナスフォート、Zepp Tokyo、大観覧車)
2000年 アクアシティお台場
2001年 日本科学未来館(Musée national des sciences émergentes et de l’innovation)
2003年 大江戸温泉物語
2012年 ダイバーシティ東京プラザ
2021年9月5日 大江戸温泉物語閉館 2021年12月 パレットタウン再開発に伴い、関連施設(Zepp Tokyo、ヴィーナスフォート等)を閉業
- 25 Porticos:The Color and its Reflections
- 1996年、フランス人でインスタレーション(Une installation artistique)で有名なDaniel Burenによて制作。

- 新島のモヤイ像
-
新島には「もやい」という習慣があった。
太平洋の只中で島民が互いに助け合って生きる、いわば共助の意識から生まれた素朴な人々の優しい心根を表す「絆」だった。
台場を訪れる人々にも「連帯の心」絆を大きく成長させる出会いであれ。

- レインボーブリッジ
-
1987年着工→1993年竣工。
全長798m、幅49m、高さ126mの吊り橋。
上部に首都高、下部中央にゆりかもめとその両脇に歩道。
名称は一般公募。
- 自由の女神像
-
高さ17.4m(台座を除くと11.5m)
重量9トン
ニューヨークにある女神像の1/7スケール。
日本とフランスの友好関係を記念して1998年に1年間の期間限定で貸し出された。
その後、あまりの評判から在日フランス大使館協力のもと、パリにある女神像から型をとり、レプリカを制作。
2000年に設置。
- La flamme de la liberté
-
「フランスにおける日本年(1997~1998)」と「日本におけるフランス年(1998~1999)」を記念し、また日仏の友好を讃えるために、「日本におけるフランス年」実行委員会、パリ市、パリ-東京協会、ならびエールフランス航空などのフランス企業はフジテレビと臨海副都心まちづくり協議会の協力のもとに芸術家マルク・クチュリエ氏(M.Marc Couturier)のオリジナル作品である本作品を、東京と日本に贈呈した。
Pour commémorer
本作品は2000年11月21日に除幕。

- ガンダム
-
ガンダムシリーズは1979年の「機動戦士ガンダム」が初代。
バンダイ公式ガンプラ総合施設ガンダムベース東京を擁するダイバーシティ東京プラザとともに2012年に建設された等身大(19.7m)のガンダム。
2017年にユニコーンガンダムに変更。
2016年にテレビアニメ化されたのが契機。
- WABI×SABI
-
2012年4月19日オープン。
1947年、長野県塩尻市木曽平沢で創業の漆器・木製品・和家具・和雑貨の製造販売を行う中村漆器産業株式会社の小売店。
東京都江東区青海1-1-10
お台場ダイバーシティ東京プラザ2F
平日11:00~20:00
土日祝10:00~21:00
公式サイト
お台場の建築
- 株式会社ダイ・インダストリー
-
2006年に設立された人材派遣事業、イベント運営事業企業。
2009年に水産加工品移動販売事業を開始。 - 東京ベイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート
- ホテルトラスティ東京ベイサイド
-
リゾートトラスト株式会社が2008年に開業したホテル。
1973年創業の企業で、国内55箇所にリゾートホテルを運営。
他、ゴルフ場14箇所、医療施設37箇所、高級老人ホーム23箇所を運営。


品川
- 品川神社
- 天比理乃咩命(あめのひりのめのみこと)…祈願成就・航海安全
- 宇賀之売命…農業・商業・産業繁栄
- 素戔嗚尊…風水害除け・疫病(病気)除け
-
1187年、源頼朝が安房国の洲崎明神の天比理乃咩命(あめのひりのめのみこと)を当地にお迎えして海上交通安全と祈願成就を祈念して創始。
1319年に二階堂道蘊(どううん)が「宇賀之売命(お稲荷様)」を、さらに1478年に太田道灌が「素戔嗚尊(天王様)」をそれぞれ祀った。
1600年、徳川家康が関ヶ原の戦いへ出陣の際に当社へ参拝し戦勝を祈願。
その後、祈願成就の御礼として仮面(天下一嘗の面)・神輿(葵神輿)等を奉納。
また、1637年徳川家光により東海寺が建立され当社がその鎮守と定められ、「御修覆所(神社の建物の再建・修復等は全て幕府が賄う)」となり、1694年と1850年の2度の社殿焼失時に将軍の命により再建が行われた。
1868年11月には明治天皇が新都東京の安寧と国家繁栄を祈願する為に当社を含む都内10の神社を「准勅祭神社」と定めた。
大東亜戦争時には、幸い戦火を免れたが、社殿の老朽化により1964年、氏子各位の協力のもと、現在の社殿に再建。 - 阿那稲荷社
-
金運、商売運にご利益がある神社。
上社には「天の恵みの霊」
下社には「地の恵みの霊」
を祀る。
下社には「八百萬神社」「大國主恵比須神社」「天王白龍辨財天社」が一緒に祀られている。
また、「一粒萬倍の泉」がある。 - 八百萬神社
- 大國主恵比須神社
-
大国主大神(大黒様)と事代主大神(恵比寿様)の両神を祀る。
大国主(父)と事代主(子)は親子関係。
大国主は農耕の神。
事代主は漁業の神。 - 天王白龍辨財天社
- 品川神社富士塚
-
1869年、北品川宿の丸嘉講社の講中300人によって造立。
神仏分離政策で一時破壊→1872年に再築→1922年第一京浜国道建設の時現在地へ移築。
毎年7月1日に近い日曜日に講員一同が白装束で浅間神社前で「拝み」を行う。
その後、裸足で富士塚に登り、山頂の遥拝所や小御嶽の祠でも「拝み」をして下山し、社殿に戻ってから平服に着替える。
かつては盛んだった行事ではあるが、現在も行っている富士講は極めて少ない。 - 忠魂碑
-
1910年4月に品川町在郷軍人会が日清・日露戦争の戦没者慰霊の為、乃木希典大将の筆により当時の東海小学校構内に建立。
その後1932年9月に権現山公園(現城南中学校校舎前)に移し、日支事変・大東亜戦争の戦没者を加えて慰霊を行った。
1950年終戦後占領軍の命令により撤去されたが、北品川三丁目田島卯之吉氏が引き取り、千葉県南行徳の源心寺に移され、慰霊を行った。
源心寺及び田島孝作氏の厚意で終戦50周年記念事業として品川神社に引き取り、戦没者の追悼慰霊祭を行い、平和の尊さを後世に伝える。
- 東海道品川宿の石垣石
-
花壇の石材は、品海公園北隣の民家基礎の石。
品川宿街道筋の土留めと目黒川の護岸を兼ねた石垣。
石材は千葉鋸山産の凝灰岩であり、幕末から明治時代の加工と言われる。
品川宿の護岸は、もともと伊豆半島産の安山岩で構築されていたが、江戸時代後期に房州石が加わる。
房州石は産地も近く、柔らかく切り出しやすい石質の為、次第に伊豆石に取って代わった。
品川は海沿いの為、運搬もしやすかった。
品川宿は「東海道の玄関」として賑わい、宿内には1,600軒もの家屋が建ち並び、7,000人規模の人口を擁した。
- 承教寺
-
元々は虎ノ門にあったが1653年に現在の地へ移転。
池上本門寺の末寺。
1745年の大火で山門、仁王門、鐘楼以外焼失。
類焼した本堂は1781年に再建。
東京都港区高輪2-8-2 - 英一蝶(1652~1724)
はなぶさいっちょう -
英一蝶は江戸中期の画家。
狩野安信に学び人物・花鳥に優れ、やがて独自の軽妙洒脱な画風を創始、和歌・発句もよくした。
はじめ多賀朝湖と称したが46歳の時「朝妻舟」という絵で将軍綱吉の放縦な生活を風刺した為、幕府の忌憚に触れ三宅島に遠島。
赦免後、英一蝶と改名。
この英一蝶の墓が当「承教寺」境内にある。
1924年2月東京府知事より史跡に仮指定された。
| 創建 | 1299年 |
|---|---|
| 宗派 | 日蓮宗 |
| 本尊 | 曼荼羅 釈迦如来図 |
- 法禅師
-
1179年、浄土宗の開祖法然が東北地方で布教活動をしている金光坊に自分の肖像を送ろうとしたところ、この地で法然像が動かなくなった。
その為、草庵に安置したのが当寺の起源。
1593年、江戸道三河岸(現・千代田区大手町)に移転。
なお、元の品川にも寺が残されたので、当時2つの法禅寺が存在した。
移転した法禅寺は戦後の1947年に安民寺と合併し、神田寺となった。
18世紀初頭、5代将軍綱吉の生母桂昌院の帰依を受け、格式ある寺院として整備。 - 法禅寺板碑・宝篋印塔・五輪塔
-
板碑は、鎌倉時代から戦国時代にかけて造られた石像の供養塔で、この板碑の石材は多くの関東の板碑同様、秩父産の緑泥片岩が使われている。
宝篋印塔・五輪塔とも、中世を代表する供養塔・墓塔。 -
これほど大量の板碑などが一箇所から出土し保存されている例は珍しく貴重。
萬霊塔(ばんれいとう)と枯骨之墳(ここつのふん)は同時に出土した人骨を弔う為に建立されたもので、遺墳碑はその経緯を記し1869年に建てられた。
板碑のうち、1452年銘の阿弥陀三尊種子を刻んだものは、品川区立品川歴史館に常設展示されている。 - 流民叢塚碑(るみんそうづかひ)
-
天保の大飢饉で亡くなった人達を祀る供養塔。
1833年に始まった天候不順は、その後数年に及び多数の餓死者を出した。
品川宿には農民などから流浪してくる者が多く、この付近で病や飢餓で倒れる人が891人を数えるに至った。
これらの死者は、法禅寺と海蔵寺に葬られた。
本寺には500余人が埋葬された。
初めは円墳状の塚で、この塚の上に1871年造立の流民叢塚碑が立てられていた。
1934年に境内が整備された折、同じ場所にコンクリート製の納骨堂が建てられ、上にこの碑が置かれた。
碑の正面には、当時の惨状が刻まれており、天保の飢饉の悲惨さを伝えるとともに、名もない庶民の存在を伝えている。
| 創建 | 1384年 |
|---|---|
| 宗派 | 浄土宗 |
| 本尊 | 阿弥陀如来 |
| 点数 | 最古 | |
|---|---|---|
| 板碑 | 116点 | 1308年 |
| 宝篋印塔 | 52点 | 1409年 |
| 五輪塔 | 104点 | 1406年 |
- 丸屋履物店
-
1865年創業の和装履物専門店。
東京都品川区北品川2-3-7
🕐9:00~19:00
日曜定休
公式サイト
- 蟻鱒鳶ル(アリマストンビル)
-
東京都港区三田4-15
建築家の岡啓輔が2005年に着工した40㎡の土地に建てた25㎡(延床面積100㎡)の完全自作RC建築。
地の蟻、水の鱒、空の鳶、巨匠のル(Le Corbusier)に由来。
- 泉岳寺
-
1612年に門庵宗関(もんなんそうかん)和尚(今川義元に孫)を拝請して徳川家康が外桜田(現在のホテルオークラ近く)に創立。
しかし1641年の寛永の大火によって焼失。
家光公が毛利・浅野・朽木・丹羽・水谷の五大名に命じ、高輪に移転復興。
浅野家と泉岳寺の付き合いはこの時以来。
創建時より七堂伽藍を完備し、諸国の僧侶200名近くが参学する、江戸三箇寺並びに三学寮として有名。
人数は少ないが、大学で仏教を学びつつ泉岳寺で修行する若い修行僧もいる。 - 江戸三箇寺
-
江戸時代に関三刹の配下として江戸府内の曹洞宗を統括した3箇所の曹洞宗寺院。
江戸僧録、江戸触頭とも言う。
関三刹と同様、宗務庁に引き継がれたが、總泉寺以外の2箇寺は付属の学寮が発展して曹洞宗大学(駒澤大学)となった。 - 赤穂事件
-
播州赤穂藩・浅野内匠頭は勅使饗応役を幕府から命ぜられた。
その役目の上司が吉良上野介。
浅野内匠頭が接待に関して、吉良上野介に指導を仰いだが、数々の嫌がらせ(harcèlement)を受けた。
それは武士の立場を著しく傷つける理不尽なものであり、1701年3月14日、浅野内匠頭は江戸城・松の廊下で刃傷に及んだ。
当時は「喧嘩両成敗」の御定法があり、浅野・吉良両名とも処罰を受けると思われていたが、赤穂藩にのみ処罰。
浅野内匠頭は即日切腹。
しかも、大名という高い位にもかかわらず庭先での切腹。
一方の吉良はお咎め無し。
赤穂藩の武士たちがこの処罰に納得するはずはなく、処罰の撤回と藩の再興を嘆願したが容れられず。
そして家老・大石内蔵助を頭とした47人の武士が2年後の1702年12月14日に吉良邸へ討ち入り、本懐を成就した。
赤穂義士たちは亡き主君に報告すべく、浅野内匠頭が眠る泉岳寺へ吉良の首を掲げながら向かった。
義士たちは逃げ隠れすることなく、幕府に自分たちの行いを報告し、討ち入りの翌1703年2月4日に四大名家(細川家・松平家・毛利家・水野家)にて切腹。 - 敵討
-
主君を殺害した者に対して私刑として復讐を行なった日本の制度で、武士が台頭した中世期からの慣行で、江戸期には警察権の範囲として制度化された。
日本最古の敵討は456年に起きた「眉輪王(まよわのおおきみ)の変」
以下詳細 - 眉輪王の義理の父・第20代安康天皇が眉輪王の父・大草香皇子を殺害し、母である中磯皇女を自らの妃とした。
- 眉輪王は事実を知り、安康天皇熟睡中に刺殺。
- 事件後、眉輪王は「私は皇位を狙ったのではない、ただ父の仇に報いただけだ」と供述。
-
その後仇討ちは中世武士階級台頭以来、その血族意識から起こった風俗として広く見られるようになり、江戸幕府によって法制化される。
江戸時代において殺人事件の加害者は原則公権力が処罰することになっていた。
しかし、加害者が行方不明になり、公権力がこれを処罰できない場合には、被害者の関係者に処罰を委託する形式を取る仇討ちが認められた。
明治になり司法制度が整備され、1873年2月7日、政府は敵討禁止令を発布。 - 中門
-
泉岳寺には三門(総門・中門・山門)があったが現在は中門と山門のみ残る。
現在の中門は1836年に再建され、1932年に大修理。
「萬松山」の額は、中国明代の禅僧・為霖道霈(いりんどうはい)による書。 - 大石内蔵助良雄銅像
-
浪曲宗家・桃中軒雲右衛門の発願により鋳造。
所有が転々とした後、泉岳寺に寄進され、1921年12月14日に除幕。
大石内蔵助が当時の風俗である元禄羽織を身につけ、連判状を手にして東の空(江戸方面)をじっと睨んでいる姿を表す。 - 山門
-
1832年再建。
2階部分には十六羅漢が安置され、1階部分の天井には「江戸三龍」の一つ、銅彫大蟠龍(ばんりゅう)(=とぐろを巻いた龍)がはめ込まれている。
「泉岳寺」の額は、晋唐の墨跡研究者・大野約庵による書。 - 本堂
-
旧本堂は第二次世界大戦で焼失。
現本堂は1953年12月14日に落成した鎌倉様式建築。
本尊は釈迦如来、他に曹洞宗宗祖・道元禅師・瑩山禅師、また大石内蔵助の守本尊である摩利支天(秘仏)等が納められている。
本堂では坐禅・読経などの修行が行われる。
正面「獅子吼」の額は「ししく」と読み、御釈迦様の説法を指す。 - 澤木興道老師像
- 仏法の究極である坐禅をもって生涯を貫いた20世紀に最も活躍した禅僧の一人。
- 梵鐘・鐘楼堂
-
1913年に作られた鐘で、朝の坐禅と夕方の閉門時に撞く。
江戸から明治まで使われていた梵鐘は、現在ウィーンの国立民族博物館に所蔵。 - 主税(ちから)梅
- 大石主税が切腹した松平隠岐守三田屋敷に植えられていた梅。
- 瑤池梅
- 義士の墓守をした堀部妙海法尼が瑤泉院から賜った鉢植えの梅を移植したもの。
- 血染の梅・血染の石
- 浅野内匠頭が田村右京大夫邸の庭先で切腹した際に、その血がかかった梅と石。
- 首洗い井戸
- 義士が本懐成就後、吉良上野介の首をこの井戸水で洗い、主君の墓前に供え報告した。
- 義士墓所入口の門
- 浅野家の鉄砲洲上屋敷(現・聖路加病院)の裏門で明治時代に移築。
- 赤穂義士墓地
-
赤穂義士は1703年2月4日に切腹した後、この地に埋葬された。
ただし間新六の遺体は遺族が引き取った。
また寺坂吉右衛門は本懐成就後、瑶泉院などの関係者に討ち入りを報告して廻り、のち江戸に戻って自首したが赦され、麻布・曹渓寺で83歳の天寿を全うした。
現在も曹渓寺に眠っている。
泉岳寺にある間新六の供養墓は他の義士の墓と一緒に建立されたが、寺坂の墓は1868年6月に供養の為に建てられた。
また、いわゆる四十七士の他に、本人は討ち入りを熱望したものの周囲の反対に遭い討ち入り前に切腹した萱野三平の供養墓がある(1767年9月建立)。
したがって泉岳寺の墓碑は48ある。 - 赤穂義士記念館
- 討ち入り300年記念に建てられた資料館。
| 創建 | 1612年 |
|---|---|
| 宗派 | 曹洞宗 |
| 本尊 | 釈迦如来 |
| 開基 | 徳川家康 |
| 関三刹 | ||
|---|---|---|
| 大中寺 | 1154年 | 栃木県栃木市大平町西山田 |
| 總寧(そうねい)寺 | 1383年 | 千葉県市川市国府台 |
| 龍穏寺 | 1430年 | 埼玉県入間郡越生町 |
| 江戸三箇寺 | ||
|---|---|---|
| 総泉寺 | 976年 | 東京都板橋区小豆沢3-7-9 |
| 青松寺 | 1476年 | 東京都港区愛宕2-4-7 |
| 泉岳寺 | 1612年 | 東京都港区高輪2-11-1 |
- PIGMENT TOKYO
-
筆や顔料などの絵画材料専門店。
最寄駅は東京モノレール及びりんかい線の天王洲アイル駅。
店内はスマホでの撮影のみ可。

| 住所 |
東京都 品川区 東品川2-5-5 TERRADA Harbor Oneビル1F |
|---|---|
| 電話 | 03-5781-9550 |
| 営業時間 | 11h30~19h00 |
| 定休日 | 月曜日 |
| 支払 | 不明 |
| リンク | 公式サイト |
柴又
- 柴又帝釈天縁起
-
開創は今から390年程前の寛永年間。
開山は禅那院日忠上人。
当山には昔から日蓮聖人の親刻になる帝釈天の板本尊があると伝えられたが、中世その所在が不明となった。
しかし今から約240年前、当山第9代の享貞院日敬上人(こうていいんにちきょうしょうにん)の代に、本堂修理の際、棟の上より1枚の板本尊が発見された。
ときに安永8年(1779年)の春、庚申(かのえさる)の日であったという。
この本尊、庚申の日に出現したというので「庚申(こうしん)」を縁日と定めた。
日敬上人は、自らこの板本尊を背に負い、折しも天明の飢饉、疫病に遭った江戸の人達に拝ませて不思議なご利益を授けたという。
このご本尊の片面には法華経薬王品の「此の経はこれ閻浮提の人の病の良薬なり。
もし人、病有らんに、この経を聞くことを得ば、病即ち消滅して不老不死ならん」という経文が彫られている。
また、他の片面には、右手に剣を持ち、左手を開いた忿怒(いかり)の相(すがた)をあらわした帝釈天が彫刻されている。
これは、除病延寿の本尊、悪魔降伏の尊形である。
すなわち、仏の教えを信仰し、これに随順する者に対して、もし災難が降りかかるならば、仏法守護の神である帝釈天が必ず出現して、この悪魔を除き退散せしめるのである。
このようにして帝釈天の信仰は江戸市中に広まり、これが当時盛んであった「庚申待」の民間信仰と結びついて、「宵庚申」の参拝が行われるようになったのである。
東京がまだ「江戸」と呼ばれたころ、市中からおよそ3里(12km)の道程を宵をかけて参詣する風俗は江戸庶民の間に深く浸透して、今日の盛んな信仰へと受け継がれてきたのである。
- 寅さん記念館
-
葛飾柴又「帝釈天」の参道でくるまやという団子屋を営むおいちゃんとおばちゃん夫婦。
主人公の寅次郎には母親の違う妹がいる。
毎度フーテンを決め込む寅次郎がたまに故郷に帰ると、なぜか周りの人を巻き込んで騒動が持ち上がる。
という設定で始まった寅さんシリーズに欠かせなかったのが、寅さんを取り巻く心温かい隣人たちと人情豊かな下町の情緒だった。
山田洋次監督とスタッフは、ドラマの設定にピッタリの場所を求めて東京近郊のあらゆる候補地をロケハンした。
しかしイメージ通りの場所はなかなか見つからず、半ば諦めかけたある日やっと辿り着いたのが葛飾柴又だった。
東京の北東部、江戸川のほとりに位置する葛飾柴又は、水と緑の下町の風情溢れる街並みが調和した門前町。
参道の突き当りにあるのが江戸時代に創立された「帝釈天」。正式名称は経栄山題経寺といい、厄除け、延寿、商売繁盛等に霊験あらたかとのこと。
帝釈天の先にあるのが、大正末期から昭和の初期にかけて建てられた「山本亭」。
書院造の和室とモダンな洋間が調和した美しい邸宅。
緑あふれる典型的な書院庭園が訪れる人の目を楽しませてくれる。
裏手の江戸川堤防をやっと登り切ると出迎えてくれるのが川面を吹き抜ける爽やかな風。
このあたりは葛飾区が「柴又公園」として整備したエリア。
河川敷で野球に興じる子供たちの歓声の先に見えるのが「矢切の渡し」。
伊藤佐千夫の名作「野菊の墓」の一場面、二度と逢うことのない恋人たちが別れていった悲しみの舞台としても知られている。遥か対岸に広がる松戸市や市川市の丘陵地帯の眺望を楽しみながら流れをさかのぼれば、都内で唯一水郷の風情を味わえる「水元公園」がある。
そして知る人ぞ知る「柴又七福神」。
良観寺(宝袋尊)から観蔵寺(寿老人)までの7寺を、徒歩1時間足らずで一気に巡ることが出来る。
- 山本亭
-
この建物は、地元ゆかりの山本工場(カメラ部品製造)の創立者でる山本栄之助翁の自宅。
関東大震災後、当地に移り込み、以降4代にわたって使われていたものを、1988年に葛飾区が取得し、1991年4月から一般公開した。
建物は、1階400㎡、2階50㎡の木造瓦葺き2階建てで、地下室、土蔵、長屋門等も備え、1926年から1930年の間に数回にわたる増改築を重ね、現在の姿となる。
伝統的な書院造と洋風建築を複合した和洋折衷の建物と、純和風の庭園とが見事な調和を保っており、その文化財的価値は、国内外問わず高く評価されている。 - 居宅
-
和室6部屋のうち角部屋にあたる2部屋は、床の間、違い棚、明かり障子、欄間から成り立つ伝統的な書院造。
家全体を取り巻く廊下は、天井が数寄屋風で、自然光を意識した大きなガラス戸やガラス欄間で包まれている。
庭は、「花の間」の床柱を背にして眺めるのが一番素晴らしく見えるように設計されている。
すべての部屋も廊下を挟んで庭に面し、壁のほとんどない開放的な意匠を見せている。 - 主庭
-
縁先の近くには池泉を、背後には植え込みと築山を設けて滝を落とすという、典型的な書院庭園。
庭園の面積は約890㎡で、松、ツツジなど約400本の樹木が植えられている。
滝は、池の最も遠い部分にあたる入江奥に設けられ、庭園に奥行きの深さと心地良い滝の音を造り出している。 - 長屋門
-
瓦葺きの木造平屋で伝統的な長屋門の形態を踏襲しながらも、外観、内部とも意匠を洋風化している点が特徴。
通路の両側にある3畳ほどの袖部屋は、門番が常駐し、客人のお付きの人、人力車の車夫などが控えていたとされる。 - 鳳凰の間
-
邸内で唯一の洋間であり、昭和初期独特のデザイン。
白漆喰仕上げの高い天井や、寄木を用いたモザイク模様の床の他、大理石のマントルピース、ステンドグラスが見所。
玄関脇に洋間の空間を設けることは、斬新なスタイルだった。 - 土蔵
-
山本亭の中で最も古い建造物だが、残念ながら築造年は不明。
外壁は土を厚く塗った2階建ての大壁造りで、基礎は凝灰岩、下端部は石張り、上端部は白漆喰塗りで仕上げられている。
西新井
- 西新井大師
- 塩地蔵
-
この地蔵菩薩は、江戸時代以降いぼ取りに霊験あり。
堂内の塩を頂き、効果があれば倍量の塩をお返しする。 - 延命水洗地蔵尊
-
この地蔵尊を信仰すると10種の福徳が授かり特に延命長遠の徳がある。
弘法大師降誕1,200年記念に建立。 - 出世稲荷明神
-
五穀の神である倉稲魂神(うかのみたま)を祀る。
弘法大師が嵯峨天皇より東寺を賜った時、明神が翁の姿となって現れ救いを垂れられたので、東寺の鎮守として祀られた。
この社殿は弘法大師降誕1,200年記念に再建。 - 奥の院
-
高野山奥の院を関東に奉迎。
かつてこの御堂の前に井戸があり、関東の高野と称され、高野山の代拝所として江戸の昔より人気。 - 十三重宝塔
- 塔身にには弘法大師の御影を謹刻し内には中国唐代の密教僧恵果より受け継がれた仏舎利一粒が納められさらに空海ゆかりの聖地より白砂聖石を埋納した。
- 四国八十八箇所霊場
同行二人お砂踏み巡礼所 -
弘法大師のご利益と観音慈悲の功徳を同時に得られる札所。
基壇の周囲、石板の下には、四国霊場と高野山の霊砂が順に敷かれている。 - 礼拝尊像
-
十一面観世音菩薩像
四国八十八所大師像
高野山奥之院大師像
弘法大師父君母君像 - 礼拝の心得
-
心穏やかに保ち願いを込め南側正面より入場。
正面にて合掌礼拝
「南無大師遍照金剛(なむたいしへんじょうこんごう)」
を唱えながら左側から順に一周する。
前の方とは間隔を空け、一列にて歩く。
最後に正面で合掌礼拝して退場。 - 不動堂
-
本尊不動明王は、不動尊又は無動尊とも言い、大日如来が救い難いどうしようもない衆生に対し右手に剣を左手に羂索(けんさく)を持ち、大火焔を放ち憤怒の相に現じ一切煩悩を調伏し仏法を教える。
堂内には不動明王を中心に右に制吒迦(せいたか)童子(どうじ)、左に矜羯羅(こんがら)童子(どうじ)の二童子を祀る修行道場。 - 羂索
- 獲物を捕らえる縄の羂索で煩悩を捕らえ、剣で断ち切る。
- 制吒迦童子
-
不動明王の眷属であり脇侍。
八大童子の8番目。 - 矜羯羅童子
-
不動明王の眷属であり脇侍。
八大童子の7番目。 - 水子供養地蔵尊
-
地蔵菩薩は釈迦入滅後、弥勒菩薩出生までの間無仏の五濁悪世の救済を仏より委ねられ、様々に姿を変え六道を化導し、三途の川の賽の河原に在っても子供達の迷いを除き救う。
供養となる五輪塔婆を献ずることは地蔵菩薩建立の意味を成し、大慈悲の功徳によって精霊を擁護し安らか成らしめる。 - 大日如来尊像
-
密教の教主にて梵名を摩訶昆盧遮那(まかびるしゃな)と言う。
摩訶は大の義、毘盧舎那は日の別名なので大日と訳す。
宇宙に遍照する理智の法身体として尊ばれているこの大日如来尊は、修験道に名高い出羽三山の一つの湯殿山の大日如来を勧請したもので1818年から1830年の建立。 - 三匝堂(さんそうどう)/栄螺堂(さざえどう)
-
この堂は一見三重塔に見えるが、江戸時代に流行した三匝堂で、俗に栄螺堂と言われる仏堂の一形式。
江戸中期本所の羅漢寺に建てられたものをはじめとして、関東以北の寺院に相当建てられたらしいが、今に残る遺構は非常に少ない。
都内では1884年改築のこの堂のみで貴重。
堂内部には、初層に本尊の阿弥陀如来と八十八祖像、二層に十三仏、三層に五智如来と二十五菩薩を祀っている。
現在は本尊が新本堂に移されている。
昔は、ここに参れば同時に諸国の霊場、諸仏を巡拝したのと同じ御利益があるとされ、サザエの殻のような堂内を巡拝した。

中野
- 中野ブロードウェイ
-
1966年に開業した日本初のショッピングセンターと集合住宅の集合体建築。
元々の敷地は、木造家屋が密集する地域だった。
1958年に中野サンモール商店街が完成すると、アーケードの行き止まりに当たるこの地区一体を買い上げ、早稲田通りに通り抜けができるビル建設計画が挙がった。
この早稲田通りへ抜けるビル1回部分の広い通路を「ブロードウェイ」と呼ぶ。
デベロッパー(promoteur immobilier)は地域住民の反対(opposition)等を乗り越えて開業。
ビル1階を直進する通路は、宮田家具の買収失敗で叶わず。 - 容積率
coefficient d'occupation du sol=COS -
新建築基準法(la nouvelle loi des normes de construction)
1965年施行(中野駅周辺は1968年から適用)
高さ31mまでで容積率737%
それまでの建築基準法では、高さ制限無しで容積率600%
旧法の方が137%も得。
そこで、旧法が適用される間に建物を企画し、高さを法定の31mに抑える反面、許容される容積率ギリギリに床面積を増やすため、天井を低くして階層を増やし、廊下を少なくして分譲可能床面積を増やし、投下資本回収に努めた。
地下1階から地上4階までは商業施設、5階から10階は住宅。 - 建蔽率
coefficient d'emprise au sol -
本館は敷地いっぱいに建っている。
別館の仲店商店街側にタワー式駐車場のデッドスペース(現在は駐輪場)を活用することで、本館別館合わせて建蔽率の規制をクリアした。 -
ブロードウェイは店舗スペースを分譲(lotissement)してる。
店舗スペースは個々のオーナーによって自由に売却や賃貸され、大手不動産会社でなはく、地元の小規模な不動産屋を仲介する。
よって、まとまった店舗スペースの確保が難しい。
故にまんだらけの店舗が飛地状態。
また、狭いスペースの物件が多く築年数も40年以上経っているため、中野駅前という好立地にもかかわらず賃料が安い。
このため、小規模起業家も出店しやすく、個性的な店舗が増えた。
- 明屋書店
HARUYA BOOK STORES -
愛媛県松山市に本社を置く1950年創業の書店。
ここ中野ブロードウェイ店は、ONE PIECEやHUNTER×HUNTER等の人気コミックの第1巻を新品で取り扱っている数少ない書店の一つ。
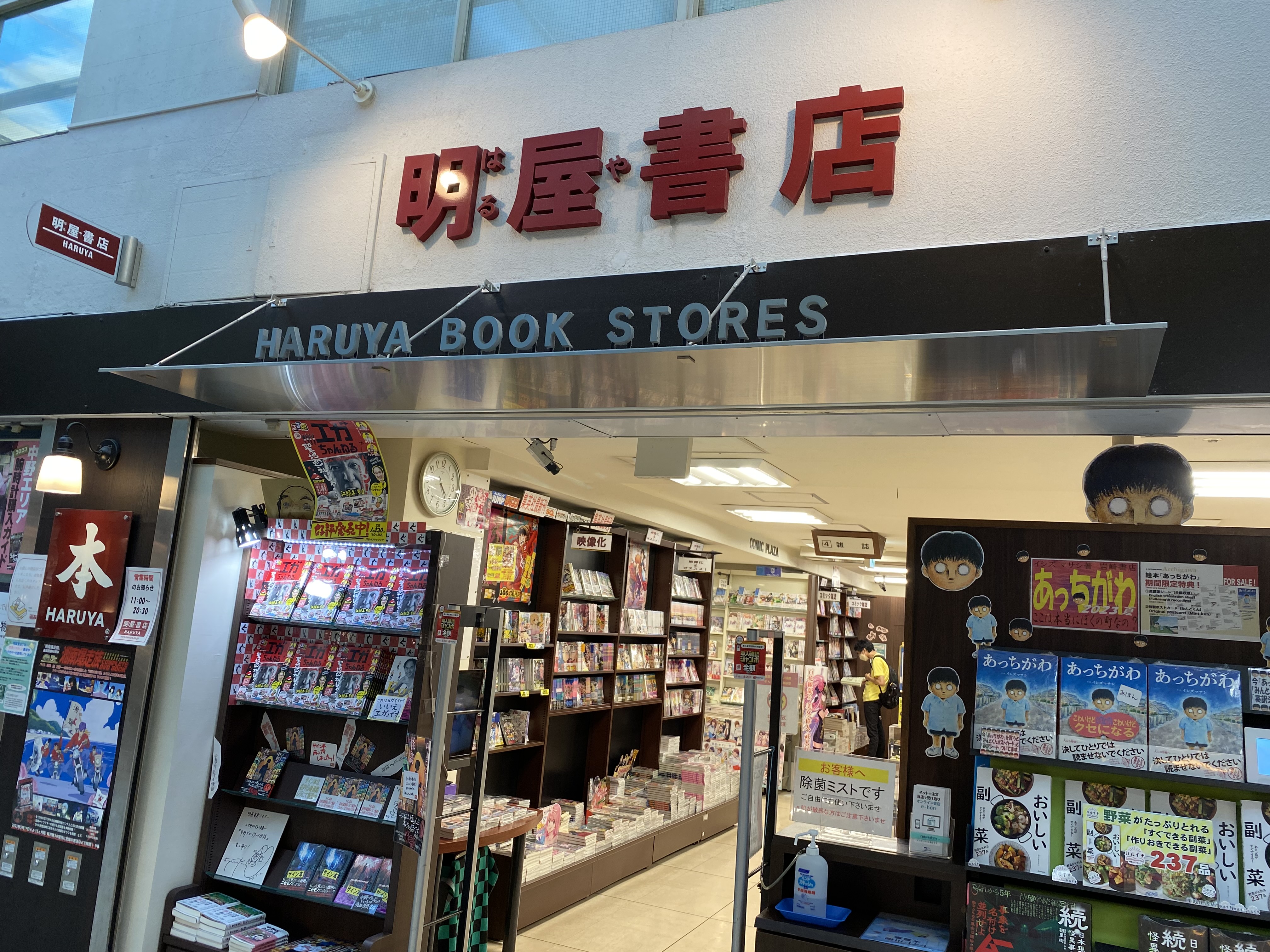
| 住所 |
東京都 中野区 中野5-52-15 中野ブロードウェイ3F |
|---|---|
| 電話 | 03-3387-8451 |
| 営業時間 | 11h00~20h30 |
| 定休日 | 無休 |
| 支払 | 現金、カード、他 |
| リンク | 公式サイト |
世田谷
- 豪徳寺
- 創建…1480年
- 本尊…釈迦如来
- 宗派…曹洞宗
- 開基…吉良政忠
-
前身は1480年世田谷城主吉良政忠建立の弘徳院。
弘徳院は政忠の伯母の庵(petite maison)
1633年彦根藩主井伊直孝が猫により門内に招き入れられ、雷雨を避けたことから、豪徳寺とし井伊家菩提寺となる。 - 山門
-
扁額「碧雲関」
外界と境内を隔てる門 - 三重塔
-
2006年落慶。
高さ22.5m
十二支が対応する方角に彫られており、猫はネズミと仲良く描かれている。
釈迦如来像・迦葉尊者像・阿難尊者像・招福猫児観音像を安置。 - 仏殿
- 1677年建立
- 招福猫児
-
豪徳寺の招福猫児は小判を持たず右手を上げている。
招福猫児は人を招いて「縁」をもたらす。
La relation humaine
福そのものを与えるわけではない。
人との大切な「縁」を活かせるかどうかは、その人次第。
報恩感謝の気持ちがあれば、自然とその人のもとに福が訪れるという教えから、小判を持たず右手だけ上げている。 - 招福殿
-
1941年建立、2022年改修。
堂内には招福観音菩薩立像を安置。
家内安全、商売繁盛、開運招福 - 納骨堂
le columbarium -
1937年建立
中2階…1人用一般納骨壇
1階…弥勒菩薩像を中心に2人用一般納骨壇
B1階…聖観世音菩薩坐像と2人用一般納骨壇と永代供養壇 - 開祖堂
-
1999年落慶
宗関大和尚椅像(開山)、秀道大和尚椅像(中興開山四世)、承陽大師(道元)椅像、常済大師(瑩山)椅像、聖徳太子椅像、そして歴代住職、藩主の位牌を安置。 - 法堂
-
1967年造営
聖観世音菩薩立像、文殊菩薩坐像、普賢菩薩座像、地蔵菩薩立像を安置。
寺宝の「井伊直弼肖像画(井伊直安作,直弼の息子)」が飾られている。 - 梵鐘
-
1697年鋳造。
区内最古。 - 地蔵堂
-
2020年落慶
地蔵菩薩半跏像を安置。
※土日祝日、正月三が日、お彼岸、お盆に開放。
| 篆額「弎世佛」 | ||
|---|---|---|
| 過去 | 現在 | 未来 |
| 阿弥陀如来像 | 釈迦如来像 | 弥勒菩薩像 |
- 世田谷八幡宮
- 応神天皇(第15代/4世紀後半)
- 仲哀天皇(第14代/応神天皇の父)
- 神功皇后(応神天皇の母/仲哀天皇の后)
-
後三年の役(1087~1094)、源義家が奥州を平定し戦地からの帰途、ここ世田谷にて豪雨に遭い数日滞在を余儀なくされた。
もとより敬神の念厚い義家は武運の神としても知られる八幡大神のご加護に感謝し、宇佐八幡宮の分霊をこの地に招き、地域民に信仰を説いた。
その時武士たちに奉祝相撲を取らせた為、現在でも奉納相撲(9月)が行われている。
1964年5月社殿改築。 - 高良(こうら)神社
-
御祭神…高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)
境内、氏子地域に散祀されていた天祖神社、高良神社、金比羅神社、六所神社、北野神社、御嶽神社、日御碕神社、稲荷神社を1912年に整理合祀された神社。 - 世田谷招魂神社
-
御祭神…日露戦争、太平洋戦争の戦没者(世田谷区域)
世田谷1丁目にあった乃木神社(乃木将軍の甥玉木正之建立)の社殿を玉木氏により譲り受け、旧軍人山の場所に世田谷招魂神社として氏子内および代田1丁目、弦巻町、経堂町の戦没者を1958年に御祀りした。
- 九品仏浄真寺
- 創建…1678年
- 本尊…釈迦如来
- 開基…珂碩(かせき)
- 宗派…浄土宗
-
6:00開門
事務所・御朱印受付は9:00頃から
全ての堂宇、仏像が写真撮影可能
九品仏浄真寺公式HP参照
さぎ草は7月下旬から8月上旬
紅葉は11月下旬から12月上旬 - 閻魔堂
-
閻魔大王は亡者の罪を裁く王。
三途の川(le fleuve des trois chemins)の辺りにいる奪衣婆(une vieille femme)が死者の衣服を剥ぎ取る。
Elle arrache des vêtements aux morts.
次に懸衣翁(un vieil homme)が衣服を木に懸け、死者の生前の罪の重さを計る。
Il pèse leurs vêtements.
三途とは餓鬼道・畜生道・地獄道を指す。 - 三仏堂
-
- 上…le bien
- 中…la moyenne
- 下…le mal
各堂の中央に上生佛、右が中生佛、左が下生佛。
上品は生まれながらの善(le bien naturel)
下品は生まれながらの悪(le mal naturel)
九品阿弥陀佛像の大修繕を行なっており、九躯とも完成するのは2034年予定。 - 殺生を行わない
- 経典を読む
- 六念処(6つの法)を修行する
- 龍護殿
-
本尊釈迦如来像を祀る。
龍護殿が此岸、向かい合う三仏堂が彼岸で極楽浄土を表す。 - 五劫思惟(ごこうしゆい)像
-
龍護殿内向かって左側の脇壇に祀る。
五劫とは時間の単位(une unité de temps)で、とてつもなく長い時間の意。
一劫=43億2千万年(4 milliards 320 millions ans)
五劫は5倍の215億4千万年(21 milliards 540 millions ans)
法蔵菩薩が五劫もの間、衆生を救うことを考え続けていた為、髪が伸びた状態になった。
法蔵菩薩は48の誓願をたて、総てが成就しなければ決して佛にならないと誓い、今から十劫の昔に阿弥陀佛となった。
つまり、430億2千万年(43 milliards 20 millions ans)前に48の誓願を総て成就した。 - 賓頭盧尊者
- 賓頭盧尊者は、撫でると除病の功徳がある。
- 二十五菩薩来迎会
おめんかぶり -
念仏行者の臨終に阿弥陀如来が二十五の菩薩を従えて西方極楽浄土よりご来迎になるという、浄土の教えを具現化した行事で、当日は三仏堂(上品堂)から龍護殿(本堂)へ懸橋がかかり、その橋を信者の方々が菩薩のお面を被って行道する儀式。
4年に1度の5月5日に執り行われる。
次回は2028年5月5日。
| 三品 | 九品 | 解説 |
|---|---|---|
| 上品 | 大乗 | |
| 上品上生 |
|
|
| 上品中生 |
経典を読まなくても大乗を理解し、因果律(le principe de causalité)を信じ、大乗を誹謗しない者。 7日後に往生できる。 |
|
| 上品下生 |
経典を読まなくても大乗を誹謗しない者。 7日後に往生できる。 |
|
- 野毛大塚古墳
-
野毛大塚古墳は全長28m、後円部の高さ10mの帆立貝式の前方後円墳で、前方部に近接して小さな造出部が付設されている。
墳丘の周囲には馬蹄形の周濠が掘られており、周濠を含めた全長は104mである。
三段に構築された墳丘は全体が河原石で覆われ、円筒埴輪がそれぞれの段に巡らされている。
後円部頂上には四基の埋葬施設があり、中央に粘土に包まれた割竹形木棺、南東側に箱式石棺、北西側に二基の箱形木棺が納められている。- 割竹形木棺…甲冑、刀剣、鉄鏃(てつぞく)等の武器・武具類、鉄鎌、銅鏡、銅釧、玉類、石製模造品、竪櫛等
- 箱式石棺…刀剣、鉄鏃、玉類、石製模造品等
- 二基の箱形木棺…刀剣、鉄鏃、鉄鎌、石製模造品、玉類等
野毛大塚古墳は関東地方の中期古墳文化を代表する5世紀前半に築造された古墳。
出土した多量の武器・武具類や石製模造品は、この古墳が南武蔵野有力な首長墓であることを示している。
城東
江戸川
- ひらい圓蔵亭
-
落語家八代目橘家圓蔵(1934~2015)師匠の住居。
1982年に八代目橘家圓蔵を襲名。
落語…Un spectacle littéraire japonais humoristique
襲名…hériter le nom de son maître
江戸川区平井3-21-24
月曜休館
13h30~17h00
入場無料
- 平井浅間神社
逆井の富士塚 -
確かではないが、1488年創建。
江戸川区内最大最古の富士塚で「逆井の富士塚」
富士塚は富士講に由来し、主として富士登山が困難な人々の為に江戸とその周辺地域に築かれた人口のミニュチュア富士。
富士塚は東京23区内に73箇所ある。
- 亀戸天神
- 侘助椿
-
椿は古くから日本人に愛され「万葉集」や「日本書紀」にその歌や記録を見ることができる。
また、茶花として親しまれ、中でも侘助椿は茶人の千利休が茶室に飾る花として特に好んだと伝えられている。
名前の由来には諸説があるが、利休に仕えていた侘助という者が愛でていた花がありそれが利休の目に留まり、その名に因んでワビスケと名付けられたという説や、侘数寄(ワビスキ)から転訛した名前であるとも言われている。
「わび」や「さび」といった日本の美意識を象徴する存在で、その花の清楚な美しさは見るものの心を静め「花の天神様」として親しまれる亀戸天神の境内に彩を添えている。
当社の創建から今日に至るまで、祭礼を中心に神社を支えてきた亀戸天神社社属神輿総代「竪川睦(たてかわむつ)」より奉納。 - 御神牛
-
菅原道真(845~903)は「乙丑の年」生まれ。
太宰府で亡くなった際、遺体を引く黒牛が臥して動かなくなり、これは道真公の御心による事としてその場を墓所と定め、社殿が建立されたのが太宰府天満宮。
また、道真公が京都から太宰府へ下向の途中、白牛によって危難から救われたという故事も伝えられている。
この神牛像は1961年、御鎮座三百年祭の社殿復興と共に奉納。
大田区
- 池上本門寺
-
鎌倉時代の僧日蓮(1222~1282)は、9年間住み慣れた未延山(山梨)から病気療養の為、常陸(茨城)の湯に向かわれ、途中の武蔵国池上の郷主・池上宗仲公の館で亡くなった。
正式名称「長栄山大国院本門寺」は、法華経の道場として長く栄えるようにという祈りを込めて日蓮が名付けた。
大檀越(grand sponsor)で武士の池上宗仲(むねなか)公は、館や周辺の土地を寺に寄進し、池上本門寺となる。
法華経の文字数69,384に合わせ、69,384坪を寄進。
1坪=3.3㎡なので、69,384坪=230,000㎡=23ha
日蓮入滅が1282年10月13日の為、毎年10月11日〜13日の3日間は、日蓮聖人を偲ぶ「お会式法要」が執り行われる。 - 池上本門寺の石段
-
加藤清正(1562~1611)の寄進によって造営。
法華経宝塔品の偈文96文字にちなんで96段ある。
別名「此経難持坂(しきょうなんじさか)」
元禄(1688~1704)に改修されているが、造営当時の祖型を残している貴重な石造遺構。
清正は1606年に祖師堂を寄進建立し、寺域を整備しているので、この石段も同時期の所産と思われる。 - 日蓮大聖人説法像
-
日蓮入滅後700年の1983年に奉納された彫刻家・北村西望(せいぼう)先生の作品。
材質は純アルミ、高さ3.4m、重量1トン。 - 五重塔
-
江戸幕府2代将軍徳川秀忠公が1607年に寄進建立。
関東に現存する最古の五重塔。
1701年に大修理。
1997~2001年に日蓮聖人立教開宗750周年慶讃記念事業の一つとして解体修理が施された。
毎年4月第1土日に開帳。 - 大堂(祖師堂)
- 鉄筋コンクリート造
- 本瓦葺
- 入母屋屋根
- 間口十八間(33m)
- 奥行十九間半(35m)
- 奥行十九間半(35m)
- 高さ九十三尺(30m)
- 屋根瓦枚数69,849枚
- 延床面積八百二十坪(2,710㎡)
-
空襲で焼失後、1964年に鉄筋コンクリート造で再建。
内陣中央に日蓮大聖人像。
向かって左に日朗聖人像、右に日輪聖人像を祀る。
日蓮の弟子の一人が日朗で、日朗の弟子の一人が日輪。 - 日蓮大聖人御尊像
-
日蓮大聖人第7回忌に当たる1288年に造立。
像高二尺八寸三分(60m)の木造寄木造。
ご胎内には御聖骨を納めた銅筒があり、右手には母君妙蓮尼の遺髪を加えて作られた拂子(※ほっす)を、左手には紺紙金泥の法華経経巻を捧持。 - ※拂子(払子)
- 僧侶が虫や埃を祓う道具。
仏教では不殺生戒がある為。 - 井桁に橘
-
日蓮宗の宗紋。
橘は日本原産唯一の柑橘類。
元々は元明天皇が「橘は果実の中で最も尊い。故に橘姓を名乗り、橘を家紋とする」と命じたことが起源。 - 奉安塔
-
1945年4月15日の空襲によりほとんどの建物を焼失した。
しかし、戦後直ちに復興事業に着手。
まず最初に日蓮大聖人御尊像と御真骨を格護する為の奉安塔が1954年4月に完成。
奉安塔は防火防災の為、鉄筋コンクリート造銅板葺きで、当初は仮祖師堂の背後(現在の大道内陣辺り)に位置したが、1962年に着工した大堂再建を機に現在地へ移された。
1964年に大堂が完成。 - 経蔵
-
方三間裳階(もこし)付き、宝形造、銅板瓦棒葺、輪蔵形式。
経蔵内に、心柱を軸に回転する八角形の書架(輪蔵)があり、かつては一切経(区指定文化財)が収められていた。
経蔵内部の柱等には、工事に関係した職人をはじめ、講名や氏名、住所等が刻まれ、経蔵建立時の寄進者が広範囲に及んだことが伺える。
『新編武蔵風土記稿』によれば、1784年の再建。
1971年境内整備により現在地へ移築されたが、江戸期の輪蔵形式の経蔵は都内でも残存例が少なく貴重。 - 日朗聖人墓塔
-
安山岩製。
石造宝塔。
高さ160cm(失われた反花座を補うと推定190cm)。
池上本門寺二世日朗の墓塔であり、塔身正面に一塔両尊(中央に題目、その左右に釈迦如来と多宝如来)を刻み、基礎部背面には日朗聖人の没年(元応二年・1320)や造立願主の名等が刻まれている。
表面の剥離や損傷の為、銘文は判読しにくいが、塔の型式から、室町時代(15世紀中頃)に造立されたと推定。
この型式の宝塔は、当時南関東の日蓮宗寺院において多く造立されているが、その中でも特に大きい。 - 御廟所
-
中央に「日蓮大聖人御廟」
向かって左に「第二祖日朗聖人御廟」
向かって右に「第三世日輪聖人御廟」 - 日蓮大聖人(1222~1282)
-
鎌倉時代の人。
当山御開山。
釈尊の信の教えである法華経を受持することによる国土安穏を説き、お題目(南無妙法蓮華経)への信仰を広めた。
1282年10月13日に池上で御入滅。 - 大国阿闍梨日朗聖人(1245~1320)
-
鎌倉時代の人。
当山第二祖。
日蓮大聖人の高弟である六老僧の一人。
「師孝第一」と称されるほど常に大聖人の側に仕えて活動。
大聖人御在世中より幕府の政都である鎌倉での布教を任され、比企谷妙本寺と当山を拠点に日蓮門下の中心として活躍。 - 大経阿闍梨日輪聖人(1272~1359)
-
鎌倉・南北朝時代の人。
当山第三祖。
日朗聖人の高弟である九老僧の一人。
日朗聖人の後継者に指名され鎌倉を拠点に門下の中心として布教活動を行うとともに、京都に進出した兄弟子の日像聖人を鎌倉より支援して日蓮教団発展に尽力。 - 「未完の龍」の由来
-
日本画家 牧進
私は、川端龍子先生の最後の書生として15年間川端家に寄居し、指導を受け、師の気迫に満ちた生き様を最期まで見続けた者である。
師龍子は、「自分は龍の落とし子であって、龍子は自分の生んだ芸術の戸籍なのだ」と雅号の由来を自叙伝に記しているが、ここぞという時には決まって龍を描いた。
龍子はこの天井画の制作に入る時、既に足腰の衰えが目立ち、大きな動きには体がついてゆけず、周囲の者が支えての制作であったが、龍子芸術みなぎる絵を仕上げようという意気込みにはいささかの衰えもなく、凄まじくも壮絶な時間が流れたのであるが、仕上がらぬまま残されたのである。
この未完の作品御奉納の仔細について、師の三女紀美子氏が語るところによると、関係者一同思案の末、親交の深かった日本画の大家奥村土牛先生のご意見を仰ぐこととなった。
そして奥村土牛先生より「未完成ですが、ここに描かれし龍はまさしく龍子先生の作そのものであり、力強く次の画面に続かんとの意思を感じさせるに十分です。立派な作品として後世に残ります」というお言葉を頂戴した。
その心強いお言葉に「どうか先生のお手でこの龍を生かしてください」と紀美子氏は懇願し、土牛先生の点睛によって、龍は命を得たのである。

日本の高層建築
| 建物名 | 高さ | 竣工 | 所在 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京スカイツリー | 634m +29 -1 |
2012年 | 東京 | 世界一高い塔 |
| 2 | Torch Tower | 390m +63 -4 |
2028年 | 東京 | 日本一高いビル(予定) |
| 3 | 東京タワー | 333m +16 -2 |
1958年 | 東京 | |
| 4 | 麻布台ヒルズ森JPタワー | 325m +64 -5 |
2023年 | 東京 | 日本一高いビル(現在) |
| 5 | 明石海峡大橋(※) | 298m | 1992年 | 兵庫 | 全長3,911m |
| 6 | あべのハルカス | 300m +60 -5 |
2014年 | 大阪 | 西日本一高いビル |
| 7 | 横浜ランドマークタワー | 296m +70 -3 |
1993年 | 神奈川 | |
| 8 | SiSりんくうタワー | 256.1m +56 -2 |
1996年 | 大阪 | |
| 9 | 大阪府咲洲庁舎 | 256m +55 -3 |
1995年 | 大阪 | |
| 10 | 虎ノ門ヒルズ 森タワー |
255m +52 -5 |
2014年 | 東京 | |
| 11 | ミッドタウン・タワー | 248m +54 -5 |
2007年 | 東京 | |
| 12 | ミッドランドスクエア | 247m +47 -6 |
2006年 | 愛知 | 中部地方一高いビル |
| 13 | JRセントラルタワーズ オフィスタワー |
245m +51 -4 |
1999年 | 愛知 | |
| 14 | 東京都庁 第一本庁舎 |
243m +48 -3 |
1990年 | 東京 | |
| 15 | NTTドコモ代々木ビル | 240m +27 -3 |
2000年 | 東京 | |
| 16 | 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー |
240m +45 -4 |
2022年 | 東京 | |
| 17 | サンシャイン60 | 239.7m +60 -4 |
1978年 | 東京 | |
| 18 | 六本木ヒルズ森タワー | 238m +54 -6 |
2003年 | 東京 | |
| 19 | 新宿パークタワー | 235m +52 -5 |
1994年 | 東京 | |
| 20 | 東京オペラシティ | 234m +54 -4 |
1996年 | 東京 |
※日本一長い橋は東京湾アクアブリッジで全長4,425m
明石海峡大橋は第2位で、吊り橋としては世界最長
第3位は岩手県の第一北上川橋梁で、3,868m
展望台
- 文京シビックセンター
-
真南方面以外を網羅。
南東に東京ドームシティ
東にスカイツリー
南西に小石川後楽園
東京ドームは真南に位置している為、屋根の端しか見えない。

| 住所 | 文京区春日1-16-21 |
|---|---|
| 開館時間 | 9:00~20:30 |
| 階層 | 25階 |
| 高さ | 105m |
| 料金 | 無料 |
| 休館 | 12/29~1/3 5月第3日曜日 |
| 最寄駅 | 1.春日 2.後楽園 3.水道橋 |
- カレッタ汐留SKY VIEW
-
B2Fから46Fまで直通エレベーターがかなり速い
ビルから旧築地市場及びお台場方面を少し観れる程度
46階からさらに1階上がった47階にも行けるが、景色は良くない
| 住所 | 港区東新橋1-8-2 |
|---|---|
| 開館時間 | 11:00~23:00 |
| 階層 | 46階 |
| 高さ | 200m |
| 料金 | 無料 |
| 休館 | 無休 |
| 最寄駅 | 1.汐留 2.新橋 |
荻窪
- 荻窪白山神社
- 創建…1470年
- 祭神…伊邪那美命(イザナミノミコト)
- 御利益…縁結び、安産、子育て、家内安全、一族繁栄
-
1470年頃、関東管領上杉顕定(あきさだ)の家臣中田加賀守が、屋敷内に五社権現社を奉斎し、社殿を建てた。
荻窪白山神社は地域の氏神様としてだけでなく、歯の神様としても有名。
ある時、中田加賀守の弟兵庫が激しい歯痛に悩んでいると、白山の神様が夢に現れ「境内の萩を箸として食事をするように」という御信託をなさった。
兵庫がお告げに従うと歯痛が止んだ。
この事情を聞いた近隣の人々は、歯痛の治る神様としても信仰し、参拝者も増えた。
1909年の古記録に、神前に供えられた萩の箸が山となっている様子が記されている他、1967年の環状8号線拡張に伴い、社殿の造営を行なった折には、古い社殿の長押から納められた萩の箸が山のように出てきた。
この社殿造営時に新調された大太鼓(直径149cm)は、当時府中の大國魂神社の太鼓に次ぐ都内第二の大きさだった。 - 境内末社
- 正一位稲荷神社
- 田守稲荷神社
- 三峯神社
-
神楽殿の裏には、中田加賀守の屋敷から遷された「正一位稲荷神社」をはじめ、下荻窪村の祈りの祠だった「田守稲荷神社」、昭和期に荻窪住民に懇願され勧請した「三峯神社」の3社が祀られている。
現在の境内末社は2004年に移築改修。
境内末社の奥に氏子から預かったお稲荷さまを狐霊保安庫にて祀る。 - 屋根の十二支と猫の石像
-
社殿や社務所は1967年に老朽化と環状八号線拡張工事の折に建て替え。
その際、瓦屋の手により、社務所の四方を守護するように十二支の瓦が奉納設置された。
十二支を決める話には諸説がるが、一般的には猫は鼠に十二支を決める日を誤って伝えられ寝過ごしてしまい、十二支に入る事が出来なかったと言われる。
そんなお話を知っていた神主が「仲間外れは可哀想」と、のんびり眠る猫の石像を参拝者の方の和みになるように境内に置き、仲間に入れてあげた。
2011年の東日本大震災で社務所の瓦は全て落ちてしまい、残念ながら十二支の瓦も全て破損してしまった。
しかし、地面に近い位置に居た石の猫は何事も無かったかのように残った。
参拝者の心を和ませ、癒しになればと、それから一つずつ石の猫は増えていった。
今では境内のあちこちに石の猫が見られるようになり、参拝者の心を和ませている。
- 大田区黒公園
-
大田黒元雄氏の屋敷跡を杉並区が日本庭園として整備し、1981年10月1日に開園。
園内には氏の仕事部屋であった記念館や蔵を保存。
この記念館は、1933年に建築されたもので、当時のものとしては珍しい構造と意匠をもった西洋風の建築物。
大田黒氏は、47有余年にわたりこの部屋で音楽活動を続けた。
室内には、生前氏が使用したピアノや蓄音機などが残されている。 - 大田黒元雄(1893~1979)
-
音楽評論家。
NHKラジオの人気番組「話の泉」(1946~1964)の解答者として活躍。
19歳の時、ロンドン大学に留学。
著作「バッハよりシェーンベルヒ」の中で日本に初めてドビュッシー(Debussy)やストラヴィンスキー(Stravinsky)の名を紹介した他、60有余年にわたって日本の音楽の育成に貢献した。
- 荻窪八幡神社
- 創建…9世紀末
- 祭神…第15代応神天皇
- 御利益…学問、家業、延命長寿、出世
-
旧上荻窪村の鎮守で、今から約1,100年前の寛平年間(889~898年)に、応神天皇を祭神として創立。
1051年、源頼義が奥州の安倍貞任(あべのさだとう)征伐の途中、ここに宿陣して戦勝を祈願し、1062年の凱旋の時、神恩に感謝して当社を祭った。
また、1477年4月、江戸城主太田道灌は、上杉定政の命をうけ石神井城主豊島泰経(としまやすつね)を攻めるにあたり、源氏の故事にならってこの神社に武運を祈願し、この時、槇(コウヤマキ)の樹1株を植えた。
この樹は「道灌槇」とも呼ばれ、500年以上の歳月が経過した現在も御神木として大切に保護されている。
元は一根二幹だったが、1934年の暴風雨で一幹折損。
1986年には、杉並区の天然記念物に指定。
なお、当社には、1294年、1388年、1422年銘の板碑や狛犬等石造物、社宝の勝海舟の大幟などがある。
勝海舟の大幟は、2016年に杉並区の有形文化財に指定。 - 江戸・東京の農業 クリの豊多摩早生
-
東京はかつて、クリの大産地だった。
大正から昭和の初期にかけて、主に北多摩の農村地帯では、雑木林にまじって広大なクリ園が、果てしなく続いていた。
このクリは、当八幡神社の近くに住む市川喜兵衛が1887年頃、栽培中の茶園内に自生のクリ苗を発見、偶然早く稔る早生の栗ができた事から、1908年、当時の郡名にちなんで「豊多摩早生」と命名。
小粒で収量はあまり多くないが、秋まで待たずに、8月中旬から下旬には収穫できるので市場では高値で取り引きされ、全国的にも有名となり各地で栽培された。
特に第二次世界大戦後、クリに大被害を与えた害虫クリタマバチに強い抵抗性をもっている豊多摩早生は、品種改良の一方の親として用いられ、伊吹(農林省果樹試験場で、銀寄に豊多摩早生を交配)という優良品種を生み出した。
吉祥寺
- La phase 1
-
1657年の明暦の大火で文京区本郷の諏訪山吉祥寺焼失。
江戸幕府は同地を大名屋敷として再建。
吉祥寺門前の住民は居住地と農地を失ったが、幕府は希望者に代地や家屋の建築費用を与え、現在の武蔵野市東部へ移住。
元の吉祥寺に愛着を持っていた住民らが吉祥寺村と命名。
因みに諏訪山吉祥寺は本郷から本駒込へ移転。 - La phase 2
-
1923年の関東大震災後も多くの人が吉祥寺に移住し人口急増。
翌1924年、成蹊学園が池袋から移転し、農村→住宅街→多く商店や学生で賑わう街へと変貌。
現在も成蹊大学、東京女子大学、立教女学院、武蔵野大学、国際基督教大学、亜細亜大学、ルーテル学院大学等があり、高田馬場、お茶の水、下北沢と並ぶ都内有数の学生街。 - La phase 3
-
更に、1931年に歌舞伎劇団の「前進座」が根を下ろし、演劇の街の側面もある。
また、付近に漫画家が多く住んでおり、吉祥寺を舞台とする漫画作品も多い。
アニメーション制作会社やゲームソフトメーカーも多く、吉祥寺駅前を中心にアニメ舞台のロケ地となることも多い。
- 井の頭恩賜公園
-
1917年5月1日開園。
43ha(430,000㎡)の敷地に4ha(43,000㎡)の井の頭池を擁する都立公園。
東京23区を横断する24.6kmの一級河川神田川の水源。
西東京の山に降った雨が地下水となり、東京湾へ向かう途中にあり、井の頭池とその周辺は土地が窪んでおり、地下水が湧き出る。
井の頭池を縁取るように植えられているソメイヨシノが見事。 - お茶の水
-
井の頭池は豊富な湧き水に恵まれ、かつては三宝寺池、善福寺池とともに「武蔵野三代湧水池」と呼ばれた。
徳川家康がこの池の湧水を関東随一の名水とほめてお茶を入れたという伝説から「お茶の水」という名が付いたとも言われている。
現在では湧水減少のため、地下水をポンプで汲み上げている。 - 井の頭弁財天
-
10世紀に創建され、1652年に寺院となった。
本尊の弁財天像は789年、最澄による作。
井の頭弁財天が池でボートを漕ぐカップルに嫉妬する為、カップルで井の頭池ボートに乗ると別れるという伝説が産まれた。
Elle est jalouse du couple qui monte dans un canot. - 鎮魂供養碑と聖観世音菩薩
- 人間が生きるために犠牲にした動植物への鎮魂の碑と像
- 帰五薀皆空
ごうんかいくう -
人間界の現象や存在は全て実体が無く空である。
五蘊は、人間の心身と環境を構成する物質的・精神的な5つの要素。- 色しき(物体)…Le corps
- 受じゅ(感覚)…Le sens
- 想そう(表象)…La représentation
- 行ぎょう(意志)…La volonté
- 識しき(認識)…La conscience
- 宇賀神像移設改修
-
「我こそ弁天の化身だ」と申して池に入水し白蛇になった松原の3枚鱗(3 écailles)が首にある娘を偲んで(consoler)供養のために作られた像。
宇賀神は、人頭蛇身で蜷局を巻いた姿。
蛇神や龍神の化身とされることもある。
仏教の神(天)である弁財天と習合し、同一神は宇賀弁財天とも呼ばれる。
江戸東京たてもの園
江戸東京たてもの園の展示高尾
- 高尾山
-
東京都八王子市高尾町。
真言宗智山派大本山高尾山薬王院有喜寺の修験道の霊場。
真言密教の聖地の一つ。
京都高雄山神護寺に見立てられる。
江戸時代に幕府直轄領となり、その後も国有林として山林保護政策によって保護。
1,300種以上の植物、100種以上の野鳥、5,000種以上の昆虫が生息。
年間登山者数3,000,000人(世界一)。 - 歴史
-
744年 聖武天皇の勅令により東国鎮護の為に僧行基が開山。
1923年 関東大震災により標高が601mから600mへ。
1927年 ケーブルカー開業。日本百景選定。
1967年 「明治の森高尾国定公園」に指定。
1972年 標高が599mになる。八王子市役所は登山客に土入り袋を持たせ、山頂に積み上げ、標高を600mに戻す案が出るも、実現せず。
2007年 ミシュラン三ツ星の観光地へ。
明治以降、高尾山薬王院参拝客に振る舞われたとろろそばが名物。 - 高尾山薬王院
- 創建…744年
- 本尊…薬師如来・飯縄権現
- 宗派…真言宗智山派
- 開基…聖武天皇
- 開山…行基
-
大本堂は1901年建立。
彩色は無く、彫刻で装飾。
入母屋造で、堂内には護摩壇がある。
本社(権現堂)は、1729年本殿建立。
飯縄権現を祀る神社(神仏習合の名残り)。
入母屋造の本殿と拝殿を幣殿でつないだ権現造。
アニメの舞台
- 【新宿】
-
Lost in Translation(Traduction infidèle)
銀魂
言の葉の庭(The Garden of Words) - 【練馬】
-
ドラえもん
うる星やつら(Lamu)
のだめカンタービレ(Nodame Cantabile) - 【世田谷】
- サザエさん
- 【西部】
-
【西東京市】ケロロ軍曹(Keroro, mission Titar)
【多摩】平成狸合戦ぽんぽこ(Pompoko)
【調布】フルメタル・パニック!(Full Metal Panic!)
【吉祥寺】GTO
【立川】とある魔術の禁書目録(A Certain Magical Index)
【立川】とある科学の超電磁砲(A Certain Scientific Railgun) - 【その他】
-
【高田馬場】鉄腕アトム
【本郷、上野広小路、代々木上原】風立ちぬ
【明治初期】るろうに剣心
【19世紀末の江戸】D.Gray-man-
【台東区】あしたのジョー
【東京タワー】カードキャプターさくら
【亀有】こちら葛飾区亀有公園前派出所
【麻布十番】美少女戦士セーラームーン
【東京タワー】魔法騎士レイアース - シティーハンター
Nicky Larson - 新宿
- キャプテン翼
Olive et Tom - 四つ木
-
海がきこえる(Ghibli)
Je peux entendre l'océan - 吉祥寺
-
耳をすませば(Ghibli)
Si tu tends l'oreille - 聖蹟桜ヶ丘
-
秒速5センチメートル
5 Centimètres par seconde - 参宮橋駅、豪徳寺駅
- デュラララ!!
- 池袋
- STEINS;GATE
- 秋葉原、ラジオ会館、万世橋
- ラブライブ!
Love Live! - 神田明神、竹むら
-
残響のテロル
Terror in Resonance/Terror in Tokyo - 東京都庁、羽田空港国際線ターミナル
-
東京喰種トーキョーグール
Tokyo Ghoul - 池袋、パフェテラスミルキーウェイ
-
君の名は。
Your Name. - 須賀神社(四谷三丁目)、新宿西口
